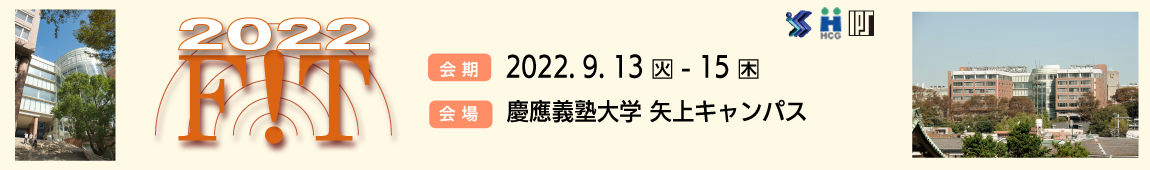| G分野 生体情報科学 |
選奨セッション
生命情報科学、インタラクション(J分野と共催) |
|
9月13日(火) 9:30-12:00 1f会場
座長 西田 知史(情報通信研究機構)
山田 渉(NTTドコモ) |
| CG-001 |
脳波の位相同期により推定された機能的結合の中心性に基づくアルツハイマー病の判別
◎荒井 祐斗・信川 創(千葉工業大学)・池田 尊司・長谷川 千秋・菊知 充(金沢大学)・高橋 哲也(金沢大学/福井大学/魚津神経サナトリウム)
×
CG-001脳波の位相同期により推定された機能的結合の中心性に基づくアルツハイマー病の判別
◎荒井 祐斗・信川 創(千葉工業大学)・池田 尊司・長谷川 千秋・菊知 充(金沢大学)・高橋 哲也(金沢大学/福井大学/魚津神経サナトリウム)
アルツハイマー病(AD)は認知機能障害の一種であり, 主に晩年に発症する進行性神経変性疾患である. 近年の研究では, ADの早期診断と早期介入により, 進行を著しく遅らせられることが報告されている. ADの病理的進行は皮質切断を起こし,認知機能に関わる脳領域間での大域的な相互作用の喪失に繋がる.本研究では,その相互作用を,脳波信号の位相同期尺度であるphase lag index (PLI)によって推定された機能的神経ネットワークのbetweenness centralityにより評価した. その結果, delta帯を除く4つのband帯でトポロジーの変化がみられた.脳波は臨床的汎用性の高いニューロイメージングであることから,この知見を応用することで,ADの生物学的指標の確立に繋がることが期待される. |
| CG-002 |
(講演取消) |
| CG-003 |
特異値分解を用いたNMFによる睡眠時脳波時系列のパワースペクトル解析
◎小山 一樹(立教大学)・坂口 昌徳(筑波大学)・乘本 裕明(北海道大学)・大西 立顕(立教大学)
×
CG-003特異値分解を用いたNMFによる睡眠時脳波時系列のパワースペクトル解析
◎小山 一樹(立教大学)・坂口 昌徳(筑波大学)・乘本 裕明(北海道大学)・大西 立顕(立教大学)
睡眠研究では脳波時系列から睡眠ステージを判定することが重要になるが,人間と比べてマウスなどの動物では研究は少ない.そこでグループ非負値行列因子分解(GNMF)を用いてマウスとトカゲの脳波時系列を解析した.GNMFでは初期値に乱数を用いるのに対し,本研究では初期値に特異値分解の結果を用いるため,解は一つに定まる.一定の時間間隔ごとに時系列のパワースペクトルを求め,各時刻のそれらの値を成分に持つ行列に対して非負値行列因子分解を適用した.その結果,マウスでは特徴量を分類することで新たな睡眠状態を捉えることが可能であると示唆され,トカゲではノンレム睡眠からレム睡眠への状態変化を捉えることができた. |
| CJ-001 |
ドームスクリーンを用いたVRにおける頭部運動補償の効果の検討
◎大道 雄也・伊藤 久祥(岩手県立大学)
×
CJ-001ドームスクリーンを用いたVRにおける頭部運動補償の効果の検討
◎大道 雄也・伊藤 久祥(岩手県立大学)
近年,メタバースへの関心の高まりに伴いVR(Virtual Reality)に関する研究が盛んに行われている.VRの映像提示手法としてはHMD(Head Mounted Display)が広く用いられているが,デバイスの特性上いくつかの課題が存在する.HMDに代わる映像提示手法としてはIPT(Immersive Projection Technology)があるが,システムの運用に係る負担やコンテンツへの没入感において課題がある.そこで本研究では,IPTを用いた手法のうちドームスクリーンを用いたVRにおいて,頭部運動補償を取り入れたVRシステムを構築し,その効果を検討する. |
| CJ-002 |
協働的仮説形成システムによるECサイト運営のデータ駆動型意思決定支援
◎渡辺 龍二・酒井 敏彦・三宅 悠介(GMOペパボ)
×
CJ-002協働的仮説形成システムによるECサイト運営のデータ駆動型意思決定支援
◎渡辺 龍二・酒井 敏彦・三宅 悠介(GMOペパボ)
本研究では,統計的スキルに乏しいECサイト運営者であっても効率的な仮説形成が可能な,協働的仮説形成システムを提案する.ECサイト運営においてデータ駆動型意思決定が注目を集めている.しかしながらこの過程において生じる統計的処理が運営者にとって大きな負担となっている.一方で従来の意思決定支援ツールは,運営者が持つ仮説の候補を活用することが難しい.本研究では運営者とシステム双方が解釈可能な仮説の表現を定義した上で,運営者が仮説の候補を提示し,システムが統計処理し応答するといった対話を実現することで困難を解決する.本報告では実データを用いた本システムの検証結果について述べる. |
| CJ-003 |
本能を活用した意思決定
○福田 収一(慶應義塾大学)
×
CJ-003本能を活用した意思決定
○福田 収一(慶應義塾大学)
現実世界が頻繁に、広範囲に変化し、さらに変化がシャープになった。そのため、将来が予測できなくなった。
また現実世界の複雑化、多様化が急激に進み、従来は、ユークリッド空間処理、すなわち、定量的、客観的な間隔尺度で対応できたが、定性的、主観的な順序尺度で意思決定を行う必要性が急激に増大してきた。
本講演では、順序尺度を基本とする定性的、主観的な情報処理が急激に重要性を増していることから、本能を最大活用し、その活動の指針を与えることにより、与えられた情報を最大活用し、意思決定をする本能支援ツールの開発を行った。 |
| ニューロコンピューティング |
|
9月13日(火) 13:10-15:10 2j会場
座長 西田 知史(情報通信研究機構) |
| G-001 |
CycleGANを利用した循環的変換による連続的画像生成
◎田中 天也・山口 裕(福岡工業大学)
×
G-001CycleGANを利用した循環的変換による連続的画像生成
◎田中 天也・山口 裕(福岡工業大学)
敵対的生成ネットワークの一種であるCycleGANは,2つの画像データセット同士の関係を学習することで画像変換を実現する.本研究ではCycleGANを参考に,画像を次々と別の数字に変換できるモデルを構築し,類似した画像の系列を生成させた.連続的に生成した画像系列を力学系の軌道とみなし,分析を行った.軌道は非周期的であり,カオス的性質を持つことが示唆された.このモデルを連想記憶モデルとして応用する可能性についても議論する. |
| G-002 |
3次元セルオートマトンを用いた神経細胞群同期シミュレーション
◎池田 翔(同志社大学)
×
G-0023次元セルオートマトンを用いた神経細胞群同期シミュレーション
◎池田 翔(同志社大学)
脳内で生じる神経細胞の発火の同期現象は,脳活動の分析等に役立ち,近年注目されている.そこで本研究では,発火の同期現象を再現する数理モデルとして,ミクロモデルには神経細胞の膜電位モデルを,マクロモデルにはセルオートマトンを用いたマルチスケール・シミュレーションを目的とした.ここで,ミクロスケールでの全細胞の周期的な同期現象の膜電位を平均化し,得られた同期波形に対してフーリエ級数を用い,マクロスケールへ組み込むマルチスケールモデルを考案し,シミュレーションに用いた.本研究のシミュレーションにより,様々な同期パターンが確認できた.これより,本研究の成果は脳機能の解明に貢献できると考えられる. |
| MEとバイオサイバネティックス |
|
9月14日(水) 9:30-12:00 4h会場
座長 堀 潤一(新潟大学) |
| G-003 |
周波数解析による脳波データの雑音の特定と除去手法の提案
○赤沢 聖斗・土屋 誠司・渡部 広一(同志社大学)
×
G-003周波数解析による脳波データの雑音の特定と除去手法の提案
○赤沢 聖斗・土屋 誠司・渡部 広一(同志社大学)
現代社会では,デジタル化が拡大していることもあり,コンピュータの利用機会が増えてきている.そして,コンピュータの操作には基本的には手を使うことが求められる.そこで,手が塞がっている,怪我をしているなどで手を使うことができない状況でもコンピュータの操作,入力を行うために先行研究では視覚的に記号を想起した脳波を識別するシステムの構築が行われた.しかし,識別精度が低く実用的ではない.そこで,周波数解析を用いて,雑音を除去する手法の提案を行なった. |
| G-004 |
周波数応答関数を使用した右腕と左腕の運動推定と電極の関係性
◎金本 翔・土屋 誠司・渡部 広一(同志社大学)
×
G-004周波数応答関数を使用した右腕と左腕の運動推定と電極の関係性
◎金本 翔・土屋 誠司・渡部 広一(同志社大学)
怪我等によって身体に障害を持ち,運動が行えない人を補助する為に、人間の脳波を活用したBCI(Brain Computer Interface)が注目されている.
BCIとは人間の脳活動情報などをコンピュータに入力するシステムであり、人間の意志や思考などは脳指令に基づいて身体と連携している為、BCIに入力すれば,物体や機器の操作が可能となる。
そこで運動前に発生する運動準備電位と呼ばれる脳波の特徴のみを用いた,左右の手と肘の運動識別が行われている.しかし十分な識別精度でない為,運動準備電位から運動ごとの脳波特徴を見出せていない.本研究では運動準備電位で運動識別が可能である理由を調査する為,準備時と運動時の脳波間の変化量を用いて識別可能な理由を調査する. |
| G-005 |
走行シーン認知における視認対象に対する事象関連電位P300の解析
◎山本 悠貴(中部大学)・我妻 伸彦(東邦大学)・信川 創(千葉工業大学)・稲垣 圭一郎(中部大学)
×
G-005走行シーン認知における視認対象に対する事象関連電位P300の解析
◎山本 悠貴(中部大学)・我妻 伸彦(東邦大学)・信川 創(千葉工業大学)・稲垣 圭一郎(中部大学)
車両運転時の交通事故の多くは視覚認知などのヒューマンエラーが原因とされる.一方で,視覚由来の交通事故は運転経験により改善される.従って,視覚由来の事故を防ぐためには,経験で変化する運転時の認知や注意に関する脳活動を理解する必要がある.これまでに我々は,走行シーンに人工的な視覚目標を呈示し,ドライバに認知させたところ注意を反映するP300の応答特性が運転経験で変容することを明らかにした.一方で,他車両や歩行者,標識などに対するP300応答については,不明なところが多い.本研究ではこうした走行シーンに存在する一般的な視認対象に対するP300応答を運転の経験量を基準に評価した結果について述べる. |
| G-006 |
確率時限ペトリネットに基づく神経伝達速度の性能評価
◎江野口 裕希・近藤 真史(岡山理科大学)・横川 智教・佐藤 洋一郎(岡山県立大学)
×
G-006確率時限ペトリネットに基づく神経伝達速度の性能評価
◎江野口 裕希・近藤 真史(岡山理科大学)・横川 智教・佐藤 洋一郎(岡山県立大学)
本研究では,非同期式回路と神経細胞が同様に電気信号を相互にやり取りして動作する点に着目し,非同期式回路の性能評価法に基づいた神経細胞のモデル化と性能評価を行った結果を報告する.モデル化に際しては,神経細胞における電気的特性である伝導と伝達について,時間的特性や確率的特性が関わる発生機序を整理し,確率時限ペトリネットによるモデル化を図った.また,性能評価ツールを拡張し,神経細胞の特有の分布を設けることで神経細胞の性能評価を可能にした.拡張したツールを用いて性能評価を行った結果,分布の中央値を基に算出した理論値に極めて近しい値が得られ,非同期式回路の性能評価法の神経細胞への応用可能性を確認した. |
| G-007 |
スペクトログラムを用いた肺音の視覚的異常検知
◎見附 拓馬・島川 博光(立命館大学)
×
G-007スペクトログラムを用いた肺音の視覚的異常検知
◎見附 拓馬・島川 博光(立命館大学)
従来、肺の診断では、専門医が聴診器で患者の肺音を聴きその特徴から異常を検知する。これは経験に依存するため、専門医不在の地方では受診できない患者が増えてしまう。また人の聴覚は年齢とともに衰えるので、医師の高齢化に伴って肺音の異常診断が難しくなる。
本研究では専門医の聴覚に依存しない異常検知手法を提案する。
患者の肺音を短時間フーリエ変換し、時間、振幅、周波数の3軸で構成されたスペクトログラムに視覚化する。さらにスペクトログラムに現れた疾病の特徴を機械学習する。
この手法により、学習後の判別器が新規患者のスペクトログラム上の異常部位を示唆することで、専門医以外の医師が肺音を診断することを補助する。 |
| G-008 |
慢性閉塞性肺疾患診断のためのLong Short-Term Memoryを用いた無拘束でのGaensler1秒率推定手法の提案
◎江本 光希・浜田 百合・栗原 陽介(青山学院大学)
×
G-008慢性閉塞性肺疾患診断のためのLong Short-Term Memoryを用いた無拘束でのGaensler1秒率推定手法の提案
◎江本 光希・浜田 百合・栗原 陽介(青山学院大学)
近年,慢性閉塞性肺疾患(COPD)等の呼吸障害に関心が寄せられている.COPDの診断はスパイロメトリーを用いて呼気流量を計測し,Gaensler1秒率等を評価指標として行われる.しかし,スパイロメトリーでは,専用のスパイロメータが必要であるため,医療機関等で測定する必要がある.そこで本研究では,在宅環境におけるベッド上でGaensler1秒率を簡易的に推定する手法を提案する.本提案手法では,ベッドマットレスの下に圧力センサを設置することで,ベッド上に横たわるヒトの呼吸運動に伴う肺・胸郭の振動を,圧力として計測し,呼気流量を推定する.推定した呼気流量にたいしLong Short-Time Memoryを適用することでGaensler1秒率を推定する.20代男女7名を対象とした検証実験の結果, RMSEが12.96%となった. |
| G-009 |
化学放射線療法におけるシスプラチンのin silico解析
◎坂下 佳歩・藤井 啓輔・川浦 稚代・松島 秀・今井 國治・永山 二歩(名古屋大学)
×
G-009化学放射線療法におけるシスプラチンのin silico解析
◎坂下 佳歩・藤井 啓輔・川浦 稚代・松島 秀・今井 國治・永山 二歩(名古屋大学)
Cisplatin(CDDP)は殺細胞性抗悪性腫瘍薬として使用されており、放射線療法との併用によって、抗がん効果は増強すると言われている。しかし、化学放射線療法による抗がん効果については未だ議論の余地があり、特にCDDPの役割を明らかにすることは臨床上重要である。そこで本研究では、化学放射線療法におけるCDDPと核酸塩基対との相互作用を量子化学的に解析し、その薬剤物性を検討した。その結果、化学放射線療法では化学療法において架橋構造を形成したDNAとは異なるDNAとCDDPが架橋構造を形成することで抗がん効果が増強されていた。このことから、化学放射線療法における抗がん効果の増強にはPt原子のラジカル化が深く関与することが示唆された。 |
| 医用画像 |
|
9月14日(水) 15:30-17:30 5h会場
座長 本谷 秀堅(名古屋工業大学) |
| G-010 |
3次元点群データを用いた口唇裂の対称性解析
細木 大祐・○神谷 亨(九州工業大学)・野元 菜美子・椎木 綾乃・大河内 孝子・中村 典史(鹿児島大学)
×
G-0103次元点群データを用いた口唇裂の対称性解析
細木 大祐・○神谷 亨(九州工業大学)・野元 菜美子・椎木 綾乃・大河内 孝子・中村 典史(鹿児島大学)
口唇裂は,約500人に一人の割合で発生し,胎児の顔面が癒合する過程において唇が完全に形成されない場合に生じる先天異常である.左右対称な口唇と外鼻を形成することを目的として治療が行われているが,医師の主観に依存した判断基準に基づいているため,手術部位の対称度合を定量的に判断する必要がある.本論文では,手術部位の対称性を解析するための顔の対称基準となる面を検出する手法,および対称性を示す指標を提案する. |
| G-011 |
仮想単色CT画像を用いた抗がん剤の可視化
◎永山 二歩・藤井 啓輔・川浦 稚代・松島 秀・今井 國治(名古屋大学)・遠地 志太(大阪大学付属病院)・塚本 一輝(藤田医科大学病院)・坂下 佳歩(名古屋大学)
×
G-011仮想単色CT画像を用いた抗がん剤の可視化
◎永山 二歩・藤井 啓輔・川浦 稚代・松島 秀・今井 國治(名古屋大学)・遠地 志太(大阪大学付属病院)・塚本 一輝(藤田医科大学病院)・坂下 佳歩(名古屋大学)
シスプラチンで代表されるPt製剤はがんの根治を目指す上で欠かせない薬剤である。その抗腫瘍効果は、DNAと架橋反応を引き起こすことによって、がん細胞をアポトーシスに誘導することが知られている。その一方で、この薬剤は正常細胞との非特異的に結合することで、強い副作用を引き起こすことが問題となっている。このことから、Pt製剤が標的外に灌流していないかを視覚的に判断することができれば、これらの副作用を事前に抑えやすくなると考えられる。そこで本研究では、Dual Energy CT装置によって得られた画像がPtに起因したものか判断するためにシミュレーションを行った。この結果、PtはCT装置によって撮像される可能性があることが示唆された。 |
| G-012 |
手指運動機能の評価に基づく手根管症候群スクリーニング
◎松井 良太(慶應義塾大学)・小山 恭史・藤田 浩二(東京医科歯科大学)・杉浦 裕太(慶應義塾大学)
×
G-012手指運動機能の評価に基づく手根管症候群スクリーニング
◎松井 良太(慶應義塾大学)・小山 恭史・藤田 浩二(東京医科歯科大学)・杉浦 裕太(慶應義塾大学)
手根管症候群は,手首の手根管という部位で正中神経が圧迫されることで,手指の痺れや運動障害等の症状を引き起こす疾患である.本研究では,手指の動きを撮影した映像により運動機能を評価し,疾患の疑いをスクリーニングする手法を提案する.検査装置を必要としない手軽な手法として,早期の診断や治療に寄与することを研究目的とする.具体的な手法として,手指を高速に開閉する動きをスマートフォンで撮影した映像に関し,骨格情報の時系列データを,患者と健常者に分類するシステムを実装した.患者15名と健常者17名の映像を用いた交差検証により提案手法を評価した結果,感度と特異度はそれぞれ79.2%,67.7%となった. |
| G-013 |
組織の機能に基づくFDG-PET像の解析
◎朝戸 天翔・戸崎 哲也(神戸市立工業高等専門学校)・千田 道雄(先端医療センター)
×
G-013組織の機能に基づくFDG-PET像の解析
◎朝戸 天翔・戸崎 哲也(神戸市立工業高等専門学校)・千田 道雄(先端医療センター)
FDGは悪性腫瘍だけでなく,糖代謝の活発な組織や炎症組織にも集積する。そのため,FDG-PETによるがんの診断では,正常組織と異常組織とを判別することが難しいという課題を抱えている。本研究では,正常組織と異常組織のFDGの取り込みの違いを定量的,あるいは可視化する方法について検討を行う。FDG-PET像から算出される曲率ベクトルの方向と体内に投与されたFDGが動く方向が一致していると仮定し,組織の機能と曲率ベクトルの関係について調査した。これまでの研究では,曲率に基づいてFDG-PET像から腸管やリンパ管といった管状の形や,がんと考えられる孤立した球状の形を表現することに成功した。 |
| G-014 |
機械学習に基づくPET像からの疑似解剖画像生成
◎笘見 晃清・戸崎 哲也(神戸市立工業高等専門学校)・千田 道雄(先端医療センター)
×
G-014機械学習に基づくPET像からの疑似解剖画像生成
◎笘見 晃清・戸崎 哲也(神戸市立工業高等専門学校)・千田 道雄(先端医療センター)
医療現場で用いられるPET像には解剖情報は含まれていない。しかしがん診断やインフォームドコンセントにおいては組織や臓器の情報は必要となる。そこで本研究ではPET像から対応する疑似解剖画像を生成することを目的とする。画像の生成には画像変換の機械学習として知られるGANの一種であるPix2pixを用いた。ここでは訓練用画像に濃度情報のみのPET像、および3チャンネルに分解したPET像それぞれにおいてPix2pixを適用して疑似解剖画像を生成し、その精度の評価を行う。 |
| G-015 |
CT画像間の変位場を用いた敵対的データ拡張の試み
◎栗山 由也・中尾 恵・中村 光宏(京都大学)
×
G-015CT画像間の変位場を用いた敵対的データ拡張の試み
◎栗山 由也・中尾 恵・中村 光宏(京都大学)
医用画像におけるデータ拡張に敵対的学習を利用することが考えられているが,大規模な一般画像群を対象に設計された方法を症例数の集積が困難な医用画像群に適用すると解剖学的に不自然な構造や不正確なCT値を持つ画像が生成される可能性がある.本研究はCT画像間で生成可能な変位場をデータ拡張の対象として活用し,画像特徴を階層的に制御可能なStyle GANによって擬似変位場を生成してデータ拡張を行う枠組みを提案する.提案方法が従来データ拡張法よりもU-Netによる肝臓と胃のセグメンテーション精度向上に貢献することを確認したので報告する. |
| バイオ情報学(BIO) |
|
9月15日(木) 9:30-12:00 6h会場
座長 倉田 博之(九州工業大学) |
| G-016 |
ラッソロジスティック回帰による脳動脈閉塞推定に役立つ脈波特徴量の分析
◎山田 紘丘・田儀 樹・大崎 美穂・嶋田 啄真・松川 真美(同志社大学)・小林 恭代・斎藤 こずえ(奈良県立医科大学)・山上 宏(国立病院機構大阪医療センター)
×
G-016ラッソロジスティック回帰による脳動脈閉塞推定に役立つ脈波特徴量の分析
◎山田 紘丘・田儀 樹・大崎 美穂・嶋田 啄真・松川 真美(同志社大学)・小林 恭代・斎藤 こずえ(奈良県立医科大学)・山上 宏(国立病院機構大阪医療センター)
後遺症や死亡を起こし得る脳動脈閉塞の迅速な診断と処置は,救急医療の喫緊の課題である.この解決に向け,我々は圧電センサによる脈波測定と,脈波からの特徴量抽出,特徴量を入力とした分類器による閉塞推定を進めてきた.今回は,閉塞推定に役立つ特徴量を同定することに主眼を置く.まず,脈波が含む閉塞からの反射波を反映するように特徴量5種類を抽出した.そして,ロジスティック回帰に各特徴量を入力する条件,および,特徴量選択が可能なラッソロジスティック回帰に全特徴量を入力する条件で実験を行った.条件間で推定性能と特徴量の重みを比較した結果,脳動脈閉塞の正確な推定に貢献する特徴量を明らかにできた. |
| G-017 |
バイオナノマシン集団による分子通信を介した信号分子濃度の協調検出方式
◎千葉 万柚香(大阪市立大学)・中野 賢(大阪公立大学)
×
G-017バイオナノマシン集団による分子通信を介した信号分子濃度の協調検出方式
◎千葉 万柚香(大阪市立大学)・中野 賢(大阪公立大学)
生体分子や生化学反応に基づくバイオナノマシンのための新しい情報通信パラダイムとして、分子通信がある。バイオナノマシンとは、生体分子で構成される微小デバイスであり、遺伝子改変細胞や人工細胞などを指す。分子通信に関するこれまでの研究において、バイオナノマシンの自己集合システムが提案されている。このシステムでは、標的を検出したバイオナノマシンが信号分子を放出し、周囲のバイオナノマシンが信号分子濃度の高い方向へ移動することで、バイオナノマシンが標的付近に集合する。本研究では、複数のバイオナノマシンで構成されるバイオナノマシンの集合体が分子通信を介して環境中の信号分子濃度を正確に検出する方法を提案する。また、提案方法に基づくバイオナノマシンの自己集合システムの設計と、コンピュータシミュレーションによる評価実験について述べる。 |
| G-018 |
分子通信を介して相互作用するバイオナノマシンの集団回転運動
◎王 潔文・中野 賢(大阪公立大学)
×
G-018分子通信を介して相互作用するバイオナノマシンの集団回転運動
◎王 潔文・中野 賢(大阪公立大学)
分子通信とは、細胞間通信に着想を得た化学信号や化学反応に基づく通信方式である。分子通信では、送信機となるバイオナノマシンが情報を符号化した信号分子を受信機となるバイオナノマシンに届けることによって情報を伝達する。バイオナノマシンとは、生体分子で構成される微小サイズのデバイスであり、遺伝子改変細胞や人工細胞などを指す。本研究では、分子通信の応用範囲を拡大することを目的として、バイオナノマシンが回転する集合体を自己組織的に形成する手法を提案する。回転するバイオナノマシンの集合体は安定であるため、複雑で大きな構造体を作ることに利用できる可能性がある。本研究ではまた、数理モデルおよび計算機シミュレーションを用いて回転するバイオナノマシンの集合体のロバスト性を評価する。 |