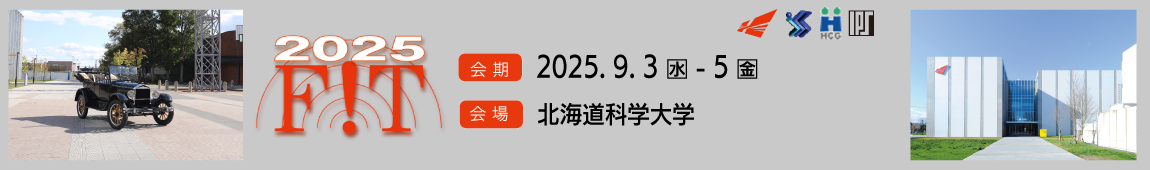| O分野 情報システム |
選奨セッション
情報システムとサービス |
|
9月3日(水) 9:30-12:00 1p会場
座長 茂木 学(拓殖大学)
野田 五十樹(北海道大学) |
| CO-001 |
食育に関する研究のトレンドについて
○千田 眞喜子(花園大学)
×
CO-001食育に関する研究のトレンドについて
○千田 眞喜子(花園大学)
食育に関する研究の内容やトレンドについて検討した結果,食育の研究は実践報告が多く,地域よりも学校での食育に関する研究が多かった.関連語検索(キーワードは給食,家庭科,栄養教諭)より,学校給食・家庭科での食育・栄養教諭の役割や配置に関する研究が多かった.論文タイトル件数は,ピーク(2007年)が新聞記事件数より1年遅れで現れた後,穏やかな減少傾向であった.ピークの主要因は2005年の食育基本法,栄養教諭制度と考察した.対応分析(外部変数は発行年)より,食の基本の学びから,子どもの食生活,家庭科や教室での意識・行動の実態,地域や環境・心に配慮した研究へと,食育に関する研究は時代と共に変容していた. |
| CO-002 |
農産物流通における出荷前需給マッチングのための供給データ推定方法の評価
○磯田 曉・引地 孝文・平野 泰宏・神谷 正人(日本電信電話)
×
CO-002農産物流通における出荷前需給マッチングのための供給データ推定方法の評価
○磯田 曉・引地 孝文・平野 泰宏・神谷 正人(日本電信電話)
農産物の卸売市場を経由する流通において、市場によって供給過多や供給不足となっていることが問題である。我々は農産物流通に関連した各種情報を活用して、出荷前の需給マッチング技術による配送先の制御によってこの問題の解消を目指している。しかし、出荷前の需給マッチングの実現には、出荷前時点での日付、品質、サイズ等の詳細な供給情報が必要である。そこで、本稿ではこれらの詳細な供給情報を、直近の出荷実績と、過去の出荷傾向や栽培特性などを基に推定する技術を提案し評価した。 |
| CO-003 |
AIの社会性とその課題:経済ゲーム実験によるAIの社会性評価指標の提案
○後藤 晶(明治大学)
×
CO-003AIの社会性とその課題:経済ゲーム実験によるAIの社会性評価指標の提案
○後藤 晶(明治大学)
本研究では,経済ゲーム実験を用い,相手が人間かAIかによってAIの社会的行動がどのように変化するかを評価した.社会的行動については,公共財ゲーム・最終提案ゲーム・信頼ゲーム・先制攻撃ゲームを用いて協調性・公平性・容認性・信頼性・誠実性・攻撃性の観点から評価を行った.実験の結果,各指標においてAIのモデルによって差異が存在していること,対象がAIであるか人間であるかによって行動が大きく異なることが示された.
これらの結果は,AIの社会的行動が状況や相手に応じて柔軟に変化し得ることを示唆している.本研究ではこれらの行動特性を評価するための新たな指標を提案し,AIの社会性評価への有効性を示した. |
| CO-004 |
撮影環境によって読み取り情報が変わるQRコード
○廣友 雅徳・池田 奈々子(佐賀大学)・瀧田 愼・白石 善明(神戸大学)
×
CO-004撮影環境によって読み取り情報が変わるQRコード
○廣友 雅徳・池田 奈々子(佐賀大学)・瀧田 愼・白石 善明(神戸大学)
スマートフォンの普及とともに,QRコードは決済サービスやWebページへの誘導などの様々な用途に用いられている.その一方で,偽装QRコードを利用した不正送金やスマホの乗っ取りなどが問題となっている.そのため,安全にQRコードを利用するには撮影環境によってQRコードの読み取り情報にどのような変化が起こるかを網羅的に把握しておく必要がある.本稿では,撮影環境によって読み取り情報が変わるQRコードを提案し,その影響について考察する. |
| CO-005 |
迷惑メール対策における送信ドメイン認証の解析とその効果
◎北倉 奈菜・陳 春祥(県立広島大学)
×
CO-005迷惑メール対策における送信ドメイン認証の解析とその効果
◎北倉 奈菜・陳 春祥(県立広島大学)
現在のメール送信は送信者情報を詐称することが可能で、多くの迷惑メールは他のメールアドレスになりすまし、送信されている。その対策方法として用いられているのが送信ドメイン認証技術であるが、その有効性はプロバイダ視点では調査が進められているが、一利用者視点では明らかにされていない。そこで本研究では、著者らが受信した迷惑メールにおいて、メールヘッダの解析プログラムを開発し解析を行い、一利用者単位での送信ドメイン認証技術の有効性を調査した。 |
| CO-006 |
岐阜県における野生生物調査システムの事業者ニーズへの適応
○廣瀬 康之・戸松 準貴・渡邉 惺也・栗田 雅也・田島 孝治(岐阜工業高等専門学校)・馬渕 洋介(岐阜県建設研究センター)
×
CO-006岐阜県における野生生物調査システムの事業者ニーズへの適応
○廣瀬 康之・戸松 準貴・渡邉 惺也・栗田 雅也・田島 孝治(岐阜工業高等専門学校)・馬渕 洋介(岐阜県建設研究センター)
近年、野生生物によって従来より育まれた生態系が崩壊したり、病原体の拡散など危険性が社会的問題となっている。この対策のため野生生物の地域ごとの生態状況の把握できるよう、岐阜県ではWebGISを利用した野生生物の生態情報システムを構築している。行政、事業者、住民等からの情報を一元的に総括することにより生息域を判断し今後の対応策を検討するものである。特に社会的課題となっている豚熱(CSF)対策としてその感染媒体となる野生イノシシを具体的対象とし、ジビエ利用等新たな社会的ニーズを考慮したシステムを開発し検証した。今回、新たな展開として事業者ニーズに適応できたことを報告する。 |
| CO-007 |
地震波形による高層建築物内の食器類に関する物理シミュレーション
◎佐藤 綾音・檀 裕也(松山大学)
×
CO-007地震波形による高層建築物内の食器類に関する物理シミュレーション
◎佐藤 綾音・檀 裕也(松山大学)
近年頻発する巨大地震では、高層建築物等による長周期地震動が観測され、高層建築物等での被害が発生している。本研究では、令和6年能登半島地震の実データを用いてシミュレーションをしたところ、高層建築物内の家具の状態を計算することが出来た。そこで、被害の実態を仮想的に検証するために、高層建築物の長周期地震動と地表での波形データを比較した。また、高層住宅における地震発生時の食器棚及び食器の最大加速度を求め、家具の破損防止に必要なガラスの強度を評価し、被害の最小化を図る方法について定量的に検証した。 |
| 減災情報システム |
|
9月3日(水) 13:10-15:10 2x会場
座長 野田 五十樹(北海道大学) |
| O-001 |
災害時におけるSNS通信の優先制御システムの設計
◎田中 秀征・佐藤 寧洋(大阪電気通信大学)
×
O-001災害時におけるSNS通信の優先制御システムの設計
◎田中 秀征・佐藤 寧洋(大阪電気通信大学)
本稿の提案システムは、災害発生地域から送信された SNS トラヒックを優先して処理することで、災害情報や救助要請などを円滑にやりとりさせることを目的としている。災害地域は気象庁が発出する防災情報をもとに特定し、送信端末の位置情報は送信元 IP アドレスから推定する。ネットワーク制御には OpenFlow を用いて、データ送信前に発出される DNS パケットをスイッチで検出し、Ryu コントローラーで解析することで、対象 SNS のドメイン名と IP アドレスを取得する。実験ネットワーク上において設計したシステムを実装し、実運用を想定した技術的な課題について検証する。 |
| O-002 |
地震時における画像データを用いた室内の環境認識技術
○小松 佑人(帝京大学/防災科学技術研究所)・福井 弘久・阿部 弘・佐藤 栄児(防災科学技術研究所)・浜田 宏一(帝京大学)
×
O-002地震時における画像データを用いた室内の環境認識技術
○小松 佑人(帝京大学/防災科学技術研究所)・福井 弘久・阿部 弘・佐藤 栄児(防災科学技術研究所)・浜田 宏一(帝京大学)
都市部に中小地震が発生した場合、都市機能を含めた社会活動の急激な低下がみられ、社会活動の混乱を招いている。また、大地震が起きた場合は、これに加え、個別建物および都市に物理的な被害が発生し、それらの迅速な被害把握と被害把握からの継続利用・活動性の判定、復旧リソースの算出が、早急な復旧活動に移行するためには重要である。そこで、迅速で高精度な被害把握、個別建物・都市機能の継続利用性・活動性の判定、復旧リソースの算出に関する技術開発を進めている。今回、画像データを用いた室内の環境認識技術について検討したので報告する。 |
| O-003 |
(講演取消) |
| O-004 |
地理的要件とハザードマップ周辺情報を事前学習したGPTによる避難ルート情報提示の検討
◎堀内 透悟・和﨑 克己(信州大学)
×
O-004地理的要件とハザードマップ周辺情報を事前学習したGPTによる避難ルート情報提示の検討
◎堀内 透悟・和﨑 克己(信州大学)
本研究は、地理情報とハザードマップ周辺の拠点情報等を事前学習させたGPTを用いて、災害時の徒歩による避難ルートを提示するシステムの構築を目的とする。国土地理院のハザードマップとGoogle Maps APIを用いて、災害危険区域における座標データ、道路名、地籍情報、周辺施設などを取得し、ChatGPTのファインチューニングの入力とする自然文を含むJSON Lines形式の追加学習データを作成した。このデータを用いてGPTをファインチューニングすることで、災害発生時に対象地域の災害リスクを踏まえた避難先候補や物資の調達場所などの避難関連情報を提示可能となった。 |
| サービスコンピューティング |
|
9月3日(水) 15:30-17:30 3x会場
座長 北島 信哉(富士通) |
| O-005 |
Verifiable Credentialsに基づくDIDの信頼性確保と関係性取得によって形成するレビューシステム
○出合 祐喜・和﨑 克己(信州大学)
×
O-005Verifiable Credentialsに基づくDIDの信頼性確保と関係性取得によって形成するレビューシステム
○出合 祐喜・和﨑 克己(信州大学)
近年、ブロックチェーン技術が発展しており、その耐改ざん性や分散性を活かした技術であるDID(Decentralized Identifier)とVC(Verifiable Credentials)を用いた、第三者検証可能な資格情報を提示できる仕組みが注目されている。本研究ではDIDに紐づいた複数のVCに含まれる情報を評価し、それらをDID間の信頼度等を可視化する方法を提案する。さらに、この信頼性に基づいて複数のDID同士の関係性をVCを用いて証明し、それをレビューシステムに活用することで不正なレビューの防止、情報信頼性の向上を実現する。 |
| O-006 |
署名された複数のアクティビティに基づくVerifiable Credentialsの発行・検証プロセスの枠組み
◎石坂 匠・和﨑 克己(信州大学)
×
O-006署名された複数のアクティビティに基づくVerifiable Credentialsの発行・検証プロセスの枠組み
◎石坂 匠・和﨑 克己(信州大学)
Verifiable Credentials(VCs)とは、検証可能な資格証明のことであり、特定の発行者によってClaimが示されたことを証明できるものである。現状、VCについてW3Cによる規約やそれに基づくサービスが存在しているが、VCが発行される根拠や過程については不透明なものが多い。本研究では、複数のVCを根拠として新たなVCを発行する仕組みや、その検証方法について提案する。ブロックチェーン技術や暗号技術を用いることで、改ざんや情報漏洩を防ぎつつこの仕組みを実現する。主に教育機関での利用を想定しており、この方法によって成績評価や修了証発行のプロセスをプライバシーに配慮しつつより信頼度の高いものにできる。 |
| O-007 |
Proposal of a workload migration plan method capable of responding to prediction errors
○金子 聡(日立製作所)
×
O-007Proposal of a workload migration plan method capable of responding to prediction errors
○金子 聡(日立製作所)
With the spread of AI, the use of renewable energy (RE) in data centers (DCs) is becoming important. Efforts are underway to control the allocation of IT loads (WL) and match power demand with RE supply on an hourly basis. In conventional technology, it was difficult to respond to the frequent renewable energy prediction errors in periodic migration planning. The proposed method creates on-demand WL migration plans to minimize data retention costs while meeting migration time and performance requirements, based on the WL migration type and environmental characteristics that the WL allows. |
| O-008 |
複数の最適化エンジンを利用する拠点間データ・アプリの最適配置案の算出方式の検討
○野村 鎮平・早坂 光雄(日立製作所)
×
O-008複数の最適化エンジンを利用する拠点間データ・アプリの最適配置案の算出方式の検討
○野村 鎮平・早坂 光雄(日立製作所)
オンプレミスやクラウド間でのデータ利活用の要望が大きい。それには、性能や課金額のパラメータを考慮して、分析アプリや処理対象データを、拠点間に配置する必要がある。その実現のために、従来ではコスト最小化などの1つのパラメータにフォーカスした1つの最適化案の算出技術がある。しかし、ユーザが背反する複数のパラメータ間で所望の案を得るには、パラメータ入力と結果の確認の繰り返す必要がある。そこで本研究では、あるパラメータに関する配置を導出する最適化エンジンを複数組み合わせ,エンジン間で配置の一致する案を結合し、複数の配置案を算出する方式を提案する。提案方式により、本課題を解決できることを示す。 |
| O-009 |
生成AIを活用したGUI変更検出
◎和久井 拓・増田 峰義(日立製作所)
×
O-009生成AIを活用したGUI変更検出
◎和久井 拓・増田 峰義(日立製作所)
マネージドサービスでは、クラウドサービスの管理ポータルにおけるGUI変更に伴い、操作画面と手順書の間で相違が生じ、作業中断や手順書更新などに追われる場合がある。本研究はこの問題に対し、定期取得した管理画面に対し生成AIが画像間の差分を検出する技術と、生成AIを活用し過検出を抑制するフィルタから成るGUI変更検出技術を提案する。本稿では、実際のクラウドサービスの管理画面で提案方式の検出性能を評価した。精度評価ではGUIの変更は漏れなく検出され、またフィルタにより過検出が85.5%削減された。 |
| 情報システムと人知 |
|
9月4日(木) 9:30-12:00 4x会場
座長 松澤 芳昭(青山学院大学) |
| O-010 |
(講演取消) |
| O-011 |
アルミ合金製造におけるベテラン社員知識の形式知化と生産効率化に向けた計量指標の探索;Wasserstein距離に基づくアルミ合金の類似度評価
◎野々村 真誉・磯田 祐世・山本 佑樹・浅田 勝義(UACJ)
×
O-011アルミ合金製造におけるベテラン社員知識の形式知化と生産効率化に向けた計量指標の探索;Wasserstein距離に基づくアルミ合金の類似度評価
◎野々村 真誉・磯田 祐世・山本 佑樹・浅田 勝義(UACJ)
本研究では、Al合金製品の少量多品種製造による製造の複雑性に起因する課題を、ベテラン社員の培った経験則により長年克服してきたという経緯に着目した。経験則を定量化し、後継者への継承と、効率的な製造プロセス設計を目指す。複雑性を克服するため、既存のAl合金製品群における合金組成の類似性を客観的に評価するための計量(metric)の確立が重要である。そこで、Wasserstein距離を適用した合金組成の類似度評価法を提案する。この計量を用いることで、合金間の類似性を適切に評価し、製造品種の集約を効率化することが期待される。本研究の成果は、製品品種の集約による生産効率化に加え、ベテラン社員の知識と経験の形式知化に資するものと言える。 |
| O-012 |
ソーシャルメディア時代における伝統文化の伝承と発展に関する一考察:中国の漢服を例として
◎周 予同・飯島 泰裕(青山学院大学)
×
O-012ソーシャルメディア時代における伝統文化の伝承と発展に関する一考察:中国の漢服を例として
◎周 予同・飯島 泰裕(青山学院大学)
ソーシャルメディア時代において、伝統文化に対してユーザーの認知・共感・発信のプロセスは大きく変容しつつある。中でも、中国の「漢服」といった伝統衣装はSNSにおいて新たな注目を集めている。本研究では、ソーシャルメディア時代における伝統文化の受容と拡散プロセスを明らかにするため、SIPSモデルを基盤に、独自の行動モデルを構築した。漢服を対象としたアンケートおよびインタビュー調査を通じて、SNS上での偶発的接触が共感・関心・参加行動につながる傾向を確認した。特に、アルゴリズムによるおすすめ機能が偶発的な接触と共感形成に与える影響に注目し、SNSが伝統文化への関心と行動を促進する可能性を示した。 |
| O-013 |
新入社員へのOJTにおけるワークエンゲージメントへの影響プロセス:ワークエンゲージメント向上に向けたOJTの効果的な取り組みの検討
◎中川 拓磨・伊東 隼人・沢田 雅章・三好 きよみ(東京都立産業技術大学院大学)
×
O-013新入社員へのOJTにおけるワークエンゲージメントへの影響プロセス:ワークエンゲージメント向上に向けたOJTの効果的な取り組みの検討
◎中川 拓磨・伊東 隼人・沢田 雅章・三好 きよみ(東京都立産業技術大学院大学)
日本においては,少子高齢化による労働力不足も相まって,従業員の働きがいや新入社員の早期離職が問題となっている.また,働きがいという点では,ワークエンゲージメントが,日本は諸外国と比較して低いことが報告されている.本研究は,OJTに焦点をあて,OJTがワークエンゲージメントに及ぼす影響を検討する.その結果から,OJTの効果的な取り組みを提案することが目的である.IT関連企業の従業員にインタビュー調査を行い,質的統合法を用いて分析した.その結果,OJTの問題点として,平準化されていない業務や業務の属人化による業務過多が抽出された.それには,会社や組織全体としての対処が必要であることが示された. |
| O-014 |
自治体事例におけるシビックプライド醸成のための住民潜在価値導出モデルでの分析精度改善手法の探求
○山本 裕(東京国際工科専門職大学)・橋本 沙也加・橋本 尚子・岡田 ゆかり(百代)
×
O-014自治体事例におけるシビックプライド醸成のための住民潜在価値導出モデルでの分析精度改善手法の探求
○山本 裕(東京国際工科専門職大学)・橋本 沙也加・橋本 尚子・岡田 ゆかり(百代)
近年、各自治体においてシビックプライド醸成活動の重要性が高まっており、ある自治体の住民アンケートから潜在的な住民価値を導出するデータ解析モデルの構築・評価を実施中である。本モデルにおいて、住民施策の向上のために(a)住民価値を意味付ける導出主成分の寄与率向上、(b)総合計画の分野ごとの住民意識の把握、(c)導出主成分に対して影響が大きい設問回答の明確化などの課題がある。
本論では上記課題解決のために、総合計画各分野ごとの設問回答の重要度評価、導出主成分とアンケート各設問回答との相関評価を行うことにより、総合計画立案に対するより精度が高い提言を導出する手法を明らかにする。 |
| O-015 |
ドラッグストアにおけるVoCとPOSの統合分析 -クレーム傾向の可視化と属性別施策の示唆-
○山崎 大(ツルハホールディングス)・本橋 洋介・浅見 隆太・田中 智規・宮下 雅貴・河野 俊輔(日本電気)
×
O-015ドラッグストアにおけるVoCとPOSの統合分析 -クレーム傾向の可視化と属性別施策の示唆-
○山崎 大(ツルハホールディングス)・本橋 洋介・浅見 隆太・田中 智規・宮下 雅貴・河野 俊輔(日本電気)
本研究では、過去の問い合わせ対応内容の学習に加え、問い合わせ時点のID-POSデータをプロンプトとして併用することで、より顧客ニーズに即した対応文の自動生成を目指した。購買履歴や商品カテゴリ、来店頻度などの属性を生成モデルに組み込むことで、個別文脈に沿った応答を実現する。大規模言語モデルを用いて生成された対応文は、実際の応答事例と比較して評価され、従来手法と比べて文脈適合性および顧客満足度の観点で有意な改善が確認された。今後はFAQやチャットボットへの応用も視野に入れ、実運用への展開を検討する。 |
| 情報システムと社会経済 |
|
9月4日(木) 15:30-17:30 5x会場
座長 松澤 芳昭(青山学院大学) |
| O-016 |
大規模イベント開催による地域の宿泊価格の変化
○鈴木 祥平(日本大学)・江﨑 貴昭(日本交通公社)
×
O-016大規模イベント開催による地域の宿泊価格の変化
○鈴木 祥平(日本大学)・江﨑 貴昭(日本交通公社)
観光立国を掲げる日本においては,定量的な指標に基づく戦略立案が求められている.しかし,公的機関によって公表される統計資料は月単位の集計が多く,週単位や日単位で地域の実態を正確に把握することは難しい.そこで本研究では誰でも無料で閲覧可能な宿泊予約サイトの価格情報を継続的に収集した.そして,そのデータを用いて,地域の平均的な宿泊価格と変動域を明らかにし,大規模イベント開催時に地域の宿泊価格が平時に比べてどのように変化したのかを分析した.さらに,大規模イベントの影響が顕在化する地域としない地域の特徴や,使用したデータの特性について考察した. |
| O-017 |
生活者の情報行動、消費行動の経時的分析
○濱岡 豊(慶応大学)
×
O-017生活者の情報行動、消費行動の経時的分析
○濱岡 豊(慶応大学)
報告者は2014年から、大学生を対象に消費に関する継続調査を行ってきた。10年間ではあるが、情報源としての雑誌の利用割合の急速な低下の一方でクチコミサイト、SNSなどの利用割合の増加など、情報行動には大きな変化が生じている。消費行動については、オンラインでの購買回数は増加したが、百貨店やアウトレットモールでの購入回数には大きな変化はない。本研究では、情報行動、消費行動の変化とその規定要因についての分析結果を報告する。 |
| O-018 |
情報システム、製品開発プロセス、組織文化、マーケティング戦略と企業の競争優位性 2007-2024
○濱岡 豊(慶応大学)
×
O-018情報システム、製品開発プロセス、組織文化、マーケティング戦略と企業の競争優位性 2007-2024
○濱岡 豊(慶応大学)
本研究では、情報システムおよび既存手法の利用状況が、「外部環境要因」「企業の内部要因」「製品開発プロセス
要因」「製品の特徴」によって規定され、さらに「製品開発の成果」が、これらによって規定されると考える。これまで、2013年、2019年にも同様の分析を行ってきたが、本研究では、その後行った2024年までのデータを用いて分析を行う。 |
| O-019 |
経済実験における実験参加者を大規模言語モデルで代替できるのか -ペルソナ情報によるシミュレーション精度向上の検証-
○日室 聡仁(NECソリューションイノベータ)・後藤 晶(明治大学)
×
O-019経済実験における実験参加者を大規模言語モデルで代替できるのか -ペルソナ情報によるシミュレーション精度向上の検証-
○日室 聡仁(NECソリューションイノベータ)・後藤 晶(明治大学)
本研究においては,経済実験における実験参加者を大規模言語モデル(LLMs)に代替することが可能であるのか検討した。経済実験を実施するにあたり、実験参加者を集めて実験をすることは多くのコストがかかる。この問題を解決するために,本研究では、繰り返し公共財ゲームを題材に、LLMsに実験参加者のペルソナ情報を与え、人間がゲームを実施した際の行動とLLMsの行動を比較することで、ペルソナ情報を与えることでシミュレーション精度が向上するかどうかを検証した。その結果,デモグラフィックなペルソナ情報を与えてもシミュレーション精度の向上には寄与しないことが確認された。 |
| 情報システムと社会動向 |
|
9月5日(金) 9:30-12:00 6x会場
座長 北島 信哉(富士通) |
| O-020 |
複数地域の統一GTFS-JPデータベースによる統合バス情報公開システムの研究
◎福士 雅弘・佐藤 柚香・松田 勝敬(東北⼯業⼤学)
×
O-020複数地域の統一GTFS-JPデータベースによる統合バス情報公開システムの研究
◎福士 雅弘・佐藤 柚香・松田 勝敬(東北⼯業⼤学)
国内のバス情報は、GTFS-JP形式のオープンデータとして公開する流れがある。GTFS-JPは自由度が高いフォーマットとなっているため、複数のバス事業者のバス情報を統合して扱うにはそれぞれのデータフォーマットの差異に対応する必要がある。そこで、複数地域のバス事業者のGTFS-JP形式のデータのフォーマットを統一し、公開するシステムを構築した。これまでに東北地域の公開されているGTFS-JPデータから、統一データベースおよびデータ整形プログラムを作成し、確認を行った。今回は、他の地方でも公開されているGTFS-JPデータを用いてシステムの実用性を検討した。 |
| O-021 |
日本の市におけるRFIの実施状況
○本田 正美(関東学院大学)
×
O-021日本の市におけるRFIの実施状況
○本田 正美(関東学院大学)
RFI(Request For Information)は、企業や官公庁などが業務の発注や委託などを計画する際に、発注先の候補となりそうな事業者に対して業務に関わる情報提供を依頼する行為や提供依頼する文書のことを指している。事業者からの情報提供を受けて、発注する製品やサービスに求める要件や調達条件などの詳細が検討されることになる。RFIで情報提供を求めた後には、より具体的な提案を求めるRFP(Request For Proposal)が作成され、事業者に対して提示される。この一連の発注者と受注者の間の情報のやりとりにつき、本研究では、日本の自治体の中でも市に着目する。自治体においても情報システム調達が行われているが、市にあってはRFIが実施されているのか。その現状について事例分析を行う。 |
| O-022 |
段階評価における属性間の分布構造差を捉える新たな距離指標の提案
◎萩田 碧偉・山崎 綾一郎(静岡理工科大学)・山岸 祐己(静岡理工科大学/浜松医科大学)・笹本 和人(静岡市)・青木 成樹(マリンオープンイノベーション機構)・橋本 正洋(マリンオープンイノベーション機構/法政大学/東京科学大学)
×
O-022段階評価における属性間の分布構造差を捉える新たな距離指標の提案
◎萩田 碧偉・山崎 綾一郎(静岡理工科大学)・山岸 祐己(静岡理工科大学/浜松医科大学)・笹本 和人(静岡市)・青木 成樹(マリンオープンイノベーション機構)・橋本 正洋(マリンオープンイノベーション機構/法政大学/東京科学大学)
段階評価を用いた調査において,属性間の評価傾向を比較する際には,平均値や相関係数といった局所的な統計量に基づく分析が一般的であり,評価分布の全体的な形状に起因する構造的な違いを捉えることが難しい.そこで本研究では, 属性間の評価傾向の違いを分布レベルで定量的に比較・構造化することを目的とし,分布の歪度や尖度といった高次統計量に基づき,Jarque-Bera検定の枠組みを応用した新たな疑似距離指標(JB距離)を提案する.実験では,地域幸福度調査の実データを用いた分析により,従来手法では捉えにくかった評価傾向の構造的差異を明示的に把握できることを示し,分布ベースの比較指標としての有効性を実証する. |
| O-023 |
窓の反射を考慮したバスの乗降者人数の計数手法に関する研究
◎松井 友哉・中原 匡哉・佐伯 祐介(大阪電気通信大学)
×
O-023窓の反射を考慮したバスの乗降者人数の計数手法に関する研究
◎松井 友哉・中原 匡哉・佐伯 祐介(大阪電気通信大学)
現在,バス業界では,利用者の減少や運転手不足などの影響により路線の見直しが進められている.こうした路線の見直しには利用者数を把握する必要があり,バス停付近の施設などでは主に人手で計数されている.しかし,人手による計数では,人的コストや人的被害の観点から自動で計数する技術の確立が求められている.既存研究では,バス車外から利用者数を調査する手法が提案されている.しかし,これらの手法では,窓の反射により誤計数する課題がある.そこで,本研究では,深層学習を用いてバスの窓を認識することで,乗降者人数の誤計数を抑制する手法を開発した.そして,実証実験を通じて提案手法の有用性と課題を明らかにした. |
| O-024 |
CBDCといった価値を有するデータを安全に送受信するためのネットワークについて
○乾 泰司(CITRON Systems)・髙橋 亘(大阪経済大学)
×
O-024CBDCといった価値を有するデータを安全に送受信するためのネットワークについて
○乾 泰司(CITRON Systems)・髙橋 亘(大阪経済大学)
現在、情報を遠隔地に送る場合に手紙やはがきという手段を利用することが可能である。一方、日本銀行券といった紙幣を遠隔地に送る場合には、現金書留という特殊な封筒を使う必要がある。因みにネットワーク上を電送されるのは、情報であり、「お金」という価値そのものは、堅固なセキュリティで守られたデータベース内に格納されている。日本銀行券に相当する「お金」がネットワークを通じ外部に出て行くことはない。ネットワーク上を行き交うのは情報であり、価値そのもの(お金)ではない。一方、最近は、多くの国でCBDCを発行する可能性がある。このような状況を背景として、これまでの決済システムと異なり、CBDCという「お金」そのものが、ネットワークを介して遠隔地に送られることを想定する必要がある。従って、電送されるCBDCを守るセキュリティ対策が必要となる。本ペーパーでは、PKI を活用しCBDCを安全に遠隔地に送る方法を提案している。 |
| 情報システムとライフインテリジェンス |
|
9月5日(金) 13:10-15:40 7x会場
座長 瀧田 愼(神戸大学) |
| O-025 |
外国人観光客の鉄道切符使用を支援するシステムの提案
◎常 舜志・杉本 徹・中村 広幸(芝浦工業大学)
×
O-025外国人観光客の鉄道切符使用を支援するシステムの提案
◎常 舜志・杉本 徹・中村 広幸(芝浦工業大学)
近年増加している訪日外国人観光客にとって日本の鉄道切符は分かりにくく、駅での切符購入や改札入場の際に戸惑うことも多い。本研究では、まず日本の鉄道切符の複雑な券種体系が外国人にとって理解困難である要因を分析する。そのうえでGPT-APIを用いた画像認識型券種判別により、鉄道切符の使用時に生じる困難を低減する支援システムを開発する。現段階で券種判別に関して90%以上の識別精度が得られることを確認している。本研究は、観光・鉄道業界に対し、インバウンド対応支援の新たな技術的アプローチを示すものである。 |
| O-026 |
ゴミ箱発見支援アプリケーションの開発検証
◎内海 智宏(釧路公立大学)・中谷 彰宏・杉町 剛大・八木 真(アイエックスナレッジ)・長谷川 正(HISホールディングス)・皆月 昭則(釧路公立大学)
×
O-026ゴミ箱発見支援アプリケーションの開発検証
◎内海 智宏(釧路公立大学)・中谷 彰宏・杉町 剛大・八木 真(アイエックスナレッジ)・長谷川 正(HISホールディングス)・皆月 昭則(釧路公立大学)
新型コロナウィルスの感染状況が改善し、2024年には全国の観光地で訪日外国人旅行者数が年間約3.600万人まで回復するなど、コロナ前のような賑わいが戻りつつある。一方で、地域のオーバーツーリズムによる散乱ゴミの被害は顕在化している。このような状況に対して行われている対策はポスター掲示、呼びかけなどの啓発活動が中心であり根本的な解決には至っていない。本研究では開発したスマートフォンアプリにゴミ箱まで案内させる機能を実装した。ゴミ箱の座標を事前に登録し、ユーザーの現在地データを取得することで、アプリ画面にゴミ箱への方向を示す矢印を表示する機能を有している。実地検証では、アプリの動作確認およびゴミ箱の発見率向上に関する有効性を評価した。 |
| O-027 |
植物の成長を時系列で直感的に理解するための3D可視化技術の開発
◎高橋 虹太・和田 直史・松本 拓・稲垣 潤・竹沢 恵(北海道科学大学)・七夕 高也(公立千歳科学技術大学)
×
O-027植物の成長を時系列で直感的に理解するための3D可視化技術の開発
◎高橋 虹太・和田 直史・松本 拓・稲垣 潤・竹沢 恵(北海道科学大学)・七夕 高也(公立千歳科学技術大学)
本研究では、植物の成長過程を直感的に理解するための没入型植物成長観察システムの構築を目指している。本システムは、定期的に取得した植物の3次元データを仮想空間内に時系列連続表示させることにより、ユーザが自由に視点を移動しながら植物の空間的・時間的形態変化を体験的に観察可能とする。これにより、従来の静的比較では得られなかった成長ダイナミクスの理解が可能となり、農業分野での作物観察効率化や教育・研究活動への応用展開が期待される。本発表では、ダイズの多視点画像を用いてGaussian Splattingにより3次元モデルを生成し、VRデバイスを用いて可視化した結果について報告する。 |
| O-028 |
大規模言語モデルを活用したマニュアルの見出し作成支援手法の提案
◎上前 諒輔・横山 想一郎・山下 倫央・川村 秀憲(北海道大学)・永田 功(YAMAGATA)
×
O-028大規模言語モデルを活用したマニュアルの見出し作成支援手法の提案
◎上前 諒輔・横山 想一郎・山下 倫央・川村 秀憲(北海道大学)・永田 功(YAMAGATA)
マニュアル利用者が迅速に目的の情報に到達するには,利用者視点で体系化された目次が必要である.その設計にはドメイン特有の専門知識と多大な工数を要し,既存マニュアルの修正でも短時間での再編成は困難である.本研究では大規模言語モデル(LLM)とプロンプトエンジニアリングを用い,未体系化マニュアル原稿から高い情報探索効率を有する目次の生成手法を提案する.提案手法はマニュアル作成の専門家が採用する情報分類基準をプロンプトに反映し,LLMの文脈理解能力を活用して利用者中心の構造を構築する.製品マニュアルを対象とした評価の結果,生成された目次は専門家作成の目次と同等の構造的妥当性と情報到達の容易性を示す. |
| O-029 |
個人のニュース接触履歴を用いた情報接触状況可視化システムの試作
◎毛利 拓海・山村 千草・藤井 亜里砂(日本放送協会)
×
O-029個人のニュース接触履歴を用いた情報接触状況可視化システムの試作
◎毛利 拓海・山村 千草・藤井 亜里砂(日本放送協会)
デジタルサービスの普及により、気づかぬうちに個人の趣味・嗜好に基づいた偏った情報ばかりに接触してしまうフィルターバブルが社会問題になっている。そこでWeb調査によりニュース情報に接触する際の意識と情報の偏りの自覚について確認するとともに、流通しているニュースと自身が接触したニュースを重ねて可視化することに対する評価や受容性について調査した。調査結果から情報の接触状況を可視化することで、情報接触の行動変容を促す可能性があることを確認した。そこで、個人がサービスを利用した履歴を蓄積するパーソナルデータストア(PDS)を用いて、自身の情報接触状況を可視化するシステムを試作し、その動作を確認した。 |