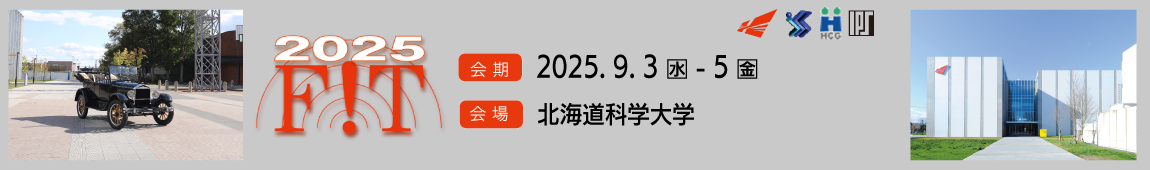| C分野 ハードウェア・アーキテクチャ |
選奨セッション
ハードウェア・データベース選奨セッション(D分野と共催) |
|
9月3日(水) 9:30-12:00 1b会場
座長 土屋 達弘(大阪大学)
鈴木 釈規(筑波大学) |
| CC-001 |
RISC-V拡張としてのSTRAIGHT ISA向けコンパイラツールチェインの設計および評価
○杉田 脩・門本 淳一郎・入江 英嗣(東京大学)
×
CC-001RISC-V拡張としてのSTRAIGHT ISA向けコンパイラツールチェインの設計および評価
○杉田 脩・門本 淳一郎・入江 英嗣(東京大学)
新しい命令セットアーキテクチャ(ISA)の研究においては,実用プログラムで有効性を評価するためにコンパイラツールチェインの整備が不可欠である.しかし,コンパイラ,アセンブラ,リンカといった各種ツールを新規ISA向けに独自実装し,既存ISAと同等の水準まで成熟させるには大きな労力を要する.命令表現が一般的なISAと異なるSTRAIGHT ISAは,そのような実装負荷の高いISAの一例である.本研究では,STRAIGHT ISAをRISC-Vの拡張命令セットとして位置づけ,既存のツールチェインを拡張することで,既存ISAと比較可能な水準のSTRAIGHT向けツールチェインを効率的かつ実用的に構築する手法を提案する. |
| CC-002 |
計算精度を動的制御可能なアーキテクチャによる音声特徴量抽出の高速化
◎三窪 大智・鈴木 渉太・杉田 脩・門本 淳一郎・入江 英嗣(東京大学)
×
CC-002計算精度を動的制御可能なアーキテクチャによる音声特徴量抽出の高速化
◎三窪 大智・鈴木 渉太・杉田 脩・門本 淳一郎・入江 英嗣(東京大学)
エッジデバイス上での音声認識は計算負荷と消費電力を抑えることが求められる。この抑制手段の一つに、認識精度が許容できる範囲内の計算精度の調整がある。使用環境によって必要な認識精度は変わるため、計算精度を落とすことは計算負荷削減の有効な手段となる。本研究では周りの環境に応じて計算精度を変化できる音声認識システムの開発を目標とし、繰り返し構造に対して動的に近似度を変えられるStochastic Iterative Approximation (SIA)をメルスペクトログラムの計算手法に適用した。評価では、異なる近似条件下で音素誤り率と処理時間をシミュレーションにより計測した。その結果、提案手法が音素誤り率の上昇を抑えつつ、処理時間を短縮できることを確認した。 |
| CD-001 |
部分属性指定に対応した近似最近傍探索アルゴリズム
◎植村 玲央・天方 大地(大阪大学)
×
CD-001部分属性指定に対応した近似最近傍探索アルゴリズム
◎植村 玲央・天方 大地(大阪大学)
近年,オブジェクトの高次元ベクトル化やモーダルの多様化に対応するため,高性能なベクトルデータ管理システムが開発されている.その傾向に伴い,システムの主要な機能の1つである近似最近傍探索(ANNS)問題が注目を集めている.本論文では,各オブジェクトが高次元ベクトルと複数の属性を有する状況を想定し,属性制約のもとでANNSを行う問題に取り組む.この問題は,属性制約を満たすオブジェクトの中から,近似最近傍を探索することを目的とする.これは,標準的な設定ではあるが,属性の完全一致が多く研究されており,部分一致に対応できる手法は少ない.本論文では,部分一致に対応したアプローチを提案し,実世界データを用いた実験により,提案アルゴリズムの優位性を示す. |
| CD-002 |
トピック間の階層構造を活用したニュース記事推薦のフィルターバブル緩和手法の提案
◎瀧口 諒久・峯 恒憲・荒川 豊(九州大学)
×
CD-002トピック間の階層構造を活用したニュース記事推薦のフィルターバブル緩和手法の提案
◎瀧口 諒久・峯 恒憲・荒川 豊(九州大学)
ニュース推薦システムは,情報閲覧においてユーザー体験向上に貢献する一方,既存の興味を過度に強化しフィルターバブルを形成する危険性をはらんでいる.本研究では,大規模ニュースデータセットMINDに対し,トピックモデルBERTopicを用いて得られたデンドログラムからユーザーの興味トピックと同一の親を持つ「兄弟トピック」を特定し,これを活用した,クリック履歴に過度に依存せず関連性と多様性のバランスを保った推薦手法を提案する.本稿ではこのアプローチの理論的背景と実装詳細を述べ,フィルターバブル緩和への実践的な有効性を論じる. |
| CD-003 |
異なる価値観への自然な接触を促進する情報推薦手法の検討
◎安田 凌真・原田 史子・島川 博光(立命館大学)
×
CD-003異なる価値観への自然な接触を促進する情報推薦手法の検討
◎安田 凌真・原田 史子・島川 博光(立命館大学)
SNSなどの情報推薦システムは、ユーザに合致した情報を優先的に提示する一方で、異なる価値観に触れる機会を損なわせる懸念がある。本研究では、ユーザが異なる視点に自然に触れ、拒否感なく受け入れやすくなる情報提示の手法を提案する。国内外に関する情報の影響度や簡潔さ等の複数の観点から推薦方法を工夫し、その有効性を定量的に評価する。多様な意見に対する接触機会の拡大と心理的抵抗の低減を両立することで、分断の緩和や対話の促進につながる情報推薦の実現を目指す。 |
| 性能最適化 |
|
9月3日(水) 15:30-17:30 3e会場
座長 本田 巧(富士通株式会社) |
| C-001 |
ランサムウェア対策に向けたストレージシステムのRedirect on Write Snapshot方式の提案と評価
◎山賀 祐典・松下 貴記・出口 彰(日立製作所)
×
C-001ランサムウェア対策に向けたストレージシステムのRedirect on Write Snapshot方式の提案と評価
◎山賀 祐典・松下 貴記・出口 彰(日立製作所)
数年前から、ランサムウエアによるセキュリティ被害が増加しており、データ損失被害を抑えるためにはバックアップ頻度を増やすことが有効である。ストレージ格納データのバックアップには、データを論理的に高速複製可能なSnapshot機能が利用される。一般的なRedirect on Write (RoW) Snapshot方式では、データ格納位置を管理する制御情報がツリー構造である。バックアップ頻度増加により、Snapshotの世代数が増加すると制御情報が多段になり、データアクセス性能が低下する問題がある。本研究では、制御情報をデータ格納位置が即座に求まるテーブル構造で管理し、複製時に制御情報をコピーして世代毎に個々に持つことで、世代数非依存のRoW方式を提案する。評価の結果、世代数が増加しても性能維持できることを確認した。本稿では、提案方式と評価について説明する。 |
| C-002 |
スケールアウト型ストレージにおけるスナップショットのノード間移行手法の提案
○佐藤 賢太・山賀 祐典・松下 貴記・出口 彰(日立製作所)
×
C-002スケールアウト型ストレージにおけるスナップショットのノード間移行手法の提案
○佐藤 賢太・山賀 祐典・松下 貴記・出口 彰(日立製作所)
近年、複数ノードをクラスタ化するスケールアウト型のアーキテクチャを採用するストレージ製品が増えている。このようなアーキテクチャでは、記憶容量や負荷の平準化のために、ノード間でボリュームやそのスナップショットを移行するリバランスが不可欠である。スナップショットは、ノード内の作成元ボリュームや他のスナップショットとデータを共有することで、消費する記憶容量を削減している。そのため、ノード間の移行ではデータの共有関係が失われ、容量消費が増加する問題が生じる。本研究では、移行時にスナップショットのデータ共有関係を特定し、移行先ノードで再構築することで、容量消費の増加を防ぐ移行手法を提案する。 |
| C-003 |
製造装置向け簡易シミュレーション環境構築技術
◎内海 力郎・大貫 智洋(三菱電機)
×
C-003製造装置向け簡易シミュレーション環境構築技術
◎内海 力郎・大貫 智洋(三菱電機)
製造装置ではPLC(Programmable Logic Controller)とメカ(物理的な機構や応答システム)が相互に連携することで一連の動作を実行する場合が多い。このような構成の装置で、全体の動きをシミュレーションするにはPLCとメカ、双方のシミュレーションが不可欠である。PLCシミュレーションはメーカー各社が提供するソフトで比較的容易に実施できる一方、メカ側のシミュレーションは一般的に実行コストが高いことが課題である。そこで、本発表ではPLCから収集したログデータに基づきメカ側の応答パターンを分析し、そのタイミングシミュレーションを自動構築する手法を提案する。 |
| C-004 |
ドライブ増設を考慮した分散RAIDのデータ配置手法の提案と評価
○藤井 裕大・千葉 武尊・大平 良徳・出口 彰(日立製作所)
×
C-004ドライブ増設を考慮した分散RAIDのデータ配置手法の提案と評価
○藤井 裕大・千葉 武尊・大平 良徳・出口 彰(日立製作所)
近年ストレージシステムにおいて、SSD大容量化に伴うドライブ障害時のデータリビルド時間の長期化が問題となっており、分散RAID技術が着目されている。分散RAIDではリビルド高速化のため、ドライブ間でデータを高効率に分散して配置することが重要である。しかし、高効率なデータ配置は分散RAIDを構成するドライブ台数毎に異なるため、容量増設によるドライブ数変化時に、大量のデータ再配置が必要となった。そこで本研究では、高効率分散と容量増設時のデータ再配置量の低減を両立するデータ配置手法を提案した。具体的には、N台のドライブで構成した際のデータ配置を基に、ドライブ増設前後のデータ配置差分が最小となるN+1台構成のデータ配置を乱数を用いて多数生成し、最も分散効率の高い配置を採用する。これを繰り返し適用することでデータ配置を決定する。本手法により生成したデータ配置をリビルド性能によって評価した。 |
| C-005 |
ストレージシステムのリモートコピー機能におけるスケールアウト化手法の提案と評価
○原 彬大・出口 彰・山本 大輔(日立製作所)
×
C-005ストレージシステムのリモートコピー機能におけるスケールアウト化手法の提案と評価
○原 彬大・出口 彰・山本 大輔(日立製作所)
災害対策のためにストレージシステムは、ホストからの書き込みと非同期で別拠点へとデータをコピーするリモートコピー機能を提供してきた。
リモートコピー機能は、データを別拠点に転送する際にホストからの書き込み順序を保つことでデータの整合性を維持している。
近年、小構成で構築し必要に合わせて拡充していくスモールスタートな運用が増えている。このため、大規模なシステムにおいては各拠点においてデータを複数台のストレージシステムに分散して格納することが一般的となってきた。
そこで、本研究はデータが複数のストレージシステムに分散している場合でもデータの整合性を保つリモートコピー機能の実現を目的とした。
本稿では、定期的に全ストレージシステムのホストからの書き込みを停止し、データの同期点を作成することでデータの更新順序を保証し整合性を維持する方式を提案し、書き込み停止による影響をモデル化し評価した。 |
| C-006 |
画像処理用NoCにおけるパケット伝送路の高効率化
◎秋山 佳菜・門田 龍弥・近藤 真史(岡山理科大学)
×
C-006画像処理用NoCにおけるパケット伝送路の高効率化
◎秋山 佳菜・門田 龍弥・近藤 真史(岡山理科大学)
Network on Chip(NoC)を応用し,格子状に配置されたコアへ割り当てた画素値を螺旋状のパケットルーティングに基づいて伝搬・演算することにより,高速な画像処理を実現する手法を提案している.これに基づいたNoC回路のFPGA実装には,画素数分のルータとコアを配置する必要があるが,パケット伝送を担うルータ間のバス幅が広く,FPGA上の配線制約に起因して回路面積が著しく増大する可能性がある.そこで本研究では,ルータ間のパケット伝送に時分割処理を導入してバス幅の削減を図る.具体的には,単一の全加算器のみを用いた直列演算器によりシリアル通信で伝搬を行う手法を提案し,HDLによる設計を通じて所望の動作を確認した. |
| エッジAI |
|
9月4日(木) 9:30-12:00 4c会場
座長 栗原 康志(富士通株式会社) |
| C-007 |
エッジAIによるResNetの高速化手法の提案
◎杼森 雄己・中西 知嘉子(大阪工業大学)
×
C-007エッジAIによるResNetの高速化手法の提案
◎杼森 雄己・中西 知嘉子(大阪工業大学)
近年、AIの発展により、インターネットを介さずに処理を行うエッジAI注目されている。本研究では、エッジデバイスであるSoC FPGAボードであるUltra96v2上でResNet50を高速に動作させる手法を提案する。先行研究ではデータ整形簡単化のため、畳み込み層の入力データをCPUからFPGAに1列ずつ処理していた。そのため、回路起動回数が多く、処理時間の増加につながっていた。そこで、本研究ではカーネルサイズ1×1・ストライド1の畳み込み層に注目し、1回あたりのデータ転送量を増加させることで回路起動回数を削減し、処理の高速化を図る。今後は他のカーネルサイズ・ストライド構成への適用を検討する。 |
| C-008 |
エッジAIによるYOLOXの動作高速化の検討
◎池田 才慈・中西 知嘉子(大阪工業大学)
×
C-008エッジAIによるYOLOXの動作高速化の検討
◎池田 才慈・中西 知嘉子(大阪工業大学)
近年、IoT技術の進展に伴い、通信遅延の解消やリアルタイム性向上を可能にするエッジコンピューティングが注目されている。本研究では、エッジデバイス上で画像AIを高精度かつ高速に動作させることを目的とする。エッジデバイスとしてAvnet社のSoC FPGAボードUltra96-V2を用い、CPUによるソフトウェア処理とFPGAによるハードウェア処理を組み合わせて推論時間の短縮を図った。YOLOX-sのConcatenate層を共有メモリを利用した処理を行うことで、出力データの再利用範囲を拡大し、処理効率を向上させた。また、出力用配列の初期化処理の削減によりさらなる高速化を検討した。 |
| C-009 |
SoC FPGAに向けたYOLOX_sモデルの量子化と精度比較
◎岩永 大翔・中西 知嘉子(大阪工業大学)
×
C-009SoC FPGAに向けたYOLOX_sモデルの量子化と精度比較
◎岩永 大翔・中西 知嘉子(大阪工業大学)
近年、モデルの小型化や処理効率の向上を目的として量子化技術が注目されており、本研究ではその導入が検出精度にどのような影響を与えるかに着目した。物体検出モデル YOLOX-S に対して INT8 量子化を実施し、C++ AI 推論ライブラリである Ceras 上で推論することで、ハードウェア実装を想定した際にどれだけの精度劣化が起きるかの検証を可能にした。浮動小数点(FP32)モデルと量子化モデル(INT8)を COCO データセットを用いて比較し、mAP(mean Average Precision)に基づいて量子化による精度を評価した。 |
| C-010 |
SoC FPGAを用いたMoveNetの高速化
◎鎌倉 生昇・中西 知嘉子(大阪工業大学)
×
C-010SoC FPGAを用いたMoveNetの高速化
◎鎌倉 生昇・中西 知嘉子(大阪工業大学)
近年,AI技術の進展により,推論処理をエッジデバイスで行うエッジAIが注目されている.しかし,エッジデバイスは低コストゆえに性能が限られており,速度と精度のトレードオフが課題となる.本研究では,ソフトウェアとハードウェアの協調動作により,精度を維持しつつ高速化を図ることを目的とする.デバイスにはSoC FPGAボードであるUltra96-V2を,AIモデルにはGoogleが2021年に発表したMoveNetを採用した.回路生成には高位合成を使用し,開発期間を短縮した.回路で動作可能な処理を増加させることで,ソフトウェアとハードウェア間のデータ共有時間を削減し,高速化を図る. |
| C-011 |
量子化推論におけるスケール整合を支援するハードウェア向け補助ツールの開発
◎石見 蒼汰・中西 知嘉子(大阪工業大学)
×
C-011量子化推論におけるスケール整合を支援するハードウェア向け補助ツールの開発
◎石見 蒼汰・中西 知嘉子(大阪工業大学)
我々は,エッジAIの高速化手法として,SoC FPGAを用い,回路とCPUを協調動作させることで推論処理の高速化を実現している.本研究は,量子化推論をハードウェアで効率的に実行するための補助ツールの開発を目的とする.量子化では層ごとのスケール不一致によって生じる頻繁な型変換を回避するため,ネットワーク構造を解析し,層間のスケール差を調整する情報をモデル構造に付加することで,整数演算のみで推論処理が進行可能となるよう支援する. |
| C-012 |
ResNetのエッジデバイス上での動作高速化手法の検討
◎岡本 遥仁・中西 知嘉子(大阪工業大学)
×
C-012ResNetのエッジデバイス上での動作高速化手法の検討
◎岡本 遥仁・中西 知嘉子(大阪工業大学)
エッジAIは、通信遅延の低減やセキュリティ面での利点から、近年注目を集めている。一方で、デバイス性能が低く、高精度なAIの処理を高速に実行するには課題がある。そこで本研究では、エッジデバイス上で高精度AIモデルの精度を維持しつつ、推論処理の高速化を図る手法を提案する。具体的には、ResNetを対象モデルとし、CPUとFPGAが同一チップ上に搭載されたFPGAボードUltra96v2を用いて、演算回路およびソフトウェア処理の最適化を実施した。特に本研究では、これまでCPUで実行していたパディング処理をハードウェア回路として実装することで、畳み込み演算の前処理段階の高速化を目指した。 |
| C-013 |
エッジ推論高速化のためのモデル構造最適化と協調動作支援ツールの開発
◎野村 美月・中西 知嘉子(大阪工業大学)
×
C-013エッジ推論高速化のためのモデル構造最適化と協調動作支援ツールの開発
◎野村 美月・中西 知嘉子(大阪工業大学)
我々は,エッジデバイス上での推論処理の高速化を目的とし,SoC FPGAを用いた回路とCPUの協調動作によって,処理性能の向上を実現している.本研究は,量子化推論をハードウェア上で効率的に動作させるための支援ツールの開発を目的とする.モデルのネットワーク構造を解析し,ハードウェア構成を考慮した層の融合や削除によって,モデルの簡単化を行う.また,従来のモデルからは得られないハードウェア実行に有利な情報をモデルに付加することで,回路とCPUの協調動作を支援する.また,協調動作に使用するメモリの管理情報をモデルに付加し,複数の層に関与するメモリ領域の管理を行う機能を持たせることで,高速化を支援する. |
| システム・LSI・アーキテクチャ |
|
9月4日(木) 15:30-17:30 5c会場
座長 今川 隆司(福井大学) |
| C-014 |
ViTのFPGA実装に向けた活性化関数GELUの軽量化
◎土橋 尚弥・黒木 修隆・沼 昌宏(神戸大学)
×
C-014ViTのFPGA実装に向けた活性化関数GELUの軽量化
◎土橋 尚弥・黒木 修隆・沼 昌宏(神戸大学)
画像認識モデルViTのFPGA実装に向けた軽量化とそれによる精度低下の抑制を目的として,活性化関数GELUの近似手法を提案する。提案手法では,2のべき乗の利用や区分的に線形近似を行うことで乗算をシフト演算に置き換え,必要なFPGAリソース数を削減する。さらに,学習途中で関数を変更することで精度の低下を抑制する。提案手法PLGELUをViT-Tinyに適用した結果,従来手法と比較して認識精度の低下を0.22 ptに抑制し,また段階的な関数変更により最大4.74 ptの精度低下抑制効果を確認した。さらに,リソース数評価のために活性化関数層のハードウェア設計を行った結果,LUT,FF,DSPをいずれも90% 以上削減し,演算サイクル数を1/4以下にできることを確認した。 |
| C-015 |
Separable畳み込みを用いた環境音認識モデルの軽量化
◎福岡 直樹・黒木 修隆・沼 昌宏(神戸大学)
×
C-015Separable畳み込みを用いた環境音認識モデルの軽量化
◎福岡 直樹・黒木 修隆・沼 昌宏(神戸大学)
FPGA実装に適した環境音認識モデルの構築を目的として,Separable畳み込みの利用によってパラメータ数および計算量の削減を図る軽量化手法を提案する。また,軽量化にともなう精度低下の抑制を目的として,Multi-Branch構造と再パラメータ化の適用を行う。提案手法を評価した結果,従来手法と比較して精度低下を最低で1.5 pt程度に抑えつつ,パラメータ数を約88%,計算量を約84% 削減可能であることを確認した。 |
| C-016 |
TinyLLaMAの推論におけるTensorRT-LLMを用いた高速化
◎岡本 航太朗・吉田 明正(明治大学)
×
C-016TinyLLaMAの推論におけるTensorRT-LLMを用いた高速化
◎岡本 航太朗・吉田 明正(明治大学)
大規模言語モデルを用いた推論において,TensorRT-LLMによる高速化が広く行われている.TensorRT-LLMは,LLMの学習済みモデルに対して,低精度演算,レイアウト最適化,カーネル融合を行うことにより,推論時間の短縮が可能になる.本研究では,大規模言語モデルの中でもローカルLLMとして用いられるTinyLLaMAを取り上げ,TensorRT-LLMにより,学習済みモデルをONNX形式,TensorRTエンジン形式に変換し,TensorRTランタイムで実行する.この結果,GPUにおける推論が高速化され,かつ,デバイスメモリの使用量の削減が可能になる.本性能評価では,NVIDIAのGPUにおいて,推論時間,メモリ使用量,精度を測定し,LLMの高速化の有効性を確認した. |
| C-017 |
準同型暗号を用いた残差ネットワークの並列処理
◎地引 壮悟・吉田 明正(明治大学)
×
C-017準同型暗号を用いた残差ネットワークの並列処理
◎地引 壮悟・吉田 明正(明治大学)
準同型暗号は,暗号化したデータを復号せず,暗号化したまま加算や乗算ができる暗号方式である.この特性を活かして,機密データを暗号化したまま扱うことができ,機械学習への応用が研究されている.画像分類の分野では,従来のCNNに残差接続を組み込んだ残差ネットワークがよく使用されている.本稿では,残差ネットワークの推論処理をC++実装し,Microsoft SEALライブラリで準同型暗号化を行い,そのコードにOpenMPによる並列処理を適用することで性能向上を図った.32コアのXeon Platinum上で,MNISTデータセットを用いて行った性能評価の結果,準同型暗号化した残差ネットワークの推論時間は短縮され,提案手法の有効性が確認された. |
| C-018 |
マイクロ波伝送線路フィルタのMLPによる代替モデルに関する検討
◎細川 皓平・竹沢 恵・松﨑 博季・真田 博文(北海道科学大学)
×
C-018マイクロ波伝送線路フィルタのMLPによる代替モデルに関する検討
◎細川 皓平・竹沢 恵・松﨑 博季・真田 博文(北海道科学大学)
伝送線路フィルタは高周波通信システムにおいて重要な役割を果たすが、その設計には専門的知識と多大な試行錯誤が必要とされる。本研究では、多層パーセプトロン(MLP)を用いた代替モデルを構築し、構造パラメータから周波数特性の予測を試みた。電磁界シミュレーションから構成した学習データにより、高い精度で特性を再現可能であることを確認し、設計における迅速な評価支援手法としての有効性を示す。 |
| C-019 |
異常検知における精度向上の研究・先行研究で精度が低かったカテゴリへの適応
○芝 涼佑・中西 知嘉子(大阪工業大学)
×
C-019異常検知における精度向上の研究・先行研究で精度が低かったカテゴリへの適応
○芝 涼佑・中西 知嘉子(大阪工業大学)
本研究では、異常検知手法の精度向上を目的として、MVTec-ADデータセットの中でも先行研究にて精度が低かった「Screw」カテゴリに着目した。物体の向きを統一して学習画像を構成することで、PatchCoreおよび本研究室が提案する高速手法(MRMG)の双方で精度向上が確認された。特にPatchCoreでは、局所特徴の比較により向きの影響を受けにくく、MRMGでは特徴のばらつきに規則性が生じたことが効果的に働いたと考えられる。今後は物体の向きや大きさをより高精度に統一し、ロバストな特徴抽出手法を導入することで、さらなる精度向上が期待される。 |
| RECONF/EMB |
|
9月5日(金) 9:30-12:00 6d会場
座長 長名 保範(熊本大学) |
| C-020 |
空調設備点検用自動無線計測システムの試作
◎竹内 勇人・田中 康一郎(九州産業大学)
×
C-020空調設備点検用自動無線計測システムの試作
◎竹内 勇人・田中 康一郎(九州産業大学)
本研究の目的は、風速や気温、湿度を自動で測定し、測定値を閲覧できるシステムを開発することで、空調設備の点検作業を効率化することである。Wi-Fi と風速・温湿度センサを活用し、通信状況や温度・湿度の変化の特徴を調査・把握することで、点検作業効率化の基盤を構築することを目指す。空調に設置可能で、自動で風速や温湿度を測定できるIoT 機器と、測定値を記録し、閲覧できるシステムの試作を行う。特に、風速については、専門の空調業者が実際に使用している携帯型風速計の測定値と比較して、誤差を許容範囲内に抑えることを目標する。これらの取り組みにより、空調設備のメンテナンス作業の効率化に貢献することを期待している。 |
| C-021 |
天井高と空気循環を考慮したCO2濃度制御の検討
◎青柳 貴之・田中 康一郎(九州産業大学)
×
C-021天井高と空気循環を考慮したCO2濃度制御の検討
◎青柳 貴之・田中 康一郎(九州産業大学)
教室のような閉鎖空間においてCO2濃度の上昇が学習効率や健康に及ぼす影響が懸念されている。本研究では、CO2センサおよび温度・気圧センサを用いて、ドーム型室内空間の環境を測定し、CO2濃度の可視化とその傾向分析を行っている。得られたデータは、過去に他教室で収集された環境データと比較し、天井高や換気手段の違いがCO2濃度に与える影響を評価している。分析の結果、CO2は室内の上部に滞留しやすく、室温が低下すると降下する傾向が確認された。また、天井が低い空間ではCO2濃度が高まりやすいことも明らかとなった。閉鎖空間におけるCO2濃度の実態把握に加え、センサ設置位置の検証を行い、安全な室内環境の実現に向けた有効な手法を検討する。 |
| C-022 |
人工衛星向け組込みソフトウェアアーキテクチャの検討
○荻野 慎平・加藤 寿和・平山 芳和(三菱電機)
×
C-022人工衛星向け組込みソフトウェアアーキテクチャの検討
○荻野 慎平・加藤 寿和・平山 芳和(三菱電機)
近年、人工衛星に対する顧客の要求は、高機能・高性能化や運用の自動化など、ますます多様化・高度化している。
人工衛星の制御は主にソフトウェアによって実現されており、これらの要求の増加はソフトウェアの規模拡大を招いている。
また、三菱電機が製造する人工衛星では、複数のソフトウェアが1つの統合制御計算機に組み込まれており、要求の変更が複数のソフトウェアに波及するという課題が存在していた。
本論文では、この課題を解決し、スケーラビリティを向上させるためにソフトウェアアーキテクチャを刷新した結果について報告する。 |
| C-023 |
2DLiDARと物体検出技術を統合した自律走行ロボットの設計
◎坂 隆希・中西 知嘉子(大阪工業大学)
×
C-0232DLiDARと物体検出技術を統合した自律走行ロボットの設計
◎坂 隆希・中西 知嘉子(大阪工業大学)
本研究では,Jetson Orin Nanoを搭載したAIロボットカー「ROSMASTER X3」を用いて,2D LiDARと物体検出技術「YOLOv8」を組み合わせた自律走行ロボットシステムの設計を行った.即席で構成したペットボトルのコースを走行対象とし,カメラ映像からYOLOv8でペットボトルを検出し,その位置から角度を算出した.さらに,2D LiDARにより対象物までの距離を取得し,2本のペットボトルの中央を通過するように進行方向を決定した.カメラとLiDARの角度情報を統合することで,リアルタイムな障害物認識と進路決定を可能にし,マッピング不要な即時走行を実現した. |
| C-024 |
FPGA上での暗号処理の効率的な実装と性能比較
◎森田 慧一・八槇 博史(東京電機大学)
×
C-024FPGA上での暗号処理の効率的な実装と性能比較
◎森田 慧一・八槇 博史(東京電機大学)
FPGA(Field-Programmable Gate Array)は、アクセラレータとして電力効率に優れている。本研究では、Data Encryption Standard(DES)を例にして、暗号処理の実装の効率化と他アクセラレータとの性能比較を行う。 |
| C-025 |
区分線形近似手法による非線形素子の高速化を用いたFPGA実装による電子回路シミュレータの初期評価
◎大本 裕真・弘中 哲夫(広島市立大学)
×
C-025区分線形近似手法による非線形素子の高速化を用いたFPGA実装による電子回路シミュレータの初期評価
◎大本 裕真・弘中 哲夫(広島市立大学)
組み込みシステムの開発では,実機の試作なしで性能を評価し,かつ実機に近い挙動を再現できる高速なシミュレーション技術が求められている.FPGA上にSPICEシミュレータを搭載し,非線形素子を含む回路の過渡解析を行う場合,解析負荷が増大がシミュレーションの高速化が大きな課題となる.
本論文ではボトルネックとなる非線形素子(ダイオードやBJT)のスタンプ処理に着目し,区分線形近似を導入することでFPGA上での高速化を図った.提案手法を実装・評価した結果,従来の指数関数演算を用いるスタンプ手法と比較して,ダイオードで最大約2.6倍,BJTで約1.7倍の高速化を達成できることを確認した. |
| DC/EMB |
|
9月5日(金) 13:10-15:40 7d会場
座長 川上 健(株式会社 東芝) |
| C-026 |
Real-Time Linuxによる定周期処理の精度向上
○内田 修平・玉田 竜一(富士電機)
×
C-026Real-Time Linuxによる定周期処理の精度向上
○内田 修平・玉田 竜一(富士電機)
マイコンの高性能化に伴い組込機器は高機能化が求められ、ソフトウェアは大規模の一途を辿っている。そこで、開発効率の向上を狙って豊富なミドルウェアを備えるLinuxの採用が増えているが、RTOSと違いLinuxは制約の時間内に処理を完了するように設計されていない。このため、タスクの切り替えが発生する定周期処理の周期にはバラつきが生じ、高速な周期でデータを収集する上で問題となる。
本稿では、この問題解決に対し、リアルタイム性能を向上したReal-Time Linuxの定周期処理の間隔と精度について測定し、その有効性を評価したので報告する。 |
| C-027 |
ベアメタルからRTOS対応ソフトウェアへの移行設計手法
◎奥村 彩花・澤田 孝雄・玉田 竜一(富士電機)
×
C-027ベアメタルからRTOS対応ソフトウェアへの移行設計手法
◎奥村 彩花・澤田 孝雄・玉田 竜一(富士電機)
近年の組込機器のIoT化に伴い、従来はベアメタル(OS未搭載)でソフトウェアを実装していた組込機器にも、ネットワーク機能等の高機能化が求められている。特に、非同期で動作するネットワーク機能はタイミング制御設計が複雑となるため、RTOSを導入することで設計容易化だけではなく保守性や拡張性の向上を図ることができる。一方で、ベアメタル開発していた開発者にとっては、RTOS導入に伴うソフトウェア設計の変更や新たな設計手法の習得が大きな課題となる。
本稿では、ベアメタルからRTOSへの移行に伴う課題を整理し、RTOS適用の判断基準と効果的な移行設計手法を報告する。 |
| C-028 |
避難所での利用を想定したThread通信によるRSSIを用いた距離推定の検討
◎片倉 寛人・中川 泰宏(千葉工業大学)
×
C-028避難所での利用を想定したThread通信によるRSSIを用いた距離推定の検討
◎片倉 寛人・中川 泰宏(千葉工業大学)
大規模災害時の避難所では、多くの人が集まり誰がどこにいるのか把握することが困難である。また、避難所特有のストレスや環境変化により高齢者らは体調を崩しやすく、巡回医による頻繁な健康チェックを行うことが難しい。したがって、高齢者らの健康状態をリアルタイムで把握するとともに、緊急時にその居場所を即座に特定できるスマートバンドの着用が望まれると考える。本研究では、災害時の避難所においてスマートバンドを用いて体調悪化者を早期に発見することを目的としている。本稿では、省電力かつセキュアなThreadプロトコルを用い、避難所環境を想定したRSSIによる距離推定について検討した結果を報告する。 |
| C-029 |
CPUリソース配分による車載インフォテインメントシステムのQoS改善法
◎服部 匠・兪 明連(東京都市大学)
×
C-029CPUリソース配分による車載インフォテインメントシステムのQoS改善法
◎服部 匠・兪 明連(東京都市大学)
近年、自動車業界では、自動車の状態に関する情報(制御系メッセージ)や、映像や音声などのエンターテインメント(情報系メッセージ)の両方が提供できる車載インフォテインメントシステムが求められている。本論文では、これらメッセージを、マルチコアプロセッサを搭載した組込みコンピュータ上で制御系メッセージのリアルタイム性を損なわずに扱う手法を提案する。 |
| C-030 |
緊急/平時デュアルコンテキスト判定のためのセンサフユージョンによる2段階判定モデルの開発
◎佐藤 博正・原田 史子・島川 博光(立命館大学)
×
C-030緊急/平時デュアルコンテキスト判定のためのセンサフユージョンによる2段階判定モデルの開発
◎佐藤 博正・原田 史子・島川 博光(立命館大学)
本研究では、複数のセンサデータに2段階の機械学習モデルを適用して、人間の緊急的な状態(コンテキスト)および平常的な状態双方を判定する分析モデルを開発する。人間がどこで何をしていてどう感じているのかを観測するために、位置情報、加速度、温度、接触判定、睡眠情報などの複数データを用いる。1段階目は短期のデータを、加速度センサを搭載したエッジ上で即時的に分析し、緊急性のある状態を判定する。2段階目は長期のデータをサーバ上でクラスタリング分析し、人間の状態や意欲を判定する。これにより、産業面では、労働意欲や疲労度確認と緊急対応の双方ができ、働き方改革に貢献する。生活面では、TPOの切り分けが可能になる。 |
| C-031 |
二値化ニューラルネットワークの重み故障による認識精度への影響
○三浦 幸也・澤畠 陸(東京都立大学)
×
C-031二値化ニューラルネットワークの重み故障による認識精度への影響
○三浦 幸也・澤畠 陸(東京都立大学)
Binarized neural networks have been proposed as a lightweight network for implementing neural networks in hardware. Although neural networks are known to be fault-tolerant, however, hardware is susceptible to physical faults and soft errors. In this paper, we assume that stuck-at faults cause the change in weights of neurons, and investigate the effect of these on the recognition accuracy of both standard neural networks and binarized neural networks. Experimental results show that the binarized neural network has a smaller decrease in recognition accuracy than a standard neural network. Therefore, the binarized neural network has an advantage over the standard neural network even if there are faults in the weights of neurons. |