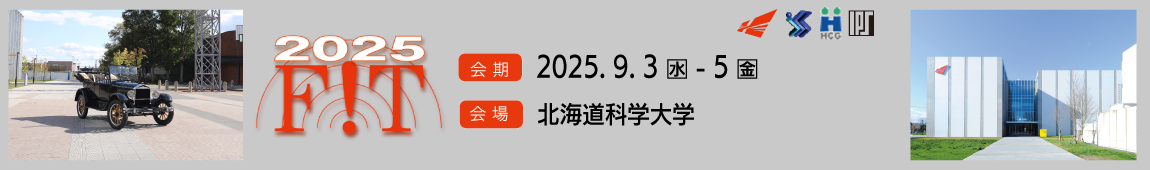| M分野 ユビキタス・モバイルコンピューティング |
選奨セッション
人物検出と自動運転 |
|
9月3日(水) 9:30-12:00 1m会場
座長 勝間 亮(大阪公立大学)
齊藤 義仰(岩手県立大学) |
| CM-001 |
庫内作業員を対象としたトラッキングによる検出漏れ抽出に基づくMLOpsの運用評価
◎加納 一馬・森 裕輝・片山 晋・浦野 健太・米澤 拓郎・河口 信夫(名古屋大学)
×
CM-001庫内作業員を対象としたトラッキングによる検出漏れ抽出に基づくMLOpsの運用評価
◎加納 一馬・森 裕輝・片山 晋・浦野 健太・米澤 拓郎・河口 信夫(名古屋大学)
深層学習技術の進展によってカメラを用いた人物検出の精度が向上し,様々な産業現場で生産性の向上を目的とした作業分析への応用が期待されている.しかし,特に長期の運用においては,偶発的な事象や経時的な変化によって訓練データにない状況が生じ,モデルが十分に機能しない場合がある.モデルの性能を継続的に維持・改善するには,再学習や検証を含む一連のサイクルを円滑化するMLOpsが有効である.本研究では,トラッキング結果に基づいて検出漏れのあるフレームを自動的に抽出し,それらを優先的にモデルの学習に利用して効果的な性能向上を図る.物流倉庫の作業員を対象としたMLOpsを構築し,実運用を通して本システムの有効性を検証した. |
| CM-002 |
SRv6 Mobile User Planeを併用するマルチバンド冗長化5G V2N2Vのフィールド実験
○三上 学(ソフトバンク)・中里 仁(東京理科大学)
×
CM-002SRv6 Mobile User Planeを併用するマルチバンド冗長化5G V2N2Vのフィールド実験
○三上 学(ソフトバンク)・中里 仁(東京理科大学)
持続可能な地域交通サービス実現に向け,自動運転BRTの隊列走行が注目されており,隊列走行では高信頼・低遅延な車車間通信が不可欠である.我々は携帯電話網を介した車車間通信であるV2N2Vについて,同一携帯電話事業者が運用する異なる複数周波数帯を同時利用するマルチバンド冗長通信による高信頼化技術及びSegment Routing over IPv6を応用したMobile User Plane であるSRv6 MUPによる低遅延化技術の検討を進めている.本稿では, 自動運転BRT隊列走行への応用を想定したSRv6 MUPを併用するマルチバンド冗長化V2N2Vについてその概要を紹介すると共に実環境における有効性を示す. |
| CM-003 |
(講演取消) |
| CM-004 |
車線レベル地図の作成と車線推定
○高木 里実・金山 雅人・柿沼 篤樹・大橋 純・加藤 圭志・三浦 庸平(本田技研工業)
×
CM-004車線レベル地図の作成と車線推定
○高木 里実・金山 雅人・柿沼 篤樹・大橋 純・加藤 圭志・三浦 庸平(本田技研工業)
自動運転車の普及に先駆けて,現行車のフローティングカーデータによる詳細位置情報サービスを実現するため,カメラのない現行車が送信するデータで車線推定を行う.OpenStreetMapの座標から,相対誤差0.48m(車線推定レベル)の車線中心線を作成し,電離層遅延や衛星補足数変化によるGPS誤差を補正,作成した車線中心線へのマップマッチングを行うことで,直線に近い区間で90%の車線正解率を実現した. |
| IoT・ネットワーク基盤技術 |
|
9月3日(水) 13:10-15:10 2v会場
座長 石田 繁巳(公立はこだて未来大学) |
| M-001 |
IoTブロックチェーン仮想座標系の実装と評価
◎越川 幸輝・Su Yue(千葉大学)・Jong-Deok Kim・Won-Joo Hwang(Pusan National University)・グエン キエン・関屋 大雄(千葉大学)
×
M-001IoTブロックチェーン仮想座標系の実装と評価
◎越川 幸輝・Su Yue(千葉大学)・Jong-Deok Kim・Won-Joo Hwang(Pusan National University)・グエン キエン・関屋 大雄(千葉大学)
ブロックチェーンと IoT (Internet of Things) と組み合わせた IoT ブロックチェーンは IoT の信頼性やセキュリティを向上させる技術として期待されている。ネットワークが巨大化するとトランザクション、ブロック送信に遠距離の往復が生じ、長い伝搬遅延が問題となる。近隣ノード同士がピアとして接続するため、ノードの位置推定を行う必要がある。本研究ではヴィヴァルディアルゴリズムを使用し、プライベートイーサリアムで位置推定を行うシステムの設計方法を与える。40 ノードのエミュレーション環境で、相対誤差 0.1 を達成し、ノード位置推定の妥当性が示された。 |
| M-002 |
Investigating Workloads of Broker Account in BrokerChain-based Sharding IoT-Blockchain
◎蘇 悦・向 陽・ぐえん きえん・関屋 大雄(千葉大学)
×
M-002Investigating Workloads of Broker Account in BrokerChain-based Sharding IoT-Blockchain
◎蘇 悦・向 陽・ぐえん きえん・関屋 大雄(千葉大学)
We investigated the load distribution of Broker accounts in sharding IoT-Blockchain systems. By emulating payment scenarios with BlockEmulator platform and Ethereum historical data, we explored how Brokers handle cross-shard transactions (CTXs). The results reveal an imbalance workload distribution, where a small number of Brokers process most CTXs. This imbalance, are named as the “hot broker” problem, exposes limitations in Broker mechanism and underscores the importance of designing more balanced and scalable solutions. |
| M-003 |
カメラと低消費電力エッジデバイスによるゴミ自動検出システムの評価
◎阿部 竜弥・富田 紘健・本間 翔太・鈴木 秀和(名城大学)
×
M-003カメラと低消費電力エッジデバイスによるゴミ自動検出システムの評価
◎阿部 竜弥・富田 紘健・本間 翔太・鈴木 秀和(名城大学)
ゴミ集積所におけるゴミの滞留状況のデータは,地域住民からのゴミに関する問い合わせへの対応時間の短縮や,ゴミ回収業務の効率化など,自治体やゴミ回収事業者にとって様々な利活用の可能性がある.筆者らは,ゴミ集積所にカメラ付きのIoTデバイスを設置し,軽量物体検出アルゴリズムによってゴミ袋を検出することにより,ゴミ集積所におけるゴミの排出および回収時刻を動的に収集するシステムを提案している.本稿では,低消費電力エッジデバイスであるSpresenseにシステムを実装し,消費電力量および処理時間について性能評価を行う. |
| M-004 |
QUIC-CYPHONICにおける経路最適化処理の仕様検討
◎六鹿 太智(名城大学)・内藤 彩乃(愛知工業大学)・鈴木 秀和(名城大学)
×
M-004QUIC-CYPHONICにおける経路最適化処理の仕様検討
◎六鹿 太智(名城大学)・内藤 彩乃(愛知工業大学)・鈴木 秀和(名城大学)
IPv4/IPv6混在環境における通信接続性と移動透過性の同時実現技術として,QUIC-CYPHONIC(QUIC-based CYberPHysical Overlay Network over Internet Communication)が提案されている.この技術では,異なるNAPT配下のデバイス間通信をクラウドサーバ経由で中継することにより接続性を確保しているため,暗号化通信経路の冗長化や中継サーバにおける負荷集中による性能低下が課題となっている.本稿では,QUICのコネクションマイグレーション機能を応用し,初期接続後の暗号化通信経路を中継サーバ経由からエンドツーエンド通信へ動的に切り替える経路最適化手法の仕様を検討する. |
| M-005 |
フィジカル空間とサイバー空間における時空間情報の整合性評価による異常検出の検討
◎本間 翔太・阿部 竜弥・鈴木 秀和(名城大学)
×
M-005フィジカル空間とサイバー空間における時空間情報の整合性評価による異常検出の検討
◎本間 翔太・阿部 竜弥・鈴木 秀和(名城大学)
複数のセンシングデータを高精度な位置・時刻情報でリアルタイムに統合し,未来予測や社会課題解決に活用する基盤の研究が進められている.スマートシティ分野では,フィジカル空間とサイバー空間における時空間情報の不整合が都市のリアルタイム把握やシミュレーション精度の低下,意思決定の遅延を引き起こす課題となっている.この課題はインフラ運用や住民サービスの質に大きな影響を与えるため,両空間の情報同期やデータ連携の高度化が求められている.本稿では,フィジカル空間とサイバー空間の時空間情報の整合性を評価することにより異常を簡易に検出する手法について検討する. |
| モバイル・位置情報・ユーザ行動分析 |
|
9月3日(水) 15:30-17:30 3v会場
座長 深澤 佑介(上智大学) |
| M-006 |
An Experimental Study of Fingerprint-based Localization in 5G Ultra Dense Network
◎Xiang Yang・Su Yue・Nguyen Kien・Sekiya Hiroo(千枼大学)
×
M-006An Experimental Study of Fingerprint-based Localization in 5G Ultra Dense Network
◎Xiang Yang・Su Yue・Nguyen Kien・Sekiya Hiroo(千枼大学)
Fingerprint-based indoor localization using Received Signal Strength Indicator (RSSI) often relies on the K-Nearest Neighbor (KNN) algorithm, which struggles in complex environments due to its inability to correlate RSSI differences with geodistances. The Feature-Scaling-based KNN (FS-KNN) algorithm addresses this by weighting RSSI differences, enhancing accuracy. Yet, the effect of key parameter, RSSI interval granularity, remain underexplored. Leveraging 5G Ultra-Dense Networking (UDN), with its broader RSSI range compared to Wi-Fi, this study evaluates FS-KNN’s performance in both network types. We analyze how RSSI interval setting impact localization accuracy, finding that FS-KNN excels in 5G UDN compared to Wi-Fi. |
| M-007 |
(講演取消) |
| M-008 |
(講演取消) |
| M-009 |
モバイルアプリ上での機械学習による情報整理と検索性向上の試み
◎嶺田 あんず・田中 康一郎(九州産業大学)
×
M-009モバイルアプリ上での機械学習による情報整理と検索性向上の試み
◎嶺田 あんず・田中 康一郎(九州産業大学)
本研究では、スマートフォンアプリにおける情報提供の質向上を目的に、Appleが提供する機械学習フレームワーク「Core ML」と、モデル作成支援ツール「Create ML」を用いて、お知らせ情報の自動分類と整理に取り組んだ。過去のお知らせデータにカテゴリラベルを付与し、テキスト分類モデルを構築。これを大学公認アプリに統合し、お知らせを自動分類して表示する機能を実装した。その上で、分類精度に影響を与える要因としてデータ分布の偏りに注目し、検証を行った。さらに、リリース後も継続的にモデルを改善できるよう、Webを通じて学習データをサーバーに送信し、アプリがそのデータを取得して分類モデルの更新に活用できる仕組みの開発を目指した。 |
| M-010 |
スマホアプリを用いた学内空間利用実態の可視化
◎木村 光翔・田中 康一郎(九州産業大学)
×
M-010スマホアプリを用いた学内空間利用実態の可視化
◎木村 光翔・田中 康一郎(九州産業大学)
大学では、図書館や中庭など学生が利用する空間を提供しているが、その実態を正確に把握する手段は限られている。そこで本研究では、学生が日常的に使用するスマートフォンを活用し、位置情報をもとに動向を取得・分析するアプリを試作した。広範囲にはGPSを、局所的な範囲にはビーコンを使用して高精度な位置情報を取得し、データは学生の同意のもと、学内に限定して収集する。また、プライバシー保護の観点から、手動で停止を忘れた場合にも自動で停止する機能を搭載している。アプリで取得したデータから、施設環境の改善や満足度向上に活用することを目指すとともに、学生の能動的な関与を促進し、環境づくりに貢献することが期待される。 |
| M-011 |
ギター演奏におけるMR技術を用いた弾弦技能育成支援システムの設計
◎加藤 真吾(東北大学)・阿部 亨・菅沼 拓夫(東北大学/東北大学サイバーサイエンスセンター)
×
M-011ギター演奏におけるMR技術を用いた弾弦技能育成支援システムの設計
◎加藤 真吾(東北大学)・阿部 亨・菅沼 拓夫(東北大学/東北大学サイバーサイエンスセンター)
MRを適用した楽器演奏技能の習得支援の試みがこれまで数多くなされている。本研究では特に、ギター演奏の技能習得に着目する。ギター演奏の技能習得支援の先行研究では、コード演奏に特化して、左手の押弦位置の表示や音の正しさを示す方法が多く提案されている。しかし、クラシックギターで必要とされる右手の弾弦の技能習得についてはこれまでほとんど検討されていない。そこで本研究では、鏡のように表示させる機能と右手の動きを記録・再現する機能を搭載したクラシックギターの弾弦技能の習得を支援するMR演奏支援システムを提案する。本発表では、支援システムの支援対象を明確化し、システム構成の基本設計と現在の開発段階について発表する。 |
| コラボレーションとネットワークサービス |
|
9月4日(木) 9:30-12:00 4u会場
座長 磯 和之(東京情報デザイン専門職大学) |
| M-012 |
テキストコミュニケーションにおける褒め方の上手さを推定するモデルの構築と精度分析
◎山野 夏・伊藤 淳子(和歌山大学)
×
M-012テキストコミュニケーションにおける褒め方の上手さを推定するモデルの構築と精度分析
◎山野 夏・伊藤 淳子(和歌山大学)
自己肯定感の低下は,主体性の低下などにつながるとされており,そのためには褒め合う行為が有効であると考えられている.既存研究では対面での褒めを主な対象としているが,対面だけでなくテキスト上のやり取りも一般化している.そこでテキストコミュニケーションにおける褒め方の支援に注目する.この実現には,テキスト会話内の褒め方を評価できる仕組みが前提となるが,いまだ明らかにされていない.このことから,テキストコミュニケーションを対象にした推定モデルを構築する.また,その推定精度を分析し,設定した特徴量の有効性を検証する.結果,比較対象モデルの推定精度を上回らなかったが,重要度の高い特徴量が明らかになった. |
| M-013 |
反対意見の生成により少数派の発言を促す遠隔会議支援システムの開発
◎佐藤 照仁・伊藤 淳子(和歌山大学)
×
M-013反対意見の生成により少数派の発言を促す遠隔会議支援システムの開発
◎佐藤 照仁・伊藤 淳子(和歌山大学)
議論における少数派は,多数派の同調圧力で発言を躊躇する傾向がある.従来の発話支援に関する研究では,個別指示による助言や発言量の可視化が提案されている.しかし,効果の一時性や被験者の非好意的反応が課題として残されている.そこで本研究では,文章生成AIによる反対意見生成機能を実装した遠隔会議システムを提案する.悪魔の代弁者のような役割を文章生成AIが担うことにより,少数派が主体的に発言しやすい環境を構築し,発言量の増加を目指す.提案システムの使用の有無による比較実験の結果,提案システムが少数派の発言時間,発言率の増加に有効であることは確認されなかったが,議論の流れに変化を与えた可能性が示唆された. |
| M-014 |
認識の齟齬を減らすための聞き手に質問行為を促すシステムの提案
○阿野 寛人・伊藤 淳子(和歌山大学)
×
M-014認識の齟齬を減らすための聞き手に質問行為を促すシステムの提案
○阿野 寛人・伊藤 淳子(和歌山大学)
日本語会話において使用される曖昧な表現は,人によって解釈が異なり,ミスコミュニケーションが起こる可能性がある.これまで,話し手に曖昧表現の修正提案を行うシステムが提案されてきたが,曖昧表現の使用頻度は減少せず,話し手に修正させることが会話の阻害につながるという問題も発生した.そこで本研究では,対面の日常会話において,聞き手からの質問によって,曖昧表現に関する認識の齟齬の解消を支援するシステムを提案する.提案システムと関連研究のシステムとの比較実験の結果,会話後の認識の齟齬の数に差があることは確認できなかったが,会話行動を阻害する程度が減少したことが確認された. |
| M-015 |
学習済み音声イベント分類器を用いた音響情報の系列解析に基づく居住空間の状況推定手法
◎湯本 稜矢・和﨑 克己(信州大学)
×
M-015学習済み音声イベント分類器を用いた音響情報の系列解析に基づく居住空間の状況推定手法
◎湯本 稜矢・和﨑 克己(信州大学)
本研究は,住居空間における非侵襲的センシング手法として音声分類を活用し,生活状況の推定を目的とするシステムを構築したものである. YAMNetを用いた音声イベント分類により,音響情報を時間分割・系列化し,状態遷移確率の解析を通じて生活空間の雰囲気推定と危険音検知を行った.雰囲気推定については,状態数,音声カテゴリの出現比率,主要状態に基づき階層的に雰囲気を定義し,言語化したフレーズにより表現する枠組みを構築.YouTube上の動画を音声入力としてモデルを検証し,分類精度や推定される雰囲気の妥当性を確認した.特に,支配的な音響状態とその遷移図が実際の映像と整合することが示され,本手法の実用可能性が実証された. |
| M-016 |
対応不可な状況の提示による非常持ち出し袋作成支援システムの開発
◎石田 大翔・伊藤 淳子(和歌山大学)
×
M-016対応不可な状況の提示による非常持ち出し袋作成支援システムの開発
◎石田 大翔・伊藤 淳子(和歌山大学)
非常持ち出し袋を作成する際,重量制限内で入れる物を適切に選択する必要がある.しかし,非常持ち出し品の種類は膨大で,個人に適した選択をすることが難しい.また,必要な被災状況を見落とす可能性がある.本研究では,ユーザに自身が作成した非常持ち出し袋では対応できない状況を提示することにより,未考慮の状況への気づきを与える非常持ち出し袋作成支援システムを提案する.対応不可な状況を提示しない手法との比較実験の結果,対応不可な状況提示は被験者全員に未考慮の状況への気づきを与えられ,個人に適した非常持ち出し袋を考える助けになることが明らかになった.また,被災状況想像力,自己対応能力の一部の項目が向上した. |
| M-017 |
注文・決済用セルフレジにおけるチュートリアル導入の効果検証
◎丸山 聖也・伊藤 淳子(和歌山大学)
×
M-017注文・決済用セルフレジにおけるチュートリアル導入の効果検証
◎丸山 聖也・伊藤 淳子(和歌山大学)
タッチパネル式のセルフレジを店舗に導⼊する動きがスーパーマーケット等で増えてい
る。しかし、操作画面内に客が即座に操作⽅法を理解できないUIが含まれることにより,
操作に困って操作時間が長くなる状況や,店員が対応しなければならない状況が生じる.
本研究では、システムの利⽤⽅法に関する知識の不⾜が操作や解釈のしづらさを⽣む⼀因
であると仮定し、セルフレジでの商品選択操作に必要となる知識を事前にチュートリアル
形式で提供するセルフレジシステムを提案する。テキスト、あるいは⾳声によりチュートリアルを⾏うシステムと⾏わないシステムで⽐較実験を⾏い、被験者のシステム利⽤に関する所要時間や疑問への効果を検証した. |
| M-018 |
IoTプラットフォーム(EdgeX Foundry)を用いた時系列データ解析と機械学習系のコンテナ構成
◎増山 維央・和﨑 克己(信州大学)
×
M-018IoTプラットフォーム(EdgeX Foundry)を用いた時系列データ解析と機械学習系のコンテナ構成
◎増山 維央・和﨑 克己(信州大学)
本研究では,オープンソースのIoTプラットフォームであるEdgeX Foundryを用いてセンサーデータ収集・解析システムを構築した.EdgeX Foundryは多様なセンサーやデータソースとの統合が容易で,柔軟かつ高い拡張性を有する.収集データはInfluxDBに保存し,PythonによるARIMAおよびSARIMAモデルを用いた時系列解析を実施した.さらにGrafanaを用いて解析結果を視覚化し,データの傾向を直感的に把握できる環境を提供した.今後は,異常検知や予測といった要求仕様に応じて,異なる解析器をコンテナ単位で容易に交換可能とする設計について検討する. |
| 行動・環境・地域センシング |
|
9月4日(木) 9:30-12:00 4v会場
座長 下坂 正倫(東京科学大学) |
| M-019 |
NIRスペクトルを用いた水深計測による農業潅水のスマート化
○中川 善継・佐野 宏靖(東京都立産業技術研究センター)・髙田 淑朗(のぞみ)
×
M-019NIRスペクトルを用いた水深計測による農業潅水のスマート化
○中川 善継・佐野 宏靖(東京都立産業技術研究センター)・髙田 淑朗(のぞみ)
近年、農業のスマート化が農業従事者の不足を補い、かつ労働負荷を軽減する方策として注目を集めている。特に、天候や作物の生育に応じた潅水管理は、栽培において不可欠である。日々の作業である潅水作業は重労働の一つであり、電磁弁を自動化し制御することが有効である。一方、光スペクトルは主に可視光の波長領域において植生の分布を把握することが可能である。本研究では、より波長の長い近赤外領域のスペクトルを用いた水位計測により、水路の自動電磁弁制御を可能とするスマート潅水が期待できる。 |
| M-020 |
スペクトログラムを用いた低SN環境下におけるEV車両音の識別に関する基本検討
◎秋草 直世・松尾 空・田中 博・宮崎 剛(神奈川工科大学)
×
M-020スペクトログラムを用いた低SN環境下におけるEV車両音の識別に関する基本検討
◎秋草 直世・松尾 空・田中 博・宮崎 剛(神奈川工科大学)
EVはエンジン音がなく走行音が小さいため、その接近に気づきにくい。そのため、車両接近通知装置(以下AVAS)の搭載が義務付けられており、走行中に人工音を鳴らすことで接近の認知を促している。しかし、実際にEVが走行する環境において人間がAVASを常に意識することは難しく、特に繁華街のように雑音が多い環境などでは認知がより困難になる。
本検討ではこのような状況を想定して、雑音環境下においてEVの音を検知する方法について取り組む。具体的には、音声データをスペクトログラムへ変換し、その画像を用いて深層学習モデルによる識別を行う手法を用いる。なお学習には、既存の画像認識用の深層ニューラルネットワークを転移学習によって適応させる。
論文では各種エンジン車と各種EVのスペクトログラムの識別を行うことで実用性を示す。また、EV音声と環境音の重畳音声のSN比を調整し、各SN比の識別率の相違から識別の限界点を明らかにする。 |
| M-021 |
放牧牛のIMUデータを用いた位置推定におけるLightGBMの有効性評価
◎玉崎 伶河・大川 剛直・大山 憲二(神戸大学)
×
M-021放牧牛のIMUデータを用いた位置推定におけるLightGBMの有効性評価
◎玉崎 伶河・大川 剛直・大山 憲二(神戸大学)
放牧牛の効率的管理のために必要な技術の一つとして位置推定が挙げられる.GPSは消費電力が高く長期利用に課題があり,IMUを用いたDead Reckoning (DR)は誤差累積が問題となる.深層学習は,精度は期待できるが計算コストやモデル解釈性が課題となる.本研究では,IMUデータから直接,決定木ベース機械学習手法LightGBMを用いて放牧牛の位置を推定する手法の有効性を評価する.精度,解釈性,学習コストの観点から,DR及びLSTMと比較し,LightGBMがバランスに優れた位置推定手法であることを放牧牛実データを用いて示す.これにより,実用的で効率的な放牧牛追跡システムの実現に貢献する. |
| M-022 |
低価格なVRステレオカメラによる低遅延配信システムの一検討
○浦野 健太・米澤 拓郎・河口 信夫(名古屋大学)
×
M-022低価格なVRステレオカメラによる低遅延配信システムの一検討
○浦野 健太・米澤 拓郎・河口 信夫(名古屋大学)
アーム型・ヒト型など様々なロボットの普及に伴い、遠隔操作システムを介した作業が注目されている。より高度な操作のためには、VRヘッドセットを使う作業者が、没入感のある低遅延な現地映像を見られることが望ましい。また多数の現場にロボットと遠隔操作システムを導入して運用するには、低価格で入手性が良いデバイスを用いる必要がある。本稿では、複数カメラに対応するシングルボードコンピュータを用い、VR映像配信システムを構築する検討を行う。 |
| M-023 |
カメラ映像による非接触魚脈拍推定手法の検討
◎大野 憲人・小林 大倭(近畿大学)・熊木 慧弥(高知大学)・熊木 武志(立命館大学)・蔭山 享佑(近畿大学)
×
M-023カメラ映像による非接触魚脈拍推定手法の検討
◎大野 憲人・小林 大倭(近畿大学)・熊木 慧弥(高知大学)・熊木 武志(立命館大学)・蔭山 享佑(近畿大学)
魚を扱う産業は様々な分野において需要が高まっており,多くの産業に利用されている.
しかし,一定区間内で魚を飼育することで魚病等が発生し,飼育が困難な場合もある.
このため,体調が悪い魚をいち早く発見することが重要である.
本論文では,映像を用いて脈拍数を計測することにより,ストレスを与えずに魚の生体情報を取得する手法を提案する.
映像から指定する関心領域(ROI)における緑色成分の平均輝度値の時間変化に対して高速フーリエ変換を適用する.
高速フーリエ変換の結果をスペクトログラムとし,最も強度の大きい成分を連続的に算出することで,魚の脈拍数を確認した. |
| M-024 |
山間農業地域におけるオフグリッドセンシングシステムの秋冬期運用
○松村 遼・酒井 徹也・児玉 満・河村 拓実・野村 典文(周南公立大学)
×
M-024山間農業地域におけるオフグリッドセンシングシステムの秋冬期運用
○松村 遼・酒井 徹也・児玉 満・河村 拓実・野村 典文(周南公立大学)
本稿は,山口県周南市からの受託事業である「畑わさび生産環境等センシング業務」における,令和6年度の成果の一部をまとめたものである。本事業は,熟練農家および新規就農者の生産環境データを分析することで,畑わさびの収穫量向上に寄与する要因を明らかにすることを目的としている。生産環境データの収集には,著者らが構築したオフグリッドセンシングシステムを用いている。令和6年度は,前年度に明らかとなった運用上の課題を解決するため,システムの改修および施策を実施し,各圃場において実運用を行った。本稿では,改修後のシステムの概要,運用状況,ならびにシステムのさらなる安定稼働に向けた改善案について報告する。 |
| M-025 |
人物立位状態におけるヒューマンレコーダを用いた脈拍推定手法の検証
◎野村 大樹・木下 翼(近畿大学)・熊木 武志(立命館大学)・蔭山 享佑(近畿大学)
×
M-025人物立位状態におけるヒューマンレコーダを用いた脈拍推定手法の検証
◎野村 大樹・木下 翼(近畿大学)・熊木 武志(立命館大学)・蔭山 享佑(近畿大学)
災害現場や工事現場に従事する救助隊員および作業員は,過酷な作業環境により疲労が蓄積しやすい.この疲労は,不快感や活動意欲の低下を引き起こし,重大な支障を及ぼす可能性がある.そのため,業務中の安全を確保するには,作業員の体調を常時把握するシステムが必要である.近年,活動や作業の記録,共有を目的として.頭部装着型カメラが広く利用されている.このカメラを活用したヒューマンレコーダを提案している.本論文では,これまで,座位状態における脈拍数の推定を行っていたが,作業現場での応用を見据え,立位状態における推定を行う.立位状態においても,従来手法と同様に被験者の脈拍数を推定できることを確認した. |
| センシング・分析・デバイス連携 |
|
9月4日(木) 15:30-17:30 5u会場
座長 齊藤 義仰(岩手県立大学) |
| M-026 |
光カメラ通信による映像と協調した音楽伝送法
◎土屋 奈月・中山 悠(東京農工大学)
×
M-026光カメラ通信による映像と協調した音楽伝送法
◎土屋 奈月・中山 悠(東京農工大学)
本研究は、ディスプレイとカメラ間の可視光通信(光カメラ通信)を利用し、映像と同期して音楽を伝送する新手法を提案する。音階と音価を直接RGB色に一括変調する独自符号化方式を設計し、楽曲内容に応じた映像フレーム列を自動生成する。理論解析により伝送レートの限界性能を導出し、実機評価としてディスプレイとUSBカメラを用いてテスト曲を伝送した結果、提案方式は4K・16fps環境で当該楽曲を誤りなく復号できた。8シンボル(8色)を用いて、屋内照明下でも安定動作することを確認した。 |
| M-027 |
(講演取消) |
| M-028 |
迅速なUWB測位環境の構築にむけたタグ配置の自動推定と外れ値対策
◎助川 豊樹(長岡技術科学大学)・小木曽 里樹・一刈 良介・佐藤 章博・蔵田 武志(産業技術総合研究所)・中平 勝子(長岡技術科学大学)
×
M-028迅速なUWB測位環境の構築にむけたタグ配置の自動推定と外れ値対策
◎助川 豊樹(長岡技術科学大学)・小木曽 里樹・一刈 良介・佐藤 章博・蔵田 武志(産業技術総合研究所)・中平 勝子(長岡技術科学大学)
本稿では,UWB(Ultra Wide Band)による屋内測位環境の構築のために,移動するスマートフォンで測距を行い設置されたタグの位置を推定することを考え,推定精度を低下させる外れ値の発生要因の分析と対策手法の検討を行う.分析に用いる測距データは,次のように取得した.スマートフォンの座標はiPhoneのARKitで取得し,UWBタグとの距離はUWBによるTwo-way rangingで測定した.UWBタグ座標の推定は,スマートフォン座標とUWBタグ座標から得られるユークリッド距離と,UWBによる測距値の絶対誤差総和を最小化することで行い,実環境の状態や移動経路と推定結果の対比から,外れ値発生要因と対策を考察する. |
| M-029 |
デマンドレスポンスのための電力需要予測根拠の可視化
◎小林 碧志・堀 磨伊也(公立鳥取環境大学)
×
M-029デマンドレスポンスのための電力需要予測根拠の可視化
◎小林 碧志・堀 磨伊也(公立鳥取環境大学)
本研究では,多様なセンサデータを用いた電力需要予測と予測根拠の可視化を行うことで効果的なデマンドレスポンスを試みる.近年,再生可能エネルギーの普及に伴い,電力需要側の制御手法であるデマンドレスポンスの重要性が高まっている.デマンドレスポンスを有効に実施するためには、精度の高い電力需要予測が不可欠である.さらに,その予測結果の根拠を利用者に理解可能な形で提示することが,将来的な行動変容を促す上で重要と考えられる.本研究では,大学講義室に設置した多様なセンサデータなどを用いて大学施設の電力需要を予測するモデルを構築し,その予測精度と可視化の有用性を評価した. |
| M-030 |
iHAC Hubを介したセキュリティカメラとECHONET Liteデバイスの連携手法の検討
◎髙木 涼生・小門口 聖矢・鈴木 秀和(名城大学)
×
M-030iHAC Hubを介したセキュリティカメラとECHONET Liteデバイスの連携手法の検討
◎髙木 涼生・小門口 聖矢・鈴木 秀和(名城大学)
日本ではHEMS標準規格としてECHONET Liteが策定され,多くのメーカーの製品に採用されている.一方,自宅の防犯対策としてセキュリティカメラの導入も進んでいるが,ベンダーごとにシステムが独立しており,ECHONET Lite対応設備が設置されたスマートホームとの連携が進んでいない.筆者らは異なる規格のIoTデバイス間の連携をサポートするシステムとしてiHAC Hubを提案してきた.本稿では,iHAC Hubを用いてセキュリティカメラとECHONET Liteデバイスのシームレスな連携の実現方法について検討する. |
| M-031 |
ミステリー街歩きをしながらフォトウォークをするためのスマートフォンアプリの開発
名和 祐真・○牛田 啓太(工学院大学)
×
M-031ミステリー街歩きをしながらフォトウォークをするためのスマートフォンアプリの開発
名和 祐真・○牛田 啓太(工学院大学)
街歩きは健康維持や観光の一環として広く楽しまれている。本稿では,目的地を知らずに散策を行う「ミステリー街歩き」を提案する。これにフォトウォークを組み合わせ,周囲の環境に意識を向け,偶然の発見を促しながら街歩きを楽しむことを狙っている。このミステリー街歩きを支援するソフトウェアをスマートフォンアプリとして実装した。利用者がおよその条件を指定すると,目的地の施設情報が検索される。この結果は利用者に提示されず,目的地の方向と,フォトウォークミッションが提示される。これに従って利用者は街歩きをする。試用では,目的地がわからないワクワク感,普段行かない場所に足を運ぶきっかけになったなどの意見が得られた。 |
| 分散移動システム技術と応用 |
|
9月4日(木) 15:30-17:30 5v会場
座長 菅沼 拓夫(東北大学) |
| M-032 |
(講演取消) |
| M-033 |
デジタルツイン連携におけるトポロジー管理手法の提案
○杉山 敬三(KDDI総合研究所)
×
M-033デジタルツイン連携におけるトポロジー管理手法の提案
○杉山 敬三(KDDI総合研究所)
複数のデジタルツイン(DT)間の連携において、所要の目的に応じて構築される個別DT群と、それらと連携して動作する上位のDTとの間で、連携するコンテキストに基づいたツリー構造のトポロジーを管理する手法を示す。トポロジー管理は、個別DT連携管理部、トポロジー管理部、個別DTプール管理部から構成する。本手法により、一つの上位DTが複数のコンテキストを使い分けながら同時に異なる連携を行う際の個別DTの管理が容易になる。 |
| M-034 |
(講演取消) |
| M-035 |
移動環境におけるデータ配信効率化のためのMPQUICパケットスケジューラ
◎松浦 薫・Alparslan Onur・佐藤 健哉(同志社大学)
×
M-035移動環境におけるデータ配信効率化のためのMPQUICパケットスケジューラ
◎松浦 薫・Alparslan Onur・佐藤 健哉(同志社大学)
複数の通信インタフェースを搭載したモバイルデバイスを移動環境下で利用する際,MPQUICを用いて複数の通信経路を同時に使用して安定的なデータ配信を継続することが期待される.ここで,セルラ通信の通信容量制限や従量課金制度により,Wi-Fiの通信速度が低下する場合のみWi-Fiとセルラ通信を併用し,そうでない場合には冗長なセルラ通信を控えることが望まれる.そこで,本研究では,Wi-Fiの受信信号強度に基づいて通信経路を動的に選択するパケットスケジューラを提案する.シミュレーション実験により,本提案手法はセルラ通信のオーバヘッドを抑制しつつ通信速度の停滞を防ぎスループットを向上させることが示された. |
| M-036 |
投機的実行におけるコンテキスト予測共有によるEthereumノード高速化
◎大塲 雄太郎・山崎 憲一(芝浦工業大学)
×
M-036投機的実行におけるコンテキスト予測共有によるEthereumノード高速化
◎大塲 雄太郎・山崎 憲一(芝浦工業大学)
Ethereumは、スマートコントラクトを用いた大規模分散型プラットフォームであり、トランザクションは伝達・合意・実行の三段階を経て処理される。この過程では、トランザクションがネットワークに伝播されてから実行されるまで、未実行の状態にある期間が存在する。関連研究Forerunnerでは、トランザクションが未実行の期間を活用し、複数の未来を想定した制約ベースの投機的実行により高速化を実現した。本研究では、生成された未来コンテキストを低速ノードと共有することで、ネットワーク全体における処理のばらつきを抑え、分散システムとしてのスループットの向上を図る手法を提案する。 |
| M-037 |
LoRAを活用した個人スタイルに対応したファッション画像生成方式
◎王 子涵・阿倍 博信(東京電機大学)
×
M-037LoRAを活用した個人スタイルに対応したファッション画像生成方式
◎王 子涵・阿倍 博信(東京電機大学)
本研究は、個人のファッションスタイルに応じた画像生成を目的に、Stable DiffusionにLoRAを適用したファインチューニング手法を提案する。従来は購買履歴などに依存するため、新規ユーザーへの対応や意図の反映に限界があった。そこでユーザー自身の服装写真やFashion IQデータセットを用い、少量のデータでもスタイルを反映できるようモデルを調整した。また、生成画像とECサイトの商品画像とのマッチングにより実用性を検証した。その結果、LoRA適用モデルはスタイルの一致度が高く、カスタマイズ性と実用性を兼ね備えた新規ユーザー対応型手法として有効であると確認された。 |
| 交通システム設計・検知・最適化 |
|
9月5日(金) 9:30-12:00 6u会場
座長 岩本 健嗣(富山県立大学) |
| M-038 |
GTFSを使用した地域公共交通向けバスロケーションシステム強化の検討
○内林 俊洋(九州大学)・末吉 智奈佐・安武 芳紘・里村 秀行・津曲 優斗・福山 侑弥・稲永 健太郎(九州産業大学)
×
M-038GTFSを使用した地域公共交通向けバスロケーションシステム強化の検討
○内林 俊洋(九州大学)・末吉 智奈佐・安武 芳紘・里村 秀行・津曲 優斗・福山 侑弥・稲永 健太郎(九州産業大学)
近年,日本の地域公共交通は人口減少や高齢化の影響を受け,交通空白地域の拡大が深刻な問題となっている.このような状況に対応するため,多くの自治体が自らを運行主体とするコミュニティバスなどの地域公共交通の運行を進めているが,限られた予算や人材の中で運行を余儀なくされている.そこで我々は,これらの課題に対処するため,地域公共交通の支援を行ってきた.しかし,こうした支援に利用しているシステムの導入に際しては,データ管理の安全性や改ざん防止の課題が存在する.そこで本研究は,ブロックチェーン技術を活用し,GTFSデータの一部をブロックチェーン上に保存することで,データの信頼性向上と改ざん耐性の強化を行う. |
| M-039 |
2種のラインモードを選択可能とするGTFS描画情報作成支援Webアプリケーションの開発
◎福山 侑弥・津曲 優斗・里村 秀行・末吉 智奈佐(九州産業大学)・内林 俊洋(九州大学)・安武 芳紘・稲永 健太郎(九州産業大学)
×
M-0392種のラインモードを選択可能とするGTFS描画情報作成支援Webアプリケーションの開発
◎福山 侑弥・津曲 優斗・里村 秀行・末吉 智奈佐(九州産業大学)・内林 俊洋(九州大学)・安武 芳紘・稲永 健太郎(九州産業大学)
人口減少や高齢化により公共交通機関の利用者が減少し、バスの路線数や便数が削減され利便性が低下している一方、高齢者の免許返納などにより公共交通の需要は高まっている。そこで本論文では、GTFSの描画情報作成支援Webアプリを開発し、事業者の負担軽減と利用者の利便性向上を目指した。主な機能は、敷地内バス停付近の描画対応、Google Maps APIのマーカー上限問題の緩和、往路復路の重複ライン確認のしやすさである。実際の利用者からは作業時間の短縮や利便性向上といった好意的な評価を得られたが、モード切り替えの操作性などに改善点も残された。今後は改善点の修正とともに停留所のマーカー検索機能など新たな機能の実装を行う。 |
| M-040 |
小規模離島におけるデマンド交通運行管理システムの設計
◎津曲 優斗・福山 侑弥・里村 秀行・末吉 智奈佐(九州産業大学)・内林 俊洋(九州大学)・安武 芳紘・稲永 健太郎(九州産業大学)
×
M-040小規模離島におけるデマンド交通運行管理システムの設計
◎津曲 優斗・福山 侑弥・里村 秀行・末吉 智奈佐(九州産業大学)・内林 俊洋(九州大学)・安武 芳紘・稲永 健太郎(九州産業大学)
現代日本では人口減少や少子高齢化が進行しており、特に地方圏では都市への人口流出によりその傾向が顕著である。また、物価の高騰や燃料費の高騰などにより、地方における公共交通の維持が困難となっている。このような課題に対し、利用者のニーズに柔軟に対応可能であり、路線バス維持に伴う財政負担の軽減が期待されるデマンド交通が有効な手段として注目されている。本論文では、小規模離島でのデマンド交通の運行管理システムの設計を行う。予約情報をもとに港を中心とした移動に対しての最適な配車を行い、表示している降車予定時刻を遵守した運行を管理、支援するシステムの設計を行なった。今後は、実証実験を行い有効性の確認をした上で、汎用化を目指す。 |
| M-041 |
自動走行カート搭載のLiDARを利用した人物判定手法
○坂本 朝陽・望月 遥貴・清原 良三(神奈川工科大学)
×
M-041自動走行カート搭載のLiDARを利用した人物判定手法
○坂本 朝陽・望月 遥貴・清原 良三(神奈川工科大学)
自動走行カート搭載のLiDARを利用して警備に活用している.警備においては人を発見することは重要な課題であり,夜間などカメラでは認識しにくい場合にも対応を要する.LiDARを用いて静止している人物を対象として人物認識の手法を提案する.立ってるだけでなく,座位であったり,寝転んでいる場合なども想定した手法である. |
| M-042 |
航空交通管制交信における自動異常検知の手法に関する検討
◎堤 羅馬・髙辻 優太・冨田 賢志・鶴岡 慶雅(東京大学)
×
M-042航空交通管制交信における自動異常検知の手法に関する検討
◎堤 羅馬・髙辻 優太・冨田 賢志・鶴岡 慶雅(東京大学)
航空交通管制交信(ATCC)における異常は,依然として航空交通における重大なリスク要因である.本研究では,約2時間分のATCC録音音声を文字起こしし,Named Entity Recognition を適用したデータに対して,機械学習により顕在的・潜在的な異常交信の自動検知を試みた.単語を正規化した上で,全体および航空機ごとの2種類の設定において,スライディングウィンドウ法により入力ベクトルを作成した.教師あり学習には Random Forest と全結合型 Neural Network,教師なし学習には One-Class SVM と Autoencoder を用い,F1スコア が最大となるようウィンドウ幅や各種パラメータを調整した.ATCCにおけるリスクの早期発見と管制支援の可能性を示す. |
| M-043 |
時空間ボクセル予約の階層管理による複数ドローンの経路計画手法の提案
◎梅田 寛斗・Alparslan Onur・佐藤 健哉(同志社大学)
×
M-043時空間ボクセル予約の階層管理による複数ドローンの経路計画手法の提案
◎梅田 寛斗・Alparslan Onur・佐藤 健哉(同志社大学)
近年,物流や3 次元測量,インフラ点検などの分野でドローンを活用した取り組みが活発になっている.そのような複数のドローンが同時に飛行する環境では,飛行経路の交差により衝突の危険性が生じる.全てのドローンの経路を計算して衝突を回避しようとする場合,ドローンの台数が増加するにつれ計算量が膨大になるという問題点がある.そこで本研究では,複数ドローンの経路計画時の計算時間を短縮することを目的とし,空間をボクセル単位で区切り,時間情報を加えた4次元空間を構築し,階層的に管理する時空間ボクセル予約を用いた経路計画手法を提案する. |
| M-044 |
複数事業者による宅配EVトラックの充電スケジューリング最適化
○和田 恭祐(専修大学)・重中 秀介・西田 遼・大西 正輝(産業技術総合研究所)
×
M-044複数事業者による宅配EVトラックの充電スケジューリング最適化
○和田 恭祐(専修大学)・重中 秀介・西田 遼・大西 正輝(産業技術総合研究所)
本研究では,複数の運輸事業者が共有する充電ステーションにおける充電タイミングの最適化を扱う.現在,各事業者が個別に最適化を行っており,事業者間の連携や公平性は考慮されてない.このような個別最適化では,充電需要が特定の時間帯に集中し,運行遅延の発生を招く可能性がある.そこで本研究では,充電タイミングを最適化することを目的として,全体の効率性を重視する手法と,事業者間の公平性を考慮する手法の2つを提案する.配達箇所の数や位置が異なるシナリオでシミュレーションを行った結果,調整により遅延が改善され.特に途中に充電ステーション,その奥に配達箇所が集中するシナリオにおいて充電タイミングの調整効果が大きいことを確認した. |
| 交通分析とモデル化 |
|
9月5日(金) 13:10-15:40 7u会場
座長 内林 俊洋(九州大学) |
| M-045 |
EVの走行データ分析に基づいた充電ステーションの最適配置法の提案
◎太田 竜平・平松 薫(埼玉大学)
×
M-045EVの走行データ分析に基づいた充電ステーションの最適配置法の提案
◎太田 竜平・平松 薫(埼玉大学)
電気自動車(EV)は、大気汚染の排出削減に貢献する可能性があることから近年注目を集めているが、市場におけるシェアは依然として小さい。その要因の一つとして、充電インフラの整備不足が挙げられる。本研究では、充電ステーションの配置に着目し、その最適配置法を提案する。具体的には、EVの走行データを基に、道のり距離に基づいたクラスタリング手法を用いて、最適な充電ステーションの配置を導出する。川口市の道路網で生成したシミュレーションデータにおいて、提案手法によって算出された配置は、単純な直線距離に基づく配置と比較して、充電が必要なEVから充電ステーションまでの総道路距離を短縮できることを示した。 |
| M-046 |
運転挙動と視線計測による自転車の運転特性分析
◎小林 純輝・奥出 真理子(茨城工業高等専門学校)
×
M-046運転挙動と視線計測による自転車の運転特性分析
◎小林 純輝・奥出 真理子(茨城工業高等専門学校)
自転車や電動キックボードなどのパーソナルモビリティは,移動の利便性向上や環境負荷を低減する手段として期待される一方,自転車事故の割合が全交通事故の2割強を占めること,特定小型原動機付自転車の利用者急増に伴い事故数も大幅に増加していることから,安全通行の対策が求められている.本研究では,パーソナルモビリティの安全な利用に向けて,利用者の運転傾向や癖を把握することを目的とする.自転車を対象に,スマートフォンに搭載された加速度センサなどと視線計測デバイス,およびアンケート調査を用いて運転行動を分析した結果,走行中の視線移動とカーブにおけるハンドル操作が,利用者の安全運転意識に関連することがわかった. |
| M-047 |
観光地における地点の環境情報分析による雰囲気抽出手法の提案
◎三輪 樹理音・宮田 大資・ヨウ シンニー(京都産業大学)・大滝 啓介・吉村 貴克・堺 浩之(豊田中央研究所)・栗 達(京都産業大学)・河合 由起子(関西大学)
×
M-047観光地における地点の環境情報分析による雰囲気抽出手法の提案
◎三輪 樹理音・宮田 大資・ヨウ シンニー(京都産業大学)・大滝 啓介・吉村 貴克・堺 浩之(豊田中央研究所)・栗 達(京都産業大学)・河合 由起子(関西大学)
MaaSの普及に伴い,観光地における目的地までのラストマイルの経路推薦では,単純な最短距離や時間だけではなく,快適さや安心感,刺激などの体験価値を重視するニーズが高まっている.本研究では,地点に対するスポット情報や画像,路面情報に加え,五感となる音と匂い情報を環境情報として分析し,地点の雰囲気を抽出する手法を提案する.本稿では,これまで我々が開発した環境情報投稿サービスより取得した約8000地点の撮影画像および6種類のタグ情報から,Resnet-18ベースの予測モデルを構築し,雰囲気抽出を検証する. |
| M-048 |
オプティカルフローを用いた交差点の交通流解析
◎堀内 晴貴・金道 敏樹(金沢工業大学)
×
M-048オプティカルフローを用いた交差点の交通流解析
◎堀内 晴貴・金道 敏樹(金沢工業大学)
本研究は、交通映像に対してオプティカルフローを適用し、車両の通行経路を可視化することで、不安全運転を機械的に把握することを目的とする。車両が交差点を通行する様子を歩道橋上から俯瞰して撮影した映像を入力とし、フレーム間の動き情報をもとに移動ベクトルを算出することで各車両の走行経路を可視化する。予備的な検討段階において、車線を遵守する車両の経路と車線を逸脱する車両の経路の違いが可視化できている。現在、不安全運転の地域差を検討するため、金沢市に加え、愛知県一宮市、静岡県磐田市などにおいても撮影を行い、今後その比較分析を進めているので、その結果を合わせて報告する。 |
| M-049 |
廉価なWi-Fi送受信機を用いた断面交通量の推計の実現可能性に関する一考察
○中原 匡哉(大阪電気通信大学)
×
M-049廉価なWi-Fi送受信機を用いた断面交通量の推計の実現可能性に関する一考察
○中原 匡哉(大阪電気通信大学)
我が国では、中心市街地の活性化に向けて回遊性の向上を図るため、歩行者交通量調査が実施されている。近年では、手観測ではなくビデオカメラやLiDARなどのIoT機器とAIを組み合わせて高精度に歩行者の人数だけでなく、その属性まで推定可能となっている。しかし、これらの方法では、顔や歩容の特徴から個人の特定につながる危険性がある課題や、地下通路などの狭小領域では、場所によっては高精度に計数可能な設置条件を満たさない課題がある。そこで、本研究では、廉価なWi-Fiの送受信機の電波情報の変動を用いた歩行者交通量の推計の実現可能性を考察する。 |
| M-050 |
生活道路交差部における車載カメラ映像に基づく車両挙動のモデル化とシミュレータの構築
◎杉本 拓海・大倉 裕貴・河崎 隆文・岩本 健嗣(富山県立大学)
×
M-050生活道路交差部における車載カメラ映像に基づく車両挙動のモデル化とシミュレータの構築
◎杉本 拓海・大倉 裕貴・河崎 隆文・岩本 健嗣(富山県立大学)
住宅地内にみられる道路は生活道路と呼ばれ、見通しの悪さや道幅の狭さにより、交通事故の発生リスクが高い道路環境である。こうした生活道路の安全対策として、一時停止標識や防護柵等の交通安全施設の設置が進められている。しかし、これらの設置が交通安全に与える影響を定量的に評価する手法は、十分に確立されていない。そこで本研究では、生活道路における幾何構造や設置物の変化が車両挙動に及ぼす影響を定量的に評価するため、生活道路交差部における車両挙動を再現するシミュレータを構築した。交差部の幾何構造や設置物の特徴に基づき、車両の速度変化や進行方向の変化をモデル化し、実測データとの比較による再現性の評価を行った。 |
| M-051 |
グラフ理論に基づく駅間の信号機区間単位での列車運行のモデル化手法
◎髙瀬 翼・國松 武俊(鉄道総合技術研究所)
×
M-051グラフ理論に基づく駅間の信号機区間単位での列車運行のモデル化手法
◎髙瀬 翼・國松 武俊(鉄道総合技術研究所)
輸送障害発生後の列車ダイヤを早期に回復させる施策の検討において、効果推定のために列車運行シミュレーションが用いられる。シミュレーション手法の一つに、グラフ理論に基づき、各列車の駅発着や駅間走行、列車間の間隔などをモデル化して計算する手法がある。本研究では、遅延対策のために設備改良すべき箇所を駅間の信号機区間単位で抽出することを目的として、駅発着をイベントとしたモデルと、駅発着に加えて駅間の信号機通過をイベントとしたモデルの2つを作成し、シミュレーション結果を比較した。その結果、後者の詳細なモデル化を行うことで、列車遅延に大きく影響している区間やその要因を詳細に特定できることを確認した。 |