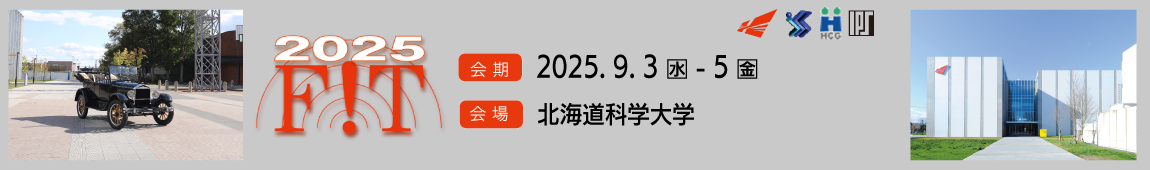| J分野 ヒューマンコミュニケーション&インタラクション |
選奨セッション
コミュニケーション&インタラクション |
|
9月3日(水) 9:30-12:00 1h会場
座長 番 浩志(情報通信研究機構)
清河 幸子(東京大学) |
| CJ-001 |
identicon-modelアバタの個人嗜好性の分析
◎安田 隆哉・佐久間 拓人・加藤 昇平(名古屋工業大学)
×
CJ-001identicon-modelアバタの個人嗜好性の分析
◎安田 隆哉・佐久間 拓人・加藤 昇平(名古屋工業大学)
アバタはMMORPGやVRSNSなどで利用される自己投射のオブジェクトであり,個人が自らの分身となるアバタを作成・選択する機会もが増加している.しかし,個人がどのような傾向でアバタを作成するのか,その特徴や一貫性については十分に明らかにされていない.前報では,探索的デザインを支援するキャラクター作成インタフェースを提案し,identiconを3Dモデル化した「identicon-model」を用いたアバタ作成の比較実験を実施した.本研究では、実験参加者がそれぞれ6体ずつ作成したアバタに着目し,同一人物が作成したアバタ群に共通する視覚的特徴やデザイン傾向を分析した結果を報告する. |
| CJ-002 |
Expression Recognition Based on Ear Canal Shape Detection Using Earbud and Ultrasound
◎Gao Tian・Dong Xuefu・Taya Akihito・Nishiyama Yuuki・Sezaki Kaoru(東京大学)
×
CJ-002Expression Recognition Based on Ear Canal Shape Detection Using Earbud and Ultrasound
◎Gao Tian・Dong Xuefu・Taya Akihito・Nishiyama Yuuki・Sezaki Kaoru(東京大学)
Earbuds are well-known for their portability, wearability, and frequent usage. This research introduces facial expression recognition using earbuds by training models with collected in-ear ultrasound data. The motivation is to enhance communication and, mainly, to help track emotional health. The strength of using earbuds for tracking is that earbuds’ wearability leads to convenience and consistency, and their close position to facial muscles gives them the potential to be the best expression detectors. The possible application could have great value in the future. |
| CJ-003 |
(講演取消) |
| CJ-004 |
「その人を知る」ためのモニタリングに向けた笑顔認識
○鎌田 一平・下西 慶・近藤 一晃・中村 裕一(京都大学)・大塚 智丈(三豊市立西香川病院)
×
CJ-004「その人を知る」ためのモニタリングに向けた笑顔認識
○鎌田 一平・下西 慶・近藤 一晃・中村 裕一(京都大学)・大塚 智丈(三豊市立西香川病院)
本研究では認知症患者の日常の生活状態や対人的な状態を観測した映像から,その人の表情を認識し,笑顔の時間的変化とその状況を経時的に記録することを提案する.喜びの感情や嬉しい,楽しいなどのポジティブ感情は,認知症患者のQOLを向上させるとともに症状の進行を遅らせることや,記憶として残り続けることが示唆されている.また,介護者にとっても介護の良い動機づけとなり,介護の向上に繋がることになる.このようなことから,「その人を知る」ための手がかりとして,また,良い状態を保つための重要な情報として笑顔を対象とし,介護の場での粒度の細かい笑顔認識を実現する手法について検討した. |
| CJ-005 |
薬剤耐性対策における医療診断AIの社会受容性とその国際比較
○伊東 啓(長崎大学)・和田 崇之(大阪公立大学)・一ノ瀬 元喜(静岡大学)・谷本 潤(九州大学)・吉村 仁・山本 太郎(長崎大学)・守田 智(静岡大学)
×
CJ-005薬剤耐性対策における医療診断AIの社会受容性とその国際比較
○伊東 啓(長崎大学)・和田 崇之(大阪公立大学)・一ノ瀬 元喜(静岡大学)・谷本 潤(九州大学)・吉村 仁・山本 太郎(長崎大学)・守田 智(静岡大学)
薬剤耐性菌の出現と拡散を抑える手段として、医療診断AIの活用が注目されているが、その社会的受容性はまだ明らかにされていない。本研究では、8か国において、「耐性菌の問題を考慮して抗生剤の処方を極力控えるAI」と「耐性菌の問題を考慮せず個人の早期回復を優先して抗生剤を処方するAI」のいずれに普及してほしいかを尋ね、計約4万人から回答を得た。その結果、全ての国で過半数の回答者が後者のAIを支持しており、選好の傾向には性別と年代による違いが見られた。これらの結果は、どのような医療診断AIが普及するかという問題が、技術的な課題にとどまらず、個人の倫理的・社会的価値観に大きく左右されることを示唆している。 |
| CJ-006 |
GROWモデルに基づく目標達成にフォーカスしたコーチング対話システム
◎山崎 紘介・櫻井 崇貴・長澤 史記・白松 俊(名古屋工業大学)
×
CJ-006GROWモデルに基づく目標達成にフォーカスしたコーチング対話システム
◎山崎 紘介・櫻井 崇貴・長澤 史記・白松 俊(名古屋工業大学)
LLMを用いた対話システムは人間らしい応答を可能にする一方、信頼される対話を行えるには至っていない。本研究では、GROWモデルに基づき、ユーザの目標と現状のギャップを明確化し、選択肢提示と意思決定を支援する対話システムを提案する。このモデルでは、目標共有による内省促進と満足度向上、話題の逸脱を防ぐ構造的対話による効率的な伴走支援、さらに一歩目の行動を後押しする設計を特徴とし、大規模言語モデルの自然な対話能力を活かしたプロンプト設計により、自己理解と実現可能性評価の支援を目指す。これにより、対話者はシステムとの間に協力関係を見出し、継続的なコミュニケーションと自己開示をもたらすことが示唆される。 |
| ヒューマンコミュニケーション基礎 |
|
9月3日(水) 13:10-15:10 2s会場
座長 志水 信哉(NTT株式会社) |
| J-001 |
2種類のアート没入空間の心理実験による比較評価
○中津 良平・土佐 尚子(京都大学)・浦岡 泰之・北川 茜・村田 耕一・務中 達也(島津製作所)・上田 祥行(京都大学)・古田 雅史(島津製作所)・野村 理朗(京都大学)
×
J-0012種類のアート没入空間の心理実験による比較評価
○中津 良平・土佐 尚子(京都大学)・浦岡 泰之・北川 茜・村田 耕一・務中 達也(島津製作所)・上田 祥行(京都大学)・古田 雅史(島津製作所)・野村 理朗(京都大学)
アート鑑賞が環境にどのような影響を受けるかを知るために、2つの異なる性質を持つ没入空間を構築し、その中でビデオアートを鑑賞してもらい心理評価実験を行った。一つはミラー型ディスプレイで囲まれた空間であり、もう一つは大型のディスプレイで囲まれた空間である。得られた心理評価結果を分散分析の手法によって比較したところ、アート鑑賞時の心理評価結果は環境の影響を受けにくいことが明らかになった。一方、比較対象となる幾何学図形や無コンテンツは環境の影響を大きく受けることが明らかになった。このことは、アートが環境条件を超えた価値を有し、それが鑑賞者に評価されることを示している。 |
| J-002 |
2種類のアート没入空間の心電データによる比較評価
○中津 良平・土佐 尚子(京都大学)・浦岡 泰之・北川 茜・村田 耕一・務中 達也(島津製作所)・上田 祥行(京都大学)・古田 雅史(島津製作所)・野村 理朗(京都大学)
×
J-0022種類のアート没入空間の心電データによる比較評価
○中津 良平・土佐 尚子(京都大学)・浦岡 泰之・北川 茜・村田 耕一・務中 達也(島津製作所)・上田 祥行(京都大学)・古田 雅史(島津製作所)・野村 理朗(京都大学)
アート鑑賞が環境にどのような影響を受けるかを知るために、2つの異なる性質を持つ没入空間を構築し、その中で被験者にビデオアートを鑑賞してもらい、その際の心電データを測定する実験を行った。一つはミラー型ディスプレイで囲まれた空間(没入空間1)であり、もう一つは大型のディスプレイで囲まれた空間(没入空間2)である。得られた心電データを定性的に比較したところ、没入空間1では平均すると被験者が交感神経活動優位の状態にあり、没入空間2では副交感神経活動優位の状態にあることがわかった。このことは、アート鑑賞の際の環境条件が生理状態に異なる影響を与えることを示しており、心理評価実験とは異なるという興味深い結果を得た。 |
| J-003 |
教育ロボの為の小学校の算数における評価の一考察 —————コンピュータとプログラミング—————
三角田 秀実・伊藤 美香(所属なし)・○和田 平司(情報処理学会)・安達 健二・内等 裕士・福永 和英・楢崎 みどり・長尾 ちひろ・大藤 まゆみ・花田 光代(所属なし)
×
J-003教育ロボの為の小学校の算数における評価の一考察 —————コンピュータとプログラミング—————
三角田 秀実・伊藤 美香(所属なし)・○和田 平司(情報処理学会)・安達 健二・内等 裕士・福永 和英・楢崎 みどり・長尾 ちひろ・大藤 まゆみ・花田 光代(所属なし)
教育ロボの為の小学校の算数についてコンピュータとプログラミングの指導における評価について検討したので報告する。 |
| J-004 |
“手を使った”アイデアの具現化方法の提案
◎上岡 遥馬・渋谷 正弘(東京都立大学)
×
J-004“手を使った”アイデアの具現化方法の提案
◎上岡 遥馬・渋谷 正弘(東京都立大学)
新しいアイデアを具現化するために、これまで文字を活用した方法が数多く発表され利用されてきた。しかし、我々は三次元形状を持つアイデアを具現化するためには文字よりも形状及び動作を試行錯誤する方法が重要と考えた。アイデアを具現化する方法として、ある機能を持つブロックを定義し、それらを組み合わせ整理及び試行できる仕組みを提案する。この仕組みでは仮想空間と現実空間を行き来し、手を使ってアイデアを具現化する。本稿では、具現化方法のプロトタイプを作成したので報告する。 |
| J-005 |
仮想空間を使用したアイデアの醸造・検証方法の提案
◎船橋 彩花・渋谷 正弘(東京都立大学)
×
J-005仮想空間を使用したアイデアの醸造・検証方法の提案
◎船橋 彩花・渋谷 正弘(東京都立大学)
本論文では閃いたアイデアを現実空間と仮想空間の融合させて醸造・試行・検証する方法を提案する。疑問に思った事柄や具現化したいアイデアをインタラクティブに解くための簡単なツールがない。そこで、仮想空間を利用した簡単なツールを提案する。具体的には三次元形状のオブジェクトを仮想空間に配置・結合・切断などが簡単にできること、配置済みのオブジェクトに対して振る舞いを定義できること、現実空間上でオブジェクトを操作・検証できるよう仮想空間を融合する方法を構築した。本稿ではこの3つの手法について具体例を挙げて述べる。 |
| J-006 |
脳血流量・心拍変動によるマルチモーダルコミュニケーションネットワークを用いた共同作業における効率性指標推定手法の提案
◎鈴木 優人・栗原 陽介(青山学院大学)
×
J-006脳血流量・心拍変動によるマルチモーダルコミュニケーションネットワークを用いた共同作業における効率性指標推定手法の提案
◎鈴木 優人・栗原 陽介(青山学院大学)
作業指示者と作業者による共同作業では,指示伝達や相槌などによる円滑なコミュニケーションが作業の効率に大きな影響を与える.筆者らはこれまで,コミュニケーション中の脳血流量を近赤外分光法で計測し,信号予測における因果性を表すネットワークを構築することで,作業の効率性指標を推定してきた.本稿では,さらにコミュニケーションによる焦りやリラックスといった交感/副交感神経の働きを評価するため心拍変動を統合する.具体的には,脳血流量および心拍変動に移動エントロピーを適用することで,脳活動と交感/副交感神経の動的相互作用を捉えるマルチモーダルコミュニケーションネットワークを構築し,効率性指標の推定を行う. |
| 高齢社会とスマートヘルスケア |
|
9月3日(水) 15:30-17:30 3s会場
座長 鏑木 崇史(国際基督教大学) |
| J-007 |
多様な重心移動訓練とリハビリ進捗の客観的評価システムの開発
◎佐藤 力斗(九州産業大学)・盛 俊光(医療法人原三信病院 香椎原病院)・梅﨑 浩嗣(医療法人相生会 金隈病院)・神屋 郁子(福岡女子大学)・下川 俊彦(九州産業大学)
×
J-007多様な重心移動訓練とリハビリ進捗の客観的評価システムの開発
◎佐藤 力斗(九州産業大学)・盛 俊光(医療法人原三信病院 香椎原病院)・梅﨑 浩嗣(医療法人相生会 金隈病院)・神屋 郁子(福岡女子大学)・下川 俊彦(九州産業大学)
骨折・靱帯損傷の患者や高齢者に対し重心移動を行うリハビリ訓練において、多様な重心運動ができるようにする方法、リハビリの進捗を客観的に評価できるようにする方法の提案をする。 先行研究では、バランスWiiボードを用いて重心移動による様々な訓練を実施できるようにしたが、特定の動きを重視したリハビリができないこととリハビリの進捗を客観的に評価することができなかった。本研究では、既存のリハビリ用ゲームの改良を行うことで多様な重心運動ができるようにした。また、左右の足に掛けた重心の荷重割合の履歴を確認できるようにし、リハビリの進捗を客観的に評価できるようにした。 |
| J-008 |
(講演取消) |
| J-009 |
嚥下障害診断補助ツールの開発
○牛島 諒羽(静岡大学)・古川 大輔(君津中央病院)・黒岩 眞吾(千葉大学)・西田 昌史(静岡大学)・西村 雅史(静岡大学/愛知産業大学)
×
J-009嚥下障害診断補助ツールの開発
○牛島 諒羽(静岡大学)・古川 大輔(君津中央病院)・黒岩 眞吾(千葉大学)・西田 昌史(静岡大学)・西村 雅史(静岡大学/愛知産業大学)
嚥下障害の診断方法は患者への負担が大きいものが多い。嚥下音を用いた簡便な診断(頸部聴診法)も実施されているが,正確な診断には高い技能が必要とされている。そこで本研究では、頸部聴診法によるスクリーニングや診断時に有効な嚥下障害診断補助システムを提案する。皮膚接触型のマイクで収録された嚥下音を入力することで、嚥下障害の自動分類と可視化を行う。スカログラムベースのCNNによる分類に加え、嚥下音の再生、判定の信頼度及び分類結果の表示,更にはAIが判定時に着目したポイントを可視化する機能を搭載している。医療現場での試用の結果,言語聴覚士の聴診によるスクリーニング結果と矛盾しない良好な結果が得られていることを確認した。 |
| J-010 |
会話を伴う日常食事環境における咀嚼音・嚥下音の自動認識
◎塚越 駿大・西田 昌史(静岡大学)・西村 雅史(静岡大学/愛知産業大学)
×
J-010会話を伴う日常食事環境における咀嚼音・嚥下音の自動認識
◎塚越 駿大・西田 昌史(静岡大学)・西村 雅史(静岡大学/愛知産業大学)
咀嚼・嚥下機能の低下は誤嚥性肺炎や窒息のリスクを高めるため、日常的かつ非侵襲な行動モニタリング手法として、皮膚接触型マイクを用いた咀嚼・嚥下の認識手法が検討されている。ただ、これまでの研究で評価されてきた食行動音の多くは防音室など制御環境での収録データに限定されており、会話や環境音が混在する実生活環境での有効性は未検証であった。本研究では、日常食事環境に近い実験設定で、3人1組が自由に会話しながら食事をする状況の試験系を構築した。自然な発話と食行動が混在する現実的な状況下でデータを収集し、SSLベースのモデルによるF1-score評価を通じて、実用的な摂食モニタリングの実現に向けた技術的課題を明らかにする。 |
| J-011 |
運転者対象物体検出能力の定量評価方式における注視点計測環境の改善
◎内山 怜哉・吉田 大祐・中田 洋平(明治大学)
×
J-011運転者対象物体検出能力の定量評価方式における注視点計測環境の改善
◎内山 怜哉・吉田 大祐・中田 洋平(明治大学)
近年,高齢運転者の運転能力低下と,それに伴う交通事故が社会問題化している.このような背景を受けて,著者らは,研究室で開発を進めてきている誘目性定量評価法と市販の装着型注視点計測システムを用いて,高齢運転者による交通事故の主要因の1つと言える対象物体検出能力を容易に定量評価可能な方式の提案を行ってきた.ただし,同方式で用いる注視点計測環境には,被験者に見せる運転状況動画像の内容や構成などに改善の余地があった.そこで,本稿では,同計測環境に対して,本邦の都市部での交通事故頻発状況を再現した運転状況動画像を拡充するなどして改善を図る.また,改善後の注視点計測環境を用いて,初期的な動作検証を実施する. |
| J-012 |
高齢者の自身の運転に対する過大評価の是正に影響する意識変化
◎井内 柊仁・吉武 宏(東京科学大学)・藤田 涼太(三菱プレシジョン)・小竹 元基(東京科学大学)
×
J-012高齢者の自身の運転に対する過大評価の是正に影響する意識変化
◎井内 柊仁・吉武 宏(東京科学大学)・藤田 涼太(三菱プレシジョン)・小竹 元基(東京科学大学)
高齢者は自身の運転を過大評価する傾向があり,それを是正することで安全運転に変容できる.そこで本研究では,高齢者の運転に対する意識変化により過大評価が是正されると考え,自己評価を効果的に適正化する安全運転教育手法を提案するため,過大評価の是正に影響する意識変化について検討した.高齢者を対象とした安全運転教育を体験する実験の結果より,高齢者は同年代のドライバと比較した自身の運転能力に対する楽観的意識が低くなることにより,過大評価の是正程度が大きくなることがわかった.そして,前記意識を安全運転教育により低減させることにより,効果的に過大評価を是正できる可能性が示唆された. |
| ヒューマン情報処理とその応用 |
|
9月4日(木) 9:30-12:00 4r会場
座長 石井 雅博(札幌市立大学) |
| J-013 |
Chatbotとの対話に基づいてパーソナリティ判定を行うシステムの構築と評価
○中津 良平・鈴木 天・土佐 尚子(京都大学)
×
J-013Chatbotとの対話に基づいてパーソナリティ判定を行うシステムの構築と評価
○中津 良平・鈴木 天・土佐 尚子(京都大学)
被験者に絵を見せて物語を作ってもらい、それに基づいて人の性格や心の状態を判断する方法としてTATと呼ばれる方法がある。この方法は人の無意識情報をベースとして性格判断や心の状態を知る方法として有名であるが、専門家と被験者の対面型で行われるという制限があり、これまで広くは使われてこなかった。我々は、TATにおける専門家をAIで置き換えることによって、誰もが気軽にAIと対話しながら自分の性格や心の健康状態を知ることのできるシステム(AI-TAT)を開発した。またそのシステムを30名の被験者にオンラインで使ってもらいシステムの評価を行った。ここではシステムの構成と評価実験の結果について報告する。 |
| J-014 |
マルチモーダル特徴量を用いたストレス推定モデルの構築
◎高鍋 俊樹・松本 和幸(徳島大学)・木内 敬太(労働者健康安全機構)・柏原 功太郎(ワークスアプリケーションズ)・梅原 英裕・中瀧 理仁・沼田 周助・吉田 稔・康 鑫(徳島大学)
×
J-014マルチモーダル特徴量を用いたストレス推定モデルの構築
◎高鍋 俊樹・松本 和幸(徳島大学)・木内 敬太(労働者健康安全機構)・柏原 功太郎(ワークスアプリケーションズ)・梅原 英裕・中瀧 理仁・沼田 周助・吉田 稔・康 鑫(徳島大学)
本研究では、動画データからストレス状態を推定する手法を検討した。オンラインカウンセリングデータセット(50名)を評価および学習用のデータセット、うつ面談データセット(84名)を学習用データセットとして用い、言語、音声、画像の特徴量を複数の特徴抽出モデルにより抽出した。10種類の特徴量の有効な組合せを確認するため、機械学習アルゴリズムを複数用いて50分割交差検証を実施した結果、音声、画像、言語特徴量を複数組み合わせてうつ面談データセットを学習データに加えた条件においてAccuracy 0.8以上を達成した。今後、ストレスチェックに向けた実用モデルの開発を目指す。 |
| J-015 |
マルチモーダルデータにおけるうつ状態検出のための音声特徴の抽出と比較
◎岡田 大和・高鍋 俊樹・松本 和幸(徳島大学)・柏原 巧太郎(ワークスアプリケーションズ)・木内 敬太(労働者健康安全機構)・梅原 英裕・中瀧 理仁・沼田 周助・吉田 稔・康 鑫(徳島大学)
×
J-015マルチモーダルデータにおけるうつ状態検出のための音声特徴の抽出と比較
◎岡田 大和・高鍋 俊樹・松本 和幸(徳島大学)・柏原 巧太郎(ワークスアプリケーションズ)・木内 敬太(労働者健康安全機構)・梅原 英裕・中瀧 理仁・沼田 周助・吉田 稔・康 鑫(徳島大学)
うつ病は世界的に深刻な精神疾患であり、客観的かつ効率的な検出手法の確立が求められている。本研究では、マルチモーダルデータを用いたうつ状態検出に有効な音声特徴量を明らかにすることを目的とし、OpenSMILEを用いて音声特徴量を抽出した。比較対象として、徳島大学が独自収集したインタビュー動画と、既存のDAIC-WOZデータセットを用いた。うつ状態検出は音声特徴量を用いてCNNで分類した。両データにおいてMFCCの寄与率が最も高く、さらに徳島大学データではスペクトル関連の特徴量の寄与率が高い傾向が見られた。本研究は、うつ状態検出における音声特徴量の有効性を示すものである。 |
| J-016 |
三次元歩行データにおける重要部位に基づく歩容認証精度の検証
◎松尾 玲亜・中川 竣介・廣瀬 誠(鳥羽商船高等専門学校)
×
J-016三次元歩行データにおける重要部位に基づく歩容認証精度の検証
◎松尾 玲亜・中川 竣介・廣瀬 誠(鳥羽商船高等専門学校)
本研究では、三次元歩行データを用いた歩容認証において、SHAP(SHapley Additive exPlanations)を用いて識別時に寄与度が高いと評価された特徴量のみを用いた場合の認証精度を検証する。従来のように全身データを必要とせず、部分的なデータのみで個人識別が可能かを評価することで、現実環境におけるカメラの死角や部分欠損といった課題への適用可能性を探る。LSTMおよびXGBoostによる機械学習モデルを用いて、AIST歩行データセットから抽出した50名分の三次元関節データを対象に実験を行い、特徴選択が認証精度に与える影響やモデル間の比較も含めてその有用性を検証する。 |
| J-017 |
実物と画像表示が段ボールを用いた防災グッズの印象に与える影響
○神亀 理恵・鈴木 彩留・堀田 裕弘(富山大学)
×
J-017実物と画像表示が段ボールを用いた防災グッズの印象に与える影響
○神亀 理恵・鈴木 彩留・堀田 裕弘(富山大学)
災害時に届けられる支援物資は段ボールを使用して輸送する場合が多いため、段ボールを防災グッズに変換することで、避難者の生活の質向上につながると考える。これまで、富山大学でのワークショップで作成した段ボール防災グッズを対象として因子分析やクラスター分析を実施し、感性評価の内容や重視するグッズの特徴を解明した。これは、実際にワークショップに参加した学生のアンケート調査に基づいた分析結果である。しかし、段ボール防災グッズを対象としたワークショップは多く開催するには費用と時間を要するので、簡便な画像表示によるアンケートが、多くの被験者データを収集しやすい。本研究では、段ボール防災グッズを作成した時のアンケート結果と、別途、画像表示により行ったアンケート結果との類似性や特異性について議論する。 |
| J-018 |
個人特性が段ボールを用いた防災グッズの印象に与える影響
◎鈴木 彩留・神亀 理恵・堀田 裕弘(富山大学)
×
J-018個人特性が段ボールを用いた防災グッズの印象に与える影響
◎鈴木 彩留・神亀 理恵・堀田 裕弘(富山大学)
災害時に届けられる支援物資は段ボールを使用して輸送する場合が多いため、段ボールを防災グッズに変換することで、避難者の生活の質向上につながると考える。
これまで、富山大学でのワークショップで作成した段ボール防災グッズを対象として因子分析やクラスター分析を実施し、感性評価の内容や重視するグッズの特徴を解明した。しかし、被災経験をはじめとする個人特性がグッズの評価に与える影響については、被災経験者の割合が少なく、課題が残されていた。
そこで、本研究では能登半島地震の発生により被災経験者が増えたと考えられる今、再アンケートを実施し、2回のアンケート結果の違いや、個人特性がグッズの評価に与える影響について分析・考察する。また、グッズを実物と画像で示した際の評価の違いについても考察する。 |
| インタラクションと視行動 |
|
9月4日(木) 15:30-17:30 5r会場
座長 中島 誠(大分大学) |
| J-019 |
悩みを相談しやすくするためのロボットの対話プロセスのデザイン
◎佐野 航太朗(立命館大学)・安尾 萌(立命館グローバル・イノベーション研究機構)・Shan Junjie・西原 陽子(立命館大学)
×
J-019悩みを相談しやすくするためのロボットの対話プロセスのデザイン
◎佐野 航太朗(立命館大学)・安尾 萌(立命館グローバル・イノベーション研究機構)・Shan Junjie・西原 陽子(立命館大学)
人は他者に対して自らが抱いている悩みを気軽に相談できない場合がある.悩みの相談が容易にできれば,悩みすぎて心身に不調が出てしまうことを防ぐことができる.本研究では,人が悩みを相談しやすくするためのロボットの対話プロセスを提案する.提案する対話プロセスは,初めにロボットから人に対して助けを求め,人が助けてくれたら謝意を示し,その後,悩みはないかと尋ねる.人が悩みを話してくれたら,解決方法のアイデアを提示し,悩みの軽減を目指すものである.被験者実験の結果,提案手法により悩みを相談しやすくなる効果が確認された. |
| J-020 |
VRコンテンツにおけるマルチモーダル情報の質と鑑賞者の視行動パターン・VRコンテンツ記憶の間の関係分析
◎中川 太一・中平 勝子・北島 宗雄・T.L.A.N. Chandrasiri(長岡技術科学大学)・小川 信之(岐阜工業高等専門学校)・矢島 邦昭(仙台工業高等専門学校)
×
J-020VRコンテンツにおけるマルチモーダル情報の質と鑑賞者の視行動パターン・VRコンテンツ記憶の間の関係分析
◎中川 太一・中平 勝子・北島 宗雄・T.L.A.N. Chandrasiri(長岡技術科学大学)・小川 信之(岐阜工業高等専門学校)・矢島 邦昭(仙台工業高等専門学校)
本稿は記憶しやすいVRコンテンツ設計へ向けた基礎研究として,VR空間で呈示されるマルチモーダル情報の質とユーザの注意および記銘量の関係を分析する.対象VRコンテンツは,前提知識が少ないと考えられる神社の建物構造とする.質を調整する呈示情報は視覚・聴覚を対象とし,視覚については配置するオブジェクト数,聴覚については音質および音量をパラメータとした.ユーザの注意に相当する量として,特定オブジェクに対する視線停留時間を採用した.以上の環境を整え,記銘のしやすさとマルチモーダル処理の結果としての注視には一定の関係があると考え,パラメータの組み合わせを変化させた際の視線停留時間と記憶の量・質の違いを比較する. |
| J-021 |
文章読後の意識的選好結果と無意識的視行動の関連性分析
◎伊藤 健人・北島 宗雄・中平 勝子(長岡技術科学大学)
×
J-021文章読後の意識的選好結果と無意識的視行動の関連性分析
◎伊藤 健人・北島 宗雄・中平 勝子(長岡技術科学大学)
AI技術の発展により,様々な領域で人とAIの協働が進んでいる.特に文章作成分野では,文章の選好がAIの出力と人の認知処理の調和を見極める手がかりとなり,その背景にある認知メカニズムの理解は協働の質向上に役立つ.本稿は,文学作品の人もしくはAIによる翻訳文を呈示刺激として用いた読者の選好判断と視行動の関連性を分析する.その際,文章選好過程には文体や表現に対する無意識的な評価過程が存在し,これは言語化されないまま視行動パターンに現れるという仮説に対する一定の知見を得る.本稿は,発展的に,知的活動における人とAIの特性理解と効果的な協働の可能性を探ることに資するものである. |
| J-022 |
イラストの輪郭点群抽出に基づく3Dプリンタブルロボットのインタラクティブデザイン
◎稲川 ジャン瑠海・小川 純(山形大学)
×
J-022イラストの輪郭点群抽出に基づく3Dプリンタブルロボットのインタラクティブデザイン
◎稲川 ジャン瑠海・小川 純(山形大学)
本研究は、イラスト画像から抽出した輪郭点群に基づいて、ヒンジ構造を有する3Dプリンタブルなソフトロボットを設計・生成する手法を提案する。ユーザはインタラクティブなGUI上で輪郭を点群として確認し、マウス操作により任意の2点を指定する。その後、GUI出力機能により、輪郭形状に厚みを持たせた3D構造と、指定点間にヒンジを含む可動構造を定義できる。さらに、本手法では、生成された形状をOpenSCAD形式で自動出力し、構造モデルの修正や再利用を容易にする。加えて、ソフトマター素材による層構造とその膨張・収縮特性を活用することで、生成モデルをソフトロボットとして機能させることが可能となることを示す。 |
| J-023 |
駐車時における自動車ハンドルの回転角フィードバックシステムの評価
◎花山 勝吾・山本 匠・杉浦 裕太(慶應義塾大学)
×
J-023駐車時における自動車ハンドルの回転角フィードバックシステムの評価
◎花山 勝吾・山本 匠・杉浦 裕太(慶應義塾大学)
自動車の駐車には慣れが必要であり,特に運転初心者によく見られる現象として,バック駐車時にハンドルの回転角が分からなくなるというものがある.そのため,タイヤの向きや予想進路を視覚的に提示することでドライバーにハンドルの回転角を知覚させるシステムが自動車に搭載されていることも多い.
本研究では,こうしたハンドルの回転角をフィードバックするシステムが駐車時の運転に影響を与えているのかを検証するため,ハンドル回転角をリアルタイムにフィードバックするシステムを実装し,運転シミュレータを用いて10人の被験者に駐車実験を行ってもらった.フィードバックシステムとしては視覚フィードバックに加え,新たな可能性として聴覚フィードバックと振動フィードバックも実装した. |
| インタフェース |
|
9月5日(金) 9:30-12:00 6q会場
座長 吉高 淳夫(JAIST) |
| J-024 |
空中フリック入力における非接触触覚フィードバック提示
◎有賀 光希・渡邉 俊哉(群馬工業高等専門学校)
×
J-024空中フリック入力における非接触触覚フィードバック提示
◎有賀 光希・渡邉 俊哉(群馬工業高等専門学校)
ハンドトラッキングを用いた空中でのフリック入力では,スマートフォンなどの平面操作と異なり触覚フィードバックが得られず,操作性に課題がある.これまでにウェアラブルデバイスを用いた触覚提示が提案されているが,非接触型の手法は一般的ではない.本研究では,ハンドトラッキングを用いた仮想フリック入力キーボードに,超音波による音響放射圧を用いた空中触覚刺激を組み合わせたシステムを構築した.空中でのフリック入力における非接触の触覚フィードバックの有用性を検証することを目的とし,仮想キーボードの入力時の触覚刺激の有無や聴覚刺激との比較による主観評価実験を実施した. |
| J-025 |
表面筋電位を用いた手描画内容の再現の検討
◎周 子越・田村 仁・望月 典樹(日本工業大学)
×
J-025表面筋電位を用いた手描画内容の再現の検討
◎周 子越・田村 仁・望月 典樹(日本工業大学)
本研究は,表面筋電位を用いて手描画動作の方向を推定し,描画内容を再現する手法を提案する.上下左右の4方向と,斜め方向を加えた8方向へ手を動かす動作の表面筋電位データを収集し,深層学習により方向を推定するモデルを構築する.自由に手描画する時の表面筋電位データを一定時間間隔で分割し,各分割時間内の手の運動方向を推定し,推定方向に基づき,描画時間内の全ての方向ベクトルを繋ぎ,手描画の内容を再現することが本研究の目的である.LSTMやTransformerを用いた結果,方向認識は高精度を示したが,描画再現には限界も確認された.特にセンサの位置ずれや動作条件が再現精度に影響することが明らかとなった. |
| J-026 |
IMU搭載ヘッドホンを用いた注視位置の簡易推定
◎森 友吾・佐藤 光起・松下 光範(関西大学)
×
J-026IMU搭載ヘッドホンを用いた注視位置の簡易推定
◎森 友吾・佐藤 光起・松下 光範(関西大学)
本研究の目的は、ユーザの注視した座標を頭部姿勢に基づいて推定することである。ユーザは、何かに興味を示したり、操作したりする際に、対象に注目するため、その方向に顔を向ける。そのため、ユーザの顔が向いている方向を検出することができれば、ユーザの注目している対象を推定することが可能になる。そこで本研究では、ユーザが装着するIMU搭載ヘッドホンから取得した回転角を用いて頭部姿勢を取得し、そのユーザの注視位置を推定する手法を提案する。本稿では、ユーザ注視位置と、システムが推定した座標を比較することで提案手法の有効性を検証するとともに、想定される使用方法について議論する。 |
| J-027 |
骨格情報の時空間パターンを用いたハンドジェスチャ認識
◎河村 寛生・中井 満(富山県立大学)
×
J-027骨格情報の時空間パターンを用いたハンドジェスチャ認識
◎河村 寛生・中井 満(富山県立大学)
ロボットとの協働空間において、円滑なコミュニケーションのために人の指示動作を認識することは重要である。本研究では「手を握って開く」、「手を振る」、「手を上下させる」、「親指を立てる」、「指を差す」、「手を突き出す」など、指示や操作でよく使われる日常動作の認識を目的とする。RGBカメラの正面に立って操作を行う場面を想定し、奥行方向を含む立体的な動作を捉えるために3次元空間での骨格を推定できるMediaPipeを使用する。両手の関節の骨格情報を時系列グラフとして表現し、これを入力としてST-GCNによってジェスチャを認識するシステムを提案する。 |
| J-028 |
仮想空間上の四脚歩行モデルに対するパッシブジョイントによる柔軟な身体性の拡張がゲームパッド操縦性に与える効果検証
◎城宝 一司・小川 純(山形大学)
×
J-028仮想空間上の四脚歩行モデルに対するパッシブジョイントによる柔軟な身体性の拡張がゲームパッド操縦性に与える効果検証
◎城宝 一司・小川 純(山形大学)
本研究では、Unity Engine上に構築した四脚歩行ロボットモデルを用いて、身体の柔軟性が操縦性に与える効果を検証する。各脚のメインジョイントに対して、バネ・ダンパ特性を持つパッシブなサブジョイントを周囲に複数付加し、仮想的な柔軟構造を実現することで、身体性の拡張を再現する。ユーザのゲームパッドによる手動操縦を通じて、柔軟構造の有無や構成パターンの違いが操作時の応答性や安定性に与える影響を比較評価する。 |
| J-029 |
LSTMを用いた空書き文章からの筆跡抽出
◎荒木 奏瑠・中井 満(富山県立大学)
×
J-029LSTMを用いた空書き文章からの筆跡抽出
◎荒木 奏瑠・中井 満(富山県立大学)
VR空間での効率的な意図伝達において手書きは有用である。しかし、空中で一画ずつ文字を書くためにはボタン操作やピンチ動作を挟むことになり不自然かつ筆記時間を要するという問題がある。これに対し、自然な一筆書きから、LSTM を用いて筆画を切り出すインタフェースを提案する。FIT2024では、文字単位で筆記区間と非筆記区間をラベル付けして学習した結果、筆跡の95.2%の区間を正しく切り出した。本発表ではこれを一筆書きの文字列に拡張し、文字間の不要な筆跡も自動消去することで筆記時間の短縮を図る。 |
| J-030 |
GCN-LSTMを用いた指差し指示位置の推定
◎中川 莉那・中井 満(富山県立大学)
×
J-030GCN-LSTMを用いた指差し指示位置の推定
◎中川 莉那・中井 満(富山県立大学)
近年,ジェスチャインタフェースによって機器の操作が可能になっており,スクリーン上の指差し指示位置を推定する研究が行われている.本発表では右手および全身の姿勢グラフを用いた,グラフ畳み込みネットワーク(GCN)で推定する手法を提案する.RGBカメラより骨格情報,Depthカメラより深度情報を取得し,これらより全身の関節の座標を得る.FIT2024では静止した状態で指差し指示位置を推定した.今回は動く指示点を差すことを目的とし,動画像からGCN-LSTMを用いて推定することを検討する. |
| 視聴覚と理解 |
|
9月5日(金) 9:30-12:00 6r会場
座長 石井 雅博(札幌市立大学) |
| J-031 |
感情誘発語を含む短文聴取時の感情生起に対する確信度と記銘しやすさの関係
◎長谷川 渉・森谷 隼介・北島 宗雄・中平 勝子(長岡技術科学大学)
×
J-031感情誘発語を含む短文聴取時の感情生起に対する確信度と記銘しやすさの関係
◎長谷川 渉・森谷 隼介・北島 宗雄・中平 勝子(長岡技術科学大学)
本稿は,自身の感情生起に対する確信度と記銘の有無の関係を調べるため,視線の認知処理傾向・心理状態の表出しやすさを利用する.確信度の高低とサッケード数・停留時間に一定の関係があると仮説を立て,感情要素を含む聴覚刺激聴取後の印章評定時視行動と聴取情報に対する記憶再生テストの結果を分析する.実験では,被験者に2つの日本語訳感情誘発語を含む短文を聴取させた後,短文に対してポジティブ・ネガティブの程度で印象評価を回答させる.加えて,一定数の短文聴取後に,自由再生法による記憶再生テストを行わせる.確信度の違いは注視する選択肢数,注視時間に表れると考え,選択肢ごとの停留時間,サッケード数を主に分析する. |
| J-032 |
瞬き頻度による疲労判断システムのためのデータセット調査
◎曽 憲超・山田 光穗・星野 祐子(東海大学)
×
J-032瞬き頻度による疲労判断システムのためのデータセット調査
◎曽 憲超・山田 光穗・星野 祐子(東海大学)
本研究では,高精度な疲労判定システムの開発を目指し,まばたき頻度を用いたアジア人向け疲労検知システムの構築に向け,既存の顔および眼部データセットの調査を行った.調査の結果,多くのデータセットが欧米人を対象としており,アジア人特有の眼の形状や開閉パターンに最適化されていないことが明らかとなった.また,アジア人に特有な眼の動きや傾向の違いを分析し,アジア人の眼部特徴に基づく新たなデータセットの設計および,Dlibによる顔特徴点検出,Eye Aspect Ratioを用いたまばたき頻度や閉眼持続時間の分析による疲労度検知システムの提案を行った. |
| J-033 |
Web閲覧中の視線と動画を活用した情報推薦装置の提案
◎李 昊聞・山田 光穗(東海大学)・石井 英里子(鹿児島県立短期大学)・星野 祐子(東海大学)
×
J-033Web閲覧中の視線と動画を活用した情報推薦装置の提案
◎李 昊聞・山田 光穗(東海大学)・石井 英里子(鹿児島県立短期大学)・星野 祐子(東海大学)
近年情報通信技術の発展により,インターネットの普及率は増加し,Web上で提供される情報も増加する一方である.このような膨大な情報の中からユーザーが本当に自分に必要な情報を見つけ出すことは困難である.我々の研究ではWebサイト閲覧中のユーザー視線情報をもとに取得した注視文章と静止画像からユーザーの嗜好を抽出し,観光関連の検索キーワード推薦システムを開発している.しかしながら,Web観光サイトは文章と静止画だけではなく,観光スポットの「説明用動画」も載せていることも多い.そこで,本研究では既存システムへ動画のユーザー注視情報抽出機能の追加を提案する. |
| J-034 |
グラフ読み取り時における注視パタンと読み取り内容の整合性分析
◎曽根 寛大・小笠原 優心・家頭 裕也・中平 勝子(長岡技術科学大学)
×
J-034グラフ読み取り時における注視パタンと読み取り内容の整合性分析
◎曽根 寛大・小笠原 優心・家頭 裕也・中平 勝子(長岡技術科学大学)
情報社会の進展により,我々は日常的に大量のデータに接している.中でもグラフは数値が示す意味とそれを読み解く人をつなぐインターフェースとみなすことができる.従って,グラフによる情報提示の最適化は,呈示されたグラフを読む者(リーダー)の視行動や認知的操作を捉える必要があると考えられる.本研究では,グラフ読み取り時の視線計測と記述回答のデータを取得し,注視パターンと回答内容の整合性を分析する.認知的操作のモデル化により,リーダーがどのように情報を処理し,記述に変換しているかを可視化する.このモデルをもとに,リーダーのグラフ読解視点を広げるためのアノテーション付与設計に資する. |
| J-035 |
グラフ読解における視覚的複雑度と解釈要因の抽出
◎小笠原 優心・曽根 寛大・家頭 裕也・中平 勝子(長岡技術科学大学)
×
J-035グラフ読解における視覚的複雑度と解釈要因の抽出
◎小笠原 優心・曽根 寛大・家頭 裕也・中平 勝子(長岡技術科学大学)
形をもつものとしての視覚情報を,時間や字数などの制約条件下で言語として他者に伝達する際,伝達者の視点によって伝えられ方が異なることが考えられる.本稿では,伝達者の視点による伝達内容の差異に関する基礎研究として,数値を視覚的に情報伝達する手法としてのグラフを対象とし,その読解に影響する潜在要因を抽出する.対象とするグラフには,軸数によって単純な低次グラフと視覚的複雑度が高い高次グラフが存在し,読解に影響する要因が多岐にわたると考えられる.本稿では,呈示されたグラフから読み取られた内容の記述データをもとに,グラフの形状特徴と照合することで伝達者視点を集約し,視覚的複雑度の整合性を分析する. |
| J-036 |
絵画鑑賞における視線誘導のための聴覚情報付与が記憶に与える影響
◎小西 廉也・小竹 元基(東京科学大学)・中平 勝子・北島 宗雄(長岡技術科学大学)
×
J-036絵画鑑賞における視線誘導のための聴覚情報付与が記憶に与える影響
◎小西 廉也・小竹 元基(東京科学大学)・中平 勝子・北島 宗雄(長岡技術科学大学)
絵画等の美術作品の鑑賞行動に対し鑑賞者の視聴覚情報の認知処理を考慮した支援を行うことは,鑑賞教育の視点で有益である.本研究では,知識獲得の前段階である記憶形成に着目し,絵画鑑賞時に記憶形成に至る認知処理を促す聴覚情報の提案を目指す.鑑賞実験は,絵画内の解説対象へ視線を誘導する情報と対象に関する新たな情報を設定した音声ガイド付きでディスプレイ上に絵画を提示し,鑑賞中の視行動の計測と,鑑賞後に記憶テストを行った.解説対象に対する鑑賞者の視行動を,その対象と鑑賞者の注視箇所間の距離に基づき分類した結果,その距離が記憶に影響することが示唆された.そこから,鑑賞者の認知処理について考察した. |
| 支援とメンタル |
|
9月5日(金) 13:10-15:40 7q会場
座長 小川 純(山形大学) |
| J-037 |
部屋の片づけ術を活用したブックマークの自動整理機能
◎宮本 凜音・中島 誠(大分大学)
×
J-037部屋の片づけ術を活用したブックマークの自動整理機能
◎宮本 凜音・中島 誠(大分大学)
日常的なWWWの利用に伴ってウェブブラウザ上に増えていく大量のブックマークを,
ユーザの心理的負担を軽減しながら効率的に管理・活用するための整理機能を提案
する.提案する機能では,「断捨離(R)」の思想や物理的な片づけ術を参考に設計し,ユーザがブックマークを無意識に溜め込んでしまう状況に対処する。具体的には,自動削除機能や通知機能などの5つの機能をGoogle Chrome拡張機能として実装し,普段のブラウジングを邪魔することなく自然にブックマークを整理できる.被験者による2週間の使用実験とアンケート調査により,本機能がブックマークの利用促進と管理効率の向上に寄与し,従来の情報管理を改善する可能性があることが示された. |
| J-038 |
PCを介したテキストコミュニケーションにおけるニュアンス表現支援システム
◎首藤 尚熙・中島 誠(大分大学)
×
J-038PCを介したテキストコミュニケーションにおけるニュアンス表現支援システム
◎首藤 尚熙・中島 誠(大分大学)
現代のテキストコミュニケーションでは、「感情やニュアンスが伝わりにくい」「文字だけでは誤解を招きやすい」といった課題がある。絵文字はそれを補う有効な手段とされているが、PC環境では入力の手間や活用不足が問題視されている。そこで本研究では、送信メッセージの内容に応じて適切な絵文字を自動で提案・表示するシステムを開発し、ニュアンスの補足や誤解の軽減に寄与するかを検証した。評価実験では、送信者・受信者双方に対するアンケートを通じて効果を測定し、有効性が一定程度確認された。一方で、絵文字の選定精度や表示方法の改善も今後の課題として示された。 |
| J-039 |
運動強度向上のための動機づけメッセージ提示技術に関する研究
◎井坂 圭太(公立はこだて未来大学)・佐藤 妙・藤村 香央里・片桐 有理佳(NTT社会情報研究所)・佐藤 生馬・石榑 康雄(公立はこだて未来大学)
×
J-039運動強度向上のための動機づけメッセージ提示技術に関する研究
◎井坂 圭太(公立はこだて未来大学)・佐藤 妙・藤村 香央里・片桐 有理佳(NTT社会情報研究所)・佐藤 生馬・石榑 康雄(公立はこだて未来大学)
近年,生活習慣病の増加が健康や医療費の観点で深刻な課題となっており,その予防には運動が重要であるが,家事や仕事が忙しいなどの理由により,運動時間を十分に確保できない現状がある.このため,短時間で効果的な運動を実現するには,運動強度を高めることが有効と考えられる.一方,運動や食事に関するメッセージによる動機づけの研究も進んでいる.本研究では,運動中に提示する音声メッセージ,特に社会的自己イメージを脅かす「Impoliteメッセージ(例:こんなものですか?)」と,社会的自己イメージを強化する「Politeメッセージ(例:この調子!)」を比較し,主観・客観の両面からその効果を検証した. |
| J-040 |
脳波デバイスと大規模言語モデルを用いた文脈適応型対話システムの提案 : "空気を読む" AIエージェントの評価
◎茶谷 瑛佑・佐藤 啓宏(京都先端科学大学)
×
J-040脳波デバイスと大規模言語モデルを用いた文脈適応型対話システムの提案 : "空気を読む" AIエージェントの評価
◎茶谷 瑛佑・佐藤 啓宏(京都先端科学大学)
脳波(EEG)は集中や疲労などの内的状態を反映する生体信号であり、近年ではこれを用いた心理状態の推定技術が進展している。一方、大規模言語モデル(LLM)の普及により対話型AIが広まる中、人間のように「空気を読む」柔軟な対話の実現には課題が残る。脳波デバイスを用いてユーザーの心理状態の変化を推定し、それに応じてLLMが適切な応答を生成することを目指す。具体的には音声入力に加え、脳波から得られるα波やβ波といった集中や疲労などの内的状態を反映する周波数帯の変化をもとにユーザーの心理状態を推定し、応答の文体や話題を動的に調整する手法を提案する。これにより、ユーザーが明示的な操作を行わずとも自然な対話が可能となる。 |
| J-041 |
量子アルゴリズム論文に見る図解表現の機能と形式
○笹倉 万里子・岩田 健一(鳥取大学)
×
J-041量子アルゴリズム論文に見る図解表現の機能と形式
○笹倉 万里子・岩田 健一(鳥取大学)
量子アルゴリズムの研究では,アルゴリズムの構造や量子回路の動作,理論的関係性などを視覚的に表現する図が用いられる.本発表では,主要な量子アルゴリズム論文を調査し,図の使用目的および図の種類・表現形式に関する分類を試みた結果を報告する.本研究は,量子アルゴリズムの研究発表や教育資料の作成に関して・図の活用という観点から示唆を与えることを目的とする. |
| J-042 |
娯楽とタスクを結びつける習慣化支援手法の検討
◎長峯 幸佑・柏原 悠斗・平山 真愛・山口 直彦(東京国際工科専門職大学)・本多 賢(事業創造大学院大学)
×
J-042娯楽とタスクを結びつける習慣化支援手法の検討
◎長峯 幸佑・柏原 悠斗・平山 真愛・山口 直彦(東京国際工科専門職大学)・本多 賢(事業創造大学院大学)
学校教育やリスキリング、リカレント教育などによるスキルアップにおいては、中長期的に地道な自己学習を継続する姿勢が求められることが多い。一方で、現代では多くの娯楽が存在する。その結果、多くの時間がこうした娯楽に費やされているため、自己学習のようなタスクを日常的に継続することが困難である。そこで、すでに習慣化されている娯楽を報酬と捉え、継続が難しいタスクと結びつけることで、タスク実行の習慣化を促せると我々は考えた。本稿では、娯楽とタスクを結びつける手法を取り入れた習慣化支援モバイルアプリを実装し、ユーザへのアンケート調査により有用性と実現可能性を検討する。 |
| J-043 |
多視点議論を促す地政学的報道スタンス可視化・情報推薦エージェントの提案
◎櫻井 崇貴・川島 壮生・長澤 史記・白松 俊(名古屋工業大学)
×
J-043多視点議論を促す地政学的報道スタンス可視化・情報推薦エージェントの提案
◎櫻井 崇貴・川島 壮生・長澤 史記・白松 俊(名古屋工業大学)
国際的なニューストピックに対する報道は、国や地域によってスタンスや論調が大きく異なることがある。こうした違いに気づかないまま情報に接することで、個人の認知に偏りや誤解が生じる可能性がある。本研究では、大規模言語モデル(LLM)を活用し、複数言語で各国の報道内容を取得・分析することで、地政学的なスタンスの違いを対話的に提示・補足するエージェントの試作を行う。ユーザとのインタラクションを通じて、ニューストピックに対する各国の反応や視点の差異をマップや表で可視化しながら、必要に応じた情報推薦を行い、言語や文化的背景が異なる相手との議論においても有益な多視点的理解や意見形成を支援することを目的とする。 |