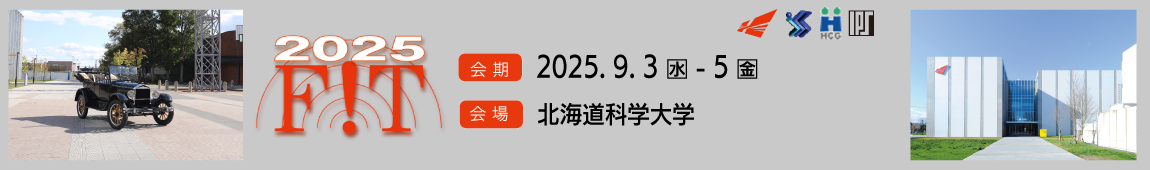| K分野 教育工学・福祉工学・マルチメディア応用 |
選奨セッション
メタバース, 教育工学, 福祉情報工学 |
|
9月3日(水) 9:30-12:00 1j会場
座長 酒向 慎司(名古屋工業大学)
酒向 慎司(名古屋工業大学) |
| CK-001 |
点群圧縮を活用したメタバース体験の低コスト化に関する取り組み
○阿部 直人・徳永 徹郎・望月 崇由(NTT人間情報研究所)
×
CK-001点群圧縮を活用したメタバース体験の低コスト化に関する取り組み
○阿部 直人・徳永 徹郎・望月 崇由(NTT人間情報研究所)
近年、観光分野やエンタメ分野においてメタバースの活用が盛んに検討・検証されており、我々は点群データを用いた仮想空間の構築と関係人口創出に向けて取り組んでいる。一方で、点群データは3D仮想空間を構築し易い利点があるものの、データ量が膨大なため高性能なPCを利用しないと没入感や操作性が損なわれる問題があった。本研究では、点群圧縮を利用して、没入感や操作性が損なわれることなく汎用端末でも点群データの仮想空間が体験可能か評価実験を行ったので報告する。 |
| CK-002 |
スマートフォンを活用した高校生向けAIプログラミング教育システムの開発と評価
○加納 徹(茨城大学)
×
CK-002スマートフォンを活用した高校生向けAIプログラミング教育システムの開発と評価
○加納 徹(茨城大学)
近年、AI技術の急速な拡大に伴い、自ら設計・開発できる人材の育成や、高校生を対象としたAI教育の必要性が高まっている。そこで本研究では、スマートフォンを活用した高校生向けAIアプリ開発の体験型授業を設計・実施し、その効果を検証した。教材には、顔認識技術を用いたWebアプリをJavaScriptで開発できる自作のプログラミング環境を用意した。高校生58名を対象としたアンケート調査(有効回答率79%)の結果、91%が「楽しかった」、87%が「プログラミングに興味を持った」と回答した一方で、AIアプリ開発が「簡単であった」と感じたのは39%にとどまった。本教材は学習意欲の向上に有効である一方、難易度や支援方法には改善の余地があることが示唆された。 |
| CK-003 |
GPTベースの対話型AIを用いた,育児中の保護者のメンタルヘルス支援に関する実用性の研究
◎田 栗華・飯島 泰裕(青山学院大学)
×
CK-003GPTベースの対話型AIを用いた,育児中の保護者のメンタルヘルス支援に関する実用性の研究
◎田 栗華・飯島 泰裕(青山学院大学)
本研究は、育児中の保護者のメンタルヘルス支援を目的として、GPTベースの音声対話型AI「ミライちゃん」の実用性を検討するものである。近年、日本ではワンオペ育児や育児孤立が深刻化しており、心理的な孤独や不安に対する支援の必要性が高まっている。本研究では、ミライちゃんを実際に育児中の保護者に使用してもらい、共感性・安心感・アドバイスの質などを評価する。得られたフィードバックを質的に分析し、AIとの対話がどのように心理的支援につながるかを検証する。今後はプロンプト設計の最適化を通じて、より効果的な対話支援モデルの開発を目指す。 |
| CK-004 |
手話CGアニメーション生成における空間位置制御手法の評価
○内田 翼・箱﨑 浩平・金子 浩之(日本放送協会)
×
CK-004手話CGアニメーション生成における空間位置制御手法の評価
○内田 翼・箱﨑 浩平・金子 浩之(日本放送協会)
手話を母語とする聴覚障害者の情報保障のため,日本語の情報を手話に翻訳して手話Computer Graphics(CG)を生成する技術の研究を進めている.手話CGにおいて,話者正面の位置で表出した手話単語のモーションデータを補間接続するだけでは,文脈に応じて変化する手話の空間位置が再現できず,手話文中の複数の固有名詞や文節の切れ目が伝わりにくい課題があった.本研究では,モーションデータの提示位置を文脈に応じて左右に制御することで,手話の空間表現を再現する手法を提案する.評価実験を通じて,提示位置を制御することで手話CGの内容理解に関する質問の正答率が向上し,日本語文の内容をより正確に表現できることが示された. |
| CK-005 |
画像計測を用いた手指リハビリデバイスの制御
◎北里 元・愛川 雄大・熊谷 大和・三枝 亮(神奈川工科大学)
×
CK-005画像計測を用いた手指リハビリデバイスの制御
◎北里 元・愛川 雄大・熊谷 大和・三枝 亮(神奈川工科大学)
近年,手指拘縮患者の症状の維持,改善を目的としたソフトアクチュエータや外骨格等のデバイスを用いたリハビリテーションが行われている.これらの研究されているリハビリテーションデバイスは人間の手指の構造特徴を捉えた装置や空気圧を用いた軽量な装置が見受けられる.しかしながら,これらの既存の装置は動作の自由度が少ないため運動内容を変更できず,リハビリテーションの効果を向上させることが難しい.本研究では,耐水性能のあるリハビリテーションデバイスを用いて温浴下で手指の温度を高め,リハビリテーションの効果を向上させる.また,画像計測を用いて手指動作の異常を検出し,動作の安全性を確保したリハビリプログラムを提案する. |
| メディアエクスペリエンス |
|
9月3日(水) 13:10-15:10 2t会場
座長 山崎 俊彦(東京大学) |
| K-001 |
深海生物の遊泳映像とヒトの心拍音を用いたセラピアVRによるリラックス効果の検証
◎多田 悠里花(湘南工科大学)・宮川 勲(名古屋短期大学)・浅野 俊幸(湘南工科大学)
×
K-001深海生物の遊泳映像とヒトの心拍音を用いたセラピアVRによるリラックス効果の検証
◎多田 悠里花(湘南工科大学)・宮川 勲(名古屋短期大学)・浅野 俊幸(湘南工科大学)
本研究は、癒しとリラクゼーションを目的としたセラピアVRシステムの改良と、その生理的影響に関する深掘りを行ったものである。従来のセラピアVRは、主に痛みや不安の緩和に活用されてきたが、我々は快適な睡眠誘導への応用に着目し、深海生物がゆったりと泳ぐ映像と心拍音を組み合わせた新たなVRシステムを提案する。これにより、視覚と聴覚の両面からリラクゼーションを促進し、血圧や心拍数の安定化を図ることを目的としている。本研究では、心拍数の収束に着目し、提示された心拍音との同調効果が自律神経に作用している可能性を示す。
以上より、本システムは睡眠支援に有効なリラクゼーション手法として有望であり、心拍の安定化メカニズムはその効果を支える重要な要因と考えられる。 |
| K-002 |
コンサート自由視点映像視聴時の嗜好を考慮したカメラワーク生成手法の検討
◎瀬谷 諒太・北原 格・謝 淳(筑波大学)
×
K-002コンサート自由視点映像視聴時の嗜好を考慮したカメラワーク生成手法の検討
◎瀬谷 諒太・北原 格・謝 淳(筑波大学)
コンサートのオンライン配信が拡大しているが、配信映像のカメラワークはカメラマンや演出家によって決定され、視聴者が視点を自由に選ぶことはできない。視聴者ごとに注目シーンは異なり、専門家によるカメラワークが常に最適とは限らないため、個々の嗜好に応じた映像が求められる。音楽やダンスに基づく自動カメラワーク生成は研究されているが、視聴者の嗜好を反映する手法は確立されていない。本研究では、自由視点映像の視聴中に操作されたカメラの位置・回転を嗜好とみなし、嗜好に基づくカメラワーク生成手法を検討する。音楽・ダンスと操作履歴を拡散モデルで学習し、最適なカメラワークの自動生成を目指す。 |
| K-003 |
HMDとQRコードを活用した文化財展示向けのARシステム
◎YAN YONGXIANG・赤嶺 有平(琉球大学)
×
K-003HMDとQRコードを活用した文化財展示向けのARシステム
◎YAN YONGXIANG・赤嶺 有平(琉球大学)
デジタル化の進展に伴い、文化施設はコンピュータとインターネットを活用したオンライン文化伝播で大きな成果を上げている。一方、来館者の知的好奇心を十分に満たすオフライン展示の在り方は、依然として重要な研究課題である。従来の展示手法は主に文字、画像のパネルや映像モニターに依存しており、近年の学術研究では手持ち端末やヘッドセットの利用が注目されている。本研究は、文化財展示の魅力を高め、来館者の学習意欲を喚起して学習効果を最大化することを目的に、HMDとQRコードを組み合わせた拡張現実展示システムを提案する。 |
| K-004 |
Meta Quest 3から取得される自己位置情報を用いた3次元再構成パイプラインの検討
◎太田 貴士・葛岡 英明(東京大学)
×
K-004Meta Quest 3から取得される自己位置情報を用いた3次元再構成パイプラインの検討
◎太田 貴士・葛岡 英明(東京大学)
近年、さまざまな3Dシーン再構成技術の発展により、実環境を反映したバーチャル環境や仮想物体を活用した新たなメディア体験の可能性が模索されている。しかし、3D Gaussian Splattingをはじめとするこれらの技術では、学習の前段階としてCOLMAPなどを用いたカメラポーズ推定が必要であり、特に3D Gaussian Splattingでは、入力画像の枚数に比例して処理時間が増加するCOLMAPの計算がボトルネックとなることがある。そこで、筆者らはARデバイスの外部カメラで撮影された画像を用いて即時に3Dシーンを再構成するような場面においては、Meta Quest 3のようなデバイスでは自己位置が取得できることに着目した。本研究では、Meta Quest 3から得られるカメラ位置情報を活用し、COLMAPと同形式のカメラポーズ情報を生成することで、3D再構成パイプライン全体の処理時間の短縮を目指した。 |
| 福祉情報工学1 |
|
9月3日(水) 15:30-17:30 3t会場
座長 菅野 亜紀(富山大学) |
| K-005 |
重度心身障碍児を対象としたスイッチ教材による因果関係の理解を支援するシステム
◎利根川 瑛・粂野 文洋(日本工業大学)
×
K-005重度心身障碍児を対象としたスイッチ教材による因果関係の理解を支援するシステム
◎利根川 瑛・粂野 文洋(日本工業大学)
重度心身障碍児の認知機能の向上のためにはスイッチ教材が有効であるとされ、スイッチ教材による入力と接続された機器の動きの因果関係を学習する教育が広く実施されている。様々な形状のスイッチ教材が開発されており、改造した無線マウスを活用し、PCを操作するスイッチ教材も教育現場で利用されている。本研究では、肢体不自由の特別支援学校と連携し、従来のスイッチ教材に関する利用上の課題を調査したうえで,その課題を解決し,より多くの教育場面での利用を目指すシステムの研究開発を行っている.本論文ではそのシステムのプロトタイプ実装,実際の教育現場での実証実験結果について報告する。 |
| K-006 |
重度障害児を対象にした遠隔操作システムの開発と実用
◎荻巣 光(島根大学)・伊藤 史人(岩手県立大学)
×
K-006重度障害児を対象にした遠隔操作システムの開発と実用
◎荻巣 光(島根大学)・伊藤 史人(岩手県立大学)
重度障害児の社会参加や自己表現の機会は依然として限られており、集団行事への参加は困難を伴う。
本発表では、多様な操作方法を受け入れることで「誰でも参加できる」ことを目指したオンライン型ゲーム大会の企画・実践と、その成果について報告する。
これまでにゲーム大会を複数回開催し、児童・保護者・支援者の積極的な参加と反応が得られた。とくにオンライン開催により、児童は移動せずに慣れた環境から安心して参加できたことは大きな利点である。大会では“競技”としての楽しさ、他者との交流、達成感の共有が観察された。
本実践では、ICTを活用したレクリエーションが教育的・発達的意義をもつ活動となり得ることを示している。 |
| K-007 |
視覚障害者のためのカラオケ支援システム
○上倉 一人・遠藤 勇佑・石井 孝太郎(東京工芸大学)
×
K-007視覚障害者のためのカラオケ支援システム
○上倉 一人・遠藤 勇佑・石井 孝太郎(東京工芸大学)
音楽を気軽に楽しむことができるカラオケは,娯楽だけでなく心身の健康増進にも役立つことが知られている.しかし視覚障害者はカラオケ映像に表示される歌詞が読めないため,歌詞をすべて覚えているか,支援者に耳元で先読みしてもらう必要がある.我々は上記の問題を解決するために,視覚障害者が晴眼者と同じように一人でカラオケを楽しむことができる支援システムの実現を目指している.本発表では構想中であるカラオケ支援システムについて説明し,本システムで必要となる技術について述べる.さらに,その中の歌詞先読みタイミングおよび曲タイトル認識に関する検討状況について述べる. |
| K-008 |
AIを用いた視覚障害者向け歩行支援システムの開発:歩行軌跡に基づく歩行可能領域推定
○村井 保之(日本薬科大学)・巽 久行(筑波技術大学)・徳増 眞司(神奈川工科大学)
×
K-008AIを用いた視覚障害者向け歩行支援システムの開発:歩行軌跡に基づく歩行可能領域推定
○村井 保之(日本薬科大学)・巽 久行(筑波技術大学)・徳増 眞司(神奈川工科大学)
本研究は、AIと小型カメラを活用することで視覚障害者の安全かつ円滑な歩行を支援することを目的とする。提案手法では、使用者が体に装着または手に持った小型カメラで進行方向を撮影し、その映像からAIが先行する歩行者を認識する。先行歩行者が通行する領域は安全が確保されている「歩行可能領域」であるとみなし、歩行者の連続的な軌跡情報を活用してこの歩行可能領域を推定・図示することで、使用者を安全な方向へ誘導する。この方式は、個別の障害物を詳細に検知するといった複雑な環境認識処理が不要であり、多数のセンサーを使用する従来手法に比べて大幅な計算負荷の軽減が期待できる利点を持つ。 |
| K-009 |
歩行計測システムによる歩行の可視化と治療効果の比較
○晒野 舞・小川 賀代(日本女子大学)・見目 智紀(北里大学)・三枝 亮(神奈川工科大学)
×
K-009歩行計測システムによる歩行の可視化と治療効果の比較
○晒野 舞・小川 賀代(日本女子大学)・見目 智紀(北里大学)・三枝 亮(神奈川工科大学)
高齢者の移動機能低下を早期に発見し,適切な介入を行うには,歩行機能の定量的かつ客観的な評価手法の確立が求められている.本研究では、深度カメラと測域センサを統合した歩行測定システムを開発し,Timed Up and Go(TUG)テストにおける起立・歩行・旋回・歩行・着座といった一連の動作を自動で三次元的に可視化・解析する手法を提案する.また、RGB画像と深度情報を用いて骨格点を抽出し,全身動作を高精度に再構成する. 骨系統疾患患者を対象に衝撃波療法の前後で複数回TUGテストを実施し,歩行機能の変化を定量的に評価した.提案手法は理学療法への臨床応用が期待される. |
| 教育工学1 |
|
9月4日(木) 9:30-12:00 4s会場
座長 倉山 めぐみ(函館工業高等専門学校) |
| K-010 |
進捗発表資料を用いた主体性・有能感・関係性に基づくモチベーション特徴の推定
○倉本 凌・島川 博光(立命館大学)
×
K-010進捗発表資料を用いた主体性・有能感・関係性に基づくモチベーション特徴の推定
○倉本 凌・島川 博光(立命館大学)
研究活動は失敗や試行錯誤を伴い,これらを乗り越えるためには意欲の維持と促進が重要である.その手段として,自己決定理論に基づく主体性・有能感・関係性を満たすコーチングが有効だと言われている.しかし,意欲は個人によって異なるため,適切なコーチングを行うには,個人の意欲を客観的に評価する手法が必要である.そこで本研究では,進捗発表資料の内容から,個人の主体性・有能感・関係性に基づいた意欲を推定する手法を提案する.進捗発表資料の単語の分散や図表の使用状況,編集履歴などの特徴量から,研究に対する意欲を定量的に推定する.本手法により,研究の進捗に対する意欲を定量評価でき,適切なコーチングが可能となる. |
| K-011 |
EQによる感情変化に応じたAI学習支援モデルの構築
◎安田 健人・原田 史子・島川 博光(立命館大学)
×
K-011EQによる感情変化に応じたAI学習支援モデルの構築
◎安田 健人・原田 史子・島川 博光(立命館大学)
近年、データサイエンス教育において教員不足や個別最適な支援の困難さが顕在化し、学習者の感情状態に応じた支援の必要性が高まっている。しかし、EQに基づくAI教育支援は未だ十分に確立されておらず、学習者の内面を客観的に捉える手法が課題である。そこで本研究では、視線計測と皮膚電気活動を用いて、自信獲得や戸惑いの瞬間を検出する小型の認知モデルを構築する。得られた感情変化を基に、AIチャットボットがリアルタイムにフィードバックを生成することで、学習者の主体性を引き出す支援を実現する。これにより、教員の負担を軽減しながら、学習者のモチベーションと成績向上を実現するEQに応じた教育支援モデルを提案する。 |
| K-012 |
ページごとの描画ログからのプログラミング未経験者の計算論的思考能力の推定
◎菅野 浩太郎・島川 博光(立命館大学)
×
K-012ページごとの描画ログからのプログラミング未経験者の計算論的思考能力の推定
◎菅野 浩太郎・島川 博光(立命館大学)
計算論的思考は論理的思考や問題解決能力の向上につながる可能性があり,近年計算論的思考が世界各国で重視されている.本研究では,タブレットと電子ペンから得られる描画データを用いて,プログラミング未経験者や低年齢者の計算論的思考能力を推定する手法を提案する.被験者にパラパラ漫画を作成させ,隠れマルコフモデルにより能力発揮期間を抽出した.さらに,ランダムフォレストで特徴量との関係を分析した.実験の結果,能力発揮期間ではペン速度や高度角,X座標の変化に有意差が見られた.本手法により,問題解決への見通しの有無を評価できる可能性がある. |
| K-013 |
大規模言語モデルを用いた非専門家向けプログラミング支援ツールの開発と実践
◎出口 大地・仙田 朋也・梶原 祐輔(公立小松大学)
×
K-013大規模言語モデルを用いた非専門家向けプログラミング支援ツールの開発と実践
◎出口 大地・仙田 朋也・梶原 祐輔(公立小松大学)
大規模言語モデル(LLM)による自然言語プログラミングは手軽だが、生成コードの誤りや意図の齟齬が課題である。本研究では非専門家でも対話的にコードを修正できる支援ツール「AI Programmer」を開発し、小中学生に撮影+落書きアプリを制作させた。ワークショップの結果、参加者の約4割が基本機能を完了し、その半数が独自機能を組み込んだ。基本機能を実装し独自機能を追加できた例もあったが、生成結果のばらつきや文法誤り、指示の反映不足が開発阻害要因となった。一貫性向上と自動修復機構の強化、生成コードの品質評価基準の整備が今後の課題である。本稿ではこれらの課題と解決方向性を報告する。 |
| K-014 |
適応学習における生徒作問課題の生成AIによる自動評価
◎加藤 空・小林 学(早稲田大学)
×
K-014適応学習における生徒作問課題の生成AIによる自動評価
◎加藤 空・小林 学(早稲田大学)
近年オンライン学習の発展により生徒の理解度を都度評価し,その結果に応じた学習コンテンツを提示する適応学習は益々重要となってきている.このとき学習評価において,生成AIの活用により記述式答案の自動採点やフィードバックの自動生成などが期待されている.本研究では生徒に問題を作成させる課題を出し,その問題の内容によって生徒の学習内容の理解度を測ることを検討する.このとき生徒が作問した問題に対して,生成AIに学習指導要領およびブルームの改訂版タキソノミーを与えて評価を行わせる方式を提案する.結果的に,与えられた問題を解くことができる能力以上の生徒の理解度を自動で評価することが可能となることを示す. |
| K-015 |
MoodleにおけるHTTPアクセスログを使った動画視聴パターンの推定手法
◎金子 元気・佐藤 寧洋・田畑 賢明(大阪電気通信大学)
×
K-015MoodleにおけるHTTPアクセスログを使った動画視聴パターンの推定手法
◎金子 元気・佐藤 寧洋・田畑 賢明(大阪電気通信大学)
本稿では、Moodle で配信されている動画において HTTP アクセスログを使った動画視聴パターンの推定手法を検討する。近年、LMS などを使用した遠隔授業などが普及してきている。その中でも Moodle は多くの大学で利用されており、動画を使った教材も数多く提供されている。各学習者が動画をどのように視聴しているのかを知ることができれば、より効果的な教材の提供や効率的な学習方法を提示できる可能性がある。そこで、汎用的な HTTP アクセスログから学習者の動画の視聴パターンを推定する方法を検討する。 |
| K-016 |
知的財産法学習支援システムのSmartphone対応とその学生評価
○赤倉 貴子(東京理科大学)・加納 徹(茨城大学)
×
K-016知的財産法学習支援システムのSmartphone対応とその学生評価
○赤倉 貴子(東京理科大学)・加納 徹(茨城大学)
これまで工学部で実施している2単位授業「知的財産法」のための学習支援システムを開発、運用してきた。本システムは学生には好評であるが、最近はSmartphone対応を望む学生が増えてきた。特にCOVID-19でのオンライン授業以降、その傾向が強くなっている。そこで、学習支援システムをSmartphone対応とし、学生のPC版とSmartphone版の学習支援システムの受入評価を比較分析した。文字の読む速さなど、さまざまな要因とそれぞれの学習支援システムの評価を比較した結果、読書が好きな学生はPC版を嫌いな学生はSmartphone版を好む傾向があることがわかった。 |
| マルチメディア応用 |
|
9月4日(木) 15:30-17:30 5j会場
座長 木谷 俊介(北陸先端科学技術大学院大学) |
| K-017 |
注視領域を考慮したドミナントカラー抽出法
◎橋本 芽・新見 道治(九州工業大学)
×
K-017注視領域を考慮したドミナントカラー抽出法
◎橋本 芽・新見 道治(九州工業大学)
画像全体のドミナントカラー(画像を代表する(印象に残る)数種類の色)を抽出する研究はあるが,写真鑑賞の経験からすれば,ある特定物体に注目することはよくある.そこで本稿では,写真の注視領域を強調するようなドミナントカラー抽出の一手法を提案する.具体的にはまず,画像を,風景画像とそれ以外(ある特徴的なオブジェクトが被写体と思われる画像)の2種類に分類する.風景画像の場合は従来手法を適用する.それ以外の場合は,顕著性マップを利用して注視領域を決定する.注視領域内での高頻色をドミナントカラーとすれば,注視領域を強調する色が抽出でき,より効率的な画像検索が期待できる. |
| K-018 |
イラストを入力とする知育菓子向け可食ロボット開発支援システム
◎今野 嘉乃・小川 純(山形大学)
×
K-018イラストを入力とする知育菓子向け可食ロボット開発支援システム
◎今野 嘉乃・小川 純(山形大学)
本研究では、2D画像に基づく3Dモデル生成技術を応用し、可食ロボットを即興的に作成可能とするシステムを提案する。可食ロボットは、可食材料によって構成される新たなロボット技術であり、一般的認知度の低さが普及の課題となっている。そこで本研究は、食育を目的とした知育菓子開発キットへの応用を想定し、Trellisによる3Dモデル生成と簡易駆動機構の統合により、画像から可食ロボットを構築する手法を示す。特に魚の画像を用いたプロトタイプにより有効性を検証する。 |
| K-019 |
VR技術を用いた学生相談システムの開発
◎原田 青空・手島 裕詞(佐世保工業高等専門学校)・小杉 大輔(静岡文化芸術大学)・志久 修・大里 浩文(佐世保工業高等専門学校)
×
K-019VR技術を用いた学生相談システムの開発
◎原田 青空・手島 裕詞(佐世保工業高等専門学校)・小杉 大輔(静岡文化芸術大学)・志久 修・大里 浩文(佐世保工業高等専門学校)
現在、不登校児童の生徒数が増加しており、一つの社会問題となっている。そのための解決手段の一つとして、学生相談やカウンセリングの取り組みが進められている。しかし、学生の性格によっては対面では本音を語ることが困難な場合があるため、話しづらさを感じにくい対話環境を作ることが求められている。また、相談時の発言やしぐさなどを観察することにより具体的な支援を検討することも多い。
そこで本研究では、しぐさ等を取得しながら高い匿名性を維持する仮想空間を開発し、その空間で対話を行うことにより相談者の自己開示性を高められるかを検証する。いくつかの実験により有効性を確認できたので報告する。 |
| K-020 |
共創型デジタルツインの構築のための3D Gaussian Splattingの点群データの重畳手法に関する試行
◎南 李玖・中原 匡哉(大阪電気通信大学)
×
K-020共創型デジタルツインの構築のための3D Gaussian Splattingの点群データの重畳手法に関する試行
◎南 李玖・中原 匡哉(大阪電気通信大学)
近年,航空機や車両で計測した点群データを利用したデジタルツインの構築が進んでいるが,狭小空間の計測が困難であることから,未構築の空間が多い.そのため,住民にも協力可能な共創型のデジタルツインの構築が検討されている.住民にも可能な簡易計測方法としてスマートフォンの写真を利用する方法が検討されているが,ローカル座標系の点群データが得られるため,デジタルツイン上に重畳することは困難である.既存研究では,エッジを基に重畳する手法が提案されている.しかし,簡易計測方法で得られる点群データ中のエッジは多量のノイズによる影響で丸みを帯やすく,重畳の指標としてそのまま利用することは困難である.そこで,本研究では,PCAを用いて推定したエッジを基に重畳する手法を試行する. |
| 福祉情報工学2 |
|
9月4日(木) 15:30-17:30 5s会場
座長 白石 優旗(筑波技術大学) |
| K-021 |
介護予防システム「窓ふきの達人」を用いたコミュニケーションの活性化に関する検討
◎小林 環・浦島 智・森島 信・鳥山 朋二(富山県立大学)
×
K-021介護予防システム「窓ふきの達人」を用いたコミュニケーションの活性化に関する検討
◎小林 環・浦島 智・森島 信・鳥山 朋二(富山県立大学)
近年、日本においては高齢化が進行しており、高齢者が要介護状態へ移行することを防ぐ介護予防の重要性が高まっている。現在、介護予防活動として広く実施されている体操には、長期的な取り組みで参加者が減少する問題が指摘されている。我々はコミュニケーションの活性化がこの問題を解決すると考え、観戦者とゲーム実施者がコミュニケーションをとりやすい高齢者向けのeスポーツゲーム「窓ふきの達人」を開発した。本稿では、介護予防活動が実施されている通いの場に参加する高齢者を対象に本システムを用いた実験を行い、アンケート結果、及び記録映像から、コミュニケーションの活性化の度合いを確認した結果について述べる。 |
| K-022 |
手話認識における動きの個人差を吸収するためのデータ拡張手法
◎本郷 望実・後藤 啓介・和田 直哉・村上 文雄(京セラ)
×
K-022手話認識における動きの個人差を吸収するためのデータ拡張手法
◎本郷 望実・後藤 啓介・和田 直哉・村上 文雄(京セラ)
手話認識モデルの精度を向上させるには,大量のデータセットが不可欠である.しかしながら,手話に関する公開データセットは限られており,新規データの収集や作成には多大なコストがかかるという課題が存在する.我々は手話動画からランドマーク座標データを抽出し,そのデータに対して手話単語認識を行う処理を構築している.そこで本研究では,手話表現の速度,動作の大きさ,利き手の違いといった動きの個人差に対応するランドマーク座標データ拡張手法を提案する.我々が作成した日本手話データセットに提案手法を適用し,Conformerを用いた連続手話単語認識実験によって有効性を確認した. |
| K-023 |
画像認識技術を用いた特殊音に着目した指文字学習支援アプリケーションの試作
◎中下 誇天・石井 幹大・伊藤 一成(青山学院大学)
×
K-023画像認識技術を用いた特殊音に着目した指文字学習支援アプリケーションの試作
◎中下 誇天・石井 幹大・伊藤 一成(青山学院大学)
聴覚障がい者と非障がい者の円滑なコミュニケーションは,多様性が重視される現代社会において重要な課題である.しかし,コミュニケーション手段の学習環境は整っていない.そこで本稿では,画像認識技術を活用した指文字学習支援アプリケーションを開発した.MediaPipeによりWebカメラ映像から手指の動きを検出し,特殊音を含めた指文字の認識を可能とし,学習モードとリズムゲームモードを搭載し,継続的な学習を支援する.
特別な機器を必要としない手軽な学習環境を実現した一方で,Z軸認識や指の重なりに起因する精度低下が課題として残った.今後は認識精度向上と機能拡張により実用性の向上を図る. |
| K-024 |
日本語発話訓練システムのための画像及び音声処理の試行
◎松下 開星・荒平 高章(九州情報大学)
×
K-024日本語発話訓練システムのための画像及び音声処理の試行
◎松下 開星・荒平 高章(九州情報大学)
本研究は,画像及び音声認識技術を用いて聴覚障がい児の日本語発話訓練を支援するシステムの開発を目的とする.システムを利用することで,視覚的なフィードバックを通じて児童の訓練意欲向上と発話能力向上を図る. |
| K-025 |
遠隔対話システムにおける情報共有を焦点にした支援アプリケーションの検討
◎高須 俊輔・山本 堅心・中村 直人(千葉工業大学)
×
K-025遠隔対話システムにおける情報共有を焦点にした支援アプリケーションの検討
◎高須 俊輔・山本 堅心・中村 直人(千葉工業大学)
高齢化の進展と核家族化は,高齢者の孤立と孤独,家族の不安を深刻化させている.特に,離れた場所に暮らす高齢者の親を持つ家族は,同居している家族と比較して十分な意思疎通が取れないという問題がある.
これらの課題に対して既存のチャットや電話などのツールはよく利用されている.しかし,チャットは,タイミングが限定されないが,高齢者にとって操作が煩雑で大きな負担になる.そして,電話は負担が少ない利点がある一方で,タイミングが限定され不在時の孤独感などは解決できていない.
そこで本稿では,高齢者と家族間において遠隔での対話における情報共有をより円滑に行うための支援アプリケーションについて検討する. |
| アクセシビリティ、教育工学2 |
|
9月5日(金) 9:30-12:00 6s会場
座長 野口 靖浩(静岡大学) |
| K-026 |
YouTube-SL-25における日本手話動画の再分類と段階的アノテーションの必要性
◎船山 滉介(筑波技術大学)・設楽 明寿(筑波技術大学/筑波大学)・加藤 伸子・白石 優旗(筑波技術大学)
×
K-026YouTube-SL-25における日本手話動画の再分類と段階的アノテーションの必要性
◎船山 滉介(筑波技術大学)・設楽 明寿(筑波技術大学/筑波大学)・加藤 伸子・白石 優旗(筑波技術大学)
本研究は,YouTube-SL-25 に含まれる “JSL” ラベル付き1,073本の動画を対象に,手話に関する専門知識を用いず視認可能な4分類軸—(i) 手話歌の有無,(ii) 同時出演者数,(iii) 話者属性,(iv) 日本語音声併用の有無—に基づき段階的アノテーションを実施し,ラベルと出現形式の乖離を検討した.その結果,手話歌が163本(15.2%)を占めるなど,出現形式が大きく異なる動画が混在していた.話者属性ではろう者を中心にCODAや聴者も含まれ,語順や非手指文法の使用から中間型とみなされる例も複数確認された.本手法は,専門的注釈に先立ってJSLラベル下の出現形式を再分類・整理する実践的枠組みとして有効である.今後は,文法的基準の導入,音声使用のばらつきを考慮した複合的注釈,および話者の自己認識に基づく分析が課題となる. |
| K-027 |
語彙学習のための Word2Vec を用いた単語固有の意味抽出手法の提案と検証
◎角田 悠翔・前田 大輝・小尻 智子(関西大学)
×
K-027語彙学習のための Word2Vec を用いた単語固有の意味抽出手法の提案と検証
◎角田 悠翔・前田 大輝・小尻 智子(関西大学)
本研究では,語彙学習支援を目的として,Word2Vecを用いた単語固有の意味抽出手法を提案し,その有効性を検証した.従来の語彙学習では,システムが類義語間の意味的な違いを教授することが困難であった.そこで本手法では,類義語組の各単語ベクトルから共通成分を除去し,固有の意味成分を抽出することで,各単語の独自性を強調することを試みた.検証実験では,類義語組において抽出した固有成分とコサイン類似度が高い単語を上位から抽出し,辞書から収集した固有の意味単語との一致率を導出した.その結果,提案手法が固有の意味単語を抽出できたのは最大で64%であった. |
| K-028 |
学生のレポートで使われる単語と授業中の集中度合いの関係の解析
○上條 浩一・塩尻 亜希・神沼 充伸(東京国際工科専門職大学)
×
K-028学生のレポートで使われる単語と授業中の集中度合いの関係の解析
○上條 浩一・塩尻 亜希・神沼 充伸(東京国際工科専門職大学)
大学などの授業では、学生の集中力を持続させ、講義内容の理解を促すことが教師にとって極めて重要である。しかし、学生が授業を通して集中力を保つことは難しい。われわれの先行研究では、60分の授業中に5分程度の短いテストを2回実施した場合、多くの学生の集中度はテスト中に比べてテスト後の講義で上昇することが観測された。しかし、個人差があり、テスト後に集中力が低下する学生もいた。このような個人差を事前に予測することができれば、授業中の集中力を維持するために、教師との距離に応じて最適な座席配置を行うなどの対策が可能になる。本研究では、学生の書いたレポートとその学生の授業中での集中度合の関係を解析し、さらに、集中度の予測を行ったので、その結果を報告する。 |
| K-029 |
シラバス情報に基づく科目間類似度と科目成績の相関に関する一考察
○浮田 善文(横浜商科大学)・齋藤 友彦(湘南工科大学)・松嶋 敏泰(早稲田大学)
×
K-029シラバス情報に基づく科目間類似度と科目成績の相関に関する一考察
○浮田 善文(横浜商科大学)・齋藤 友彦(湘南工科大学)・松嶋 敏泰(早稲田大学)
大学教育において、深い学びの視点から授業改善を検討する際には、個々の科目だけでなく、関連する科目全体との関係を把握することが重要である。大学では開講科目のシラバス情報が公開されているため、授業内容についてはこの情報を活用することで、科目間の類似度を算出することが可能である。一方、学修成果を含めた科目間の関連性を明らかにするには、各科目の成績情報が必要となる。そこで本研究では、筆者が所属する大学の全開講科目を対象に、匿名化された成績情報を用いて、類似度の高い科目間における成績の相関を求め、その関係性を明らかにすることを目的とする。 |
| K-030 |
スクラム学習教材「プロトタイピングスプリント教材」による企業勤務者と学生の学習効果比較
○鈴木 昭弘・松﨑 博季・松川 瞬・松本 拓(北海道科学大学)
×
K-030スクラム学習教材「プロトタイピングスプリント教材」による企業勤務者と学生の学習効果比較
○鈴木 昭弘・松﨑 博季・松川 瞬・松本 拓(北海道科学大学)
企業のDX推進や業務効率化の流れの中で,ソフトウェア開発はIT企業に限らず一般企業にも広がりつつある.それに伴い,今後は一般企業においてもソフトウェア開発におけるプロジェクトマネジメントの重要性が高まると考えられる.
我々はこれまで,ITエンジニアを目指す大学生を対象に,スクラムの知識と経験を獲得するための学習教材「プロトタイピングスプリント教材」を開発してきた.本教材は,スクラム開発のプロセスをロールプレイ形式で体験しながらプロトタイプアプリケーションの開発を行うグループワーク型の教材である.
本研究では、この教材を非IT系の一般企業に勤める実務者に適用し,大学生との比較実験を行った.学生に対する実験結果と実務者に対する実験結果を比較し,有効性と課題について考察する. |
| K-031 |
大学生が教えるプログラミング教室の検討
◎谷村 謙拓・荒澤 孔明・杉尾 信行・松崎 博季・真田 博文(北海道科学大学)
×
K-031大学生が教えるプログラミング教室の検討
◎谷村 謙拓・荒澤 孔明・杉尾 信行・松崎 博季・真田 博文(北海道科学大学)
近年,高校と大学との教育的連携である「高大連携」が注目されている.本研究では,その一環として,大学生が高校生に授業を実施する取り組みについて報告する.本取り組みでは,大学生が授業資料の作成から実施までを一貫して行うことで,大学教員の負担軽減を図るとともに,大学生が大学での学びを活かし,理解の定着を促すことを目的としている.また,新学習指導要領の施行により指導する大学1年生が高校時代に「情報Ⅰ」でプログラミング教育を受けているという背景がある.そこで,本年度は大学1年生を中心とした高大連携授業の実施を計画している.さらに,大学生による情報教育の可能性と,高大連携の新たな展開について検討していく. |
| K-032 |
成果に基づいた技術者の初期専門能力開発(IPD)モデル:IEA PCとIPD活動サイクルによる資質能力向上への試案
○小林 守(茨城県立産業技術短期大学校)・松村 正明(聖徳大学短期大学)
×
K-032成果に基づいた技術者の初期専門能力開発(IPD)モデル:IEA PCとIPD活動サイクルによる資質能力向上への試案
○小林 守(茨城県立産業技術短期大学校)・松村 正明(聖徳大学短期大学)
初期専門能力開発(IPD)は、IEA(国際エンジニアリング連合)のGA&PC(修了生としての知識・能力と専門職としてのコンピテンシー)にて推奨されている国際的同等性を鑑み工学系高等教育機関で修了した技術者に対し、実務に就いてから必要となる資質能力(コンピテンシー)を初期のうちに開発するモデルを試案する。IPDとしてIEA PC(専門職としてのコンピテンシー)要素への対応、IPD活動サイクル、および活動成果を出発点とした多角的な視点から資質能力の開発について報告する。IPDを導入することは技術者の初期専門能力開発を支援し国際的な専門職技術者を早期に増やすことにつながる。このIPD活動するには社会全体で支援する環境を整えることが重要となる。 |
| 福祉情報工学3 |
|
9月5日(金) 13:10-15:40 7s会場
座長 内田 翼(NHK放送技術研究所) |
| K-033 |
モバイルアプリケーション上で動作する構音障害者向け音声認識の検討
◎山本 堅心・高須 俊輔・中村 直人(千葉工業大学)
×
K-033モバイルアプリケーション上で動作する構音障害者向け音声認識の検討
◎山本 堅心・高須 俊輔・中村 直人(千葉工業大学)
構音障害者の発話を正確に聞き取ることは容易ではなく,コミュニケーションを円滑にとれないという問題がある.構音障害者の音声認識を行う手法に,Whisperを構音障害者音声でFine-tuningする方法が提案されているが,実用システムとしての実装は行われておらず,容易にすぐ利用できる状態ではない.そこで本研究では,既存手法を活用し,モバイルアプリケーション上で動作するコミュニケーション支援のための構音障害者向け音声認識を検討する. |
| K-034 |
マイクロホンアレイによる掻破音の無拘束多点観測およびMUSIC法を用いた就寝中における掻破部位の判別
◎堀池 哲平・栗原 陽介(青山学院大学)
×
K-034マイクロホンアレイによる掻破音の無拘束多点観測およびMUSIC法を用いた就寝中における掻破部位の判別
◎堀池 哲平・栗原 陽介(青山学院大学)
アトピー性皮膚炎患者の就寝中に生じる掻破行動は無意識下で起こるため,どの部位をどの程度の頻度で掻破したかを把握することは困難である.筆者らはこれまで,掻破音のエネルギーとゼロ交差率,スペクトルフラックスに基づき,就寝中の掻破行動の回数や時間を客観的に推定する手法を検討してきた.
本研究では,掻破行動をより客観的に推定する為に,掻破部位の判別を行う.具体的には,寝具下に設置した6 個のマイクロホンアレイで掻破音を無拘束で多点計測し,MUSIC 法を適用することで掻破音源である掻破部位を判別する手法を提案する.検証実験では,左右の肩・腹部・大腿部の計6 部位を対象に判別精度の評価を行う. |
| K-035 |
身体の3Dモデルを利用した体重推定手法
◎小松 大倭・吉野 孝(和歌山大学)
×
K-035身体の3Dモデルを利用した体重推定手法
◎小松 大倭・吉野 孝(和歌山大学)
起立困難者に対する体重測定は,大型の計測装置を必要とする.このような装置は高額であり医療現場や介護現場でも導入が難しく,また,設置されている場合でも,起立困難者を装置に移動させることは計測者・被計測者双方にとって大きな負担となっている.本研究では,この課題を解決するための新たな体重推定手法として,あらかじめ体重などの属性情報を付与した3次元身体モデルを用意し,これを被計測者の身体寸法に基づいて調整することで,被計測者の身体を仮想的に再現する.さらに,元の3Dモデルと調整後のモデルの体積差に着目することで,被計測者の体重を推定する方法を提案する. |
| K-036 |
安静時呼吸運動の準周期性に基づく最大吸気圧/最大呼気圧の無拘束推定法の提案
◎河野 友樹・栗原 陽介(青山学院大学)
×
K-036安静時呼吸運動の準周期性に基づく最大吸気圧/最大呼気圧の無拘束推定法の提案
◎河野 友樹・栗原 陽介(青山学院大学)
COPD診断においては,呼吸筋力を評価する指標である最大吸気圧(MIP)/最大呼気圧(MEP)を得るために,スパイロメーターを用いた努力呼吸が必要とされる.しかし,この方法は患者にとって身体的負担が大きく,簡易に評価可能な手法の確立が求められている.筆者らはこれまで,呼吸筋力が肺・胸郭系の運動に与える影響を反映する指標として,無拘束で計測した就寝時の安静状態での呼吸信号から得られる振幅,速度変化に着目し,MIP/MEPを推定する手法を提案してきた.本研究では,さらに呼吸筋力が呼吸運動の周期に影響を与えるとし,呼吸運動の準周期性を用いることでMIP/MEPの推定精度を向上させる手法を提案する. |
| K-037 |
ESNを用いた筋電位による関節トルク推定
○村上 美里・都城 宏治・櫻沢 繁(公立はこだて未来大学)
×
K-037ESNを用いた筋電位による関節トルク推定
○村上 美里・都城 宏治・櫻沢 繁(公立はこだて未来大学)
人間の手指では筋収縮により指関節トルクが制御されている一方で,普及型の筋電義手では指関節角度制御が採用され,装着者の違和感の原因となっている.そのためトルク制御型筋電義手を開発できれば操作性が高くなると考えられる.そこで,できるだけ少ない電極で得られる筋電位情報から,指の各関節トルクを推定する推定器が必要となる.そこで本研究では,ESNを用いて筋電位から示指の各関節トルクを推定することを目的としてトルク測定器を開発しトルク推定システムを構築した. その結果, 筋電位から示指の各関節トルクを推定することが可能であると分かった. 推定精度は関節の連動性や可動域の大きさに影響を受けると考えられる. |