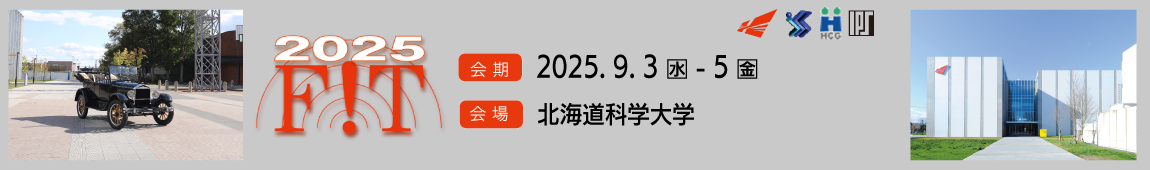| N分野 教育・人文科学 |
選奨セッション
電子化知的財産・社会基盤と教育 |
|
9月3日(水) 9:30-12:00 1n会場
座長 小向 太郎(中央大学)
長 慎也(明星大学) |
| CN-001 |
欧州データ空間(European Data Space)戦略にみるEUデータ主権強化の法的側面と課題からみる日本への示唆
○寺田 麻佑(一橋大学/理化学研究所)・板倉 陽一郎(ひかり総合法律事務所/理化学研究所)
×
CN-001欧州データ空間(European Data Space)戦略にみるEUデータ主権強化の法的側面と課題からみる日本への示唆
○寺田 麻佑(一橋大学/理化学研究所)・板倉 陽一郎(ひかり総合法律事務所/理化学研究所)
本稿は、欧州データ戦略の中核をなす欧州データ空間(European Data Space)構想におけるEUのデータ主権強化の法的側面と課題を分析し、日本のデータガバナンスへの示唆を検討するものである。欧州(EU)一般データ保護規則(GDPR)に加え、データガバナンス法(Data Governance Act)やデータ法(Data Act)により、EUは個人データ・産業データ双方の統制と利活用を両立する制度を構築しようとしている。本研究では、こうしたEUの制度的動向が日EU間のデータ移転や法制度の調和に与える影響を踏まえ、日本における信頼性あるデータガバナンスの構築に向けた課題と展望を示す。 |
| CN-002 |
SNS情報の品質向上のための放送通信混在方式の社会システム的分析
○金子 格・寺田 麻佑(一橋大学)・湯田 恵美(三重大学)
×
CN-002SNS情報の品質向上のための放送通信混在方式の社会システム的分析
○金子 格・寺田 麻佑(一橋大学)・湯田 恵美(三重大学)
SNS上の有害情報はSNSの有用性を著しく低下させている。特に偽情報やフィッシングの弊害は顕著である。SNSは現在通信サービスとして法規制を受けていることがその遠因となっていると考えられる。我々はその一部を放送配信として配信すれば、通信サービスであることの問題のいくつかが解消すると考える。本報告ではそのような複合システムの社会システム的効果を検討する。適切な方法で放送配信を混在させれば、これまでのSNS利用はすべてそのまま継続可であり,個人のプライバシーと自由を担保したSNS利用は維持される。SNSの利便性を持って信頼性を担保した放送配信にもアクセス可能とすることが期待される。 |
| CN-003 |
地域経済・相互扶助・地域資源を循環させるデジタル地域通貨:システム設計と社会実装
○藤原 正幸(公立小松大学/北陸先端科学技術大学院大学)・井上 杜太郎(北陸先端科学技術大学院大学)・小林 重人(札幌市立大学)・吉田 昌幸(上越教育大学)・宮﨑 義久(宮城大学)
×
CN-003地域経済・相互扶助・地域資源を循環させるデジタル地域通貨:システム設計と社会実装
○藤原 正幸(公立小松大学/北陸先端科学技術大学院大学)・井上 杜太郎(北陸先端科学技術大学院大学)・小林 重人(札幌市立大学)・吉田 昌幸(上越教育大学)・宮﨑 義久(宮城大学)
地域コミュニティにおけるデジタル地域通貨の利用、特に地方自治体への導入はもはや新しいものではなくなっている.地域経済を回す決済手段としての役割は当然ではあるが,地域コミュニティの活性化に有効性のあるデジタル技術の応用が課題である.本研究では地域経済・相互扶助・地域資源の循環を目的として,地域交換取引制度(LETS)を採用したデジタル地域通貨の設計と開発を行った.これはQRコード決済機能だけでなく,決済時のスタンプ付与,利用者間のコメント機能,薪やペレット購入時のCO2削減量概算および可視化などの機能を備える.実際に地方自治体において3ヶ月間の流通実験を実施し,有効性を一部確認した. |
| CN-004 |
高大接続を見据えた「情報㈵」からみるデータサイエンス教育の関係分析
○林 宏樹(雲雀丘学園中学校・高等学校)・井手 広康(愛知県立旭丘高等学校)・渡辺 博芳(電気通信大学)
×
CN-004高大接続を見据えた「情報㈵」からみるデータサイエンス教育の関係分析
○林 宏樹(雲雀丘学園中学校・高等学校)・井手 広康(愛知県立旭丘高等学校)・渡辺 博芳(電気通信大学)
DS・AIリテラシーの重要性が高まる中,高等学校「情報Ⅰ」が必履修化され,大学入学共通テストの科目となった.本研究では,この「情報Ⅰ」における「データの活用」分野と大学DS・AI教育の「モデルカリキュラム」との接続を明らかにすることを目的とし,学習指導要領解説とモデルカリキュラムの比較,及び共通テスト関連の公開問題5種類の分析を行った.結果,共通テストは,多様なグラフ読解,基本統計量の理解,相関の解釈といった基礎的なデータリテラシーに関する問題が出題されていた.学習指導要領も含めて検討すると,モデリカリキュラムのうち,実践的なデータハンドリングや深い因果推論,ELSIなどは大学での学習が必要な領域であることが示された.本発表では分析に基づき,高大接続における「情報Ⅰ」の役割と課題,今後のDS教育連携への示唆を報告する.展望として教科書分析も加え,DS教育の高大接続の方向性を見出す. |
| CN-005 |
学習用自作プログラミング言語の生成AIによる実行環境生成の試み
○倉橋 農(羽衣国際大学)・越智 徹(大阪工業大学)・尾崎 拓郎(大阪教育大学)・島袋 舞子(沖縄国際大学)・今井 正文(豊橋創造大学)
×
CN-005学習用自作プログラミング言語の生成AIによる実行環境生成の試み
○倉橋 農(羽衣国際大学)・越智 徹(大阪工業大学)・尾崎 拓郎(大阪教育大学)・島袋 舞子(沖縄国際大学)・今井 正文(豊橋創造大学)
発表者らは、アンプラグドのプログラミング教材「ハンバーガー・ロボ」を開発している。この教材は関数やリテラルを表すカードを並べ、プログラムを完成させるものである。本発表では、アンプラグド教材を補うものとして、この学習用言語をソフトウェア上で実行する環境を、生成AIを利用して構築することを試みる。その際、 1) BNFの作成やAST構文木の生成など形式的な指示を段階的与えることで効率的かつ正確な環境構築が可能、 2) 実行環境の生成AIによる開発の過程により学習者が何を学べるか、の2点に重点を置いて、報告する。 |
| 電子化知的財産・社会基盤と人文科学 |
|
9月3日(水) 13:10-15:10 2w会場
座長 須川 賢洋(新潟大学) |
| N-001 |
諸外国のデータ保護法制における「契約の履行のために必要不可欠な場合」の検討
○板倉 陽一郎(ひかり総合法律事務所/理化学研究所)・寺田 麻佑(一橋大学/理化学研究所)
×
N-001諸外国のデータ保護法制における「契約の履行のために必要不可欠な場合」の検討
○板倉 陽一郎(ひかり総合法律事務所/理化学研究所)・寺田 麻佑(一橋大学/理化学研究所)
個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直し(第二次)に関して,個人情報保護委員会は2025年3月5日に「個人情報保護法の制度的課題に対する考え方について」を公表した。見直しが想定される項目として「個人データの第三者提供等が契約の履行のために必要不可欠な場合を始め、目的外利用、要配慮個人情報取得又は第三者提供が本人の意思に反しないため本人の権利利益を害しないことが明らかである場合(…)について、本人の同意を不要としてはどうか。」との提案を含んでいる(第1・1(2))。欧州一般データ保護規則(GDPR)6条1項(b)の影響を受けた適法化事由を提案するものであるが,具体的にどのような「契約」について認めていくかについては,具体的な議論未だしである。本発表では,GDPRや,英国のUK GDPR等,既に同様の規定を有するデータ保護法制における具体例を検討し,日本法への示唆を得る。 |
| N-002 |
個人情報保護法の制度的課題と令和7年改正に向けた考察
○新保 史生(慶應義塾大学)
×
N-002個人情報保護法の制度的課題と令和7年改正に向けた考察
○新保 史生(慶應義塾大学)
個人情報保護法の「3年ごと見直し」に基づく令和7年改正に向けた検討状況を整理し、AI技術の進展や国際的データ移転の増加を踏まえて顕在化した制度的課題を論じる。本人同意要件の見直し、要配慮個人情報や子どもの個人情報の保護に関する法的・制度的課題を分析する。 |
| N-003 |
大学における情報倫理教育の内容に関する探索的研究
○吉見 憲二(成蹊大学)
×
N-003大学における情報倫理教育の内容に関する探索的研究
○吉見 憲二(成蹊大学)
近年、情報倫理に関する問題の拡大を背景に、大学における情報倫理教育の比重が高まってきている。他方で、「情報倫理」という単語が包含する概念は拡大の一途を辿っており、単一の学問分野ではカバーしきれないほど複雑化している。こうした状況下では、情報倫理に関連した授業で何を取り上げるのか、そして、何を取り上げないのかは担当教員の裁量に任されることになり、同一の科目名であってもまったく異なる内容を教えることになりかねない。本研究では、そうした問題意識から情報倫理に関する授業がどのように扱われているのかについて、公開されているシラバスの情報をベースに検討する。 |
| N-004 |
ブロックチェーンを伝統工芸の「箱書」に応用する方法:NFT,TBA,SBTを用いた継承システム
○川嶋 比野(戸板女子短期大学)・川嶋 力(bon soleil)
×
N-004ブロックチェーンを伝統工芸の「箱書」に応用する方法:NFT,TBA,SBTを用いた継承システム
○川嶋 比野(戸板女子短期大学)・川嶋 力(bon soleil)
箱書きとは,茶道具・陶磁器・美術品等を収納する箱に,作者や所有者の署名,銘,来歴などを記すことである.ブロックチェーンの改ざん不可能なデータ保存機能を使い,箱書きに応用するシステムを構築した.Ethereumの規格であるERC-721の非代替性を利用し,作品に紐づくNFTを作者のウォレットにMintし,作者を証明できるようにした.次にERC-6551のトークンにアカウントを持たせる機能を利用し,NFTに紐づくTBAを発行した.さらに,ERC-5192の譲渡不可能な機能を利用し,TBAにSBTをMintできるようにした.作品の受賞歴や使用歴のSBTはNFTの譲渡と伴に次の所有者に継承される. |
| N-005 |
若者ことばの使用実態に見られる属性差―ウエイトバック集計による再評価
◎原田 健生・山本 康裕・柴田 希隆・石川 泉吹・山崎 綾一郎(静岡理工科大学)・山岸 祐己(静岡理工科大学/浜松医科大学)・谷口 ジョイ(静岡理工科大学/国立国語研究所)
×
N-005若者ことばの使用実態に見られる属性差―ウエイトバック集計による再評価
◎原田 健生・山本 康裕・柴田 希隆・石川 泉吹・山崎 綾一郎(静岡理工科大学)・山岸 祐己(静岡理工科大学/浜松医科大学)・谷口 ジョイ(静岡理工科大学/国立国語研究所)
本研究は,若者ことばの使用実態に関する大規模調査データにウエイトバック集計を適用し,先行研究と比較して分析結果にどのような違いが生じるかを検証したものである.既に,無調整のデータを用いた独立性検定および残差分析により,地域差や性差,年代差に関する考察は行ったが,本研究では,回答者分布の偏りを補正したデータを用いて同様の分析を行い,語ごとの定着や衰退・消滅の傾向について検証した.その結果,特定の語において地域・年代といった属性別の傾向に違いが見られ,調整の有無によって結果が変わる可能性が示された.これにより,若者ことばの動態をより正確に把握するうえで,サンプリング補正が有効であることが分かった. |
| N-006 |
若者ことばの定着と衰退・消滅:多項分布型レジームスイッチングによる時期特定の試み
◎髙橋 基規・原田 健生・山本 康裕・柴田 希隆・石川 泉吹・山崎 綾一郎(静岡理工科大学)・山岸 祐己(静岡理工科大学/浜松医科大学)・谷口 ジョイ(静岡理工科大学/国立国語研究所)
×
N-006若者ことばの定着と衰退・消滅:多項分布型レジームスイッチングによる時期特定の試み
◎髙橋 基規・原田 健生・山本 康裕・柴田 希隆・石川 泉吹・山崎 綾一郎(静岡理工科大学)・山岸 祐己(静岡理工科大学/浜松医科大学)・谷口 ジョイ(静岡理工科大学/国立国語研究所)
本研究は,現代日本語における若者ことばについて大規模調査を実施し,その結果を多項分布型レジームスイッチングによって分析することで,過去にどのような変化が生じたのか,またその変化が生成された時期についての特定を試みるものである.本調査で扱う時系列データ(生年)や地理的データ(出身地・在住地)は,情報量が多く,そのまま可視化しても解釈が困難である.よって本研究では,収集データに対してウエイトバック集計による「重み付け」を行った上で,データを単純化し,若者ことばの使用・理解にかかる変化とその時期を特定している.本手法により,特定の語が出現した時期,あるいは衰退・消滅の時期が推定できることが示された. |
| 情報セキュリティ教育・その他 |
|
9月3日(水) 15:30-17:30 3w会場
座長 越智 徹(大阪工業大学) |
| N-007 |
心停止者発見時の意思決定・実技訓練支援システムの開発
○皆月 昭則(釧路公立大学)
×
N-007心停止者発見時の意思決定・実技訓練支援システムの開発
○皆月 昭則(釧路公立大学)
心肺蘇生法(以下CPR)で胸骨圧迫の正しい姿勢・動作に従うことは救命率の向上につながる.本研究ではCPR訓練の諸課題に対応するために胸骨圧迫の姿勢と自動体外式除細動器 (以下AED)の設置場所への誘導方法に着目した.開発した胸骨圧迫の訓練システムは,バランスWiiボードやKinectセンサーカメラの機器を用いて実装した.胸骨圧迫を実施しながらAEDの併用で救命率を向上させるための方策としてAED設置場所への屋内・屋外誘導が必要であることから,AEDを発見する機能を実装したスマートフォンアプリケーションを開発した.システムは,実際に心停止者に遭遇した際の救急隊に適切に引き継ぐまでの時間を考慮した救助者の交代を想定した訓練形式として,複数人の救助者で胸骨圧迫を実施するリレーモードの訓練形式(以下,胸骨圧迫訓練リレー)で実施した. |
| N-008 |
Webサーバのアクセスログ監視体験ゲームの試作
◎柳田 雪乃・石井 幹大・伊藤 一成(青山学院大学)
×
N-008Webサーバのアクセスログ監視体験ゲームの試作
◎柳田 雪乃・石井 幹大・伊藤 一成(青山学院大学)
2025年度から共通テストに導入される「情報Ⅰ」に対応し,「情報社会の問題解決」分野の理解を深めるため,Webサーバのアクセスログ監視を体験できる教育用ゲームを開発した.本ゲームは,不正アクセスを特定するセキュリティハッカーとしてプレイする構成とし,ログの構造やSQLインジェクション,XSSなどの攻撃手法の知識を直感的かつ体験的に学べるよう設計した.視覚的なフィードバックやインターフェースにより,学習者の興味・理解を促進するほか,毎回変化する前提条件によって応用力も養うことができる.これにより,従来の教科書的学習を補完する新たな情報セキュリティ教育の形を提案する. |
| N-009 |
研究と情報のインテグリティ
○池田 紀子(紀梢技術士事務所)
×
N-009研究と情報のインテグリティ
○池田 紀子(紀梢技術士事務所)
近年、研究の国際化・オープン化の進展や国際情勢の変化により、公正な研究活動を脅かすリスクが顕在化している。これらのリスクは研究の信頼性を損なうのみならず、社会、国家、さらには国際社会の安全保障に関わる問題として認識されつつある。このような状況においては、普遍的な価値に基づく「研究インテグリティ」と、国家利益の保護や国際社会の安全保障のための「研究セキュリティ」との両立が重要な課題となっている。本発表では、これらのリスクに対処する視点として、一般財団法人公正研究推進協会(APRIN)の教材「研究インテグリティ」およびOECDの情報インテグリティの枠組みをもとに、今後の対応のあり方を考察する。 |
| N-010 |
情報セキュリティインシデントの擬似体験を通じた情報セキュリティ教育の多元的展開
○花田 経子(慶應義塾大学)
×
N-010情報セキュリティインシデントの擬似体験を通じた情報セキュリティ教育の多元的展開
○花田 経子(慶應義塾大学)
学校において情報モラル教育が実施されているにも関わらず、学校現場において生徒たちのSNSトラブルやSNSを使ったいじめ行為、児童ポルノなどの性犯罪被害・加害、不正アクセスなどのサイバー犯罪が多く発生している。本稿では情報セキュリティリスクに対する実効性ある教育活動を、短時間かつ簡易に実施していくための手段として、情報セキュリティインシデントを擬似体験しリスクに対する対応能力を向上させるためのボードゲーム型教材を提案している。さらに本教材を多元的に展開させていくことで問題解決を図ろうとしている。 |
| N-011 |
順序尺度の確率分布における情報量を活用したGPAに代わる評価指標の提案
◎山崎 綾一郎(静岡理工科大学)・吉永 悠人(遠州鉄道)・山岸 祐己(静岡理工科大学/浜松医科大学/良品計画)・谷川 邦(静岡理工科大学)・髙林 貴仁(良品計画)・足立 智子(静岡理工科大学)
×
N-011順序尺度の確率分布における情報量を活用したGPAに代わる評価指標の提案
◎山崎 綾一郎(静岡理工科大学)・吉永 悠人(遠州鉄道)・山岸 祐己(静岡理工科大学/浜松医科大学/良品計画)・谷川 邦(静岡理工科大学)・髙林 貴仁(良品計画)・足立 智子(静岡理工科大学)
GPAは原則,教員による段階評価(S,A,B,…)をもとに算出されるが,この評価は教員の主観に依存することが多い.この場合の段階評価は本来,順序尺度として扱うべきだが,GPA算出時には間隔尺度として扱われている点も問題である.これらの問題を解決する手法として,項目反応理論が挙げられるが,小規模サンプル向けのモデルを用いたとしても,正確な分析には最低でも300程度のサンプルサイズが必要とされる.さらにIRTではハイパーパラメータの設定も求められ,その習得が実用上の障壁となっている.本研究では,順序尺度の確率分布における情報量に着目し,パラメータチューニングが不要なモデルを提案する. |
| N-012 |
ディープラーニングを用いたKnowledge Tracingによる模擬試験受験者の知識状態評価の試み
○伊藤 彰・對間 博之・倉本 卓・市川 尚(神戸常盤大学)
×
N-012ディープラーニングを用いたKnowledge Tracingによる模擬試験受験者の知識状態評価の試み
○伊藤 彰・對間 博之・倉本 卓・市川 尚(神戸常盤大学)
項目反応理論では異なるテストを受験した受験者を同じ尺度で評価することができる。その際、等化やリンキングを行うが、困難度を測定した項目バンクの構築や受験者に共通項目を課すなどテストのデザインに制約がある。大学単位で実施する国家試験受験のための模擬試験では、知識状態が変化する同一母集団に試験を繰り返すため等化が困難である。
そこで、時間経過による知識状態をモデル化できるKnowledge Tracing(KT)を使用する。その中でもdeep-iRTモデルはIRTと同様の解釈性をもつため、問題の質評価の点でも有用である。本研究ではディープラーニングに基づくKTの国家試験模擬試験への適用を試みた。 |
| 情報教育における生成AIの利用 |
|
9月4日(木) 9:30-12:00 4w会場
座長 土肥 紳一(東京電機大学) |
| N-013 |
生成AIとRAGを用いた学生向け多言語支援システムの構築
◎石 澤蘭・松本 一教・須藤 康裕(神奈川工科大学)
×
N-013生成AIとRAGを用いた学生向け多言語支援システムの構築
◎石 澤蘭・松本 一教・須藤 康裕(神奈川工科大学)
本研究では、日本語能力が十分でない留学生が、授業中に日本語で記述された教材を理解する際に直面する課題に着目し、生成AIとRAGを活用した支援システムの設計および予備的な実験結果について報告する。
本システムは、留学生が授業内容を理解する支援を行うとともに、日本語能力の向上を目的としている。そのため、単なる翻訳ツールでは本来の目的を十分に達成することができない。
システムの主な機能は、学習者の母語による註釈の付けや、必要に応じた簡潔な補足説明を通じて、日本語教材の内容を動的に拡張する点にある。これらの補助情報は、各学習者の日本語能力に応じて調整され、個別最適化された支援を提供する。 |
| N-014 |
LLMとゲーミフィケーションを用いた自主学習のモチベーション継続のための学習支援システムの開発
土屋 円華・◎北村 公亮・小野 良太(北海道情報大学)・宇野 礼於(SurpassOne)
×
N-014LLMとゲーミフィケーションを用いた自主学習のモチベーション継続のための学習支援システムの開発
土屋 円華・◎北村 公亮・小野 良太(北海道情報大学)・宇野 礼於(SurpassOne)
近年、ICTを活用した教育支援が進む中、特に自主学習では「時間がない」「やる気が続かない」といった課題が指摘されている。本研究では、資格取得などを目指す学習者の継続的な学習を支援するシステムの開発を目的とする。提案するのは、目標に応じた学習計画を自動生成する「学習計画自動作成システム」、通知機能を活用し実施状況を記録・調整する「学習状況確認通知システム」、学習進捗に応じてキャラクターが成長する「キャラクター育成システム」である。これにより計画的な学習を促進し、モチベーション維持を支援する。今後は、実際の利用による効果検証を予定している。 |
| N-015 |
大規模言語モデルの埋め込み順序回帰による解釈しやすい難易度推定
○江原 遥(東京学芸大学)
×
N-015大規模言語モデルの埋め込み順序回帰による解釈しやすい難易度推定
○江原 遥(東京学芸大学)
教材等の難易度をAIに推定させる事は,難易度の基準と観点の解釈・理解が必要であり適切な教材生成のためにも重要となる,教育情報システムの基礎的なタスクである.既存研究では教育AIの難易度推定の目的でも自然言語処理の手法をそのまま適用してしまっている研究が多数であり,「少なくとも簡単な問題ではない」といった人間が直感的に行っている知見をうまく活用できていない.本研究では,BERTや大規模言語モデルの文脈内学習などの現代的なAI手法を用いた難易度推定を,埋め込み空間上の順序回帰問題として整理し定式化する枠組みを提案する.この定式化の方法は複数あり定式化ごとに異なるモデルができるため,既存のものも新規なものも含まれる.この枠組みにより,様々な難易度尺度の基準についてのAI手法の捉え方を埋め込み空間上で幾何学的・直感的に解釈でき,AI手法と人間が協働しやすくなると期待される.実験では,実際の難易度データセット上で網羅的に性能を比較する.さらに学習履歴データと組み合わせた個別学習支援への応用も論じる. |
| N-016 |
プログラミング教育支援のための大規模言語モデルを利用した音声からの説明図生成
◎湊 敢太郎・山崎 禎晃・大原 剛三(青山学院大学)
×
N-016プログラミング教育支援のための大規模言語モデルを利用した音声からの説明図生成
◎湊 敢太郎・山崎 禎晃・大原 剛三(青山学院大学)
近年,IT人材の需要が高まる一方,プログラミングにおけるアルゴリズムの理解は学習者にとって容易ではない.本研究ではプログラミング実習授業における受講者のアルゴリズム理解を支援するために,教員の口頭による説明を図に変換するシステムを提案する.従来の説明図生成では,課題の事前決定や音声への非対応などの制限があったのに対し,提案システムは音声認識と大規模言語モデルを組み合わせることで任意の課題・説明に対応できる.また,音声分割や文書校正などの前処理により,口語表現や音声認識エラーの影響を軽減する.評価には実際の実習授業で録音した指導音声を利用し,生成した説明図の一貫性や正確性を確認した. |
| N-017 |
プログラミング学習における作問学習の自動評価の適用可能性について
◎山本 明澄・蜂巣 吉成・吉田 敦・桑原 寛明(南山大学)
×
N-017プログラミング学習における作問学習の自動評価の適用可能性について
◎山本 明澄・蜂巣 吉成・吉田 敦・桑原 寛明(南山大学)
プログラミングの学習方法として,作問学習がある.作問学習は与えられた制約を満たすようなプログラム記述問題を学習者が作成する.一般的な学習方法と比べて高い学習効果が期待できるが,評価が難しい.本研究では作問学習の評価方法とフィードバックを提案し, 学生を対象とした作問学習の実験の評価結果から評価方法とフィードバックが妥当かを確認した.学習者は提出物として,出題文に対しての問題文,問題文の模範解答プログラム,模範解答プログラムの実行例を作成する.それらの評価の一部を生成AIによって行うことで人手による評価の手間を省く. |
| N-018 |
多人数講義における学修者からの意見把握を支援するカテゴリ提案・意見分類ツールの開発と検討
◎横山 寧々・尾崎 拓郎(大阪教育大学)
×
N-018多人数講義における学修者からの意見把握を支援するカテゴリ提案・意見分類ツールの開発と検討
◎横山 寧々・尾崎 拓郎(大阪教育大学)
高等教育機関における多人数講義では,学修者への深い理解や参加意欲向上を促すために双方向性の担保を行うことが重要であり,とりわけ授業者によるフィードバックが有効である.しかし,授業者が学修者からの膨大な意見に目を通し,内容を把握することには多大な労力・時間を要する.本研究では,フィードバック作成のために授業者が学修者からの意見を迅速かつ容易に把握できることを目的とし,生成AIを活用した自動でカテゴリ提案及び意見分類可能なツールを提案する.提案ツールの有効性を評価するため,ツール使用時と不使用時における意見の内容把握にかかる作業工程を比較した結果,工程数の減少を確認することができた. |
| 教育学習支援情報システム |
|
9月4日(木) 15:30-17:30 5m会場
座長 関谷 貴之(東京大学) |
| N-019 |
小型ドローンを用いた図書館書籍確認支援のための背ラベル抽出手法の提案
○土江田 織枝・野口 祥汰・林 裕樹(釧路工業高等専門学校)・香山 瑞恵(信州大学)
×
N-019小型ドローンを用いた図書館書籍確認支援のための背ラベル抽出手法の提案
○土江田 織枝・野口 祥汰・林 裕樹(釧路工業高等専門学校)・香山 瑞恵(信州大学)
本研究では,図書館書庫における書籍の存否確認作業の効率化と高所作業の負担軽減を目的とし,小型ドローンで撮影した書棚画像から書籍の背ラベルを抽出し識別する手法を提案する.特に,背ラベル検出にはカスケード分類器を用い,その有効性を評価した.実験の結果,背ラベルが完全に視認可能な状況においては高い検出精度を示し,本手法の有用性が確認された.一方で,書籍の幅が狭くラベルが折り込まれている場合や,影・反射・遮蔽物などの影響を受けると検出精度が低下することが明らかとなった.今後は,部分的にしか視認できない背ラベルに対応可能な検出手法の開発およびデータセットの拡充が課題である. |
| N-020 |
VDT症候群予防システムにおけるユーザ評価に基づく通知方法の検討
○土江田 織枝・山田 昌尚・林 裕樹(釧路高専)・香山 瑞恵(信州大学)
×
N-020VDT症候群予防システムにおけるユーザ評価に基づく通知方法の検討
○土江田 織枝・山田 昌尚・林 裕樹(釧路高専)・香山 瑞恵(信州大学)
本研究では,VDT症候群の予防を目的として,ユーザの姿勢やまばたきをリアルタイムに検出し,適切なフィードバックを行うシステムを開発した.MediaPipeを用いてカメラ映像からまばたきや姿勢を解析し,検出結果に応じて音や視覚による通知を行う.評価実験では,小学生から高齢者までを対象に,通知方法の違いによる「気づき」や受容性を調査した.通知音は静かな環境で有効であり,視覚的通知は騒音環境で効果が高かった.一方で,視覚的通知は一部のユーザに煩わしく感じられることがあり,通知の頻度やデザインへの配慮が求められた.通知手段に対する反応には個人差があり,状況や好みに応じた通知方法の選択が,実効性と受容性の向上に寄与することが確認された. |
| N-021 |
講義室外からの不正な出席情報の提出を防止するためのNFCタグを用いた出席管理システムの開発
◎平原 照也・中村 潤(中央大学)
×
N-021講義室外からの不正な出席情報の提出を防止するためのNFCタグを用いた出席管理システムの開発
◎平原 照也・中村 潤(中央大学)
本研究では、講義室外からの不正な出席情報提出を防止するため、NFCタグを用いた出席管理システムを開発した。従来の出席コード方式の課題であった出席コードやURL流出を解決すべく、各座席に設置されたNFCタグをスマートフォンで読み取ることで、トークンとセッションを発行し、正規の出席者のみがフォームにアクセスできる設計とした。さらにUUIDによる端末識別、出席受付の切替機能により、多重提出や不正アクセスを排除した。本システムは大学の講義室内での正確な出席情報の把握を目的とする。 |
| N-022 |
学業成績データを用いた退学兆候者検出の検討
◎久保田 愛麗・小川 賀代(日本女子大学)
×
N-022学業成績データを用いた退学兆候者検出の検討
◎久保田 愛麗・小川 賀代(日本女子大学)
教育現場において学生の成績低下を早期発見し,適切な支援を通じて退学や休学等のドロップアウトを未然に防止することが求められる.これまでの研究では,課題提出に関するログデータを用いて1授業内におけるドロップアウト兆候者の検出を検討し,自己組織化マップ(SOM:Self-Organizing Maps)を用いた分析手法が有効であることが明らかになっている.そこで本研究では,より高い汎用性の実現を目指し,半期ごとの学業成績データを対象として退学兆候者検出への本手法の適用可能性および有効性を確認する. |
| N-023 |
任意の短期間の授業ログを用いた柔軟な学生の成績予測手法の検討
◎髙橋 龍人・望月 久稔(大阪教育大学)
×
N-023任意の短期間の授業ログを用いた柔軟な学生の成績予測手法の検討
◎髙橋 龍人・望月 久稔(大阪教育大学)
教育データの分析を通じて教育・学習を支援するラーニングアナリティクスの研究が盛んである.また,学生の成績を予測できれば,教員は成績不振の学生を発見し,適切な支援や指導を講じることができる.そこで本研究では,短期間の授業ログデータを用いた高精度な成績予測を目的とし,そのための前処理手法を検討する.任意の期間におけるMoodleログデータから小テストの平均点などの特徴量を抽出し,将来の授業回におけるそれらの特徴量の値を機械学習モデルにより予測する.その後,予測した特徴量を用いて成績を予測し,提案手法の有効性を決定係数の比較により評価する. |
| N-024 |
カリキュラム評価や履修科目の選択を支援するシステムの開発
◎仲山 莉功(九州産業大学)・神屋 郁子・藤野 友和(福岡女子大学)・下川 俊彦(九州産業大学)
×
N-024カリキュラム評価や履修科目の選択を支援するシステムの開発
◎仲山 莉功(九州産業大学)・神屋 郁子・藤野 友和(福岡女子大学)・下川 俊彦(九州産業大学)
高等教育機関において、教育プログラムの自己点検・評価とその結果に基づく改善活動が重要視されている。その対象にカリキュラムが存在するが、カリキュラム構造に基づく客観的な評価手法は十分に確立されていない。本研究の目的は、先行研究で提案された指標や可視化手法をシステム化し、汎用的な可視化ツールとして利用可能にすることである。そのために、先行研究にて示されたネットワーク図の表示方法の改良、関連度の高い科目のハイライト機能の実装、ネットワーク図を補助する情報を出力する機能の実装などを行う。それにより、大学スタッフによるカリキュラムの自己点検・評価や、学生の履修科目の選択を支援する。 |
| 情報リテラシー・情報教育一般 |
|
9月4日(木) 15:30-17:30 5w会場
座長 尾崎 拓郎(大阪教育大学) |
| N-025 |
オンデマンド教材・受講方法の改善に向けた視線計測と受講記録の分析
上妻 大輝・○牛田 啓太(工学院大学)
×
N-025オンデマンド教材・受講方法の改善に向けた視線計測と受講記録の分析
上妻 大輝・○牛田 啓太(工学院大学)
遠隔授業が一般化してきた。本講では,特にオンデマンド型授業に注目し,その受けられ方を調査する。オンデマンド型授業が学生にどのように受け入れられているか,教員の意図どおりに教材が活用されているかを調べた。3科目の,教材の形式が異なるオンデマンド型授業の受講のようすを,視線情報とともに記録するとともに,受講後アンケートを実施した。その結果,適切な強調が受講者の注意を引けること,適切に内容を区切ると情報の整理がしやすいこと,メモを取るのに一時停止をする傾向があること,動画教材は再生速度を速めて受講されることが多いこと,動画教材は短く区切ると集中力が維持されやすいことなどがわかった。 |
| N-026 |
情報科教科書の索引用語の変遷とその特徴:数学科及び公民科との比較分析
○伊藤 智子・伊藤 智義・下馬場 朋禄(千葉大学)・平岡 斉士(放送大学)
×
N-026情報科教科書の索引用語の変遷とその特徴:数学科及び公民科との比較分析
○伊藤 智子・伊藤 智義・下馬場 朋禄(千葉大学)・平岡 斉士(放送大学)
本研究では,高等学校の情報科・数学科・公民科の3教科の教科書の索引用語を対象に,各教科の世代ごとの用語数や特徴の変遷を比較・分析した.索引に含まれる用語数,共通語数,およびJaccard係数に基づく類似度を算出した結果,情報科では世代を追うごとに用語数が増加している一方で,教科書間の共通性は低いことが判明した.数学科では用語の変化が少なく,類似度が高かった.公民科は用語数が多く,一定の共通性を保っていた.これらの結果は,情報科における索引用語の一貫性や,他教科の比較を通じた教科の特性や関連性を考察する上で有用である. |
| N-027 |
教師あり学習と教師なし学習を学ぶ体験型フィジカル教材の提案
○加藤 利康(日本工業大学)
×
N-027教師あり学習と教師なし学習を学ぶ体験型フィジカル教材の提案
○加藤 利康(日本工業大学)
近年,生成AIをはじめとするAI技術の発展により,人工知能は私たちの生活に密接な存在となっている.最新のAI戦略2022では,すべての大学・高専生(約50万人卒/年)や社会人(約100万人/年)にも学習機会を提供することが求められているが,授業形式のみでは学習機会の拡充に限界がある.こうした課題に対応するため,先行研究では自動走行ロボットを用い,標識認識により速度制御を学習する教師あり学習をテーマにした体験型フィジカル教材を開発した.本研究は,学習者にAIの知識をさらに深めてもらうため,教師なし学習における特徴抽出やクラスタリングの仕組みを学ばせる教材を提案する. |
| N-028 |
非情報系学生向けCS教育の再検討
○岩田 健一・笹倉 万里子(鳥取大学)
×
N-028非情報系学生向けCS教育の再検討
○岩田 健一・笹倉 万里子(鳥取大学)
現代社会において、情報技術の基礎理解は、コンピュータサイエンス(CS)専攻の学生だけでなく、すべての大学生にとって不可欠である。本研究では、非情報系学部の学生を対象としたCS教育のあり方を再検討し、一般教養科目としてCSをどのように位置づけ、どのような内容を提供すべきかを考察する。従来の情報リテラシー科目との違いを明確にしつつ、アルゴリズム的思考やデータ構造への理解を重視した教育の意義を探る。実際の授業実践を通じて得られた知見をもとに、非専門家にとって有効なCS教育の構成要素と今後の課題について提案を行う。 |
| N-029 |
関係人口創出に向けた高校生向け離島再現型メタバース構築体験活動の実践
○徳永 徹郎・阿部 直人・望月 崇由(日本電信電話)
×
N-029関係人口創出に向けた高校生向け離島再現型メタバース構築体験活動の実践
○徳永 徹郎・阿部 直人・望月 崇由(日本電信電話)
近年、人口減少や高齢化により地域機能の維持が課題となっている地域において、関係人口の役割がますます重視されている。私たちは、高松市男木島を対象に、島全体を計測して得た点群データを用いて3次元仮想空間を構築し、関係人口創出への適用を検討してきた。本研究では、高校生を対象に、関係人口となり得る可能性を見据え、地域社会の課題に対する興味関心を高めることを目的とし、また、キャリア形成支援の一助となるよう、計測やデータ処理などメタバース構築に関する一部の作業を体験する課外活動プログラムを立案し実施した。ここでは、そのプログラムの実施内容とアンケート調査結果について報告する。 |
| プログラミング教育関連 |
|
9月5日(金) 9:30-12:00 6v会場
座長 渡辺 博芳(電気通信大学) |
| N-030 |
コーディングシーケンスを用いたプログラミングスキル判定指標の検討
○荒木 力樹・納富 一宏(神奈川工科大学)
×
N-030コーディングシーケンスを用いたプログラミングスキル判定指標の検討
○荒木 力樹・納富 一宏(神奈川工科大学)
プログラミングスキルの判定は,作成されたプログラムのソースコードを見るだけでは困難であり,ソースコーディングにおける編集操作の過程の情報の確認が必要である.筆者らの先行研究では,編集時の打鍵情報を時系列で記録したデータを「コーディングシーケンス」と呼び,その分析によりプログラミングスキルを判定する手法について検討してきた.本発表では,プログラミングスキル判定に資する指標の決定を目的として,プログラミング実験により収集したコーディングシーケンスの分析により,従来指標と新たに設定した指標について比較・検討した結果を報告する.今後,コーディングシーケンスからプログラミングスキルの自動判定を目指す. |
| N-031 |
視覚特別支援学校における10キープログラミング教材の評価
◎月野 駿佑・木室 義彦・家永 貴史(福岡工業大学)
×
N-031視覚特別支援学校における10キープログラミング教材の評価
◎月野 駿佑・木室 義彦・家永 貴史(福岡工業大学)
我々は,全盲児童も使える10キープログラミングロボット教材を開発している.この教材は,各種センサと無線通信機能も有しており,小中高で利用可能なものとなっている.しかし,学校現場での教材利用は未検証であった.このため,全国42の視覚特別支援学校にプログラミング教材および説明書のみを送付し,授業等を実施してもらい,教材に対するアンケート調査を行った.この結果,児童生徒にとっては,プログラミングの結果を音や触れられることが有用なこと,プログラミング未経験の教員でも指導可能なこと,中学校技術や高校情報で利用可能なことが確認された. |
| N-032 |
コンピュータを使うLチカを行う前の前提知識について
○土肥 紳一(東京電機大学)
×
N-032コンピュータを使うLチカを行う前の前提知識について
○土肥 紳一(東京電機大学)
地域貢献の要望が届くようになり,子供が電子工作に興味を持たせるための工夫を考えるようになった.そこで着目したのが,発光ダイオードをチカチカと点滅させるLチカである.Lチカはコンピュータを使った制御で実施することが多い.シングルボードコンピュータにLEDを複数組み込み,プログラムで制御できるものもある.このようにいったん組み込まれてしまうと,使用するLED素子の特徴や性質を理解することは難しくなる. 本論文では使用するLEDの素子に着目し,コンピュータを使わない手動によるLチカに焦点を当て,そこに隠れているハードウェア固有の問題を取り上げ,コンピュータを使ったLチカへ発展させるための準備について述べる. |
| N-033 |
AST解析・変数重み付け・乱数制御を利用したJavaプログラミング課題採点システムの構築
◎岡崎 壮汰・土屋 誠司・渡部 広一(同志社大学)
×
N-033AST解析・変数重み付け・乱数制御を利用したJavaプログラミング課題採点システムの構築
◎岡崎 壮汰・土屋 誠司・渡部 広一(同志社大学)
本研究では,Javaのプログラミング課題の採点を効率化するため,プログラミング課題の自動採点システムを構築する.採点手法として,(1)抽象構文木(AST)の解析,(2)ブラックボックステスト,(3)重み付けによる採点時の重要変数の特定と検証の3点を組み合わせる.(2)のブラックボックステストの精度向上のため,答案のプログラムに乱数生成が含まれる場合に乱数の値を固定する機能を実装する.(3)の重要変数の特定では,変数が重要であるかを判断する複数の指標をもとに重要度を重み付けする方式を用いる.これらの機能により,プログラミング課題の自由度を尊重しつつ,柔軟かつ高性能な自動採点を可能とする. |
| N-034 |
C言語における関数の戻り値とブロック構造の確認が可能な自動採点ツールの提案
◎白石 太陽・水谷 泰治・西口 敏司・橋本 渉(大阪工業大学)
×
N-034C言語における関数の戻り値とブロック構造の確認が可能な自動採点ツールの提案
◎白石 太陽・水谷 泰治・西口 敏司・橋本 渉(大阪工業大学)
プログラミング演習において自動採点が行われている.この自動採点において,関数で行うべき処理や戻り値の仕様が課題で求められているものとは異なるが,最終的なプログラムの出力結果が正しいために,誤って正解と判定してしまう場合がある.
本研究ではC言語のプログラムを対象に,実行時に呼び出された関数の戻り値を出力する機能,およびプログラム内のブロック構造を出力する機能を提案する.これらの機能により,関数の戻り値が誤っていないかを確認したり,各ブロックに想定していない処理が存在するかを判定することができるようになり,誤採点を減らすことができる. |
| N-035 |
オンラインジャッジのコンテスト機能の実装とプログラミング教育での運用について
○國持 良行(静岡理工科大学)
×
N-035オンラインジャッジのコンテスト機能の実装とプログラミング教育での運用について
○國持 良行(静岡理工科大学)
オンラインジャッジシステムは,プログラミングコンテスト等でよく使われるプログラムの自動採点するWebサイトである.プログラミングの導入教育に活用するために,クラウド上にSist Online Judgeシステム(SOJと略す)を開発した.学生が正課外でプログラミングを自主的に学習し,その能力を高めることを目標としている.2023年度には日ごろの学習成果を確認するために,SOJにコンテスト機能を追加した.そして,プログラミングの授業における演習や試験で活用し,受講者のプログラミング能力の把握に役立てている.ここでは,実装した機能を紹介し,その運用の効果について検証する.また,現状の課題についても考察する. |
| 人文科学とコンピュータ |
|
9月5日(金) 9:30-12:00 6w会場
座長 土山 玄(お茶の水女子大学) |
| N-036 |
歴史的文化財の形状のデジタルアーカイブ化に適した簡易3次元復元手法に関する調査
◎上野 烈士・中原 匡哉(大阪電気通信大学)
×
N-036歴史的文化財の形状のデジタルアーカイブ化に適した簡易3次元復元手法に関する調査
◎上野 烈士・中原 匡哉(大阪電気通信大学)
近年,歴史的文化財の保護に関するSDGsの達成に向け,デジタル上に現実空間の形状を保存するデジタルアーカイブ技術の開発が進められている.ただし,歴史的文化財は全国各地に点在しており,測量業者が網羅的に計測するのは現実的ではない.そのため,一般人でも3次元形状を復元可能なスマートフォンによる撮影画像を用いて共創的にデジタルアーカイブ化する方法の実現が期待されている.既存研究では,NeRFと3D Gaussian Splattingによる3次元復元が注目されているが,どちらの手法が記録に適しているのかが明らかになっていない.そこで,本研究では,同一の歴史的文化財を対象に,可視化結果や寸法値の再現性の観点から,各既存手法の有用性を比較する. |
| N-037 |
欠損領域の補完による歴史的文化財の設計値の復元に関する研究
◎小林 満里奈・中原 匡哉(大阪電気通信大学)
×
N-037欠損領域の補完による歴史的文化財の設計値の復元に関する研究
◎小林 満里奈・中原 匡哉(大阪電気通信大学)
近年,歴史的文化財の設計値や外観を推定,復元し保存する取り組みが推進されている.例えば,首里城では,火災による焼失を受けて復興プロジェクトが立ち上がり,画像から焼失した正殿などの3次元モデルを復元することに成功した.しかし,本来は設計値や外観に関連する資料が少ないため復元が難しく,事前に設計値や外観を保存することが望ましい.既存研究では,地上設置型のレーザスキャナを用いて図面復元に必要となる設計値を抽出する手法が提案されている.しかし,本機器で計測した点群データには,測定環境や障害物などによって,計測できない箇所が生じる場合があり,欠損箇所の図面復元が困難となる課題がある.そこで本研究では,設計値の抽出のために欠損箇所を推定し,補完する手法を提案する. |
| N-038 |
文化分析におけるオントロジーアプローチ:遺伝子オントロジーとシミュレーションオントロジーによるコンセプトカフェ文化の理解への架け橋
○岡野 悠太郎・山田 和範(東北大学)
×
N-038文化分析におけるオントロジーアプローチ:遺伝子オントロジーとシミュレーションオントロジーによるコンセプトカフェ文化の理解への架け橋
○岡野 悠太郎・山田 和範(東北大学)
コンセプトカフェ(コンカフェ)は2010年代後半以降,日本で急速に人気を集め,独自の文化的現象へと発展してきた.本研究では,数百店舗に及ぶ既存カフェの大規模調査を通じ,各店舗のテーマを標準化された識別子で注釈付けし,テーマ的関係性や文化的意義に基づいた階層構造の中で整理する,データ駆動型オントロジーを構築した.また,特定のテーマが社会的変化やエンターテインメントコンテンツとどのように結びついているかを文化的に分析した.本研究は,コンカフェの多様性と進化の理解に資する包括的な枠組みを提供し,今後は類似テーマに基づくクラスタリングとトレンド概念の抽出を通じて,文化変容の動態を明らかにしていく. |
| N-039 |
ジャンルごとの語彙多様性を再現するために必要なテキストサイズの推定
○鄭 弯弯(名古屋大学)
×
N-039ジャンルごとの語彙多様性を再現するために必要なテキストサイズの推定
○鄭 弯弯(名古屋大学)
語彙の多様性を測定する指標の安定性については、既存研究において50語、100語、150語といった増分による評価が数多く行われている。しかし、「指標が安定になったかどうか」ではなく、「どの程度の語数から、個人やジャンルの語彙的特徴が再現性をもって安定的に捉えられるか」という問いは、極めて重要であると考えられる。本研究では、「ジャンルに固有の語彙多様性を安定して再現するために、どの程度のテキストサイズが必要か」という問いを立て、日本語コーパスに含まれる複数のジャンル(演説、自然会話、小説とニュース)を対象に、ジャンルごとに語彙多様性を安定的に再現するために必要なテキストサイズの推定を試みた。 |
| N-040 |
博物館におけるOCRを使用した展示パネルからの展示物名・説明文の取得
◎山里 拓夢・赤嶺 有平(琉球大学)・根路銘 もえ子(沖縄国際大学)
×
N-040博物館におけるOCRを使用した展示パネルからの展示物名・説明文の取得
◎山里 拓夢・赤嶺 有平(琉球大学)・根路銘 もえ子(沖縄国際大学)
近年博物館法が改正され、博物館資料のデジタルアーカイブ(DA)化が促進されている。しかし技術職員の不在などから多くの博物館にとってDAの作成はハードルが高い。この問題解決のために、本研究室ではDAの作成から公開までを自動化する研究を行なっており、その試みとして博物館内で撮影された画像からDAを作成する研究を行なっている。DA作成のためには、展示物の名前や説明文が必要となる。そのため、本研究では展示物の横に設置されている説明パネルの画像から、画像補正とOCRを用いて展示物名と説明文を取得する。また、100%の精度で取得することはできないため、取得テキストの正誤判定システムも提案する。 |
| N-041 |
画像内の展示物と説明パネルの関係性推定に関する研究
◎志田 晃一・赤嶺 有平(琉球大学)・根路銘 もえ子(沖縄国際大学)
×
N-041画像内の展示物と説明パネルの関係性推定に関する研究
◎志田 晃一・赤嶺 有平(琉球大学)・根路銘 もえ子(沖縄国際大学)
2022年の博物館法改正で博物館の事業に博物館資料のデジタルアーカイブ(DA)の作成と公開が新たに位置づけられたことによりDA作成需要の増加が見込まれる。本研究室ではDA作成の自動化として、既に展示されている博物館資料を撮影した画像から展示物とその説明パネルの情報を抽出してDA化する手法について研究を行っている。撮影した画像内には複数の展示物やパネルが存在している場合があり、抽出した展示物画像やパネルの説明文を適切に組み合わせる必要がある。本研究では、展示物とパネルの座標情報からそれらの組み合わせの有無を予測するモデルの構築を目指している。 |
| N-042 |
城跡と古道及び周辺地形の3D可視化アプリの開発
◎有銘 真之助・赤嶺 有平(琉球大学)・根路銘 もえ子(沖縄国際大学)
×
N-042城跡と古道及び周辺地形の3D可視化アプリの開発
◎有銘 真之助・赤嶺 有平(琉球大学)・根路銘 もえ子(沖縄国際大学)
沖縄にはグスク(城跡)をはじめとする多くの文化的遺産が各地に点在しており、これらは単なる建造物としての価値にとどまらず、周囲の自然地形や当時の交通網(古道)との関係性からもその歴史的・文化的意義を読み取ることができる。しかし、こうした空間的関係性を視覚的に理解する手段は限られている。そこで本研究では、フォトグラメトリ技術により取得したグスクや古道の3Dモデルと地形データ、史跡情報を統合し、Webブラウザ上で直感的に閲覧・操作可能なアプリケーションの開発を目的とする。3Dモデルの作成にはopenMVGおよびopenMVSを用いる。さらに、複数の表示対象を効果的に切り替えられるユーザーインターフェースを設計し、ユーザビリティと理解促進を図る。 |