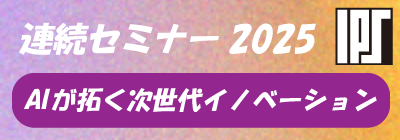連続セミナー2025「AIが拓く次世代イノベーション」
第11回【2025年12月5日(金)13:00-15:40】 ※オンライン開催(Zoomウェビナー)
デジタル社会を支える新たなトラスト ~技術と社会の両面から~
ソーシャルメディアや生成AIなどの急速な浸透をはじめとする社会のデジタル化は様々なメリットをもたらす一方で、情報の過度な偏重・流通や高度な加工も容易になり、偽情報や陰謀論など新たな混乱や問題も引き起こしている。 特に、アナログ社会において信頼のよりどころとされてきた社会制度や技術の一部は、デジタル社会でそのまま踏襲することは難しく、技術と社会の両面から新たなトラストを形成していく必要がある。
本セミナーでは、この新たなトラストの形成に向けて技術と社会の両面から最新の取組みを紹介するとともに、両者の協調に向けた展望や、それぞれが担うべき役割について論じる。
※本セミナーは、配布資料とアーカイブ配信をご提供いたします。
-
[13:00-13:10]オープニング
 島岡政基(セコム株式会社 IS研究所 デジタルプラットフォームディビジョン 主幹研究員)
島岡政基(セコム株式会社 IS研究所 デジタルプラットフォームディビジョン 主幹研究員)
【略歴】1998年慶應義塾大学大学院理工学研究科修士課程修了.同年セコム(株)入社.2004年より同IS研究所.2005~10年国立情報学研究所特任准教授(後に客員准教授),2019年筑波大学システム情報系客員准教授,2020年より同システム情報工学研究群准教授(協働大学院)を兼務.2022~24年経済産業省商務情報政策局情報経済課(出向).博士(情報学).認証基盤とトラストの研究開発に従事.2023年より本会SPT研究会主査.ほかCSEC研究会幹事,論文誌ジャーナル/JIPネットワークグループ編集委員・主査,同各種特集号編集委員などを歴任. -
[13:10-13:30] Session1「セキュリティ分野におけるトラスト研究に向けた取組み」

これまでの情報セキュリティは、情報資産や情報システムの機密性・完全性・可用性を守ることに重点を置いてきた。しかし、デジタル社会が進展する中では、情報だけでなく、情報を利用する人やシステムに対するトラスト(信頼)を確保することが喫緊の課題となっている。この変化に対応していくには、情報セキュリティを単なる技術ではなく、人々や社会のトラストを支える機能のひとつとして位置づけ直す必要がある。こうした観点から、情報科学や工学に加えて、心理学や社会学といった人文・社会科学の知識も取り入れた「総合知」に基づく分野横断的なアプローチの重要性が増している。このセッションでは、セキュリティ心理学とトラスト(SPT)研究会における、分野横断的なトラスト研究の取組みについて紹介する。
島岡政基(セコム株式会社 IS研究所 デジタルプラットフォームディビジョン 主幹研究員) -
[13:30-13:50] Session2 「情報社会における社会的側面からのトラスト形成」

現在、インターネット等の情報通信における技術的トラストがさまざまな脅威にさらされると共に、政治や行政、社会におけるさまざまな場面で人々が「トラスト」を喪失しつつある。トラストを確立して維持することは技術的にも社会的にも重要であるが、そのためにはさまざまな専門の知見を総合したアプローチが必要とされる。トラストを確立・回復して維持するためのアプローチや可能性について検討を加える。
また政治や行政におけるトラストの確立には、法律という制度を用いることも必要であるが、急速に進化する技術に対して法整備が追いつかないという状況が生じている。その一つは選挙に関係する問題である。フェイク情報、誹謗中傷、世論誘導などに対して、各国がどのように法整備を行って対処しようとしているのかを検討する。湯淺 墾道(明治大学 専門職大学院ガバナンス研究科 教授)
【略歴】1970年生。青山学院大学法学部卒業。2008年九州国際大学副学長。2011年情報セキュリティ大学院大学情報セキュリティ研究科教授。2020年情報セキュリティ大学院大学副学長。2021年より明治大学専門職大学院ガバナンス研究科教授。2024年より明治大学学長室専門員。一般財団法人日本サイバー犯罪対策センター理事、一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター理事、総務省情報通信政策研究所特別研究員、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)社会技術研究開発センター(RISTEX)SDGsの達成に向けた共創的研究開発プログラム(情報社会における社会的側面からのトラスト形成)プログラム総括ほか。 -
[13:50-14:00]休憩
-
[14:00-14:40]Session3 「可視化によるトラスト形成:パーソナライズされたデジタル情報空間のリテラシー教育」

現在の情報化社会において、その膨大すぎる情報のせいで、我々はどの情報を閲覧するかの決定を人工知能を使った推薦システムに依存してしまっている。この状況は、快適ではあるが情報の取捨選択権を手放したともいえるだろう。AIによる推薦は我々の興味関心にのみ着目し、情報の真偽や有用性を評価しない。その意味で、我々が接する情報は常に偽・誤情報や炎上などの社会リスクに晒されている。にも関わらず、我々が見る情報が人工知能によってパーソナライズされていることが社会的にほとんど認知されていない。この現状と認識のギャップは情報社会におけるトラストを考える上で大きなリスクである。
そこで、利用者の情報空間に対する基礎的認識・行動について調査分析を行い、デジタル情報空間の可視化技術を開発し、可視化を用いたリテラシー教育を開発した。本講演ではその成果を報告する。
鳥海 不二夫(東京大学 大学院工学系研究科 教授)
【略歴】2004年東京工業大学大学院理工学研究科機械制御システム工学専攻博士課程修了(博士(工学)),同年名古屋大学情報科学研究科助手,2007年同助教,2012年東京大学大学院工学系研究科准教授,2021年同教授. 計算社会科学,人工知能技術の社会応用などの研究に従事. 計算社会科学会副会長.情報法制研究所理事.人工知能学会.電子情報通信学会,情報処理学会,日本社会情報学会,AAAI各会員.「科学技術への顕著な貢献2018(ナイスステップな研究者)」 -
[14:40-14:50]休憩
-
[14:50-15:35]パネルディスカッション「今後のトラスト研究の展望とIT・セキュリティ技術の果たす役割」
ここまでのセッションを踏まえ、今後のトラスト研究について社会的アプローチと技術的アプローチの両面から展望するとともに、その中でIT・セキュリティ技術がデジタル社会において果たす役割、あるいはデジタル社会からIT・セキュリティ技術に対する期待について議論する。
-
 村山 太一(横浜国立大学 大学院環境情報研究院 社会環境と情報部門 助教)
村山 太一(横浜国立大学 大学院環境情報研究院 社会環境と情報部門 助教)
【略歴】2022年から2024年まで大阪大学産業科学研究所での特任助教を経て、2024年から横浜国立大学助教。
-
 上島 淳史(慶應義塾大学 文学部 助教)
上島 淳史(慶應義塾大学 文学部 助教)
【略歴】 2021年東京大学大学院人文社会系研究科修了。博士(社会心理学)。日本学術振興会特別研究員(PD)を経て、2024年4月より慶應義塾大学文学部助教。専門分野は社会心理学。
-
 満塩尚史(順天堂大学 健康データサイエンス学部 准教授)
満塩尚史(順天堂大学 健康データサイエンス学部 准教授)
【略歴】 システム監査、情報セキュリティコンサルティングに従事し、経済産業省・IT総合戦略室政府CIO補佐官、デジタル庁セキュリティアーキテクトを歴任。現在、順天堂大学健康データサイエンス学部准教授。CRYPTOREC暗号技術活用委員会、デジタル庁本人確認ガイドラインの改定に向けた有識者会議、経済産業省ウラノス・エコシステムの拡大及び相互運用性確保のためのトラスト研究会などのメンバーとして活動。
-
 阿部涼介(慶應義塾大学 政策・メディア研究科 特任助教)
阿部涼介(慶應義塾大学 政策・メディア研究科 特任助教)
【略歴】慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任助教.同研究科 修士課程卒(修士 (政策・メディア)).2022年3月同大学同研究科博士課程単位取得退学.2022年4月より現職.デジタル証明書およびブロックチェーン技術の研究に従事.2022年3月よりWIDEプロジェクトボードメンバ,2023年4月よりTrusted Web推進協議会タスクフォースメンバ. -
[15:35-15:40]クロージング
 島岡政基(セコム株式会社 IS研究所 デジタルプラットフォームディビジョン 主幹研究員)
島岡政基(セコム株式会社 IS研究所 デジタルプラットフォームディビジョン 主幹研究員)