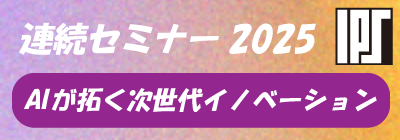連続セミナー2025「AIが拓く次世代イノベーション」
第5回【9月12日(金) 13:00~16:00】 ※オンライン開催(Zoomウェビナー)
世界のAIガバナンス政策、安全性評価、国際標準を巡る最新動向
近年、AI技術は、引き続き急速な進展を遂げるとともに、その社会的な影響はグローバルに拡大し続けており、この結果、世界各国・地域のAI政策は、その安全性の確保に向けたガバナンス政策を含めて、もはや当該国・地域のイノベーション・経済安全保障政策の中核的な政策と位置づけられつつあります。その際、その社会文化的状況、経済産業的・地政学的な状況な差異を背景に、これらの政策は、各国・地域間の多様性とその対立をはらみながらも、他方で、AIの開発・利用に係るグローバルな相互運用性の確保に向けた取組みも積極的に進められつつあります。
このような問題意識のもと、本セッションでは、世界各国のAIガバナンス政策を巡る最新の状況を紹介した上で、その中で、特に、安全評価手法、AI国際標準の観点からのグローバルな相互運用性確保に向けた最新の動向や課題について紹介いただきます。
※本セミナーは、配布資料とアーカイブ配信をご提供いたします。
-
[13:00-13:05]オープニング
 市川 類(東京科学大学データサイエンス・AI全学教育機構(DSAI)/一橋大学イノベーション研究センター(IIR)特任教授)
市川 類(東京科学大学データサイエンス・AI全学教育機構(DSAI)/一橋大学イノベーション研究センター(IIR)特任教授)
【略歴】1990年東京大学修士課程修了(広域科学)、1997年MIT修士修了(技術政策)、2013年政策研究大学院大学博士修了(STI政策)。博士(政策研究)。1990年、通商産業省(現経済産業省)入省。その後、各種の技術・イノベーション政策、特にデジタル・AI政策に従事。2013年内閣官房IT総合戦略室内閣参事官、2017年産総研AI研究戦略部長等、2020年一橋大学イノベーション研究センター教授。2023年より現職:東京科学大DSAI特任教授、一橋大IIR特任教授、JST/CRDSフェロー。 -
[13:05-13:55]Session1「世界のAI規制・ガバナンス政策を巡る最新動向」

近年、AI技術は、引き続き急速な進展を遂げるとともに、その社会的な影響はグローバルに拡大し続けており、この結果、世界各国・地域のAI政策は、もはや各国・地域のイノベーション・経済安全保障政策の中核的な政策と位置づけられつつあります。そのような中、世界各国・地域のAIガバナンス・規制政策は、その社会文化的状況、経済産業的・地政学的な状況な差異を背景に、多様性と対立をはらみながら、急速に変化しつつあります。
このような中、本講演では、AI技術の進展とそのガバナンス・規制政策の生成及びその多様性に係る社会メカニズムを説明した上で、生成AIの登場による世界でのAI安全に係る関心の高まりから、AI技術・産業の変化に伴う各国のAI機会への追求への重点の変化も含めて、世界各国及び国際機関におけるAIガバナンス・規制政策に係る最新の動向と全体像について説明し、今後の世界・日本のAIガバナンス政策の方向について読み解きます。
市川 類(東京科学大学データサイエンス・AI全学教育機構(DSAI)/一橋大学イノベーション研究センター(IIR)特任教授)
-
[13:55-14:05]休憩
-
[14:05-14:55]Session2「AISIとセーフティ評価を巡る最新動向」

AI技術は急速に進歩し、社会への普及が広がる中、その利便性と同時に安全性への関心も高まっている。我が国は、国際的なルールの検討を行うため広島AIプロセスを主導するなど、AIの安全性に関するグローバルな議論を推進している。そうした中、安全性確保に向けた国際的な枠組みつくりも検討が始まっている。こうした世界の潮流に軌を一にして、2023年12月21日のAI戦略会議では岸田総理大臣から英国や米国に続きAIセーフティ・インスティテュート(AISI)の設立が表明され、「統合イノベーション戦略2024」(2024年6月4日閣議決定)にもあるとおり、2024年2月14日にAIセーフティ・インスティテュートを発足させた。AI安全性の中心的機関として、AISIの方針や直近の取り組み、AIセーフティに関する評価やレッドチーミングの基本的な考え方や世界のAIセーフティ評価の最新動向などについて紹介する。
北村弘(AIセーフティ・インスティテュート(AISI) 技術統括、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)デジタル基盤センター・デジタルエンジニアリング部 エキスパート)
【略歴】AISI国際ネットワークTrack3:Risk Assessment of Advanced AI Systems日本代表、東京大学未来ビジョン研究センター客員研究員、国立研究開発法人産業技術総合研究所客員研究員、東洋大学総合情報学部 AI 監査研究プロジェクトおよび東洋大学 AI 監査研究会委員、経産省共同事務局|総務省オブザーバ— AI事業者ガイドライン、CDLE AIリーガルGr長、AI法研究会メンバー等を歴任。 -
[14:55-15:05]休憩
-
[15:05-15:55]Session3「AI国際標準化の現状」

ISO/IEC JTC1/SC42 において人工知能の国際標準化が2018年より進められている.2025年5月時点で,34の国際規格の出版を完了しており,46の国際規格の開発が進んでいる.SC42のParticipating member 47ヶ国,Observing memberは 24ヶ国となっており,活動の裾野は広がっている.SC42の活動においては,10ある国際コンビーナ職に日本からWG2, WG4, JWG1, JWG3と多くの貢献をしている.また,プロジェクト提案についてもユースケース関連(24030),機能安全関連(23281, 5469, 22440-1,2,3),データ品質関連(5259-1,2,3,4,5),ライフサイクル関連(5338), ヒューマン・マシン・チーミング等,トップクラスの貢献をしており,各国との協力関係も充実して来ている.
SC42の活動ならびに世界各国の関係各機関の活動などについて,概要を述べる
杉村 領一(国立研究開発法人産業技術総合研究所 情報・人間工学領域 連携推進室 チーフ連携オフィサー)
【略歴】1980年松下電器産業株式会社入社、1984年新世代コンピュータ技術開発機構(ICOT)出向。1999年パナソニックOWL(UK)社長。2001年 松下電器モバイルネットワーク研究所所長。2004年 パナソニックモバイルコミュニケーションズモバイルシステム開発センター所長、Symbian Supervisory Board Memberなど。2006年 ESTEEMO副社長、LIMO財団設立メンバー、財務担当役員。2012年 NTTドコモ入社、戦略アライアンス担当部長、プロダクトイノベーション担当部長、TIZENアソシエーション議長、FIDOアライアンスD@SWG議長。2016年 現職。2018年4月 ISO / IEC JTC 1 / SC 42国内専門委員会委員長。 工学博士(京都大学)、教養修士(英国ランカスター大学)IMPM,IMPMディプロマ(INSEAD、フランス)。人工知能学会理事、ソフトウェア科学会理事、電子情報通信学会評議員を歴任。筑波大学客員教授. -
[15:55-16:00]クロージング
市川 類(東京科学大学データサイエンス・AI全学教育機構(DSAI)/一橋大学イノベーション研究センター(IIR)特任教授)