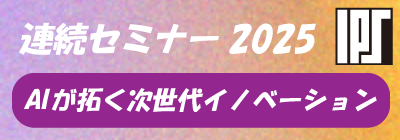連続セミナー2025「AIが拓く次世代イノベーション」
第8回【10月20日(月) 13:00-15:30】 ※オンライン開催(Zoomウェビナー)
音楽・アニメ・食事: 情報技術が切り拓くメディア体験・制作の未来
情報学分野の研究開発によって、メディア体験・制作の新たな可能性が次々と切り拓かれています。そこで本セミナーでは、通常は同じ「メディア」というカテゴリで取り上げられることの少ない、「音楽」「アニメ」「食事」という三つの多様なトピックを敢えて取り上げて、それぞれの未来がどう切り拓かれつつあるのかを議論します。各トピックについて、事前知識がなくても講演を楽しめるように、研究者自身による具体的な研究事例・動画等を豊富に交えながら紹介します。
※本セミナーは、配布資料とアーカイブ配信をご提供いたします。
※アフタートーク(懇談会)の情報を追加いたしました。
-
[13:00-13:05]オープニング
 後藤 真孝(国立研究開発法人産業技術総合研究所 上級首席研究員)
後藤 真孝(国立研究開発法人産業技術総合研究所 上級首席研究員)
【略歴】1998年早稲田大学大学院 理工学研究科 博士後期課程修了。博士(工学)。現在、産業技術総合研究所 上級首席研究員。2009~2017年にIPA未踏IT人材発掘・育成事業PM、2016~2022年にJST ACT-I研究総括を兼任。現在、JST 創発PO、早稲田大学 客員教授、統計数理研究所 客員教授、筑波大学連携大学院 教授等を兼任。日本学士院学術奨励賞、日本学術振興会賞、ドコモ・モバイル・サイエンス賞、市村学術賞、星雲賞等、73件受賞。 -
[13:05-13:45]Session1「情報技術が切り拓く音楽体験の未来」

音楽に関連した情報技術が発展することで、人々の音楽体験がどのように多様で豊かになっていくのかを議論します。コンピュータ上で音楽のあらゆる側面を扱う研究分野である「音楽情報処理」では、身近で魅力的な様々な技術が研究開発されてきました。既に音楽の鑑賞や創作の多くの場面で利用されていて、コンピュータやインターネットの環境を活かして音楽を聴いたり制作したりできるのは音楽情報処理が発展したおかげですし、新しい技術も次々と生まれています。
本講演では、そうした技術の中でも特に、信号処理や機械学習に基づいた音楽理解技術(音楽の中身を自動解析する技術)によって、どのような新たな価値を生み出せるのか、どのような音楽体験の未来が切り拓かれるのかを議論します。具体的なイメージが得られるように、産業応用やヒューマンコンピュータインタラクション(HCI)の観点も交えつつ、我々の研究成果を中心に様々な事例を紹介します。後藤 真孝(国立研究開発法人産業技術総合研究所 上級首席研究員)
【略歴】1998年早稲田大学大学院 理工学研究科 博士後期課程修了。博士(工学)。現在、産業技術総合研究所 上級首席研究員。2009~2017年にIPA未踏IT人材発掘・育成事業PM、2016~2022年にJST ACT-I研究総括を兼任。現在、JST 創発PO、早稲田大学 客員教授、統計数理研究所 客員教授、筑波大学連携大学院 教授等を兼任。日本学士院学術奨励賞、日本学術振興会賞、ドコモ・モバイル・サイエンス賞、市村学術賞、星雲賞等、73件受賞。 -
[13:45-13:55]休憩
-
[13:55-14:35]Session2「情報技術が切り拓くアニメ制作の未来」

アニメは世界中で大変人気がある商業芸術ですが、その制作工程はあまり知られていません。本講演では、まず、コンピュータ登場以前からの長い歴史の中でクリエータが培ってきたアニメづくりのノウハウの一端を紹介するとともに、こうした歴史を踏まえたうえで、情報技術による創造性支援ツールがどのように制作工程を支援できるのか紹介します。とくに、アニメの「設計図」ともいわれ、ほとんど全工程に関係する絵コンテについて、アニメ制作の現場を見聞きしてきた研究者の観点で扱います。また、アニメはその多くが漫画原作を持ち、劇中で音楽が流れたり、逆に音楽に併せて制作されたりするなど、他のメディア表現とも深い関わりがあります。日本はとくにクリエータやファンのコミュニティが盛んで、コンテンツに関する研究開発では技術だけでなく社会的側面も重要です。本講演では、こうした社会技術的システムを扱う研究アプローチについても紹介します。
加藤 淳(国立研究開発法人産業技術総合研究所 主任研究員)
【略歴】博士(情報理工学)。2014年より国立研究開発法人 産業技術総合研究所研究員、2018年より主任研究員。同年よりアーチ株式会社技術顧問を兼務。2024年度パリ=サクレ大学に客員科学者として滞在。Human-Computer Interaction全般、とくにクリエイタ向け創造性支援ツールの研究に取り組む。技術移転にも取り組み一般公開サービスを開発、運営。ナイスステップな研究者2024など受賞多数。 -
[14:35-14:45]休憩
-
[14:45-15:25]Session3「情報技術が切り拓く味覚メディアの未来」

味を記録・再生し、遠隔で共有するなど、味覚を自在に操る——それが「味覚メディア」の世界です。白黒やアニメなどあらゆる映像にAI推定で味を付与し画面を舐めて味わえるテレビ、甲殻アレルギーでも安全にカニクリームコロッケを味わえたり毒キノコの味も楽める調味家電、カカオやワインの品種・産地の差の再現、音声入力で一口毎に違う味を楽しめるスプーン、熟成度を自在に操って賞味期限を死語にする「味のタイムマシン」、「脂質ゼロの油」「脂質糖類ゼロのクリーム」を生成する装置などを実現してきました。
本講演ではさらに、味のみならず香りと栄養もメディア化することで食を再構築するビジョンを提示し、最新の進捗を披露します。カロリーを抑えつつ栄養と満足感を同時に得る夜食、宇宙滞在や医療現場での個別最適食など、多岐にわたる応用を視野に入れ、サステナブルな資源利用も同時に叶えることで、新たな食の豊かさを実現します。宮下 芳明(明治大学 総合数理学部 先端メディアサイエンス学科 教授・学科長)
【略歴】「味覚メディア」の概念を提唱。明治大学教授。千葉大学客員教授。電気で減塩食品の塩味を強める「エレキソルト」をキリンホールディングスと開発・販売。内閣府オープンイノベーション大賞 日本学術会議会長賞、CES2025イノベーションアワード2部門受賞。アサヒグループジャパンとともに、個々の味覚・嗅覚・栄養ニーズに基づく食体験の創造を目指す共同研究を行っている。著書に「13歳から挑むフロンティア思考」等。イグ・ノーベル賞(栄養学)受賞。 -
[15:25-15:30]クロージング
 後藤 真孝(国立研究開発法人産業技術総合研究所 上級首席研究員)
後藤 真孝(国立研究開発法人産業技術総合研究所 上級首席研究員) -
[15:30-16:00] アフタートーク(懇談会)