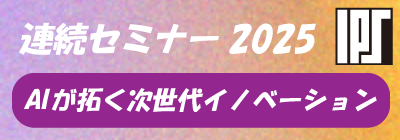連続セミナー2025「AIが拓く次世代イノベーション」
第1回【6月13日(金)開催 9:00~11:50】 ※オンライン開催(Zoomウェビナー)
人工知能(AI)研究開発動向の俯瞰と展望
本セッションでは、近年急速な技術発展を示している人工知能(AI)について、研究開発の潮流や注目動向を俯瞰するとともに、今後の展望を論じます。まず、AI分野動向の俯瞰的調査に携わっている福島(JST CRDS)が、AI分野の研究開発動向を大きく3つの潮流として捉えて概観します。続いて、栗原(慶大、人工知能学会の現会長)と浦本(花王、人工知能学会の元会長)が、アカデミアと産業界のそれぞれの立場から、取り組み状況・注目動向や今後の展望を紹介します。最後にパネル討論を通して、今後の方向性や課題について議論します。連続セミナー2025では、AI分野のさまざまな話題を取り上げていく予定ですが、そのイントロダクションとして、やや広い観点からAI分野の動向を概観します。
※本セミナーは、配布資料とアーカイブ配信をご提供いたします。
-
[9:00-9:05]オープニング
福島 俊一(国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター フェロー)
-
[9:05-10:05]Session1「AI研究開発の動向俯瞰」

AI分野の研究開発動向を大きく3つの潮流として捉えて概観します。第1の潮流は「AI基本原理の発展」、現状の基盤モデル・生成AIの課題やさらなる高性能化への取り組みです。第2の潮流は「AIリスクへの対処」、生成AIの悪用問題も含め、深刻化するAIリスクに対する取り組みです。第3の潮流は「AI×○○」、AIが様々な分野に活用され、社会・産業・科学等のプロセスが変革されつつありますが、これをどのように進めていくかについての取り組みです。AIはもはや単なる道具にとどまらないものになっており、人とAIが共生・協働する社会をどう描くかを考えていくことが必要になってきました。このような3つの潮流の観点から、技術課題、注目事例、政策動向等にも触れながら、状況・方向性の把握・整理を試みます。
福島 俊一(国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター フェロー)
【略歴】1982年東京大学理学部物理学科卒業、NEC入社。以来、中央研究所にて自然言語処理・情報検索等の研究開発・事業化に従事。1992年情報処理学会論文賞、1997年情報処理学会坂井記念特別賞、2003年オーム技術賞等を受賞。2011~2013年東京大学大学院情報理工学研究科客員教授。2016年から科学技術振興機構研究開発戦略センターフェロー、人工知能分野を中心に研究開発動向の俯瞰的調査・戦略提言を担当。工学博士、情報処理学会フェロー。 -
[10:05-10:15]休憩
-
[10:15-10:35]Session2「アカデミアから見たAI研究開発の状況と展望」
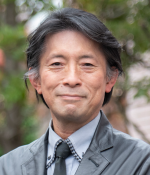
すでに注目は生成AIからAIエージェントに移りつつあり,この流れはおよそ70年間の道具としてのAI研究開発から自律性を持つAIへの研究開発という,人類が生み出したこれまでのテクノロジーと一線を画す大きな進化が始まったと言える.高い自律性と汎用性を持つAIの実現に向けての諸課題を整理するとともに,そのチャレンジにおける日本の立ち位置について考察する.ChatGPT級のLLMを実現させた米国ビックテックや,勢い凄まじい中国でのヒューマノイド型ロボット研究開発と同規模での取り組みが不可能であろう日本として,どのような戦略をとるべきなのか? 一方,どのレベルまでの高い自律性をAIに持たせるのか,そして,そのようなAIが社会に浸透できるのかについては,日本と欧米での態度に大きな差異がある中において,日本型の人とAIが共生する社会が世界を牽引していく可能性についても考察したい.
栗原 聡(慶應義塾大学 理工学部 管理工学科 教授)
【略歴】慶應義塾大学理工学部 教授.人工知能学会 会長.慶應義塾大学共生知能創発社会研究センター センター長。慶應義塾大学大学院理工学研究科修了。博士(工学)。NTT基礎研究所、大阪大学、電気通信大学を経て、2018年より現職。科学技術振興機構(JST)さきがけ「社会変革基盤」領域統括。オムロンサイニックエックス社外取締役、総務省・情報通信法学研究会構成員など。マルチエージェント、複雑ネットワーク科学、計算社会科学などの研究に従事。著書『AIにはできないー人工知能研究者が正しく伝える限界と可能性』(角川新書)、『AI兵器と未来社会キラーロボットの正体』(朝日新書)、編集『人工知能学事典』(共立出版、2017)など多数。 -
[10:35-10:55]Session3「産業界から見たAI利活用の状況と展望」

生成AI技術は、テキストや画像など、日々の業務で取り扱う多様なデータに対して、汎用的かつ高度な処理を可能にするものであり、企業活動における広範な業務の自動化・自律化をもたらす、これまでにない可能性を秘めている。多くの企業でAIチャットボットなどの導入が進み、AIエージェント活用に向けた取り組みも本格化しつつある。一方で、導入はしたものの期待した成果が得られず、大きな業務変革に結び付かないといった課題も顕在化している。さらに、各国・地域で活用と規制に関するルール整備が進み、グローバルに事業を展開する企業にとっては、技術動向や規制環境を継続的に把握する重要性が高まっている。本講演では、産業界の視点から、生成AI技術に寄せられる期待と現状の取り組み、そして今後の展望について議論する。
浦本 直彦(花王株式会社 デジタル戦略部門データインテリジェンスセンター 執行役員)
【略歴】日本IBM入社後、東京基礎研究所で自然言語処理、データ統合、Web技術などの研究開発に従事。2017年、三菱ケミカルホールディングス入社、2020年より執行役員CDOとしてDX推進をリード。2023年4月、花王入社、2025年1月より、執行役員 デジタル戦略部門 データインテリジェンスセンター長としてAI技術を活用したデータの高度利活用を推進。2018年-20年、人工知能学会会長。情報処理学会フェロー。 -
[10:55-11:05]休憩
-
[11:05-11:45]パネル討論
福島 俊一(国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター フェロー) -
栗原 聡(慶應義塾大学理工学部管理工学科 教授)
-
浦本 直彦(花王株式会社 デジタル戦略部門データインテリジェンスセンター 執行役員)
-
[11:45-11:50]クロージング
福島 俊一(国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター フェロー)