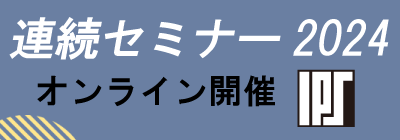連続セミナー2024「人とAIが共生する社会に向けた情報技術」
第11回【12月6日(金)14:20-17:05】
都市はWell-beingと持続可能性の両立を追い求める
スーパーシティやデジタル田園都市構想に代表されるように都市が抱える様々な問題をデジタル技術によって解決を図る取組が国内外で進められている。都市の中に張り巡らされたセンサ網からデータを取得・分析し、都市サービスをカスタマイズすることの本質的な挑戦は「人間中心」と「持続可能性」の追及にある。本セミナーでは、都市のデジタル化におけるグローバルトレンド、Well-being/持続可能性の取り組みについて紹介する。
※本セミナーは、配布資料とアーカイブ配信をご提供いたします。
-
[14:20-14:30]オープニング
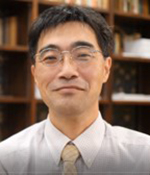 鍛 忠司(株式会社 日立製作所 研究開発グループ サービスシステムイノベーションセンタ 主管研究長)
鍛 忠司(株式会社 日立製作所 研究開発グループ サービスシステムイノベーションセンタ 主管研究長)
【略歴】1996年日立製作所入社.以来,企業情報システム,公的認証基盤,分散システム,産業制御システム,などに向けたサイバーセキュリティの研究開発および国際標準化に従事.現在,サイバーセキュリティに加え,デジタルトラスト,スマートシティなどの研究開発を担う.2020年より現職.情報処理学会,IEEE CS会員.博士(情報科学). -
[14:30-15:10] Session1「Well-Beingとサステイナビリティから見たスマートシティの動向」

G20グローバルスマートシティアライアンスは、都市のデジタル化と持続可能な発展を推進するために2019年に設立されました。このアライアンスは、世界経済フォーラムが事務局を務め、地方自治体、企業、研究機関、市民社会など多様なステークホルダーを結集し、スマートシティ技術の責任ある利用を促進するためのガイドラインとしてモデルポリシーを策定しています。
モデルポリシーで扱うトピックは、プライバシー、セキュリティ、オープンデータ等のデータガバナンスに加え、近年、サステイナビリティに関するモデルポリシーを始めとして、スマートシティに関する新たな課題に対応するための枠組みを提供しています。
本講演では、G20グローバルスマートシティアライアンスを、都市のデジタル化におけるグローバルトレンドも含めつつ紹介した上で、Center For Urban Transformation の取組も紹介します。前田 恵美(世界経済フォーラム Center For Urban Transformation G20グローバル・スマート・シティーズ・アライアンス(CUT)地域統括)
【略歴】東京大学法学部卒。一橋法科大学院修了。都内法律事務所勤務後、消費者庁消費者制度課個人情報保護推進室にて個人情報保護法改正作業に従事。内閣府IT総合戦略室参事官補佐兼任。米系IT企業の公共政策部にて、プライバシー、セキュリティ、オンラインセーフティ等、IT政策の議論に関わる。2024年より世界経済フォーラム日本オフィス。Center For Urban Transformation に所属し、G20グローバルスマートシティアライアンスに加えて、センターの他の取組み、イベント等に関わる。 -
[15:10-15:20]休憩
-
[15:20-16:00] Session2 「スマートシティサービスインフラはどうあるべきか?」

スマートシティやスマートコミュニティなど、ICTを活用した高機能・高効率インフラが導入された地域では、新たなサービス提供や問題解決への取り組みが進められており、その核心は、分野を超えた情報流通にあります。情報流通により、センシング・アナライズ・サービス・アクションのサイクルを回し、地域の発展を促しますが、一方で個人情報の取り扱いや法令順守といった課題も存在します。同様に、大規模言語モデルを利用したサービスは有望ですが、大量の情報を必要とし、その利用や権利に関する議論も活発化しています。情報をどのように管理し、サービスとして具体化するのか、そのためのインフラはどのように構築すべきか、この問いに技術的観点で回答する必要があります。本講演では、米国Global City Team ChallengeやIEEE P1451.1.6、IEEE P2992のチェアとしての経験、さらにIEEE 2413-2019で採用されたスマートシティサービスの提供を念頭に置いた、その一解答としての情報インフラについて、基本技術群およびソフトウェア・ハードウェアコデザインの観点から概説します。
西 宏章(学校法人 慶應義塾 慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科 教授)
【略歴】慶應義塾大学において博士課程を修了後、技術研究組合新情報処理開発機構、株式会社日立製作所中央研究所での研究活動を経て、2014年より慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科教授。
スマートグリッドやスマートコミュニティ、新世代インターネットアーキテクチャに関する研究を進めており、技術標準化活動としてIEEE P21451-1-6WGチェア、IEEE P2992 WGチェアなどを務め、構築技術の標準化を推進している。 また、美園タウンマネジメント代表理事、おもてなしICT協議会理事長、エッジプラットフォームコンソーシアム理事、Urban Technology AllianceにおけるDirectorなど関連団体の委員を兼任しており、技術の社会実装も進めている。 -
[16:00-16:10]休憩
-
[16:10-16:50]Session3 「人に共感するスマートシティ実現に向けて」

従来のスマートシティは、技術を通じて人々から共感を得ることを重視してきましたが、今後は都市自らが人々に共感し、成長することが求められます。市民が共創のパートナーとして積極的に参加するリビングラボや、市民のウェルビーイングを定量的に計測する都市評価指標は、都市の共感力を育む重要な取り組みと言えます。本講演では、日立東大ラボでの実践事例を中心に、スマートシティにおけるリビングラボの実装手法や都市評価指標を活用したウェルビーイングの捉え方について考えます。講演を通して、技術と共感が融合した都市プランニング/マネジメントのあり方を探ります。
笹尾 知世(麗澤大学 工学部工学科情報システム工学専攻 准教授)
【略歴】2011年首都大学東京卒業。2013年東京大学大学院修士、2016年博士課程修了。博士(環境学)。2015年より日本学術振興会特別研究員(DC2・PD)として参加型センシングによる住民参加型住環境デザインを研究。2017年徳島大学助教、2020年より東京大学特任助教を経て、2024年から麗澤大学准教授。日立東大ラボにてスマートシティにおける市民参画や都市評価の研究に従事し、2023年に「Society 5.0のアーキテクチャ」を共著。専門は都市デザイン、住民参加、アーバンコンピューティング。 -
[16:50-17:05]クロージング
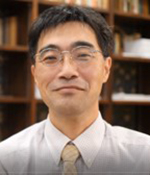 鍛 忠司(株式会社 日立製作所 研究開発グループ サービスシステムイノベーションセンタ 主管研究長)
鍛 忠司(株式会社 日立製作所 研究開発グループ サービスシステムイノベーションセンタ 主管研究長)