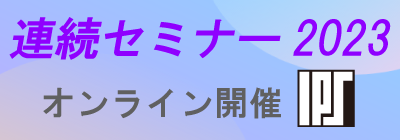連続セミナー2023「人とAIが共生する社会に向けた情報技術」
第9回【11月6日(月) 13:00~16:00】
Software EngineerのためのGreen Software入門
「Green Software Foundation」に焦点を当てたこのイベントでは、ソフトウェアのサステナビリティについて深く学びます。データセンターやエネルギーについての議論が多い中、私たちが重視するのはコンピュータを制御するソフトウェアの最適化です。このグローバルコミュニティはソフトウェアの持続可能な開発に力を注ぎ、その重要性を世界に広めています。この機会に、サステナビリティの観点からソフトウェア開発をどのように改革できるかを学び、グリーンソフトウェアの未来を一緒に創造しましょう。
-
[13:00 - 13:05]オープニング
 畠山 大有(日本マイクロソフト株式会社 カスタマーサクセス事業本部 シニアクラウドソリューションアーキテクト)
畠山 大有(日本マイクロソフト株式会社 カスタマーサクセス事業本部 シニアクラウドソリューションアーキテクト)
【略歴】独立系ISVでのソフトウェア設計・開発エンジニアを経て2002年よりMicrosoft勤務。MSNでのデータセンター運用エンジニアを経て、プリセールス、マーケティングでも一貫してエンジニアリングの世界に身を置く。現在は顧客プロジェクトにてMVP開発とそのOutputで活動中 -
[13:05 - 13:50]Session1 「Energy Productivity x00% for carbon neutral with {Smart} Public Core Internet」

デジタル田園都市国家構想は、デジタル技術を用いた社会インフラの根本的な進化を ネットワークコンピューティングインフラを用いて実現するもので、AS IS システムでのエネルギー効率の向上と TO BEシステムでのエネルギー効率の向上を By IT と Of IT の両方で実現させなければならない。 ハードウェアの進化は当然のことながら、ソフトウェアの進化も同時に実現させなければ、人類が必要とする電力エネルギーを地球が提供できないことになってしまうであろう。NTTが先導するIOWN構想は、コンピューティングのハードウェアを電子から光子に進化させる取り組みである。また、同じハードウェアでも、どう利用するか、すなわち ソフトウェアの出来栄え次第で、莫大なエネルギー効率の差が発生することは明白なことではあるが、ハードウェアのムーアの法則に乗っ取った進化によって、重要視されないようになってきていた。ChatGPTに代表される人工知能システムは、莫大な電力量を消費する。我々は、ハードとソフトの両面で、電力エネルギーの浪費にならないように、Energy Productivityの向上を実現しなければならない。
江崎 浩(東京大学 大学院 情報理工学系研究科 教授)
【略歴】1987年 九州大学 工学部電子工学科 修士課程 了。同年4月 (株)東芝 入社。1990年より2年間 米国ニュージャージ州 ベルコア社、1994年より2年間 米国ニューヨーク市 コロンビア大学 CTRにて客員研究員。 1998年10月より東京大学 大型計算機センター助教授、2001年4月より東京大学 情報理工学系研究科 助教授。2005年4月より現職(東京大学 情報理工学系研究科 教授)、WIDEプロジェクト代表。 MPLS-JAPAN代表、IPv6普及・高度化推進協議会専務理事、JPNIC理事長、日本データセンター協会 理事/運営委員会委員長。工学博士(東京大学)。 -
[13:50-14:00]休憩
-
[14:00 - 14:35]Session2「Green Software Foundation にみるソフトウェアのグリーン化に関する動向」

ChatGPTに代表されるようなAIの広がりや、工場をはじめとしてIoTの導入が進む中で、ITによる電力消費が近い将来に急激に増えていくと言われており、これが世界的な温室効果ガスの排出量の増加につながる可能性があります。そのような中、ソフトウェアの観点からITのグリーン化への貢献を考えるGreen Software Foundationが2021に発足し、40を超える会社・組織が参画し、参加人数は1,000人を超え、活動の幅がますます広がっています。本セッションではGreen Software Foundationの活動概況をお伝えし、グローバルにおけるソフトウェアのグリーン化の動向についてお伝えします。
下垣 徹(株式会社NTTデータグループ コーポレート統括本部 サステナビリティ経営推進部 グリーンイノベーション推進室 室長)
【略歴】NTTデータに入社後、技術部隊としてビッグデータ基盤を中心としたオープンソースソフトウェアの技術開発を行い、様々なお客様への導入支援、講演や執筆等のプロモーション活動を実施。新卒採用及び経験者採用の責任者、先進技術部門の責任者等を経て、現職に至る。現在はNTTデータにおける環境部門の責任者として、自社の脱炭素化及び国内外のグリーンビジネス展開を推進。 -
[14:35-14:45]休憩
-
[14:45 - 15:15]Session3「ソフトウェア観点でのグリーン化とその評価方法」

サステナビリティをITの文脈で考えるとき、その実現手段や評価手法はハードウェアや設備面で対処を行うものが大半です。しかし、ソフトウェア面は考慮しなくてもよいのでしょうか。ドライバーの運転技術が自動車の燃費を左右するように、ソフトウェアの挙動がハードウェアの消費エネルギーを左右することはないのでしょうか。
ソフトウェアの面からITシステムのグリーン化を考える非営利団体「Green Software Foundation(GSF)」が2021年に設立され、持続可能性がソフトウェア開発の重要な評価項目になることを目指して産学協同でグローバルな取り組みが始まっています。ツールのような手段だけではなく、教育コンテンツやISO採択を目指す評価基準など様々な成果物が公開され始めています。それらを活用しながらグローバル基準のサステナブルなソフトウェア開発をはじめる「きっかけ」をご紹介します。末永 恭正( 株式会社NTTデータ 技術開発本部 IOWN推進室 テクニカルリード)
【略歴】2006年にNTTコムウェアへ入社しOSS導入支援に従事。オープンソースの Java 実装であるOpenJDK の Reviewer など、Java を中心とした OSS やコミュニティで活動中。 2019年よりNTTデータでJava技術支援に従事するが、2021年からはグリーンソフトウェア 関連の研究開発・コミュニティ活動にも従事。 -
[15:15-15:25]休憩
-
[15:25 - 15:55]パネルディスカッション「Green Software が実社会・実ビジネスにもたらすものとは? また、そこに至るまでの課題と解決策は何か?」
-
[15:55 - 16:00]クロージング
 畠山 大有(日本マイクロソフト株式会社 カスタマーサクセス事業本部 シニアクラウドソリューションアーキテクト)
畠山 大有(日本マイクロソフト株式会社 カスタマーサクセス事業本部 シニアクラウドソリューションアーキテクト)