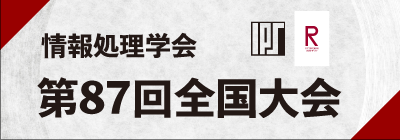インダストリアルセッション
●開催日時:3月13日(木) 12:40-14:30
●開催会場:第4イベント会場(立命館大学 大阪いばらきキャンパス AC330)
ゴールドスポンサーの各社様とインダストリアルセッションとして申し込まれた各社様における技術開発の取組や製品について紹介をします。
プログラム
12:40-12:45 オープニング
12:45-13:00 アイ・システム株式会社
13:00-13:05 休憩
13:05-13:20 日本アイ・ビー・エム株式会社
13:20-13:25 休憩
13:25-13:40 ソフトバンク株式会社
13:40-13:45 休憩
13:45-14:00 株式会社 ARISE analytics
14:00-14:05 休憩
14:05-14:20 TechShare株式会社
14:20-14:25 クロージング
-
アイ・システム株式会社

【講演タイトル】プログラム可視化ツール「i-Tool」のAIを利用した開発
【講演内容】弊社が開発しているプログラムの可視化ツールである「i-Tool」について、近年のプログラミング言語に対応するべく、AIを利用した研究内容をご紹介いたします。玉川 俊幸(アイ・システム株式会社 通信プロダクトソリューション事業部)
【略歴】2023年にアイ・システム株式会社に入社。通信・プロダクトソリューション事業部にて行政システムやサプライチェーン管理システムの開発および改修を担当。各プロジェクトと並行して、生成AIを活用したシステムの開発・研究を社内で推進/発信。 -
日本アイ・ビー・エム株式会社

【講演タイトル】迫りくる耐量子暗号時代~Quantum Safe(耐量子安全性)の必要性~
【講演内容】近年、量子コンピューターの技術開発が急速に進み実用化が議論されつつあります。一方で、量子コンピューターの普及は、これまで解読できなかった暗号化された重要データを手に入れることを可能にするブレークスルーとなりうるため、量子時代にはサイバー攻撃による被害がこれまで以上に深刻かつ重大になることは必至です。
2024年8月13日、米国商務省の国立標準技術研究所(NIST)は3つの耐量子計算機暗号標準(Post-Quantum Cryptography Standards)を発表しました。これは、今後量子コンピューターがより一般に使われるものになり、現在のデジタル社会における信用基盤となっている公開鍵暗号がその信頼を失うときが現実のものとして近づいてきていることを示しています。量子時代にも安全なシステムのために耐量子暗号対応を検討する時期がすでに来ています。耐量子対策とはなにか、技術的な課題や検討項目についてご紹介します。佐藤 史子(日本アイ・ビー・エム株式会社 東京基礎研究所)
【略歴】東京工業大学大学院理工学研究科基礎物理学専攻を修了後、日本アイ・ビー・エム株式会社に入社。以来、東京基礎研究所にてソフトウェア、クラウド、セキュリティ等の研究に従事。東京工業大学大学院情報理工学研究科計算工学専攻にて博士号取得。最近では、アプリケーション・モダナイゼーションでのAI活用やプラットフォームのセキュリティの研究リーダーを務める。博士(工学)。 -
ソフトバンク株式会社

【講演タイトル】主要国際学会からみるAIの最新動向とソフトバンクのAI開発への取り組みのご紹介
【講演内容】本講演では、主要な国際学会に参加した経験を基に最新のAI動向をご紹介します。特に、生成AI(Generative AI)、大規模言語モデル(LLM)、およびマルチモーダルモデルの最新技術やそれらがもたらす社会への影響に焦点を当ててご説明します。
また、ソフトバンクがどのように先進的なAI技術を取り入れ、プロダクト開発を実施しているかを具体例を交えてご紹介し、さらに、AI開発を支援するための各種サービスについてもご案内します。荒 哉太(ソフトバンク株式会社 IT統括 AI戦略室 R&D推進室)
【略歴】2019年ソフトバンク株式会社入社。OCR(光学文字認識)の開発を担当した後、コンピュータビジョンを中心としたAIの研究開発業務に従事。現在はマネージャーとしてAIに関する様々な技術の研究開発を推進。 -
株式会社 ARISE analytics

【講演タイトル】カスタマーサポート領域における生成AI活用事例のご紹介
【講演内容】ARISE analyticsでは、KDDIが推進する新たな顧客体験(CX)の創造を実現するため、データ分析やAI技術を活用した支援を行っています。今回、KDDIカスタマーサポート領域における業務変革支援の一つとして、チャットボットに生成AIを実装し、オンラインでの完結率を向上させることでお客さまの課題解決までの時間を短縮しました。既存の定型AIでは特定できなかったインテント(お客さまのお問い合わせ意図)を、生成AIを活用することで特定可能とします。本セッションでは、その詳細についてご紹介いたします。田口 尚樹(株式会社 ARISE analytics Personal Growth Division, Support Transformation Unit, CS業務革新 Team)
【略歴】2022年よりKDDIのカスタマーサービス領域にてコールセンターにおける顧客インテント分析高度化やチャットボットへの生成AI実装支援に従事。 -
TechShare株式会社

【講演タイトル】深層強化学習・模倣学習によるヒューマノイドロボット開発のイノベーション
【講演内容】昨今、テスラ—社のヒューマノイドをはじめ、ヒューマノイドロボットを工場など労働力として社会実装を目指す動きが急加速している。このトレンドの作り出している根幹は、深層強化学習と模倣学習によるロボット開発手法のイノベーションである。本セッションでは、Unitree社の最新ヒューマノイドロボットや最新の5指ハンドを搭載した双腕ロボットアーム(人体の上半身を模擬したロボット)などを実例として、実機デモと最新ロボット開発のトレンドの概説を通して、近未来のヒューマノイドロボット開発の概要を紹介する。重光 貴明(TechShare株式会社 代表取締役)
【略歴】1995年サイバネットシステム入社。MATLAB/Simulinkの国内販売事業を担当。営業部長、マーケティング部長、事業部長などを歴任し、2006年取締役に就任。2009年MathWorks社に入社。Industry Marketing部門のSenior Mangerとして日本の産業別販売戦略を統括。2012年TechShare株式会社を創業し、代表取締役に就任。現在に至る。