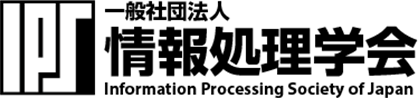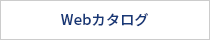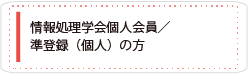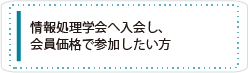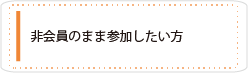****************************************************************
情報処理学会
「第 82 回バイオ情報学(SIGBIO)研究会」
「第 153 回数理モデル化と問題解決(MPS)研究会」
合同研究会
電子情報通信学会
「ニューロコンピューティング(NC)研究会」
「情報論的学習理論と機械学習(IBISML)研究会」
との連催
講演募集 および 連動論文投稿のご案内
****************************************************************
日時:2025年 6 月 21 日(土) ~ 23 日(月)
会場:琉球大学 文系講義棟室
開催形態:現地開催のみ
※感染症に関する状況等により現地開催が不可能になった場合には、
Zoomのみによる完全オンラインに変更となる可能性もあります。
発表申込締切: 2025年 5月 6日(火) (厳守: 締切延長はありません)
予稿集原稿締切:2025年 5月 20日(火) (厳守: 締切延長はありません)
※ 連動論文に投稿の場合は,研究会予稿集用原稿と論文誌用原稿の両者をご提出いただく
必要があります.それぞれ,投稿先と締切日が異なりますので十分ご注意ください.
** TOM連動論文投稿締切日:2025年05月17日(土)17:00 **
** 研究会予稿集原稿提出締切日:2025年05月20日(火)23:59 **
** TBIO連動論文投稿締切日:2025年05月24日(土)17:00 **
詳細は下記をご覧ください.
発表申込方法: 以下のURLの「発表申込」メニューよりお申込ください.
SIGBIO研究会はこちらからお申込ください.
MPS研究会はこちらからお申込ください.
※ 申込先研究会によってセッションが異なりますのでご注意ください。
なお,「研究会への連絡事項」欄には
(1) 発表タイプ
- SIGBIO研究会からお申込みの方は下記のB1-B4より選択ください。
[B1] ロングトーク(予稿6ページ[推奨],発表20分,質疑応答5分)
[B2] ロングトーク(予稿6ページ[推奨],発表20分,質疑応答5分)及びTBIOへ投稿
(※ TBIO投稿申し込みフォームも併せてご記入ください.)
[B3] ショートトーク(予稿2ページ[推奨],発表10分,質疑応答5分)
[B4] ディスカッショントラック(予稿は表題・著者・概要のみ記載,発表10分,質疑応答5分.あらゆる賞の選考対象外となります.)
- MPS研究会からお申込みの方は下記のM1-M3より選択ください。
[M1] ショートトーク(予稿2ページ[推奨],発表10分,質疑応答5分)
[M2] ロングトーク(予稿6ページ[推奨],発表20分,質疑応答5分)
[M3] ロングトーク(予稿6ページ[推奨],発表20分,質疑応答5分)及びTOMへ投稿
(※ TOM投稿申し込みフォームも併せてご記入ください)
(2) 発表者の身分,研究会登録の有無について(該当するものを選択)
1. 社会人,SIGBIO登録会員
2. 社会人,SIGBIO非登録会員
3. 学生,SIGBIO登録会員
4. 学生,この発表申し込み後にSIGBIO会員登録予定
5. 学生,SIGBIO登録予定なし(SIGBIO学生奨励賞の対象外となります)
6. 学生,MPS登録会員
7. 学生,この発表申し込み後にMPS会員登録予定
8. 学生,MPS登録予定なし
をご記入下さい.
注1)ショートトーク (予稿 2 ページ以内、発表 10 分、質疑応答 5 分) も受け付けます。
アイデア段階の研究発表など積極的にお申し込み下さい。
注2)バイオ情報学研究会では,研究会と連動してトランザクション TBIO への
投稿を受け付けます.連動投稿では通常のTBIO同様,英語の原稿のみを受け付け,
採否の判定を研究会の開催日にお伝えを致します.
TBIO への投稿原稿の〆切は 2025年 5月 24日(土) 17:00 (厳守) です!
TBIO へ投稿する場合は,講演はロングトークのみとなります.
詳細は,下記-----以下をご覧ください.
注3)MPS 研究会では,研究会と連動してトランザクション TOM への投稿を受け付けています.
TOM への投稿原稿の〆切は 2025年 5月 17日(土) 17:00 (厳守)です!
TOMへ投稿する場合は,講演はロングトークのみとなります.
注4)上記開催期間中に参加できない日がある場合は,
発表申し込み時に「研究会への連絡事項」欄に参加可能日を記載してください.
プログラムを公開した後の発表時間変更のお申し出は,ご期待に添えない場合があります.
----------------------------------------------------------------------
なお,SIGBIO研究会およびMPS研究会登録は情報処理学会のホームページより行うことができます.
また,情報処理学会会員でなくとも準登録会員として登録することができます.
また,「バイオ情報学論文誌」(TBIO)でも,研究会登録会員を著者に含む優秀論文に対し,
「SIGBIO論文賞」を授与しておりますので,奮って研究会登録をお願いいたします.
ご発表申込後,別途後日に情報処理学会より執筆要領,提出締切などのお知らせが届きます.
詳細は執筆要領をご確認ください.
※ 原稿作成についてはこちら
----------------------------------------------------------------------
発表申し込み時に,「研究会への連絡事項」の欄で,
「[B2] ロングトーク(予稿6ページ[推奨],発表20分,質疑応答5分)及びTBIOへ投稿」
を選択される皆様へ(TBIOは英文論文誌です)
●「TBIO投稿申し込みフォーム」の内容を記載して下さい.
記載がない場合は,TBIOへ投稿しないものと判断されてしまいますのでご注意下さい.
をご覧ください.
●TBIOへの投稿原稿は,以下の「TBIOの原稿の投稿方法」に従って投稿して下さい.
★TBIO の論文原稿と予稿集の原稿の2つの原稿の提出が必要です!
★予稿の提出が締切に遅れた場合は発表も投稿もキャンセルとなります!
★論文誌原稿の提出が締切に遅れた場合は研究会と非連動の扱いとなり,
判定を研究会でお伝えすることは保証できません!
●TBIOの原稿の投稿方法
2025年 5月 24日(土) 17:00 までにPDFのページ数無制限の投稿論文を
To: tbio-editors[AT]googlegroups.com ※[AT]は@になおしてください。
Cc: 担当編集委員に電子メールで送信してください.
なお,原稿提出までに担当編集委員から連絡がない場合は,
担当編集委員にCcする必要はありません.
----------------------------------------------------------------------
第 82 回SIGBIO研究会およびTBIO連動投稿に関するお問合せは
吉本 潤一郎(藤田医科大学)
E-mail: junichiro.yoshimoto[AT]fujita-hu.ac.jp
※[AT]を@に直してください.
までお願いいたします.
----------------------------------------------------------------------
発表申し込み時に,「研究会への連絡事項」の欄で,
「[M3]ロングトーク(予稿6ページ[推奨],発表 20 分,質疑応答 5 分)及び TOMへ投稿」
を選択される皆様へ
発表申し込み時に「研究会への連絡事項」の欄に、以下の
● TOM 投稿申し込みフォーム
の内容を記載して下さい。記載がない場合は、TOM へ投稿しないものと判断されますので、ご注意下さい。
また、TOM への投稿原稿は、以下の
● TOM の原稿の投稿方法
に従って投稿して下さい。
★ TOM の論文原稿と予稿集原稿の 2 つの原稿の提出が必要です!
★ 予稿の提出が締切に遅れた場合、発表と投稿の両方がキャンセルとなります!
★ 論文誌原稿の提出が締切に遅れた場合、研究会と非連動の扱いとなり、判定を研究会でお伝えすることは保証できません!
TOM へ投稿する場合、発表はロングトーク (予稿 6 ページ (推奨)、発表 20分、質疑応答 5 分) のみとなります。
● TOM 投稿申込みフォーム: 次の事項を全て含めて作成して下さい。
+ キーワード (直接関係するもの 3 個以内と間接的に関係するもの 5 個以内)
+ 論文中で参照する予定の参考文献 (新規性や有効性に直接関係するもの 3件以内と間接的に関係するもの数件)
+ 論文の内容に関して、以下の中から当てはまるもの (複数でも可) を選び、それぞれの説明を 300 文字程度の日本語もしくは 100 語程度の英語で行なう。(日本語 300 文字/英語 100 語を越えても可)
- 1.『新しい数理モデルの提案』の場合:
どのような新規性を提案するか説明する。
- 2.『既存数理モデルの改良』の場合:
改良点にどのような新規性があるかを説明する。
- 3.『特定の応用分野に限定した新しい数理モデルの提案』の場合:
提案するモデルが当該応用分野に対して有効である根拠と特定の応用分野に限定する理由を説明する。
- 4.『既存数理モデルの新しい応用分野への適用』の場合:
既存モデルが当該応用分野に対し有効である根拠とこれまでになぜモデルの適用がなされていなかったかの説明をする。
- 5.『既存数理モデルの概知応用分野に対するより効果的な適用』の場合:
提案手法の既存手法に対する有効性を説明する。
- 6.『その他の本論文誌対象分野』の場合:
投稿予定の論文の概要とそれがなぜ上記 1 から 5 に該当しないか、新規性もしくは有効性をどのように主張するかを説明する。
(この説明文は適切な査読者選定のために必須のものです。新規性/有効性に関する説明を簡潔明瞭に記述して下さい。なお、上記 6 項目は本論文誌の採録基準でもあります。)
+ 似た内容あるいはタイトルで、当学会あるいは他学会に論文投稿がある場合は、既発表内容と本投稿内容の差異を 300 文字程度の日本語もしくは 100 語程度の英語で簡単に記述して下さい。また、既発表論文のコピーを提出して頂ければ、査読者選定に役立ちますので、可能ならば提出をお願い致します。(国際学会や研究会での発表は、学会規定により既発表とはみなされませんが、似たタイトルのものがある場合、査読者の助けとするため、上記に準じて記述/提出して頂いても結構です。)
+ 投稿論文の査読者を推薦できる方 3 名を以下に記載して下さい。ただし、著者と同じ組織に属する人、利害関係のある人は控えて下さい。
氏名・所属・メールアドレス
1.
2.
3.
● TOM の原稿の投稿方法
2025年 5月 17日(土) 17:00 (厳守) の締切までに PDF のページ数無制限の投稿論文を
To: trans-mps-editors (at) ipsj.or.jp
Cc: 担当編集委員
に電子メールで送信して下さい。
担当編集委員から連絡がなく、担当編集委員が不明の場合は、担当編集委員に Cc しなくて構いません。
---------------------------------------------------------
【発表について】
現地開催(琉球大学 文系講義棟室)です.
現地開催の場合,パソコン接続用のプロジェクタを用意しております。
発表用のパソコンは、持ち込みが原則となっています。
以下の URL も参考にして下さい。
・BIO 研究会に関する最新情報は
・MPS 研究会に関する最新情報は
・トランザクション TOM に関する最新情報は
をご覧下さい。
-------------------------------------------------------------
【ペーパレスについて】
研究発表会はペーパレスで行います。
<MPS 研究会にご登録されている方>
研究発表会の【一週間前】に「情報学広場」の電子図書館
当日は資料をプリントアウトしてご持参頂くか、ご自身の PC にダウンロードの上 PC をご持参下さい。
<MPS 研究会にご登録されていない方>
参加申し込み後、自動送信されるメールに以下のような文面でダウンロード方法を記載させていただきます。
--------------
研究報告ダウンロード:
研究報告は 6月**日~6月**日 まで以下よりダウンロードいただけます。
ユーザーID:***** パスワード:*****
研究会登録会員の方は電子図書館(情報学広場)からもダウンロード可能です。
--------------
尚、当研究会にご登録して頂くと、バックナンバーも含めて当研究会の資料を全て「情報学広場」でご購読頂けます。
是非この機会に登録をご検討下さい。
電子図書館「情報学広場」の利用方法につきましては、下記の URL のページをご参照下さい。
○ 研究会登録は、お申し込みと登録費をご入金頂いて正式登録となります。
入金の確認には 1 週間程度お時間を頂きますので、ご了承下さい。
お振込がお済みになりましたら、keiri (at) ipsj.or.jp までご連絡頂き、
BookPark 閲覧希望の旨お伝え下さい。
○ 上記のお手続きがお済みになりましたら、本会電子図書館上のユーザ登録(無料) をして下さい。
*研究会「数理モデル化と問題解決研究会」をチェックして下さい。
*登録まで最大 3 日掛かりますので、ご留意下さい。
##########################################################################
本 CFP に関するご質問は、第 153 回 MPS 研究会担当幹事
吉本 潤一郎(藤田医科大学)
E-mail: junichiro.yoshimoto[AT]fujita-hu.ac.jp
※[AT]を@に直してください.
までお願い致します。
##########################################################################
**********************************************************************
**********************************************************************
本 CFP の以下の説明は、TOM に投稿される方への注意事項です。
**********************************************************************
**********************************************************************
1) 本論文誌に投稿して不採録となった論文を修正して再投稿する場合、論文誌のみの投稿 (注) となります。下記の「TOM 申し込み方法 2」に従ってお申し込み下さい。TOM 原稿の投稿方法は上記 CFP と同じです。この時、判定のタイミングと口頭発表の有無に対して、次の 2 種類の投稿方法があります。
+ 研究会当日に判定/口頭発表ありの場合
申し込み時に、『投稿のタイプ: 論文誌再投稿』、『研究会当日の判定希望: 有』を選択し、前回の論文 ID を記載して下さい。申し込み締切日と TOM 原稿の締切日は、それぞれ、該当研究会の発表申し込み締切日、TOM 原稿の締切日と同一です。ただし、研究会発表用予稿は必要ありません。また、口頭発表は、査読結果によって研究会当日に求められることがありますので、その準備をして研究会に参加して下さい。
(※ただし,オンライン開催の場合は後日メールにて査読結果をご連絡致します)
+ 判定は不定期/口頭発表なしの場合
申し込み時に、『投稿のタイプ: 論文誌再投稿』、『研究会当日の判定希望:無』を選択し、前回の論文 ID を記載して下さい。研究会とは無関係に投稿できます。ただし、研究会と連動した論文誌投稿とは異なり、投稿論文の判定日が決まっていないため、査読期間が長引く可能性があります。口頭発表は必要ありません。
2) 過去に本研究会で研究発表を行なった予稿原稿をもとに論文誌投稿を行なう場合、論文誌のみの投稿 (注) となります。下記の「TOM 申し込み方法2」に従ってお申し込み下さい。TOM 原稿の投稿方法は上記 CFP と同じです。この時、判定のタイミングと口頭発表の有無に対して、次の 2 種類の投稿方法があります。
+ 研究会当日に判定/口頭発表ありの場合
申し込み時に、『投稿のタイプ: 既発表投稿』、『研究会当日の判定希望: 有』を選択し、第何回 MPS 研究会に発表したかを記載して下さい。申し込み締切日とTOM 原稿の締切日は、それぞれ、該当研究会の発表申し込み締切日、TOM原稿の締切日と同一です。ただし、研究会発表用予稿は必要ありません。また、口頭発表は、査読結果によって研究会当日に求められることがありますので、その準備をして研究会に参加して下さい。
+ 判定は不定期/口頭発表なしの場合
申し込み時に、『投稿のタイプ: 既発表投稿』、『研究会当日の判定希望: 無』を選択し、第何回 MPS 研究会に発表したかを記載して下さい。研究会と連動せずに無関係に TOM 原稿を投稿できます。ただし、研究会と連動した論文誌投稿とは異なり、投稿論文の判定日が決まっていないため、査読期間が長引く可能性があります。口頭発表は必要ありません。
3) TOM への原稿投稿後のタイトル・著者変更は担当編集委員にお問い合わせ下さい。原則として認めませんが、担当編集委員の判断により個別対処致します。担当編集委員が分からない場合は編集委員長までお問い合わせ下さい。
(注) 1) および 2) に該当する論文誌投稿の場合、MPS 研究会での正式な講演はありませんし、研究会での予稿原稿も必要ありません。つまり、この場合の論文誌投稿は情報処理学会事務局とは無関係であり、学会誌の会告のページのプログラムも掲載されず、研究会技術研究報告には印刷されないわけです。
『研究会当日に判定/口頭発表あり』の場合、通常の研究会発表と連動した論文誌投稿から、研究会発表部分を削除した形になりますが、投稿論文の締切は通常の研究会発表と連動した論文誌投稿の締切と同じ日になります。また、研究会当日に判定を行なう関係上、正規の研究会講演とは別枠で投稿論文に関する発表を求められる場合がありますので、研究会には参加が必須となります。
『判定は不定期/口頭発表なし』の場合、研究会当日の判定はありませんので、口頭発表は必要ありません。この場合、査読手順は通常の基幹論文誌投稿の場合に準じて行なわれます。このため、判定日を明確にお約束できません。
「TOM 申し込み方法 2」
メールのタイトルを「TOM 論文投稿希望」とし、以下の情報を記載して、
To: trans-mps-editors (at) ipsj.or.jp
にお申し込み下さい。
+ 投稿のタイプ (いずれかを選択して下さい。)
論文誌再投稿 or 既発表投稿
+ 研究会当日の判定希望 (いずれかを選択して下さい。)
有 or 無
+ 過去の発表に関する情報
過去の論文 ID (論文誌再投稿の場合): MPS??-??-?
過去に発表した研究会 (既発表投稿の場合): 第 ?? 回 MPS 研究会
+ タイトル
+ 著者全員の氏名 (論文での掲載順)
+ 講演者氏名 (研究会当日の判定希望有の場合のみ)
+ 講演者所属 (研究会当日の判定希望有の場合のみ)
+ 本発表に関する連絡先 (資料、講演プログラム等の送付先)
氏名:
所属:
住所:
電話番号:
メールアドレス:
+ 75 文字程度の日本語での概要もしくは 30 語程度の英語での概要(研究会のホームぺージ掲載用に、研究会講演のみの場合と同様の長さの概要が必要です。)
+ キーワード (直接関係するもの 3 個以内と間接的に関係するもの 5 個以内)
+ 論文中で参照する予定の参考文献 (新規性や有効性に直接関係するもの 3件以内と間接的に関係するもの数件)
+ 論文の内容に関して、以下の中から当てはまるもの (複数でも可) を選び、それぞれの説明を 300 文字程度の日本語もしくは 100 語程度の英語で行なう。(日本語 300 文字/英語 100 語を越えても可)
- 1.『新しい数理モデルの提案』の場合:
どのような新規性を提案するか説明する。
- 2.『既存数理モデルの改良』の場合:
改良点にどのような新規性があるかを説明する。
- 3.『特定の応用分野に限定した新しい数理モデルの提案』の場合:
提案するモデルが当該応用分野に対して有効である根拠と特定の応用分野に限定する理由を説明する。
- 4.『既存数理モデルの新しい応用分野への適用』の場合:
既存モデルが当該応用分野に対し有効である根拠とこれまでになぜモデルの適用がなされていなかったかの説明をする。
- 5.『既存数理モデルの概知応用分野に対するより効果的な適用』の場合:
提案手法の既存手法に対する有効性を説明する。
- 6.『その他の本論文誌対象分野』の場合:
投稿予定の論文の概要とそれがなぜ上記 1 から 5 に該当しないか、新規性もしくは有効性をどのように主張するかを説明する。
(この説明文は適切な査読者選定のために必須のものです。新規性/有効性に関する説明を簡潔明瞭に記述して下さい。なお、上記 6 項目は本論文誌の採録基準でもあります。)
+ 似た内容あるいはタイトルで、当学会あるいは他学会に論文投稿がある場合は、既発表内容と本投稿内容の差異を 300 文字程度の日本語もしくは 100語程度の英語で簡単に記述して下さい。また、既発表論文のコピーを提出して頂ければ、査読者選定に役立ちますので、可能ならば提出をお願い致します。(国際学会や研究会での発表は、学会規定により既発表とはみなされま
せんが、似たタイトルのものがある場合、査読者の助けとするため、上記に準じて記述/提出して頂いても結構です。)
+ 投稿論文の査読者を推薦できる方 3 名を以下に必ず記載して下さい。ただし、著者と同じ組織に属する人、利害関係のある人は控えて下さい。また、推薦された方が必ずしも査読者になるとは限りません。
氏名・所属・メールアドレス
1.
2.
3.
----------------------------------------------------------------------
【TOM への投稿の形式について】
----------------------------------------------------------------------
『情報処理学会論文誌: 数理モデル化と応用 (TOM)』への投稿は、査読作業に
おける郵送時間の短縮等を目的として、電子メールでの投稿を標準としていま
す。原稿を以下の形式で送付して下さい。
投稿はできるかぎり電子メールにて PDF 形式で送付して下さい。この時、圧
縮ソフト等を利用して、容量を小さくして頂いて構いませんが、特殊なソフト
を利用した場合は、どのような処理をしたのかを担当編集委員に伝えて下さい。
場合によっては別の送付方法を要求されることがあります。
独自ファイル形式のままでの電子的送付は、担当編集委員により再生が不可能
な場合があるので、他のデータ形式で再送をお願いすることがあります。
標準的な PDF 形式で送付できない場合は、担当編集委員が承諾した場合に限
り、救済措置として紙ベースでの原稿を受け付ける場合があります。ただし、
この場合、以下の 2 点が満たされることが必須条件です。
+ 通常の締切日 (PDF 形式で送付する場合) より 7 日前までに担当編集委員
の元に郵送等で到着すること。これに遅れた場合は不採録とします。
+ 論文が採録された際に、カメラレディ形式の原稿を著者が自分で準備できる
こと。本論文誌では写植は行なわず、著者の責任でカメラレディ原稿を準備
して頂きます。カメラレディ原稿を自力で作成できない場合には、本論文誌
では投稿を受付けられません。
----------------------------------------------------------------------
【採録結果の通知】
----------------------------------------------------------------------
研究会と連動して TOM へ論文を投稿する場合には、下記のように判定がなさ
れます。
本論文誌への採録/不採録については、研究会開催日当日に (原則として研究
会終了直後に) 開催される編集委員会の席上において、1 件ずつ協議の上で決
定し、その場で投稿者ご本人にお伝えします。
※ただし,オンライン開催の場合には後日メールにて査読結果をご連絡します.
そのため,オンライン開催の場合には,後述のように会場に残って頂く必要
はありません.
投稿者は研究会終了後、特段の事情がない限り会場に残り、採否結果を直接聞
いて下さい。採否結果が出た論文については 1 件ごとに著者を個別にお呼び
して結果をお伝えします。査読者から指示された採録条件等も、その際にご説
明します。投稿件数が多かった場合など、編集委員会の議事進行の都合によっ
ては、研究会終了後 1-2 時間程度掛かる場合もありますことをご承知おき下
さい。会場に残られない場合には、翌日以降に編集長または担当編集委員から
電子メールで結果をお伝えします。
会場に残って結果を直接聞かれるか否かの選択は投稿者の自由としますが、会
場を離れる場合には必ず編集委員会に断ってからお帰り頂くようにお願い
します。「条件つき採録」の場合などに、著者の意見を確認しないと採否が決
定できない場合がありますので、可能であれば会場に残って当日中に採否結果
を聞いて頂くことを推奨します。
**********************************************************************
情報処理学会論文誌: 数理モデル化と応用のご案内
**********************************************************************
情報処理学会数理モデル化と問題解決研究会では、平成 10 年度より研究会運
営による論文誌を発行しています。この論文誌は、既存の情報処理学会論文誌
の別冊として刊行されます。本論文誌に投稿するには、本研究会にて通常の研
究発表を行う必要があります。研究会論文誌投稿に関する具体的な手順は以下
の通りです。
1) 研究会開催日より 11 週から 12 週間 (各回の CFP をご覧下さい。) 前ま
でに研究会申し込みをすると同時に、本論文誌投稿の意志表明を行なって
下さい。なお、申し込み先は
To: trans-mps-editors (at) ipsj.or.jp
です。
2) 研究会開催日より約 3-4 週間ほど前までに、6 ページ以内の研究会予稿を
情報処理学会事務局の指示に従って提出し、同じく約 5 週間ほど前(詳細
は各回の CFP を御覧下さい。) までにページ数制限なしの論文誌投稿論文
原稿を PDF 形式で
To: trans-mps-editors (at) ipsj.or.jp
Cc: 担当編集委員
宛に電子メールで送って下さい。(担当編集委員が不明の場合は、担当編集
委員への Cc は不要です。)
3) 研究会当日、講演の後、査読者もしくは本論文誌編集委員との詳細な質疑
応答を行なった後、当日のうちに採録/不採録の判定を行います。プレゼン
テーションが非常に悪い場合は判定結果に悪影響を与える場合があります。
4) 採録決定後は、本論文誌編集委員の指定する締切日までに、カメラレディ
原稿を用意して下さい。書式に関しては別途指示を行います。
5) TOM の論文にページ数の制限はありませんが、刷り上がり 1 ページあたり
1万数千円の掲載料をお支払頂きます。掲載料につきましては、以下を参考に
して下さい。
6) 本論文誌は年間 3 回程度発行の予定です。