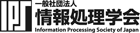- [10:00-10:05]「オープニング」 木村 康則(国立研究開発法人科学技術振興機構)
- [10:05-10:50]「人工知能分野を俯瞰する」 福島 俊一(国立研究開発法人科学技術振興機構)
- [11:00-11:40]「ロボティクス分野を俯瞰する」 茂木 強(国立研究開発法人科学技術振興機構)
- [11:45-12:15]「社会システム科学を俯瞰する」 青木 孝(国立研究開発法人科学技術振興機構)
- [13:15-13:30]「コンピューティングアーキテクチャ分野を俯瞰する」 木村 康則(国立研究開発法人科学技術振興機構)
- [13:30-14:20]「革新的コンピューティングの創生に向けて〜量的変化から質的変化へ〜」 井上 弘士(国立大学法人 九州大学)
- [14:30-14:45]「量子コンピューティング分野を俯瞰する」 嶋田 義皓(国立研究開発法人科学技術振興機構)
- [14:45-15:35]「量子コンピュータと機械学習の基礎と応用」 湊 雄一郎(MDR株式会社)
- [15:45-16:00]「ブロックチェーン分野を俯瞰する」 的場 正憲(慶應義塾大学/国立研究開発法人科学技術振興機構)
- [16:00-16:50]「ブロックチェーン技術のビジネスへのインパクトと今後の課題」 高木 聡一郎(東京大学大学院情報学環)
コーディネータ:木村 康則
国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 上席フェロー
【略歴】1981年東工大院修士了。同年富士通入社。1985年~1988年(財) 新世代コンピュータ技術開発機構出向。1995年スタンフォード大学客員研究員。2002年~2005年東京大学客員教授。2007年富士通次世代テクニカルコンピューティング開発本部長。2011年米国富士通研究所 President&CEO。2014年富士通研究所フェロー。2017年科学技術振興機構(JST) 上席フェロー。2019年富士通退職、引き続きJST勤務。博士(工学)。
人工知能分野を俯瞰する

講師:福島 俊一
国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター フェロー
【略歴】1982年東京大学理学部物理学科卒業,NEC入社。以来,中央研究所にて自然言語処理・サーチエンジン等の研究開発・事業化および人工知能・ビッグデータ研究開発戦略を担当。工学博士。2005~2009年NEC中国研究院副院長。2011~2013年東京大学大学院情報理工学研究科客員教授(兼任)。2016年4月から科学技術振興機構研究開発戦略センターフェロー。2015~2017年人工知能学会理事(人工知能学会第31回全国大会実行委員長)。1992年情報処理学会論文賞,1997年情報処理学会坂井記念特別賞,2003年オーム技術賞等を受賞。
ロボティクス分野を俯瞰する
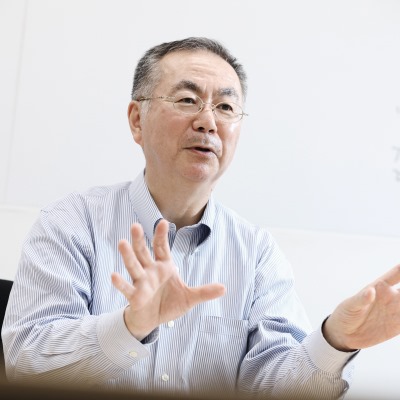
講師:茂木 強
国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター フェロー
【略歴】1980年京都大学理学部卒業。同年4月三菱電機(株)入社。汎用機からミニコンのコンパイラの開発に従事。1991年米国スタンフォード大学留学。以後、情報技術総合研究所にて情報システム技術部門統括を経て、2013年より、国立研究開発法人 科学技術振興機構研究開発戦略センターにて情報科学技術分野に関する研究開発戦略策定に従事。
社会システム科学を俯瞰する
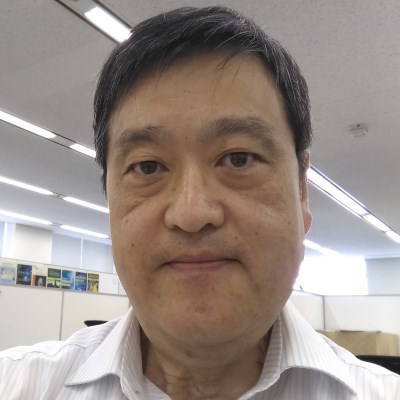
講師:青木 孝
国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター フェロー
【略歴】1985年3月東京大学大学院情報工学専攻修士課程終了。同年富士通入社。以来、富士通研究所にてロボットのソフトウェア/ハードウェアの研究・開発およびJavaチップのシステムソフトウェア開発に従事。その後、スーパーコンピュータ「京」の開発やユビキタスプラットフォーム研究所所長、研究所技術のテクノロジーマーケティングを担当。2018年から科学技術振興機構研究開発戦略センターフェロー。
コンピューティングアーキテクチャ分野を俯瞰する
(1) 布線論理型やニューロモーフィックなどの新しいアーキテクチャのプロセッサ
(2) 計算機科学の観点から、ソフトウェアも含めた量子コンピューター
(3) 大規模なデータセンターを運用し、ビジネスに活用するための技術
(4) 大規模データ処理のための計算処理そのものとデータベースの技術
(5) さまざまなサービスを結びつけ、新たなサービスを創りだし、それらを人々に届けるためのサービスプラットフォーム技術
(6) IoT をどのように設計すべきかというアーキテクチャ技術
(7) 分散システムやP2P ネットワークとしてのブロックチェーン技術
なお、(1)、(2)、(7)に関しては、本講演の後にトピックスを紹介する。
講師:木村 康則
国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 上席フェロー
【略歴】1981年東工大院修士了。同年富士通入社。1985年~1988年(財) 新世代コンピュータ技術開発機構出向。1995年スタンフォード大学客員研究員。2002年~2005年東京大学客員教授。2007年富士通次世代テクニカルコンピューティング開発本部長。2011年米国富士通研究所 President&CEO。2014年富士通研究所フェロー。2017年科学技術振興機構(JST) 上席フェロー。2019年富士通退職、引き続きJST勤務。博士(工学)。
革新的コンピューティングの創生に向けて〜量的変化から質的変化へ〜
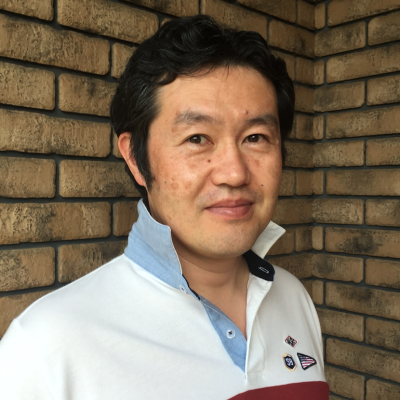
講師:井上 弘士
国立大学法人 九州大学 大学院システム情報科学研究院 情報知能工学部門 教授
【略歴】1996年に九州工業大学大学院情報工学研究科博士課程(前期)、2001年に九州大学大学院システム情報科学研究科情報工学専攻博士課程(後期)をそれぞれ修了。博士(工学)。2001年より福岡大学工学部電子情報工学科助手。2004年より九州大学大学院システム情報科学研究院助教授、2015 年より同大教授、現在に至る。高性能/低消費電力プロセッサ/メモリ・アーキテクチャ、スーパーコンピューティング、超伝導コンピューティング、ナノフォトニック・コンピューティング、量子コンピューティング、などに関する研究に従事。2000年情報処理学会創立40周年記念論文賞、2008年科学技術分野の文部科学大臣表彰若手科学者賞。2018年よりJSTさきがけ「革新的コンピューティング技術の開拓」領域総括。
量子コンピューティング分野を俯瞰する
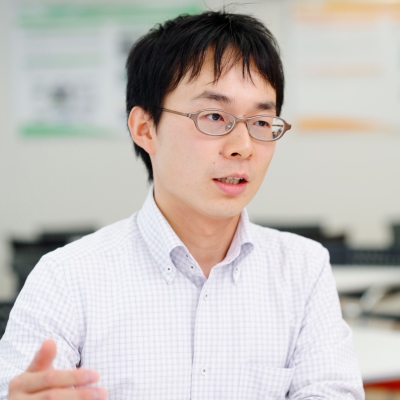
講師:嶋田 義皓
国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター フェロー
【略歴】JST 研究開発戦略センターフェロー。博士(工学、公共政策分析)。2008年東京大学大学院工学系研究科物理工学専攻博士課程修了。2008年日本科学未来館科学コミュニケーター、2012年JST戦略研究推進部主査を経て、2017年4月より現職。2018年に政策研究大学院大学科学技術イノベーション政策プログラム博士課程修了。専門分野は、物性物理、科学コミュニケーション、ICT、科学政策。
量子コンピュータと機械学習の基礎と応用
講師:湊 雄一郎
MDR株式会社 代表取締役
【略歴】1978年東京都世田谷区生まれ。2004年東京大学工学部建築学科卒業(構造計算力学)。2005年株式会社隈研吾建築都市設計事務所勤務。2008年MDR株式会社設立〜現在に至る。
2008年環境省エコジャパンカップ・エコデザイン部門グランプリ。2015年総務省異能vation最終採択。2017年内閣府ImPACT山本プロジェクト、プログラムマネージャー補佐。2019年文科省さきがけ量子情報処理領域アドバイザー。
ブロックチェーン分野を俯瞰する
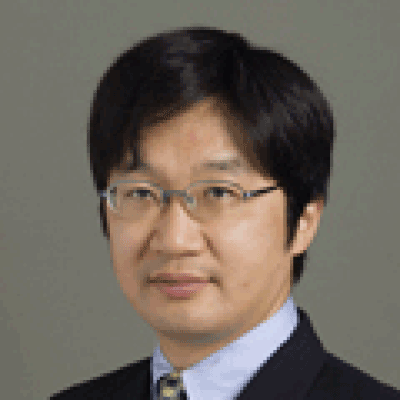
講師:的場 正憲
慶應義塾大学 理工学部物理情報工学科 教授/国立研究開発法人 科学技術振興機構 研究開発戦略センター フェロー
【略歴】慶應義塾大学理工学部物理情報工学科教授(兼)JST-CRDSフェロー、博士(工学)。2011年4月より、JST-CRDSでシステム・情報科学技術を中心とする挑戦的戦略研究領域、特に萌芽的研究領域の調査研究に従事。専門は、強相関電子物理、複雑系の科学、新物質探索・設計、発見科学(そして、Beyond Disciplineの気概と勇気をもって前人未踏の新しい分野に挑戦し、困難や試練に耐えて開拓に当たることができる「自我作古」人材の育成)。
ブロックチェーン技術のビジネスへのインパクトと今後の課題
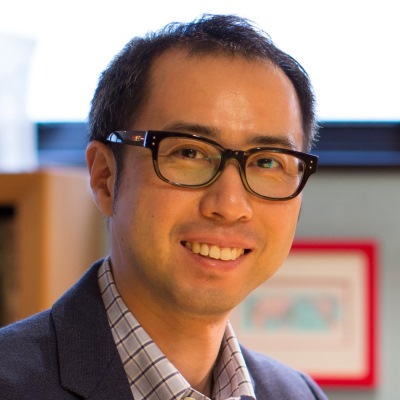
講師:高木 聡一郎
東京大学大学院情報学環 准教授
【略歴】東京大学大学院情報学環准教授。国際大学グローバル・コミュニケーション・センター(GLOCOM)主幹研究員を兼務。株式会社NTTデータ、同社システム科学研究所、国際大学GLOCOM教授/研究部長/主幹研究員等を経て2019年より現職。これまでに、国際大学GLOCOMブロックチェーン経済研究ラボ代表、ハーバード大学ケネディスクール行政大学院アジア・プログラム・フェローなどを歴任。専門分野は情報経済学、デジタル経済論。主な著書に「ブロックチェーン・エコノミクス 分散と自動化による新しい経済のかたち」(翔泳社)など。2019年にKDDI財団よりKDDI Foundation Awardを受賞。東京大学大学院学際情報学府博士課程修了。博士(学際情報学)。