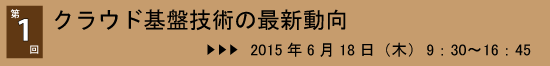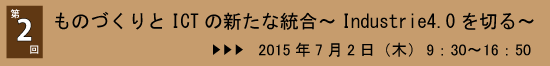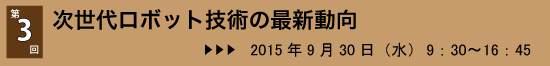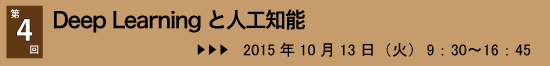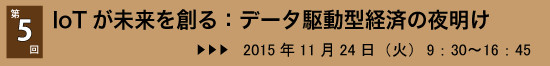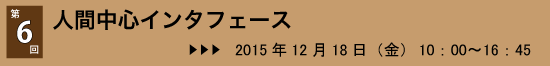プログラム
トータルコーディネータ:浦本直彦(日本アイ・ビー・エム(株) 東京基礎研究所)
|
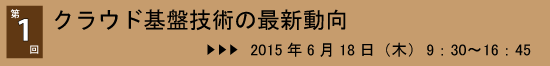
コーディネータ:棟朝 雅晴(北海道大学 情報基盤センター 副センター長・教授)
クラウドコンピューティングを支える基盤技術については、オープンクラウドの流れが定着し、コモディティー化しつつある部分もありますが、一方でコンテナ技術やインタークラウドなど新たな技術も急速に発展しつつあります。本セミナーにおいては、OpenStackなどオープンソースによるクラウド管理ソフトウェアからOpen Compute Projectに代表されるハードウェアのオープン化にわたるオープンクラウドの最新動向について紹介するとともに、SDN(Software Defined Network)やSDDC(Software Defined Data Center)、Dockerなどのコンテナ技術、クラウド間の連携を実現するインタークラウドなど、クラウド基盤を支える最新の技術動向について紹介し、今後に向けた展望を議論します。
|
|
|
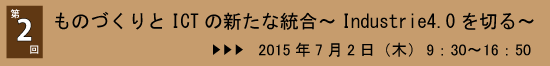
コーディネータ:永野 博(国立研究開発法人 科学技術振興機構 研究開発戦略センター 特任フェロー)
製造業の実力と輸出で世界から一目おかれるドイツが第四次産業革命を政策に掲げた「インダストリー4.0」を打ち出してから早や4年、日本では昨年あたりから経済界のドイツをみる目が変ってきた。産業の現場を舞台としたソフトウェアに自信を持つドイツは、その情報技術と得意の製造技術を結合して、ポストIT時代における産業や社会の在り方を構想し、そのために求められる企業(経営と製造の両面)、産業界、教育、社会の運営システムの革新を目指して、政府、産業界、学界が一体となった取り組みを始めている。本セミナーでは、我が国の専門家とドイツの関連企業より講師を招き、ドイツの「インダストリー4.0」について、その発想、政策立案と産業界の関係、技術面での挑戦と課題、標準化の進展、我が国へのインパクトなどについて、「インダストリー4.0」の持つ歴史的意義について、議論を深めることとしたい。
|
|
|
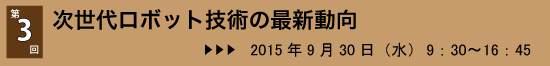
コーディネータ:比留川 博久(国立研究開発法人 産業技術総合研究所 ロボットイノベーション研究センター 研究センター長)
安倍総理によるロボット革命実現会議の開催にも牽引され、ロボット技術による社会革新の実現が政府の成長戦略の重要分野となっている。期待される応用としては、製造業の効率化、物流の効率化、医療福祉を含むサービス業の高品質化、交通システムの省エネルギー化などが挙げられる。本セミナーでは、次世代ロボットの基盤となる最新技術の研究開発動向について、産学官の最前線で活躍されている講師陣をお招きし、紹介していただく。具体的には、人の注視のセンシング、コミュニケーションロボット、ロボットの自律移動技術、産業用ロボットの最新技術、サービスロボット安全規格についてご講演をお願いした。これらのご講演を通じて、次世代ロボット技術全般についての動向の把握が出来るものと期待される。
|
|
|
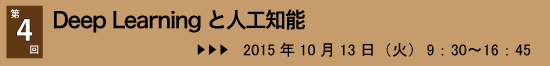
コーディネータ:松原 仁(公立はこだて未来大学 システム情報科学部複雑系知能学科 教授)
近年人工知能が再びブームになっています。技術的には機械学習の手法の一つであるDeep Learningの著しい進歩がブームの基盤になっています。個別の知能ではなく汎用の知能の実現を目指す研究も本格的になってきました。本セミナーでは機械学習によってプロ棋士に勝つまでになったコンピュータ将棋、Deep Learningの基本、そのDeep Learningが人工知能に何をもたらすか、汎用の人工知能を目指す試み、および人工知能実用の代表例としてのWatsonについてその第一人者にわかりやすく話をしていただきます。
|
|
|
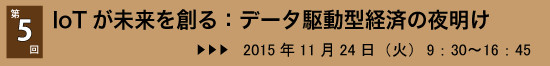
コーディネータ:森川 博之(東京大学 先端科学技術研究センター 教授)
社会を支える基盤として「データ」の価値が認識されつつあります。OECDにおいても、新たな成長の源泉として「データ」の価値が議論されています。インターネットや携帯電話は既に広く普及したものの、社会の変革という視点ではまだまだ初期的な段階にいるにすぎません。都市、交通、農業、医療、介護、バリアフリー、環境、教育、労働などのそれぞれの産業にIoT(Internet of Things)が適用されてこそ、産業構造、経済構造、社会構造の大きな変革につながります。本セミナーでは、データ駆動型経済の実現に向けIoTが果たすべき役割を実例を示しながら明らかにするとともに、IoTプラットフォームからセキュリティまでIoTの飛躍に必要となる事項について議論します。
|
|
|
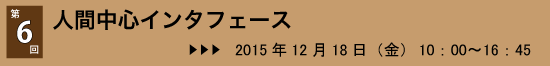
コーディネータ:黒須 正明(放送大学 教養学部情報コース 教授)
ヒューマンインタフェースという研究領域は、HCI(Human Computer Interaction)とも呼ばれ、コンピュータを利用した対話型機器やシステムとユーザである人間との接点となる場に焦点をあてている。そこからは、実世界指向、拡張現実感、仮想現実感、ウェアラブルコンピューティングなどの技術が生みだされ、生活や業務、エンタテイメントなどに関連した分野で様々な機器が提案されるに至っている。ただし、そこで重要なことは、ユーザである人間の諸特性や多様な利用状況に適合し、さらに彼らの必要性に適合していることである。その点については、ユーザビリティ工学やUX(User Experience)デザインといった立場があるのだが、HCIの新技術とは必ずしも適切な形での連携がなされているとは言えない。本セミナーでは、インタフェース技術開発、人間中心設計、そしてその基礎となる心理学の専門家をお招きして、現状と今後の課題を明らかにしたい。
|
|