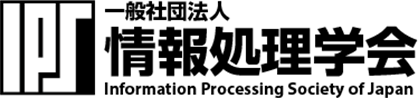「研究会イベントのオンライン開催から垣間見えた
昭和的価値観と令和的価値観」
西垣 正勝(調査研究担当理事)
新型コロナ禍での生活は、私にとって、「昭和的な価値観」と「令和的な価値観」について改めて考える契機となった。
研究会各種イベントのオンライン化は、大学に所属する一研究者の立場からしても、本会調査研究理事の立場からしても、自身への影響が最も大きかった様式変化の1つである。本会も岡部寿男先生(京都大、当時副会長)の陣頭指揮により2020年3月全国大会の開催を一早くオンライン化したが、このような先行事例の知見を上手に活用し、それぞれの研究会が迅速にイベント開催のオンライン移行を成功させたことは不幸中の幸いであった。発表スライドを用いて発表者から聴講者に語りかけるスタイルの研究発表は、1対N型の一方向情報伝達であり、その意味ではオンライン研究発表の聴講はテレビ放送の視聴と類似している。また、発表後の質疑応答は、発表者と質問者の間でやり取りされる1対1型の双方向情報伝達であり、その意味では質疑応答は電話での会話と類似している。テレビや電話は昭和時代に大衆化されており、私たちはこれらの電子機器を使用するにあたってのスキルをこれまでに十分に培っていた。すなわち研究会イベントは、元来、私たちの生活様式の中でオンライン化に向けての準備がすでに整っていた情報メディアであり、これが研究会イベントのオンライン化が比較的スムースに進んだ大きな要因と言えよう。
研究会イベントのオンライン化によって、多くのイベントにおいて参加者が増加した。これまでは遠方のために現地に赴くことができなかった研究者も、オンラインであれば居住地からイベントに参加できる。これまでは多忙のために現地に赴くことができなかった研究者も、大学や企業での仕事の隙間に研究発表を聴くことができる。オンライン化の効用は莫大であり、大変喜ばしいことであるのだが、往々にして利便性は人間を怠惰にさせる方向に働きがちである点にいささかの懸念を抱いている。現地まで出張すること、あるいは、発表会場の雑踏の中に紛れることは、ある意味の面倒さを包含しており、これを億劫に感じた場合には、参加者は自身の興味がある研究発表だけをオンライン視聴するという方法を選択するのだろう。自分の好きなものだけをリーズナブルに入手するという消費者行動は、まさに令和時代を象徴するサブスクリプションビジネスだと感じる。いずれ私たちは、イベントに現地参加できる余裕があるときでさえ、「まぁオンラインでよいかな」と思うようになってしまうのではないだろうか。
研究会イベントは、これまで、研究発表会の形態を採りながら、発表セッション時間外の発表者と質問者の議論、休憩時間における参加者同士の情報交換、懇親会での研究者ネットワークの醸成、交通費・宿泊費・お土産代・二次会費などによる経済貢献、等々、実にさまざまな目的を参加者あるいは現地に提供してきた。万一、近未来の研究会イベントが「令和的」なサブスクリプション型へと完全に変遷してしまったとしたら、研究者がフィルターバブルに捕らわれてしまう危険性が生じ得るという直接的な問題だけでなく、これまで研究会イベントが担っていた「昭和的」な種々の社会機能をも私たちは手放してしまうことになってしまわないだろうか。
現地に乗り込んで終日イベント会場(およびその周辺)でワイワイやる昭和的価値観の参加者が減って、自分の必要性と好みに応じてオンラインで情報を収集する令和的価値観の参加者が増えていく。カジュアルなイベント参加は、研究会の大衆化ともいえる好ましき変革である。一方で、現地だからこそ得られる発見、Face-to-Faceであるからこそ生まれる深い結び付きは、その尊さを知る昭和世代の著者からは「なくすには惜しい逸品」に映る。人は物理的世界に生きて、自然の恵みを食すことによって生命を紡いでいる。人は「土から離れては生きられない(Lusheeta Toel Ur Laputa、1986年8月2日公開の記録より)」のだと、新型コロナ禍を経験してしみじみと感じる。
昭和的価値観と令和的価値観。その両者をWin-Winの関係で共存させる良好なハイブリッド様式を見つけていくことこそが、本会が目指すべき本当の意味でのDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進なのだと信じたい。
蛇足となるが、周囲の研究室の学生の面々の意見を訊くところでは、オンライン研究会やオンライン国際会議の場合は現地の景勝地を訪れることができないため、「発表に対するモチベーションは”だだ下がり”だ」という。また、同僚の意見を訊くところでは、オンライン飲み会は(旧知での少人数の集まりを除いて)上手に機能しておらず、「やはり懇親会はFace-to-Faceでないと」ということである。かくいう私もそう思っているうちの一人だ。これらの事実から判断するに、どうやら新型コロナ終息後には研究会イベントに現地参加する人々はある程度は戻ってきそうである。
これは、情報通信技術自体がリアルな旅行や懇親会の充足感をもたらすレベルにはまだまだ達していないという事実の裏返しである。真のDXの達成には、各研究会が関与する種々の技術をさらに高めていくことが必須となる。情報処理学会は昭和の時代から各研究会の活動をサポートしてきた(本会は昭和35年創立)が、その役割は令和の時代を迎えても変わることはない。