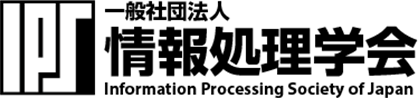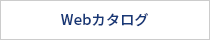総務理事という役職をいただいて2年目になります。今までセミナー委員や財務理事などを経験させていただきましたが、総務理事となって情報処理学会の全体像を考えることが多くなりました。こうした貴重な経験をさせていただいていることに、感謝いたします。
さて今回は、学会の重要なテーマである「会員増」についてこの場をお借りして私見を述べさせていただきます。
総務省統計局の発表によると
☆1、2025年8月時点で日本の総人口は約1億2,330万人で、前年同月比の59万人減少とされています(前年同月比 0.48%減)。
また、[A. 15歳未満人口]は約1,368万人で前年同月比2.5%減、さらに[B. 15〜64歳人口]が約7,355万人で前年同月比0.25%減、[C. 65歳以上人口]は:約3,619万人で0.13%減です。一方で増えたのは、後期高齢者に相当する[D. 75歳以上人口]であり、約2,101万人で前年同月より62万人増えているそうです。この数字を見る限り、いわゆる「少子高齢化社会」はすでに始まっているわけです。
今後10年間で[C. 65歳以上人口]のおそらく大部分が[D. 75歳以上人口]へ移動し、[B. 15〜64歳人口]の何割かが[C. 65歳以上人口]に移動し、[A. 15歳未満人口]から何割かがBへ、と移動します。[A. 15歳未満人口]がどのくらい増えるかは何とも言えませんが、大幅な増加は予想されていません(2024年の合計特殊出生率は1.15となり2023年度の1.20を下回っています
☆2)。
日本の少子高齢化の進行は当面の間進行することが確定しており、15歳以上人口が当分減り続けることは事実です。このような事実を見ると、情報処理学会が現在掲げる「会員増」は非常にチャレンジングなテーマであることが再認識されます。数字だけで見れば、情報処理学会の会員数は微増・微減をしつつも2万人程度を堅持しているのがこの数年であり、そのこと自体が今の日本の状況においては健闘しているといってよいのではないでしょうか。
では、会員の内訳はどうでしょうか?
日本の人口推移と逆に、ジュニア会員・学生会員が増えているのが現在の情報処理学会です。
日本の未来を担う若い方々がこうして会員になってくださるのは、とても重要なことであり、若い世代への啓もう活動や各種イベントに奔走されている先生方, 支部を含めた理事・役員の皆様、事務局の皆様の努力が着実に形になっていることを実感いたします。その喜ばしいことに水を差すつもりは毛頭ないのですが、現在[B.15〜64歳人口]の人口エリアにいる私としては、会員増のテーマについて思うところがあります。
若手へのアプローチは継続的に必要であり、引き続き注力すべきことは情報処理学会のみならず日本の未来を託す人材の育成という点でも疑いはありません。一方、あまり現時点では力が入っていない対象層が[C. 65歳以上人口]と[D. 75歳以上人口]であるように感じています。学会には長年会員への優遇制度はありますが、その優遇制度に当てはまらない会員の方々が、定年を迎えた後に正会員を継続せずに静かに退会していくのを食い止める施策も必要と思われます。のみならず、新たな層として定年を機に「違う分野を勉強してみたい」とか「大学に入りなおすほどではないが勉強はしたい、今まで縁がなかったが最近話題になっているAIやITを知りたい」という方が新たに会員になる可能性はないのでしょうか? 「年齢は高いが初心者」な方々は、従来学会の想定会員とは異なっていることもあり、会員勧誘の対象にはなっていなかったと思います。しかし、このような知的関心が高いけれどなかなか踏み出せない方や、今までの企業人人生とは違う学びのコミュニティに興味がある方々に、新たな枠組みの会員制度を提供することも考えてよい時期ではないかと思います。もちろん、まずビジネスモデルとしての検討は必要でしょう。年会費とイベント参加をサブスクリプションモデルにしたり、イベントはチケット制で購入してもらう、また特別プログラムとして情報処理学会側も理事経験者や元教職にあった方々の力を借りて「入門」を定期的にリアルな環境で提供したり、など実施に際してはそれなりにワークもかかることですが、試験的に小さくトライしてみるのもよいと思います。こうした試み自体が、昨今のIT技術の進化が、学習を始める年齢を問わないということの証明にもなります。たとえば81歳でスマホアプリ開発を始めた若宮正子さんのような人材がまだ日本に眠っているのであれば、それを発掘し伸ばすお手伝いをすることは学会として社会に貢献する一つの方法かもしれないと思います。
また、人口統計には現れませんが、日本のIT企業で働く外国籍の方々も相当数が存在しています。厚生労働省によると令和6年(2024年)10月末時点で、情報通信業に従事する外国人労働者数は約9万人でこの産業の3.9%の就業人口を占めています
☆4。
その方々に情報処理学会は見えているのでしょうか? 英語での対応などの難しさもあり、今までは積極的に検討されてこなかった領域ではないかと思います。そもそもその方々に情報処理学会に参加するモチベーションがあるのかさえ、調査されていないと思いますので、そこから始めてみるのは意味があると思います。
会員増(特に有料会員)は、情報処理学会の経営基盤である会費の収入増に結び付くことは自明ですが、経済面と同様に重要なこととして、学会としての存在感を維持向上させるという点においても、きわめて重要なことではないでしょうか。日本において2万人超の会員を擁するITに関連する学会であるということは、多くの技術者・有識者を代表する資格があるということも意味します。会員が減少することによって、こうした存在としての価値と意義が損なわれていきかねません。これは経営基盤の堅持と同じくらい重要なテーマだと思います。
本年は2021年から始まった5カ年中期計画の仕上げの年であり、次の5年を考えるタイミングでもあります。より良い次の情報処理学会のために、会員増のテーマを始め多くの課題に取り組む所存です。多くの方々からの忌憚のないご意見をいただければ幸いです。
出典
☆1 https://www.stat.go.jp/data/jinsui/
☆2 令和6年(2024)人口動態統計月報年数(概数)の概況:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai24/dl/gaikyouR6.pdf
☆3 https://www.ipsj.or.jp/member/service-ichiran.html
☆4 外国人雇用状況の届出状況まとめ(令和6年10月末時点):厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50256.html