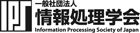- [10:00-10:10]「オープニング」 越塚 登(東京大学大学院情報学環)
- [10:10-11:00]「オープンデータとその流通を支える技術」 武田 英明(国立情報学研究所)
- [11:10-12:00]「mdx: データ科学・データ活用のための新しい学術情報基盤」 田浦 健次朗(東京大学)
- [13:00-13:50]「説明責任が求められるシステムにおけるAI活用とデータ」 田丸 健三郎(日本マイクロソフト株式会社)
- [14:00-14:50]「都市の中核を構成する地理空間情報の円滑な流通に向けて」 関本 義秀(東京大学)
- [15:00-15:50]「公共交通オープンデータの推進から考えるデータ駆動型社会への道」伊藤 昌毅(東京大学)
- [16:00-16:50]「オープンなデータ流通基盤としてのFIWARE」望月 康則(日本電気株式会社)

コーディネータ:越塚 登
東京大学大学院情報学環 教授
【略歴】1994年東大院理学系研究科博士課程修了、博士(理学)。東工大院情報理工学研究科・助手、東工大院人文社会系研究科・助教授等を経て、2009年より現職。2019年8月より東京大学大学院情報学環長。専門は計算機科学(Computer Science)。特に、IoTやLinked Open Data、Operating System、Block Chainなどの研究に取り組んでいる。
オープンデータとその流通を支える技術

講師:武田 英明
国立情報学研究所 情報学プリンシプル研究系 教授
【略歴】1991年、東大大学院工学研究科博士課程修了後、ノルウェー工科大学、奈良先端科学技術大学院大学などを経て2003年より国立情報学研究所教授。同研究所学術コンテンツサービス研究開発センター長(2006-2010年)、東京大学人工物工学研究センター寄付講座教授(2005-2010年)、大阪大学サステイナビリティ・サイエンス研究機構 特任教授(2006-2010年)なども務める。専門は人工知能とウェブ情報学、学術コミュニケーション。工学博士。
mdx: データ科学・データ活用のための新しい学術情報基盤

講師:田浦 健次朗
東京大学 大学院情報理工学系研究科電子情報学専攻 教授/東京大学 情報基盤センター(兼務) 情報基盤センター長
【略歴】1997年、東大大学院理学系研究科博士課程修了。東京大学情報理工学系研究科電子情報学専攻。2018年より東京大学情報基盤センター長。 専門は並列処理、 高性能計算、プログラミング言語。 理学博士。
説明責任が求められるシステムにおけるAI活用とデータ

講師:田丸 健三郎
日本マイクロソフト株式会社 業務執行役員NTO/内閣官房政府CIO補佐官/一般社団法人AIデータ活用コンソーシアム 副会長
【略歴】1992年マイクロソフト入社。米国 Microsoft Corporation(WA)にて、主にメッセージングシステム、ディレクトリサービスおよびグローバル分散処理システムの研究開発を担当。機械学習によるルーティングの最適化、コミュニケーションデータ(自然言語)の分析、モデル化に従事。その後、アジア(日本、台湾、韓国、中国)におけるサーバー製品群の研究開発グループ統括責任者を務めた後、2009年10月より業務執行役員 NTO、2019年5月より政府CIO補佐官を兼務。
都市の中核を構成する地理空間情報の円滑な流通に向けて

講師:関本 義秀
東京大学 生産技術研究所(工学系研究科社会基盤学専攻・先端学際工学専攻・空間情報科学研究センター兼任) 准教授
【略歴】1973年5月31日 神奈川県生まれ
1992年3月 鹿児島県私立ラサール学園高等学校卒業
1992年4月 東京大学理科一類入学
1997年3月 東京大学工学部土木工学科卒業
1999年3月 東京大学大学院工学系研究科社会基盤工学専攻修士課程修了
2002年3月 同 博士課程修了
2002年4月 国土交通省国土技術政策総合研究所 高度情報化研究センター情報基盤研究室 研究官(任期付)
2007年4月 東京大学空間情報科学研究センター 産学官連携研究員
2007年9月 同 特任講師
2010年4月 同 特任准教授
2013年4月~ 東京大学生産技術研究所 人間・社会系部門 准教授(工学系研究科社会基盤学専攻兼務)
2013年6月~ (空間情報科学研究センター兼務)
2015年4月~ 放送大学客員准教授
2017年4月~ (工学系研究科先端学際工学専攻兼務)
公共交通オープンデータの推進から考えるデータ駆動型社会への道

講師:伊藤 昌毅
国立大学法人 東京大学 生産技術研究所 特任講師
【略歴】東京大学生産技術研究所 特任講師。2002年慶應義塾大学環境情報学部卒業、同大学院にて博士(政策・メディア)取得。鳥取大学助教などを経て現職。専門は交通情報学。産官学を繋ぐカンファレンス「交通ジオメディアサミット」や全国の公共交通のオープンデータ化支援などを実践。国土交通省 バス情報の静的・動的データ利活用検討会 座長、同 都市と地方の新たなモビリティサービス懇談会 委員、沖縄県 沖縄観光2次交通の利便性向上に向けた検討委員会 座長なをどを務める。
オープンなデータ流通基盤としてのFIWARE

講師:望月 康則
日本電気株式会社 NECフェロー
【略歴】現在、NEC フェローとしてスマートシティにかんするデジタル変革とIoTエコシステムに関する活動に注力している。2019年3月までは執行役員としてNECの全社技術戦略の策定を担当。NECにて30年以上にわたり研究者および研究部門長としての職歴を有し、AIを含むコンピュータサイエンス、ICTシステム、半導体集積回路・デバイス、固体物理などの幅広い技術領域に精通している。2017年3月には NECを代表してFIWAWRE Foundationのボードメンバーに就任。COCN「デジタルスマートシティの構築」サブリーダー、世界経済フォーラム第四次産業革命東京センター・スマートシティプロジェクトフェロー。他に、経団連、JEITA、OECDなどでの活動にも参画。東大・電子工学・博士課程修了(1987年)。