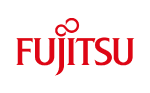よくある質問
情報処理学会ではITプロフェッショナル(実務家)のためのシンポジウムとして、2004年度から毎年度「ソフトウエアジャパン」を開催し、多数の企業・大学等からのご支援を頂いております。
IT関連業界において現場で活躍されている産業界の方々を中心に、学界・官公庁関係の方々、次世代を担う若手の技術者・研究者の方々等、多くの方々がともに問題意識を共有し議論、交流を深められる場として、またIT産業の今後を皆様と考える機会といたしまして、今年度も「ソフトウエアジャパン2014」を開催いたします。
過去のソフトウエアジャパン
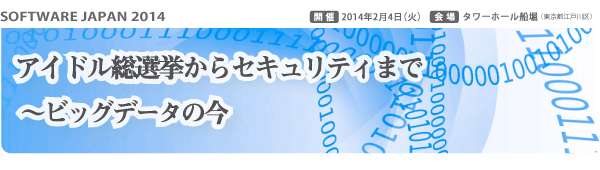
ITフォーラムセッション 「IPA/SEC 情報処理推進機構 ソフトウェア高信頼化センター」
| データの分析に基づくシステムの信頼性向上 | |
| 【セッション概要】 今日、私たちを取り巻く環境の多様化とその変化はますます激しさを増し、それに伴い、私たちの生活や社会経済活動にとって必要不可欠なITシステムにおいては、その規模及び複雑さが増大し続けています。また、私たちの活動やITシステムの稼働に付随して生み出されるデータの量も、爆発的に増加しています。このような状況において、高信頼なサービス水準を維持し続けるためには、その目的に適切なデータを抽出して分析し、その結果を業界や世代を超えて幅広く共有・伝承していくことが必須となっています。本セッションでは、このようなデータの分析に基づく高効率で高信頼なソフトウェア/システムの構築・運用に関し、IPA/SECにおける取組みと成果、及び国内3大学における実践的な調査研究の内容等について紹介します。 |
|
| プログラム[会場:4F 研修室] | |
| 09:30-10:00 講演-1 山下博之 (情報処理推進機構 技術本部 SECシステムグループリーダー) 10:00-10:40 講演-2 坂東幸一 (電気通信大学 大学院 情報システム学研究科 研究員) 松野裕 (電気通信大学 大学院 情報システム学研究科 助教) 10:40-11:20 講演-3 野中誠 (東洋大学 経営学部 経営学科 准教授) 11:20-12:00 講演-4 松本健一 (奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 教授) |
|
| 司会:山下 博之 (独立行政法人情報処理推進機構 技術本部 ソフトウェア高信頼化センター システムグループリーダー) | |
 |
【略歴】1981年京都大学大学院修士課程(情報工学)修了。同年、日本電信電話公社(現NTT)入社。以後、研究所において、通信制御処理システム、高機能通信プロトコル、分散協調処理、著作権管理、コンテンツ流通等に関する研究開発・標準化活動に従事。2003年10月に(株)NTTデータに転籍。2004年~2008年、JSTに出向。2009年4月に(株)NTTデータアイ入社、同時にIPAに出向。2003年10月~2008年4月、科学技術振興調整費プログラムオフィサー。米国PMI認定PMP。情報処理学会電子化知的財産・社会基盤研究会主査。情報規格調査会SC6専門委員会委員長。IEEE、情報処理学会、電子情報通信学会各会員。 |
| 先頭に戻る | |
| 09:30-10:00 講演[1] 山下 博之 (独立行政法人情報処理推進機構 技術本部 ソフトウェア高信頼化センター システムグループリーダー) |
|
| IPA/SECにおけるデータと知見の分析・共有の取組み | |
|
【講演概要】IPA/SECでは、重要インフラ分野を中心に、製品や機器及びITサービスの高信頼化を目指し、システムの障害事例情報の分析や対策手法の整理・体系化を通して得られる「教訓」を業界・分野を超えて幅広く共有し、類似障害の再発防止や影響範囲縮小につなげる仕組みの構築に取り組んでいます。また、ソフトウェア開発データを収集・分析し、統計情報として整理した『ソフトウェア開発データ白書』として発行すると共に、分析データの比較により新規プロジェクトの計画策定時の参考としたり、実施中プロジェクトの妥当性を確認したりするベンチマーキングの推進に取り組んでいます。本講演では、これらの取組みの概要と最新の成果等について紹介します。 |
|
 |
【略歴】1981年京都大学大学院修士課程(情報工学)修了。同年、日本電信電話公社(現NTT)入社。以後、研究所において、通信制御処理システム、高機能通信プロトコ ル、分散協調処理、著作権管理、コンテンツ流通等に関する研究開発・標準化活動に従事。2003年10月に(株)NTTデータに転籍。2004 年~2008年、JSTに出向。2009年4月に(株)NTTデータアイ入社、同時にIPAに出向。2003年10月~2008年4月、科学技術振興調整 費プログラムオフィサー。米国PMI認定PMP。情報処理学会電子化知的財産・社会基盤研究会主査。情報規格調査会SC6専門委員会委員長。IEEE、情 報処理学会、電子情報通信学会各会員。 |
| 先頭に戻る | |
| 10:00-10:40 講演[2] 坂東 幸一 (電気通信大学 大学院 情報システム学研究科 研究員) 松野 裕 (電気通信大学 大学院 情報システム学研究科 助教) |
|
| 新聞報道による情報システム事故の信頼性・安全性の分析 | |
|
【講演概要】IT化の進展は人々の生活に多大な利便性を与えている反面、市民に大きな影響を与える事故や不具合、さらには犯罪行為を引き起こしています。著者らはこれらのIT関係事故の現状を把握するために、社会を支える重要なインフラである通信ネットワークと金融情報システムの事故に焦点を絞り、代表的な全国紙4紙によって報道されている事故情報をセキュリティ関係も含めて広く収集を行っています。本講演ではこれらの事故情報を活用することにより、情報システム事故のトレンドを事故内容、事故の重大性、事故の原因(フォールト)などの観点から分析することにより、これらシステムの信頼性と安全性の現状について分析した結果を報告します。 |
|
 |
坂東幸一【略歴】1964年3月北海道大学工学部電子工学科卒業、同年4月から日本電気(株)にてデータ交換機やコンピュータのハードウェア開発、医療機器事業等に従事、1992年から四国日本電気ソフトウェア(株)、NECフィールドサービス(株)などに勤務、2002年退職、2009年3月電気通信大学大学院後期課程修了。博士(工学)。現在、同大学研究員として情報システムの信頼性などの研究に従事。日本信頼性学会、電子情報通信学会、情報処理学会の会員。 |
 |
松野裕【略歴】2001年東京大学工学部電子工学科卒業。2006年同大学院新領域創成科学研究科博士課程修了、博士(科学)。プログラミング言語、ディペンダビリティ、システム保証に興味を持つ。現在電気通信大学大学院情報システム学研究科助教。日本信頼性学会、日本品質学会、電子情報通信学会、情報処理学会の会員。 |
| 先頭に戻る | |
| 10:40-11:20 講演[3] 野中 誠 (東洋大学 経営学部 経営学科 准教授) |
|
| ソフトウェア品質データ分析を通じた組織的改善の促進 | |
|
【講演概要】ソフトウェア信頼性の確保と向上には、ソフトウェア開発に関わる固有技術に加えて、組織的かつ継続的なプロセス改善が必要です。そのようなプロセス改善を実践する一つの鍵は「事実に基づく管理」です。ソフトウェア品質データを分析して「事実」を把握し、これに基づいて品質目標とその達成方法を計画し、達成状況をデータで確認し、プロセス改善などの適切な処置をするというPDCAサイクルの実践が必要であり、その原動力が品質データ分析です。本講演では、組織的改善に結びつくソフトウェア品質データ分析の具体例を紹介します。本講演の内容が組織的改善を促し、信頼性の高いソフトウェアを継続的に開発できる組織能力の涵養につながれば幸いです。 |
|
 |
【略歴】2000年早稲田大学大学院理工学研究科経営システム工学専攻単位取得退学。早稲田大学助手を経て現職。IPA/SEC高信頼性定量化部会主査、日科技連ソフトウェア品質委員会(SQiP)運営委員長。共著『データ指向のソフトウェア品質マネジメント』2013年度日経品質管理文献賞受賞。情報処理学会、電子情報通信学会、IEEE、ACM、日本品質管理学会、経営情報学会、日本経営工学会、経営システム学会、プロジェクトマネジメント学会各会員。 |
| 先頭に戻る | |
| 11:20-12:00 講演[4] 松本 健一 (奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 教授) |
|
| ソフトウェア品質の第三者評価のための基盤技術~ソフトウェアプロジェクトトモグラフィの開発~ | |
|
【講演概要】ソフトウェア品質の第三者評価の普及と高度化を目的とする新たな枠組み「ソフトウェアプロジェクトトモグラフィ(SPT)」について、IPA/SEC・2012年度ソフトウェア工学分野の先導的研究支援事業の成果を中心に紹介します。SPTは,一般的なソフトウェア開発管理システムが収集・蓄積しているソフトウェア開発データを、「要件」、「作業」、「組織」、「プロダクト」、「課題」の5つの観点に分類した上で、解析結果と関連するプロダクト断片を付加し、スナップショットと呼ぶデータ複合体の時系列として再構成することで、「品質評価に必要となるソフトウェアプロジェクトデータの提供」と「提供されたデータに基づくプロジェクト理解」を容易にするものです。 |
|
 |
【略歴】1985年大阪大学基礎工学部情報工学科卒業。1989年同大学大学院博士課程中退。同年同大学基礎工学部情報工学科助手。1993年奈良先端科学技術大学院大学助教授。2001年同大学教授。工学博士。エンピリカルソフトウェア工学、特に、プロジェクトデータ収集/利用支援の研究に従事、情報処理学会、電子情報通信学会、日本ソフトウェア科学会、ACM、IEEE各会員、電子情報通信学会フェロー、IEEE Senior Member。 |
| 先頭に戻る | |
Copyright (C) 2013 Information Processing Society of Japan All Rights Reserved.