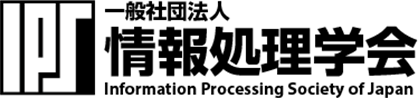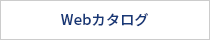Vol.63 No.4(2022年4月号)
Vol.63 No.4(2022年4月号)
|
満柏
社会人
|
芸術家が,芸術を研究する情報学の研究者を見つけるには,どうすればいいでしょうか? |
|
|
大きく分けて3種類の研究をしている科学者がいます.まず芸術作品の研究をする科学者,次に芸術体験の研究者,最後に芸術制作を研究する科学者です.1つ目の作品研究は,素材や技法,時代や作者,主題や形式を対象としています.いつ,どこで,誰が,どのように,何を作ったのか.いわば物としての芸術の研究者です.2つ目は感性の研究と言い換えてもよいでしょう.芸術体験をする人の感覚はどのように働いているのでしょうか.何らかの手段で感動している脳の状態が再現できれば,芸術は必要ないのでしょうか.こちらは芸術を効果の側から研究していることになります.最後はプログラム等による作品制作の研究です.これは作品と体験の研究を統合したものと言えるかもしれません.絵画や音楽,あるいは文学でさえも,作品の具体化には素材への理解が欠かせませんし,制作を終えるためには出来栄えを判断する感性が必要です.おそらく「情報学の研究者」と限定した場合でも,研究者の関心の中心がどこにあるのかで,研究活動の内実は大きく異なります.特定の研究テーマを持っている研究者を探すことは難しいかもしれませんが,関心の近い研究者が見つかるとよいですね. |
 小山田智寛
東京文化財研究所 |
|
|
|
レオナルド・ダ=ヴィンチ(Leonardo da Vinci)は芸術を研究した科学者といえます.彼および同時代のルネサンスの芸術家たちが発明した遠近法は有名です.近代以降ではポール・セザンヌ(Paul Cézanne)も芸術を研究した科学者といえるでしょう.彼はたとえば同じ山の絵を何枚も描くことによって,自分の心が感じた印象を理論的に研究しました.前者の遠近法はコンピュータ・グラフィクスの基礎になり,今日では多くの科学者がその新しい表現を研究しています.後者の印象の研究はどうでしょうか? 印象は他者には観察しにくい情報であり,科学として扱いにくいかもしれません,しかし,今日の人工知能は,この印象の情報をますます柔軟に扱えるようになってきています.したがって,人工知能に絵を描かせることによって,心で感じた印象を科学としてますます研究できるようになるかもしれませんね.私はそうしています. |
|
|
まず,何はともあれ本会のWebページで,「芸術」を検索すると902件,「アート」を検索すると634件の項目がヒットします(2022年2月10日現在).芸術も,情報学もともに広範な領域なので,それぞれの項目を地道に調べていくと,「この人に会ってみたい」あるいは「この人の話を聞きたい」という人が見つかる可能性があります.もし見つかったら,その人の所属先なり,あるいは連絡先など(これも検索すれば見つかる場合があります)に,メールなどで連絡してみるのがよいと思います.他者との協働を志向する研究者は,基本的にオープンなマインドの持ち主なので,それで返事がなかったら,その人はそもそも芸術には関心がない研究者だと思っていただいて,ほぼ間違いありません.芸術やアートを,単に道具として利用しているだけの研究者も多いので,ここは注意が肝心です. |
 久保田晃弘
多摩美術大学 |
|
|
|
芸術の1つである「音楽」を扱う「音楽情報処理」の分野を,約30年間研究しています.また,2010年6月の情報処理学会誌に「音楽情報学」の解説を執筆しました.その立場から回答します. |
|
| 目次に戻る | ||