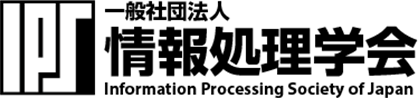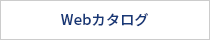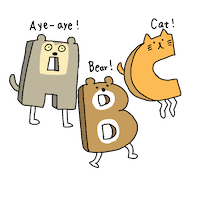Vol.63 No.3(2022年3月号)
Vol.63 No.3(2022年3月号)
|
高橋響子
[ジュニア会員] 大学院生
|
大学院生です.提案手法の略称の決め方が気になります.特にユニークなものは意図して付けたものだったりするんですか(それとも偶然?)?. |
|
|
どんなに良い研究でも,他人に知ってもらえないと届きません.名前や略称は他人に紹介しようとしたときに最初の接点になるので,とても重要です. |
 米澤香子Wieden + Kennedy Tokyo
|
|
|
|
地球上では膨大な種数の生物が暮らし,我々人間(ヒト)もその一種にすぎません.文明の発展とともにヒトは周りにいるさまざまな生物を認識し,それらに『名前』を与えてきました.近代に入ると,西洋の博物学者が書物の中であらゆる生物種に対して世界共通の学術的な生物種名,いわゆる『学名』を命名するようになりました.現在はスウェーデンの博物学者カール・フォン・リンネ(Carl von Linné)が1750年代に体系立てた2語のラテン語(例:ヒトはHomo sapiens)で種の学名を示す手法が採用されています.新種が発見されるとニュースなどで話題になることがあります.この『新種の発見』とは,これまで学名が与えられていなかった生物種に対して学名が命名されたことを意味します.言い換えると,これまで誰も目にしたことのなかった生物種が発見されても,学名が命名されない限りその種は『名無しの権兵衛』というわけです. |
|
|
提案手法の略称の決め方についてのご質問ですが,ここでは研究成果となる手法やシステムのネーミングの仕方についてご紹介します. |
 中小路久美代
[正会員] 公立はこだて未来大学 |
|
| 目次に戻る | ||