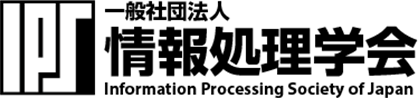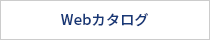Vol.61 No.8(2020年8月号)
Vol.61 No.8(2020年8月号)
|
匿名希望
中学生 |
大学の研究費はどこから出されているのでしょうか. |
|
|
個人で行う研究から多数の研究者がグループで行う研究まで,さまざまな研究活動が大学で行われていますが,それを支える研究費は大別すると次の3つに分類できます.(1)国からの資金,(2)企業からの資金,(3)個人・団体からの寄付金・助成金等. |
 西尾章治郎 [名誉会員] 大阪大学 |
|
|
|
大学で行われている研究活動には,政府が分野や目標を定めてプロジェクトとして行うもの,企業が費用を負担する共同研究で具体的な製品開発に結びつけるためのものなどさまざまな形態があります.しかし,研究分野の縛りがなく,研究の目的を外部から設定されずに研究者が自由な発想に基づいて行う研究(curiosity-driven research)を支えているのは,我が国では文部科学省所管の科学研究費助成事業(通称「科研費」)です.科研費は,人文学・社会科学から自然科学までのすべての分野にわたり,基礎から応用までのあらゆる独創的・先駆的な学術研究を対象としています.研究者が応募した研究計画の中から厳正な審査を経て採択される研究費を競争的資金と呼びます.科研費は,日本政府全体の競争的資金の半分以上を占め,令和2(2020)年度の予算額は2,373憶5千万円です.科研費の審査は,学術論文の審査などと同様に,専門分野の近い複数の研究者による審査(ピアレビュー)によって行われています.科研費には毎年10万件を超える応募があり,平成30(2018)年度は約2万6千件が新規に採択され,前年度以前から継続している研究課題と併せて約7万5千件が支援を受けています.国立大学である京都大学を例に挙げますと,政府からの委託や企業との共同研究を除き大学として行った研究の研究費は平成30(2018)年度は189億円で,そのうち134億円が科研費による助成です.科研費はすべての研究活動の基盤となる学術研究を幅広く支え,科学の発展の種を蒔き芽を育てる大きな役割を果たしています. |
|
|
「大学に所属する研究者(教員)が研究費を得る方法」の視点から答えることとします. |
 橋本和仁
物質・材料研究機構/総合科学技術・イノベーション会議 議員 |
|
| 目次に戻る | ||