Vol.59 No.11(2018年11月号)
Vol.59 No.11(2018年11月号)
トミオ
[ジュニア会員] 大学生 |
1つの研究テーマにはどのくらいの期間を使いますか? |
|
|
お答えは人により変わりますが,私の場合は3年間です.私の研究分野はデータシステムといいます.美しい設計原理と精妙巧緻な実装技芸から構成されるこの分野を研究するには,研究以前に各種基盤システム(OS,CPU,コンパイラ等)に関する理解と,実装手法の習得が必要です.そのため研究期間は長期化する傾向があります.1年目では練習として,世界最先端と言われている技術を1つ取り上げて,それに勝つ技術を作ります.研究以前に勉強も必要なため,1年間程度が必要です.これは1つの「点」における改善ですから,面白くありません.2年目では,ほかの最先端技術を網羅的に再実装し,それらの特性を調査します.これにより点と点がつながり,人類が保有する技術を線として理解可能になります.その線を上回るような新技術を得るべく,問題を根底から考え直します.ひたすら考え抜きます.2年目後半~3年目前半にだいたい何かを思いつきます.そのあと,アイディアの優位性を示すべく,設計・実装・実験をし,論文を書いて研究を終えます.
編集部注:※会誌掲載時から内容を更新しております。 |
 川島英之
[正会員]
慶應義塾大学 |
|
|
|
これは分野やテーマに強く依存するご質問だと思うので,私個人に限った話として回答します.私はコンピュータグラフィクスに関する研究を行うことが多く,この分野の研究では,着想から論文投稿までをおおよそ0.5年~1.5年程度で完了させています.周辺分野の調査とテーマ決定に1カ月程度,実装に1カ月程度,評価実験に1カ月程度,論文執筆に1カ月程度,というのが理想的だと思っています.ただし,研究の中盤や終盤で,より良い方法を思いついて実装を繰り返すことも多く,その場合はさらに数カ月~1年の時間がかかります.この提案手法を洗練するステップが,研究期間を延長させやすい曲者です.研究は創造的な活動で,終わりというものが存在せず,手法の洗練はいつまででもやっていられます.手法の洗練自体はまったく悪いことではないのですが,使える時間は有限なので,あるタイミングで論文化し発表する必要があります. |
|
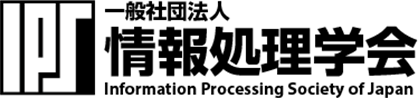


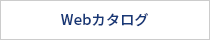


 井尻 敬
井尻 敬