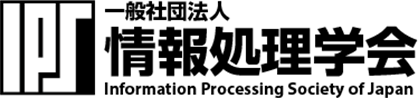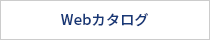2024年度研究会活動報告
2024年度研究会・研究グループ活動報告
コンピュータサイエンス領域
◆データベースシステム(DBS)研究会
[主査:中島伸介,幹事:森嶋厚行,北山大輔,小林亜樹,清水敏之,莊司慶行,杉浦健人,Le Hieu Hanh]
1.定例の研究会活動報告
第179回,第180回の定例の研究会を開催した.なお,第179回は対面,第180回はオンラインで,いずれの研究会も盛況であった.
第179回研究会は,「WebDB夏のワークショップ」と題し,情報基礎とアクセス技術研究会(IFAT)および電子情報通信学会データ工学研究会(DE)と合同の研究会として実施した.開催日は9月11(水)〜12日(木),会場は淡路夢舞台国際会議場(兵庫県)であり,2023年度CS領域功績賞受賞記念講演(飯沢篤志氏・リコーITソリューションズ株式会社「ウェルビーイングと研究」),若手招待講演(伊藤 寛祥氏・筑波大学「個人と社会をつなぐAI技術:well-beingの最大化に向けて」,陸 可鏡氏・名古屋大学「高次元空間近似最近傍探索向けの隣接グラフ」)に加えて,一般講演41件(DBS 29件,IFAT 4件,DE 8件)の発表があった.
第180回研究会は,例年通り,情報基礎とアクセス技術研究会(IFAT)および電子情報通信学会データ工学研究会(DE)と合同で開催した.開催日は12月26日(木)に完全オンライン形式で開催した.発表件数は,一般講演9件(DBS 3件,DE 5件,IFAT研1件)であり,参加者数は20名(オンライン)であった.
2.シンポジウム・国際会議等の報告
DBS研究会では,関連学会・研究会である日本データベース学会及び電子情報通信学会データ工学研究会と,データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム(DEIMフォーラム)を実施してきた.これは,関連分野で最大の規模で実施されるシンポジウムである.開催期間は2024年度は,2025年2月27日(木)〜3月1日(土)・3月3日(月)〜4日(火)であり,具体的には,前半はオンラインによる口頭発表,後半は対面形式(福岡国際会議場・福岡県)でチュートリアル,インタラクティブセッション,プレナリセッション等を行う直列ハイブリッド形式であり,発表数400件以上,参加登録者数800名以上と盛況であった.
◆ソフトウェア(SE)工学研究会
[主査:鷲崎弘宜,幹事:伊原彰紀,新原敦介,竹内広宜,竹之内啓太,徳本 晋,福田浩章,槇原絵里奈,横川智教]1.ビジョンとコンセプト
2021年度からの新体制運営にあたり策定した次のビジョンとコンセプトを引き続き2024年度も掲げて,それらを達成する形で各種の研究会活動を発展的に計画および実施した.
- ビジョン: ソフトウェアエンジニアリングのプロフェッショナル集団やそれに連なるアーリーキャリア・学生および周辺の関係者が集い交流するとともに,人々や社会の価値創造に貢献するソフトウェアエンジニアリングに向けた研究,実践および人材育成の成果発表と議論を通じて深化と拡大を進め,その結果を社会へ発信するとともに更なる深化および拡大の基礎を得る.
- コンセプト1「集う」: ソフトウェアエンジニアリングに携わる多様な利害関係者が立場・性別・年代・主張を超えて集い,行動規範をもって相互の理解と交流を深め,連携する.この達成のため,国内外の会議を交流機会を活発に開催した.旗艦会議であるソフトウェアエンジニアリングシンポジウム2024について過去最多の対面参加があり,討論機会であるウィンターワークショップ2025について過去最多レベルの参加があった.また,COMPSACやISSRE等の国内開催の重要国際会議について研究会メンバが主体的に参画協力し,国際連携を拡大した.
- コンセプト2「研究する」: 理論研究にもとづくソフトウェアおよびソフトウェア開発の基本原則の解明や新たなアイディアの創造,事例研究にもとづく実証経験とを突き合わせ,ソフトウェアエンジニアリングの地平を広げつつ,実践へとつなげる.この達成のため,引き続き卓越研究賞を設けて世界トップレベルの研究を促すとともに,量子ソフトウェア工学の講演や様々なワーキンググループ(要求工学WG,国際的研究活動活性化WG,ソフトウェア評価WG,学連携促進WG,ダイバーシティWG)活動の継続など,分野の広がりに引き続き務めた.
- コンセプト3「実践する」: ソフトウェアエンジニアリングのプラクティスや実践経験を共有および深掘りし,知識,スキル,コンピテンシとして体系化し,ソフトウェア社会における産業発展に貢献するとともに,さらなる研究を促す.この達成に向けて,産学連携に基づく成果発表や議論が活発にあり,また研究会メンバが主体となり,実践や人材育成ほかの基礎を与えるソフトウェアエンジニアリング知識体系ガイド IEEE-CS SWEBOK Guideの第4版の刊行に貢献した.
- コンセプト4「育成する」: 実証済みのソフトウェアエンジニアリング高等教育や職業訓練および組織開発運営成果を共有するとともに,プロフェッショナルが高い倫理感および職業意識を持ち社会的地位を高めることに貢献する.この達成に向けて,引き続き学生奨励賞を設けるとともに,研究集会において若手の奨励や育成に向けたあり方について議論した.また,研究会推薦博士論文速報への応募を広く呼びかけた.
2. 定例の研究会活動報告
第217-219回の研究発表会を計画し,合計70件の研究発表(招待講演・活動報告を含む)があった.これらは特に「集う」「研究する」「実践する」に資するものである.- 第217回 7月25-27日 北海道 小樽経済センター・オンラインハイブリッド開催,発表 全25件 (SIGSE/SIGSS/SIGKBSE連立開催,うちSIGSE扱い11件)
- 第218回 11月4日-5日 立命館大学大阪いばらきキャンパス・オンラインハイブリッド開催,発表 8件
- 第219回 3月3-4日 早稲田大学 西早稲田キャンパス・オンラインハイブリッド開催,発表 29件
分野は,要求分析から設計・実装・テストに至るソフトウェアライフサイクル全般にわたるとともに,社会のソフトウェア化および生成AIほかの発展を反映して,ソフトウェアビジネスや組織変革に関わるデジタルトランスフォーメーション(DX),生成AIとソフトウェア工学の関わりの発表も多く見られた.
3.シンポジウム・国際会議等の報告
次のシンポジウムおよびワークショップを実施した.(1) ソフトウェアエンジニアリングシンポジウム2024(SES2024)
2024年9月17-19日の3日間にわたり神奈川県・慶應義塾大学・オンラインにてハイブリッド開催した.対面を基本としつつオンライン併用により広範な参加機会を確保し,ソフトウェアの企画,開発,運用,保守,マネジメントおよび価値創造に関わるあらゆる人々に向けて開催し,多くの参加を得た.前年度に引き続きビジョンとコンセプトを明確とし,それに沿って人とAIの共生や機械学習システムならびに量子ソフトウェア工学に関する基調講演や多数の研究・実践・一般・既発表・ポスター論文,萌芽的なワークショップなど充実のプログラムを企画した.さらに前年度に引き続き安心して集うための行動規範を定めた.ソフトウェアエンジニアリングの未来のため,事前申し込みの学生は参加無料とした.
(2) ウィンターワークショップ2025・イン・下関(WWS2025)
2025年1月10-11日の2日間にわたり,下関市 海峡メッセ下関・オンラインのハイブリッド形態にて6つのテーマに分かれて研究発表および討論した.データサイエンス,要求工学,生成AI,ダイバーシティ,サービスコンピューティングおよび産学連携の様々なテーマで集い,議論ならびに交流を深める重要な機会となった.
4.その他
上記に加えて「集う」の広範な実現にあたり,学会として主催するFITや全国大会に参画協力した.今後も引き続きビジョンとコンセプトを明確としながら,それらを達成するように活動の計画と実施を進め,研究会会員に対するサービスレベルの向上に努め,充実した活動を行っていきたい.特に若手や産業界人材のさらなる活躍機会や,他分野とのさらなる連携強化について検討課題であり,2025年度からの新体制において強化と発展が期待される.◆システム・アーキテクチャ(ARC)研究会
[主査:津邑公暁,幹事:岩崎裕江,大西隆之,栗原康志,八巻隼人]
1.定例の研究会活動報告
第249~252回の研究発表会を開催した.その全ての発表会を,電子情報通信学会 コンピュータシステム研究専門委員会(IEICE CPSY)と共催し,他の研究会と共催・連催する場合も,CPSY と合同でセッションを構成した.- 第249回 2024/06/10(月)~02(水)@石和びゅーほてる および オンライン
HotSPA.IEICE CPSY,DC,RECONF と連催.若手奨励賞 2件. - 第250回 2024/08/07(水)~09(金)@あわぎんホール および オンライン
SWoPP.IEICE CPSY,DC,IPSJ HPC,OS,PRO,IEICE RECONF,JSIAM MEPA と連催,同時・連続開催.若手奨励賞2件. - 第251回 2024/12/16(月)~17(火)@沖縄産業支援センター および オンライン
IEICE CPSY,IPSJ HPCと連催・共催.若手奨励賞 1件. - 第252回 2025/03/21(木)~23(土)@おきえらぶフローラルホテル および オンライン
ETNET.IEICE CPSY,DC,IPSJ EMB,SLDM と連催・共催.若手奨励賞 1件.
2.シンポジウム・国際会議等の報告
- 2024/08/07(水)に開催された The 8th cross-disciplinary Workshop on Computing Systems, Infrastructures, and Programming (xSIG 2024) を主催した.
3.総括
2015年度から全ての研究発表会をIEICE-CPSYと連催しているが,2023年度もこれを継続した.また,2017年度からスタートしたxSIG(cross-disciplinary Workshop on Computing Systems, Infrastructures, and Programming)を引き続きPRO,HPC,OS 研究会と主催し,積極的に領域を跨いだ議論を展開する場を提供した.研究発表会については,発表・聴講に対する時間的・距離的ハードルを下げるため,ハイブリッド形式を主とすることで,オンライン参加の余地を残す方針をとった.2024年度の新たな試みとしては,IEICE-RECONFとの連催を増やし,交流の促進を図った.具体的にはまず,これまでCPSY/DCと連催していたHotSPAに新たにRECONFにも参加いただいた。またSWoPPにて,これまではCPSY/DCと合同でセッションを構成してきたが,今回新たにRECONFの発表も合わせてセッションを構成した.RECONFとのこれらの連携は次年度以降も継続予定であり,両研究会の交流促進により,今後も本分野の活性化ならびに人材育成に努めたい.
4.その他
昨年度に引き続き,他研究会との連携を進め幅広い議論を展開した.CPSYとの連携を継続し,両幹事団による拡大幹事会や,両運営委員・専門委員による拡大委員会を定期的に開催し,積極的に情報共有を行うとともに,運営の効率化に努めた.また,RECONFとの連携を上述のとおり強化した.SWoPPでは,第250回の開催を記念して,企画パネルを開催した.歴代主査をパネリストに迎え,本分野の今後に関するディスカッションを行った.昨今,国内でも半導体の重要性が見直されつつある状況において,ARCがスコープとする,デバイスからアプリケーションまで幅広い分野の横断的アプローチがより一層重要となっていることから,引き続き近隣分野との連携を拡大・強化しつつ,魅力的な技術交流の場を提供していきたい.◆システムソフトウェアとオペレーティング・システム(OS)研究会
[主査:品川高廣,幹事:松原克弥,川島英之,穐山空道,佐藤将也,深井貴明,吉村 剛]
1.定例の研究会活動報告
第163〜166回の研究発表会を開催した.
- 第163回 2024年5月30日(木)~ 5月31日(金) 大濱信泉記念館(沖縄県石垣市)(ハイブリッド開催)
システムソフトウェア一般に関する発表を募集し,耐故障性,仮想化,ストレージ,並行性制御,セキュリティ,保護,の6セッション計16件の発表がおこなわれた. - 第164回 2024年8月7日(木)~8月9日(金) あわぎんホール(徳島県徳島市)(ハイブリッド開催)
「並列/分散/協調処理に関するサマー・ワークショップ」の一部として複数研究会の共催の形態で開催した.セキュリティ,ストレージ・ネットワーク,クラウド・組み込み,分散処理・並行処理の4セッションで計15件の発表がおこなわれた. - 第165回 2024年9月19日(木)~9月20日(金) 大阪教育大学 天王寺キャンパス みらい教育共創館 (大阪府大阪市)(ハイブリッド開催)
IOT研究会と共催で開催した.システムソフトウェア一般に関する発表を募集し,OSセッション1,OS/IOT合同セッション2の計8件の発表がおこなわれた. - 第166回 2025年3月6日(木)~3月7日(金) けんしん郡山文化センター(福島県郡山市)第3会議室(ハイブリッド開催)
システムソフトウェア一般に関する発表を募集し,リアルタイムシステム・性能最適化,仮想マシン,セキュリティ,ネットワーク,メモリ,ストレージ6セッションで計20件の発表がおこなわれた.
2.シンポジウム・国際会議等の報告
- 第36回コンピュータシステム・シンポジウム 2024年12月2日(月)〜3日(火) 慶應義塾大学来往舎(神奈川県横浜市)大会議室(来往舎2階)(ハイブリッド開催)
コンピュータシステム全般に関する発表を募集し,4セッションで論文ありが11件,論文なしが1件,計12件の発表がおこなわれた.また,企業スポンサーがGold4社,Silver6社から応募があった。また,ポスター発表20件,招待講演2件,トップカンファレンス凱旋講演4件を実施した.
3.総括
今年度も引き続き研究発表会及びシンポジウムをハイブリット開催とした.現地参加者数や発表者数もコロナ禍前に戻りつつあり,一方でオンライン参加者も一定数いることから,このままハイブリッド開催を続けていく予定である.slackも参加者による使用は減少しているが,運営委員及び幹事の連絡用として有用であり,Googleドライブなども併用してオンラインツールを活用した効率的な研究会運営をおこなった.また,今回のコンピュータシステムシンポジウムでは,昨年に引き続き企業展示とスポンサー募集を実施して大変盛況であった.企業側からの要望に基づき,来年度からは応募時期に自由度が高い年間スポンサーという制度に移行することとした.昨年度実施した研究会ホームページのリニューアルは,引き継ぎも比較的うまくいって感じによる独立した更新が比較的簡単に行っていける体制の構築はできた.引き続き旧コンテンツ移行など更新作業を続けていく予定である.
◆システムとLSIの設計技術(SLDM)研究会
[主査:金本俊幾,幹事:岸田 亮,熊木武志,五十嵐友則,井上貴雄]
1.定例の研究会活動報告
以下に示す第206~208回の研究発表会を開催した.
- 第206回:発表件数 11件,11月7日,場所:キャンパスプラザ京都
テーマ:Work-in-progress (WIP) Forum 2024
協賛:IEEE Circuits and Systems (CAS) Kansai Chapter - 第207回:発表件数 61件,11月12日〜14日,場所:大分コンパルホールとオンラインのハイブリッド開催
テーマ:デザインガイア2024 -VLSI設計の新しい大地-
連催:VLD/ICD/DC/RECONF研究会
協賛:IEEE CASS Japan Joint Chapter
IEEE CASS Kansai Chapter
IEEE SSCS Kansai Chapter
IEEE CEDA All Japan Joint Chapter - 第208回:発表件数 52件,3月17〜19日,場所:おきえらぶフローラルホテル フローラル館 コンベンションホール
テーマ:組込技術とネットワークに関するワークショップ ETNET2025
合同:情報処理学会 EMB/ARC研究会
連催:電子情報通信学会 CPSY/DC研究会
2.シンポジウム・国際会議等の報告
以下のシンポジウムを開催した.
- DAシンポジウム2024: 8月28日〜8月30日,場所:鳥羽シーサイドホテル,発表件数 42件
3.総括
年初計画に上げた3回の研究会,1回のシンポジウムを無事開催した.
当研究会のフラグシップイベントであるDAシンポジウム2024は,昨年度のオンライン参加者が少数であったことから,昨年,一昨年のオンライン併催のハイブリッド形式から変更し,現地参加のみで開催した.しかしながら台風10号の影響により会場にたどり着けない可能性を考慮し,急遽オンラインでの発表及び聴講を可能とした.参加者数は,昨年度の102名に対して,107名とやや増加した結果となった.参加費の値上げで参加者の減少を見込んでいたが例年通りの参加者数であった.発表件数は昨年度の36件を上回る42件となった.招待講演として4件発表いただいたほか,リコンフィギャラブルシステム研究会の協力による特別セッションを設け,FPGAに関する3件の講演を実施いただいた.本シンポジウムの恒例となっているコンテストは,昨年度から新たな方向性を導入し,今年度は数独を速く解くシステム設計を課題とした.昨年度の1チームから,今年度は参加人数を増やすためにFPGA 競技だけではなくプログラミング競技のみの参加も認め,結果として4チームが参加した.
当研究会が単独開催した WIP Forum2024は,学生会員の活性化の取り組みとして3年前から新たに企画・実施している研究会イベントである.発表件数は11件,参加者は21名となり,発表者にとって,他大学や企業の研究者から様々な観点でのフィードバックを得る場となった.当研究会から3件,共催頂いたIEEE CASS Kansai Chapterから1件の表彰を行った.次年度も当研究発表会をDAシンポジウムと並ぶ,重要イベントとなるよう,強化・拡充していく.
オンライン・トランザクション TSLDMは,2刊 (Vol.17 June Issue, Vol.18 February Issue) を計画通り発行した.
4.その他
活動履歴や予定の詳細については,下記をご参照ください.
http://www.sig-sldm.org/
◆ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)研究会
[主査:片桐孝洋,幹事:滝沢寛之,中尾昌広,中島耕太,小松一彦,小林諒平]
1.定例の研究会活動報告
2024年度は,第194~198回の研究発表会を開催し,合計94件の発表があった.
- 第194回研究発表会は,5月8日(水)に東京工業大学で対面(視聴はオンライン)開催し,9件の発表,および1件の招待講演があり,110名の参加申込があった.
-
第195回研究発表会は,8月3日(木)~4日(金)の3日間,ARC,PRO,及びOSなどの研究会と共同で2024年並列/分散/協調処理に関するサマー・ワークショップ(SWoPP2024)として徳島にて対面(視聴はオンライン)で開催され,30件の発表があり,248名の参加申込があった.
-
第196回研究発表会は,9月30日(月)に九州大学で対面(視聴はオンライン)開催し,6件の発表があり,83名の参加申込があった.
- 第197回研究発表会は,12月16日(月)~17日(火)の2日間,沖縄で開催した.今回で2回目となるARCおよび電子情報通信学会CPSYと共同開催の研究会である.対面(視聴はオンライン)で開催し,21件の発表が行われ,121名の参加申込があった.
- 第198回研究発表会は,2025年3月17日(月)~19日(水)の3日間,北海道で対面(視聴はオンライン)により開催した.今回初となる,QS研究会との合同研究会を開催した.28件の発表が行われ,294名の参加申込があった.
これらの研究発表会では,GPUを用いた深層学習や高性能ストレージシステムなどの最先端の研究および技術開発の発表がなされた.加えて本年度も,次世代HPCシステムに関する研究が継続されていることが垣間見れた.また,量子コンピュータとHPCシステムを連携する研究,および量子コンピュータシステム開発の発表もあり,新しい研究の息吹を感じさせた.
また,2023年度の研究発表の中から,コンピュータサイエンス領域奨励賞2件,山下記念研究賞2件を推薦した.
2.シンポジウム・国際会議等の報告
本研究会は,ARC,PRO,OSと共同で,2024年8月にThe 8th cross-disciplinary Workshop on Computing Systems, Infrastructures, and Programming(xSIG2024)を主催した.本シンポジウムは,SWoPP内でハイブリッドにて開催された.本シンポジウムの特徴は,査読付きの会議であるが,予稿集を作成せず,将来の学術論文誌,国際会議での発表を妨げることなく,むしろそれをプロモートすることにある.また,若手研究者,特に学生の研究活動を支援することに力をいれている.xSIG2024では,26件の一般論文発表が行われた.
3.総括
HPC研究会の2024年度の5回の研究発表会は,前年に引き続き,現地開催,かつ視聴のみオンライン参加可能のハイブリッド形式とした.前年度より多くの方に参加いただき,本形式による開催は定着したものと考えている.今後も,ハイブリッド開催の実施形態の考慮は必要であると考え,状況に応じ柔軟に対応していく予定である.
HPC分野では,引き続き「富岳」を用いた計算科学分野とコンピュータサイエンス分野の双方で,大規模HPC環境を効率的に利用した科学技術研究成果が創出されている.また,次期システムである「富岳NEXT」に向けたフィージビリティスタディも最終年度となり,多くの関連発表がなされた.また,Society 5.0の人工知能・機械学習技術の研究,特にLLMなど生成AI技術の進展がめざましく,HPCの観点で多くの研究発表がなされた.さらに本年度は,QS研究会との合同研究会を新設し,HPCの観点での量子コンピュータ研究も進展している.
このように変化する技術情勢の中で,従来のシステムの省電力性能に加えて,新しいHPCシステムの研究が引き続きHPC分野に期待されている.
4.その他
HPC研究会では,2018年に打ち出した ①学生,若手研究者のEncourage,②HPC研究に関する成果の産業応用,計算科学を含む実アプリへの展開の促進の方針がある.この方針に基づき2021年度に学生発表を対象とした賞を創設し,引き続き運用を続けている.2023年度はARCとCPSY研究会との共催研究会,本年度にはQS研究会との共同研究会を実施した.今後も新しいHPC研究の活動を広げていく活動を行い,HPC分野の発展に尽力していく所存である.
◆プログラミング(PRO)研究会
[主査:森畑明昌,幹事:安部達也,今井敬吾,上野雄大,鵜川始陽,塚田武志,中野圭介,平石 拓,堀江倫大,水島宏太,横山大作]
1.定例の研究会活動報告
第149-153回の研究発表会を開催した.このうち,第150回(8月,SWoPP 2024)が他研究会との共同開催であり,残りの4回が単独開催である.いずれの回も現地とZoomによるハイブリッド開催とした.
招待講演2件を含む計40件の発表があった.1件あたり原則として発表25分,質疑・討論20分の時間を確保し,参加者が研究の内容を十分に理解するとともに,発表者にとっても有益な示唆が得られるように努めた.また,学生や萌芽的な研究等の発表を促進することを目的に,発表20分,質疑・討論10分の「短い発表」もあわせて募集し,13件の発表があった.さらに,学会の支援する若手研究者招待講演制度を利用し,第149回と第153回において60分の特別講演をそれぞれ1件実施した.
若手を対象としたコンピュータサイエンス領域奨励賞の受賞者を2名,コンピュータサイエンス領域功績賞の受賞者を1名選出し,第151回研究発表会の場で表彰した.
研究発表会は「情報処理学会論文誌 プログラミング(PRO)」と連携している.論文誌に投稿された論文は,まず研究会で発表され,発表会の直後に開催される論文誌編集委員会において議論し,査読者を定めて本査読を行う.2024年度の投稿件数は23件であった.なお,査読に際しては,論文の欠点を見つけて評価する減点法ではなく,論文の長所を見つけて評価する方針を徹底している.
2.シンポジウム・国際会議等の報告
情報処理学会4研究会(ARC,HPC,OS,PRO)の共同主催により,xSIG 2024を,8月7日に現地(あわぎんホール)およびオンラインのハイブリッド形式で開催した.
日本ソフトウェア科学会インタラクティブシステムとソフトウェア研究会の主催により12月11〜13日に開催された第32回インタラクティブシステムとソフトウェアに関するワークショップ(WISS2024)に協賛した.
3.総括
発表件数は,2023年度がやや少なめであったが,2024年度は例年通りの水準に回復した.今後もより積極的な広報や開催時期・開催場所(オンライン化も含む)の検討などにより,発表件数の維持・増加に努める方針である.
4.その他
2025年度もこれまで同様に5回の研究発表会を予定している.アフターコロナにおける望ましい開催形態を模索中だが,本研究会においては気軽な参加・発表と研究者の相互交流の場の提供という双方を実現する観点から,オンライン・対面での参加を両方とも促進したいと考えている.◆アルゴリズム(AL)研究会
[主査: 小野廣隆,幹事: 大舘陽太,小林靖明,中島祐人]
1.定例の研究会活動報告
研究発表会を5回(第198~202回)開催し,全体で49件 (内,招待講演2件) の発表があった.
- (198回) 2024年5月8-9日(水・木)6件.京都大学 吉田キャンパス
- (199回) 2024年9月5-6日(木・金)4件.広島工業大学 五日市キャンパス + オンライン
- (200回) 2024年11月26-27日(火・水)11件 (+招待講演1件).室ガス文化センター
- (201回) 2025年1月14-15日(火・水)13件 (+招待講演1件).くまもと県民交流館パレア
- (202回) 2025年3月18日(火)13件.福井工業大学 福井キャンパス
このうち,
第198回は電子情報通信学会コンピュテーション研究会 (COMP) との連催,
第199回は第21回情報科学技術フォーラム (FIT2024) および電子情報通信学会コンピュテーション研究会 (COMP) との共催,
第200回は電子情報通信学会の回路とシステム研究会 (CAS) およびシステム数理と応用研究会 (MSS) との連催,
第201回は人工知能学会の人工知能基礎問題研究会 (FPAI) との併催である.
4研究会との併催は数年前から継続しており,隣接研究分野の研究会と共同での研究会開催が定着している.第200回では,金沢大学の浅野哲夫教授に“輸送問題:新たなモデル“,第201回では熊本大学の佐竹翔平准教授に“圧縮センシングとRamsey理論の交叉点 -RIP行列とRamseyグラフ-“と題して招待講演をしていただいた.また,第202回については福井工業大学 AI&IoTセンターとの共催として開催された.
2.シンポジウム・国際会議等の報告
アルゴリズム研究会では,韓国における同分野の研究コミュニティと連携して,Korea-Japan Joint Workshop on Algorithms and Computation (アルゴリズムと計算理論に関する日韓合同ワークショップ) を過去20年以上に渡り開催している.2024年度においては,Sungshin Women’s UniversityのSang Duk Yoon氏が中心となり,第24回目のワークショップを8月2・3日にSungshin Women’s University (韓国ソウル市) にて開催した.日本や韓国を中心に約70名が参加し,離散最適化・文字列処理・計算量解析・幾何アルゴリズムなど多岐にわたる分野で26件の発表があり,活発な議論が行われた.また,オーストリア科学技術研究所 (Institute of Science and Technology Austria) のHerbert Edelsbrunner教授による基調講演“Merge Trees of Periodic Filtrations”と東京大学の定兼邦彦教授による基調講演“Introduction to Secure Computation”が行われた.3.総括
2024年度はFIT2024の併催として行われた第199回を除いて,すべて対面のみで研究発表会を行った.オンラインを併用しなかったために発表者・参加者数の減少の可能性があったが,実際にはそのようなことはなく,例年度以上の盛り上がりをみせた.本研究会が研究対象とするアルゴリズムの研究は長い歴史を持ち,日本国内における理論計算機科学の理論的基盤の大きな一翼を担っているが,実応用・社会への波及という観点からは隣接分野への展開もより一層重要となっている,来年度以降も引き続き,連催・併催での研究会や招待講演を通じて応用分野との連携を深めるとともに,国際連携活動も継続していきたいと考えている.
◆数理モデル化と問題解決(MPS)研究会
[主査:渡邉真也,幹事:笹山琴由,関嶋政和,花田良子,林 亮子,吉本潤一郎,松田 健,高田雅美]
1.定例の研究会活動報告
- 第148回 MPS研究会(2024/06/20-2024/06/22, 沖縄)
IPSJ BIO研究会,IEICE NC研究会,IBISML研究会と併催の形で沖縄科学技術大学院大学にて実施.
ベストプレゼンテーション賞 3件. - 第149回 MPS研究会(2024/07/22, 米国 ラスベガス)
the 2024 International Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications (PDPTA'24) の併設ワークショップ ‶Mathematical Modeling and Problem Solving’’ として開催. - 第150回 MPS研究会(2024/09/05, オンライン)
完全オンラインにて実施. - 第151回 MPS研究会(2024/12/9-2024/12/10, 大阪)
関西大学にて実施.ベストプレゼンテーション賞 2件. - 第152回 MPS研究会(2025/03/22-2025/03/23, 北海道)
北海道 室蘭市 きらん にて実施.ベストプレゼンテーション賞 1件.
2.シンポジウム・国際会議等の報告
3.総括
4.その他
◆組込みシステム(EMB)研究会
1.定例の研究会活動報告
第66回~68回の研究発表会を開催.組込みシステムは情報処理各分野の横断的分野であることから,本年度も一部は各関連研究会との共催,およびEdgeTech+ 2024との併設開催として研究発表会を実施した.
- 第66回研究会(7月19日,ハイブリッド):単独開催.招待講演2件,口頭発表5件
- 第67回研究会(11月20日 - 21日):EdgeTch+ 2024との併設開催.招待講演1件, 口頭発表20件
- 第68回研究会 (3月17~19日,ハイブリッド):ETNET2025として,システム・アーキテクチャ研究会,システムとLSIの設計技術研究会,および電子情報通信学会コンピュータシステム研究会,ディペンダブルコンピューティング研究会と共催,口頭発表16件.
2.シンポジウム・国際会議等の報告
- APRIS2024 (11月5日~6日, 併設イベント:ロボットコンテスト 11月2日~4日)
組込みシステム研究会の運営委員,Prince of Songkla Universityを中心としたメンバーで実行委員会を構成し,主に日本,タイの2か国(その他,台湾,中国,香港,イタリア)からの参加者で英語講演によるシンポジウムAPRIS2024を開催した.前半3日間は学生や若手技術者がデザイン思考を取り入れたモデルベース設計・チーム開発手法を学びながらロボットサービスのアイデアをまとめるロボットコンテスト,後半の 2日間の本会議は基調講演・招待講演・研究報告・パネルディスカッションからなる対面メイン(一部オンライン形式)のハイブリッド形式での国際学会とした.
本会議では,ロボット・IoT関連の技術に関する講演が行われた.基調講演2件,招待講演3件,研究論文発表はRegular Paper 6件,Work In Progress Paper 18件,ポスター 8件で,発表件数は合計32件と,昨年の発表件数と同じであった.本会議の参加人数は73名であり,活発に交流がなされた.本会議の参加登録人数(国籍)はフランスから1名、タイから19名、日本から41名、韓国から1名、中国から4名、Malaysiaから1名、ベトナムから1名、インドネシアから1名、台湾から1名であり活発に研究情報の交流がなされた.
ロボットチャレンジはドローン応用開発に関するチュートリアルおよびプロジェクト形式演習(PBL)を実施した.PBLのチャレンジャーは、タイから4名と日本から4名(修士2名、学部生2名)の合計8名が混合で4人の学生チームを2チーム作り、プロジェクトを遂行した.また、PBLではデザイン思考を講義し、PBLでは講義に基づいて顧客と開発チームのロールプレイングをしつつ顧客からの要求を引き出し,整理,それに基づき各チームで考えた応用を実現する自律航行システムの開発を行った.今年度から導入した協調シミュレーション環境である箱庭上で各応用を実現した.最後にシミュレーション環境でのデモンストレーションと開発成果のプレゼンテーションを実施した.また今年度からプロジェクト推進における異分野、異文化コミュニケーションの大切さや難しさを理解し、実プロジェクトで実践できるようにすべく、講義と演習を最初に実施し、PBL終了後に振り返りを実施した.本コンテストは組込みシステムをモデルベース・モデル駆動で設計開発するための技術の向上に資するものであり、文部科学省で推進されたenPiT-Embの教育プログラムの一環として行われた.
3.総括
研究活動の国際化を考慮して立ち上げたAPRISが7回目の開催を迎え,前回同様の論文数を集めることができた.一方,参加者は若干減ったものの,海外からの参加者は増えた.研究発表会では,本研究会の特徴の一つである「短い発表」のカテゴリを実施し,研究初期段階のアイデアの発表を推奨し,APRISと研究発表会の棲み分けができている.EdgeTech やETNETなど,共催やイベントがある研究会は投稿が多かった.
4.その他
2024年度は,ほぼ「対面での開催」としたが,発表数は春の研究会以外は比較的堅調であった.今後,WGなどの立ち上げ,ポスター発表の再実施,発表の表彰など検討し,若手の奨励,参加・発表数の増加に努めたい.
◆量子ソフトウェア(QS)研究会
1.定例の研究会活動報告
- 第12回の研究発表会を6月27日および6月28日に開催した.一般の発表は16件で,2日間の開催として1件あたり30分(発表25分,質疑5分)のプログラム構成とした.招待講演を2件設け,量子アニーリングについて門脇正史氏(産総研/デンソー),量子シミュレーションのためのアルゴリズムについて水田郁氏(東京大学)に講演いただいた.参加登録者は98名,現地参加者は58名で,活発に質疑が行われ有意義な議論が多く見られた.
- 第13回研究会を,10月28日(月)および29日(火)に開催した.ハイブリッド開催とし,会場には六本木ヒルズ森タワー18階 株式会社メルカリ イベントスペースを利用した.14件の研究発表があった.さらに,招待講演を2件設け,量子HPC連携プラットフォームを構築するJHPC-quantumプロジェクトについて佐藤三久氏(理化学研究所)に,文科省調査研究新計算原理チームの報告について天野英晴氏(東京大学)に講演いただいた.114名の参加登録があり,有意義な議論が活発に行われた.1日目には懇親会を開催し,32名の参加があり,うち5名が学生であった.
- 第14回研究会を3月17日(月)から19日(水)にかけて開催した.QS研究会として初の共催研究会をHPC研究会と実施した.対面・オンラインのハイブリッド開催とし,対面会場として北海道大学・学術交流会館を使用した.HPC,QS両研究会からそれぞれ28,33件の発表があり,対面195名,オンライン50名が参加した。1,3 日目はそれぞれQS,HPC研究会からの発表とし,2日目は両研究会の発表の混成とした.2日目夜の懇親会には約100名が参加し盛会であった.
2.シンポジウム・国際会議等の報告
特に実施しなかった.
3.総括
今年度も3回の研究発表会を実施し,形態は,昨年度同様,ハイブリッド開催だが発表は原則対面のみとした.それぞれの会において発表および質疑そして懇親会は活況を呈し,当該分野のコミュニティの形成が力強く促進されていると感じられた.また,ハイパフォーマンスコンピューティングと量子コンピューティングの融合が新たな潮流となりつつある中で,第14回量子ソフトウェア研究会と第198回ハイパフォーマンスコンピューティング研究会の共催が実現したことは極めて時宜に適ったものであり,200名近い現地参加者をみたことはその証左といえる.登録会員数は2025年3月の時点で196名となり,研究会発足後5年目においても増加の傾向は維持されている.
4.その他
2025年度も,3回の研究発表会を6月10月3月にそれぞれ2日間の日程で開催する予定である.また,HPC198QS14合同研究発表会の非常な盛会を受けて,2026年3月のQS研究会もHPC研究会と共催することを計画しており,さらなる連携を追求していきたい.
情報環境領域
◆マルチメディア通信と分散処理(DPS)研究会
[主査:菅沼拓夫,幹事:後藤佑介,川上朋也, 孫 晶鈺,坂本真仁,倉田真之]
1.定例の研究会活動報告
2.シンポジウム・国際会議等の報告
3.総括
◆ヒューマンコンピュータインタラクション(HCI)研究会
1.定例の研究会活動報告
第208~212回の研究発表会を開催した.各回の発表件数等は以下の通りである.
- 第208回(東京都 東京大学本郷キャンパス,オンラインのハイブリッド)2024/6/6-7
EC,日本バーチャルリアリティ学会,ヒューマンインタフェース学会デバイスメディア指向ユーザインタフェース専門研究委員会(SIGDeMO),映像情報メディア学会 ヒューマンインフォメーション研究会(HI),電子情報通信学会メディアエクスペリエンス・バーチャル環境基礎研究会(MVE)と共催もしくは連催
発表件数:35件(内HCI研21件) - 第209回(北海道 北海道大学)2024/7/22-23
発表件数:23件 - 第210回(兵庫県 淡路夢舞台国際会議場)2024/11/18-19
発表件数:33件(内HCI研19件) - 第211回(沖縄県 沖縄産業支援センター)2025/1/14-1/15
発表件数:48件 - 第212回(東京都 芝浦工業大学豊洲キャンパス,オンラインのハイブリッド)2025/3/5-7
招待講演:増井俊之氏(慶應義塾大学)「ニバーサルなユーザインタフェースを目指して」
発表件数:56件
2.シンポジウム・国際会議等の報告
インタラクション2025シンポジウム(2025/3/2-4)をCN研・UBI研・EC研・DCC研と共催した.今回のインタラクションは,EC研の三武 裕玄(明治大学)が大会長を担当し,学術総合センターで実施された.参加者数は800人超となり,大変活気のあるシンポジウムとなった.
3.総括
通常研究会での発表件数が,昨年の182件から195件(HCI研としては147件から167件)となり,微増した.一方でハイブリッド開催を実施していた2022年度の214件よりは少なく,対面形式を中心とした発表に移行した影響が考えられる.ただし依然として発表件数は高い水準にある.また,前述のようにインタラクション2025シンポジウムも,多くの参加者を迎え,大成功であった.このように,研究会活動は全体として引き続き活発である.
4.その他
2025年度も引き続き研究会の更なる活性化に努める所存である.
◆情報システムと社会環境(IS)研究会
[主査:居駒幹夫,幹事:荻野紫穂,柿崎淑郎,松澤芳昭,後藤 晶]
1.定例の研究会活動報告
第168-171回の研究発表会を開催した.4回の研究発表会を開催し計42件の発表があった.情報システムの分析・設計・開発・運用などに関して多様な研究報告が行われた.
- 第168回(6月15日,青山学院大学青山キャンパスおよびオンライン,発表8件)
- 第169回(8月22~23日,新潟工科大およびオンライン,発表16件)
- 第170回(12月14日,東海大学品川キャンパスおよびオンライン,発表9件)
- 第171回(3月4日,東京都立産業技術大学院大学およびオンライン,発表9件)
また,研究発表会の中で有識者による時宜にかなったテーマの招待講演や特集セッションを開催することにし,以下を実施した.
- 第168回 「論文執筆サポート」セッション
- 第169回 招待講演「町工場の業務プロセスをWebアプリケーションで包括的に最適化した事例と結果」長澤 博(株式会社テック長沢), 情報処理学会論文誌情報システム論文特集号の総括および同誌同特集号への掲載を目指した論文の執筆についての報告
- 第171回 特集セッション「若手の会」
2.シンポジウム・国際会議等の報告
第14回災害コミュニケーションシンポジウム(共同開催)
災害コミュニケーションシンポジウム
一般社団法人情報処理学会,セキュリティ心理学とトラスト(SPT)研究会,インターネットと運用技術(IOT)研究会と共に主催,グループウェアとネットワークサービス研究会(GN)が協賛,京都大学防災研究所が共催して,12月26日に行った.年末の多忙な時期にもかかわらず積極的な参加者を得ることができ,活発な議論が行われた.
3.総括
本年度も,情報システムにおける広い分野からの多くの種類の発表や議論が活発に行われた.当研究会が編集母体となる情報システム関連のジャーナル特集号の発刊も継続し,2013年度から始めた若手研究者を中心とする研究会(若手の会)での優れた発表に対する「若手の会奨励賞」も授与した.
◆情報基礎とアクセス技術(IFAT)研究会
[主査:金沢輝一,幹事:竹内孔一,高久雅生]
1.定例の研究会活動報告
第155-158回の研究会を開催した.
- 第155回 2024/06/28(金) 国立情報学研究所で開催
- 第156回 2024/09/11(水)~12(木) 淡路夢舞台国際会議場で開催
IEICE DE, IPSJ DBSと共同開催.学生奨励賞の表彰を実施. - 第157回 2024/12/26(木) オンライン開催
IEICE DE, IPSJ DBSと共同開催
「生成AI」,「データと人間社会」および「データアルゴリズム」の3セッション構成で開催.学生奨励賞の表彰を実施. - 第158回 2025/03/27(木) 筑波大学東京キャンパス文京校舎で開催 IPSJ DCと共同開催
2.シンポジウム・国際会議等の報告
2024年度は実施なし.
3.総 括
当研究会は「情報基礎(情報に関する原理の解明)」と「アクセス技術」をテーマに理論と実践の両面を一体とした研究を推進している.
近年は大規模言語モデルを応用した情報分析や対話型システムの研究発表が盛んとなっている.
2024年度は,分野の異なる研究者同士が意見を交換し合う機会である共同開催の研究発表会を増やすことができた.うち1回はあえてオンラインのみの開催とした.情報アクセス技術をテーマとする当研究会として今後もよりよいオンライン会合のノウハウの蓄積に積極的に取り組んでいきたい.
4.その他
活動の詳細を下記のWebサイトで随時報告しています.
http://ipsj-ifat.org/
研究会メンバに研究会の案内や関連情報を提供するメーリングリストを運用しています.
http://ipsj-ifat.org/index.php?id=11
◆オーディオビジュアル複合情報処理(AVM)研究会
[主査:松村誠明]
1.定例の研究会活動報告
2.シンポジウム・国際会議等の報告
3.総括
◆コラボレーションとネットワークサービス(CN)研究会
[主査:井上智雄,幹事:宮田章裕,川口信隆,角田啓介,市川裕介,磯 和之]
1.定例の研究会活動報告
2024年度は以下の通り,第123-125回の研究発表会を開催した.
- 第123回(2024年5月10日 オンライン開催):発表7件
SPTと共催,電子情報通信学会LOIS研究会と連催.
コラボレーション活性化のため、企画セッション「研究紹介ライトニングトーク」を実施. - 第124回(2025年1月23日- 1月24日 鹿児島県・アマホームPLAZA):発表64件
CDS,DCCと共催. - 第125回(2025年3月5日- 3月6日 東京都・芝浦工業大学豊洲キャンパスとオンラインのハイブリッド開催):発表12件
2.シンポジウム・国際会議等の報告
2024年度は以下の通り,シンポジウム2回,国際会議1回,ワークショップ1回を開催した.
- DICOMO2024シンポジウム(2024年6月26日 - 6月28日 岩手県・花巻温泉ホテル千秋閣):
発表223件,デモ16件,招待講演・特別講演9件
1997年より開催しているDICOMOシンポジウムは,DPS,MBL,CSEC,ITS,UBI,IOT,SPT,CDS,DCCと共催である.
- 第30回コラボレーション技術とソーシャルコンピューティングに関する国際会議(CollabTech2024)(2024年9月11日- 9月14日
スペイン・バルセロナ POMPEU FABRA大学)
論文発表22件(Full paper: 12件, Work in Progress paper: 10件),ポスター発表7件,招待講演2件
2005年に第1回を開催以来,継続的開催している国際会議CollabTech 2024は,標記研究分野における論文発表(Full paper 12件,Work-in-Progress paper 10件),ポスター発表(7件)および招待講演2件のプログラムを構成し,8カ国から54人(うちオンライン5人)の参加を得て開催された.
- コラボレーションとネットワークサービスワークショップ2024(2024年11月21日-11月22日 石川県・吉田屋山王閣):
発表30件(査読付き論文3件,一般論文20件,ポジションペーパー4件,国際会議報告3件)
コラボレーションとネットワークサービスワークショップは,通算では第21回となる,CN研究会コミュニティでは恒例の行事である.研究会形式で30件の発表を2泊3日のプログラムで構成し,41名の参加者を得て開催された.
- インタラクション2025(2025年3月2日-3月4日 東京都・学術総合センター):
一般講演18件,インタラクティブ発表 294件
1997年より開催しているインタラクションシンポジウムをHCI,UBI,EC,DCCと共催した.
29回目となる「インタラクション2025」は,招待講演,登壇発表,インタラクティブ発表(デモ),インタラクティブ発表(ポスター)で構成され,登壇発表25件と,インタラクティブ発表(デモ)180件,インタラクティブ発表(ポスター)90件が採択された.773名の参加者を得て開催された.
3.総括
本研究会は,1992年に研究グループとして発足以来,人と人をつなぐコラボレーション技術に関して,理論から応用,情報科学から社会科学と幅広い学際的研究活動を活発に推進してきた.昨年度より昨今の技術の進歩を踏まえ,研究会名称を「コラボレーションとネットワークサービス研究会」に変更し,心理学をはじめとする他分野も含めた研究者が多様なコラボレーションを実現できる環境作りにより一層注力している.
本研究会では,定例研究会以外にも,合宿形式のワークショップ(CNワークショップ),国際会議(CollabTech),2回の研究会合同シンポジウム(DICOMO,インタラクション)を主催している.今年度はオンライン開催,現地開催,オンラインと現地のハイブリッド開催が混在した.オンライン・オフライン双方に長所と短所があるが,コロナ禍から社会が徐々に正常化している現状から,今後は現地開催が増えるとともに,オンラインやハイブリッドは参加の裾野を広げる手段として有効活用していくことになると考える.本研究会はまた,論文誌ジャーナル特集号を発行しており,令和6年度特集号においても多くの論文(12件)を採録した.
4.その他
研究会関連メンバへの関連情報提供サービスとして,毎月メーリングリストによるニュースレターを発行している.またSlackチャンネルにおいても様々なイベント情報などの周知を随時実施している.
◆ドキュメントコミュニケーション(DC)研究会
[主査:菅沼 明,幹事:秋元良仁,天笠俊之,高橋慈子]
1.定例の研究会活動報告
今年度は,4回の研究会を開催し,27件の研究発表があり,そのうち2件の招待講演であった.
- 第133回研究会
日時:令和6年7月11日(木)~12日(金)
場所:御影公会堂 301集会室
電子情報通信学会ライフインテリジェンスとオフィス情報システム研究会(LOIS)と連催
テーマ:ライフログ活用技術,オフィス情報システム,ドキュメントのデジタル化,行動認識/行動推定と情報通信システムおよび一般
- 第134回研究会
日時:令和6年11月29日(金)
場所:オンライン開催(Zoom)
テーマ:ドキュメントを用いたコミュニケーションおよび一般
- 第135回研究会
日時:令和7年1月24日(金)
場所:オンライン開催(Zoom)
テーマ:ドキュメントのアクセシビリティおよび一般
- 第136回研究会
日時:令和7年3月27日(木)
場所:筑波大学東京キャンパス文京校舎118講義室
情報処理学会情報基礎とアクセス技術研究会(IFAT)との連催
テーマ:ドキュメントコミュニケーション分野一般
2.シンポジウム・国際会議等の報告
2024年度は実施なし.
3.総括
4.その他
◆モバイルコンピューティングと新社会システム(MBL)研究会
[主査:吉村 健,幹事:田村孝之,廣森聡仁,米澤拓郎, 荒川 豊,長谷川達人,西村康孝,北出卓也]
1.定例の研究会活動報告
第111-114回の研究発表会を開催した.
- 第111回研究発表会 5月15日〜17日 現地開催のみ 沖縄県青年会館
合同開催:情報処理学会マルチメディア通信と分散処理研究会(DPS),高度交通システム研究会(ITS)
連催:電子情報通信学会センサネットワークとモバイルインテリジェンス研究会(SeMI) - 第112回研究発表会 9月26,27日 現地開催のみ 愛媛大学城北キャンパス
合同開催:情報処理学会コンシューマ・デバイス&システム研究会(CDS),ユビキタスコンピューティングシステム研究会(UBI),高齢社会デザイン研究会(ASD)
※2022年度優秀論文,優秀発表,奨励発表の表彰式を実施 - 第113回研究発表会 11月5日~7日 現地開催のみ WiP 新和歌ロッジ(5日),研究発表会 和歌山県民文化会館大会議室(6日,7日)
合同開催: 情報処理学会高度交通システムとスマートコミュニティ研究会(ITS) - 第114回研究発表会 2月27日,28日 現地開催 大阪大学 中之島センター 10F 佐治敬三メモリアルホール
合同開催:情報処理学会ユビキタスコンピューティングシステム研究会(UBI)
連催:電子情報通信学会センサネットワークとモバイルインテリジェンス研究会(SeMI)
共催:大阪大学D3センター
本年度の定例研究会は計画通り4回実施した.MBL枠で申し込みされた発表件数(招待講演除く)は 81件(5月: 16件,DICOMO: 35件,9月: 11件,11月: 11件,3月: 8件)であり,活発な研究発表が行われている.2024年度は優秀論文4件,優秀発表4件,奨励発表8件,WiP奨励賞1件を選出し,研究発表の奨励 と会員拡大に努めている.
2.シンポジウム・国際会議等の報告
- マルチメディア,分散,協調とモバイル(DICOMO2024)シンポジウム
6月26日~28日 現地開催のみ 花巻温泉
共催:情報処理学会マルチメディア通信と分散処理(DPS)研究会,グループウェアとネットワークサービス(GN)研究会,コンピュータセキュリティ(CSEC)研究会,高度交通システムとスマートコミュニティ(ITS)研究会,ユビキタスコンピューティングシステム(UBI)研究会,インターネットと運用技術(IOT)研究会,セキュリティ心理学とトラスト(SPT)研究会,コンシューマ・デバイス&システム(CDS)研究会,デジタルコンテンツクリエーション(DCC)研究会,IoT行動変容学(BTI)研究グループ
3.総括
2024年度は,研究発表の場は完全に現地主体へとなるとともに発表件数も増加傾向となり,活発な意見交換が見られた.また,論文誌特集号の企画についても滞りなく進めた.25年度はICMU2025の開催が予定されており,国内外の研究者相互の交流ならびに大学と産業界の連携のための意見交換の場を積極的に提供できると考えられる.今後も,これらの交流で培われた研究者・開発者間の人的ネットワークを基軸に,研究会をさらに充実・発展させていきたい.
◆コンピュータセキュリティ(CSEC)研究会
[主査:千田浩司,幹事:三村 守,沖野浩二,井口 誠, 森 達哉,矢内直人, 掛井将平]
1.定例の研究会活動報告
第105回~第108回の研究発表会を開催した.
- 第105回 2024年5月30日~31日(とりぎん文化会館 (鳥取県民文化会館) +オンライン,発表28件)
合同開催:IOT研究会
連催:情報通信マネジメント研究専門委員会(ICM) - 第106回 2024年7月22日~23日(札幌コンベンションセンター,発表89件)
合同開催:SPT研究会
連催:情報セキュリティ研究専門委員会(ISEC),
連催:技術と社会・倫理研究専門委員会(SITE),
連催:情報通信システムセキュリティ研究専門委員会(ICSS),
連催:マルチメディア情報ハイディング・エンリッチメント研究専門委員会(EMM),
連催:ハードウェアセキュリティ研究専門委員会(HWS),
連催:バイオメトリクス研究専門委員会(BioX) - 第107回 2024年12月3日~4日(福井県繊協ビル,発表37件)
合同開催:SPT研究会,EIP研究会 - 第108回 2025年3月17日~18日(群馬県庁昭和庁舎,発表72件)
合同開催:DPS研究会
各研究発表会にてそれぞれ数件のCSEC優秀研究賞を授与した.また,推薦論文制度の規程に基づき対象論文の推薦を行った.加えて第108回より、学生の発表を対象とした「CSEC優秀学生研究賞」の表彰を行った.
2.シンポジウム・国際会議等の報告
- コンピュータセキュリティシンポジウム2024(CSS2024):
セキュリティ心理学とトラスト研究会(SPT)との共催で,マルウェア対策研究人材育成ワークショップ2024(MWS2024),プライバシーワークショップ2024(PWS2024),ユーザブルセキュリティワークショップ2024(UWS2024),OSSセキュリティ技術ワークショップ2024(OWS2024),ブロックチェーンセキュリティワークショップ2024(BWS2024),形式検証とセキュリティワークショップ2024(FWS2024),AIセキュリティワークショップ2024(AWS2024)と併催の形で,10月22日~10月25日に神戸国際会議場+オンライン(聴講のみ)にて開催した.
CSS全体の1051名,投稿数は269件であり,昨年度の参加者数959名,投稿数214件を大きく上回った.
CSSおよび各ワークショップの優秀な論文に対しては,各論文賞(CSS2024最優秀論文賞/優秀論文賞,CSS2024学生論文賞)やCSS奨励賞を授与した.
また,セキュリティ分野の著名な実務者を招いた基調講演を設けた. -
19th International Workshop on Security(IWSEC2024):
今回で19回目の開催となる国際会議であり,電子情報通信学会情報セキュリティ研究専門委員会(ISEC)との共催で,国立京都国際会館にて2024年9月17日~19日の日程で開催した.
21件のポスター発表に加え,47件の投稿論文から17件(採択率36.2%)の非常にレベルの高い論文を精選し,充実した内容の論文集が作成された(Springer LNCSシリーズで出版).日本を含む11ヶ国から計120名以上が参加し,国際色豊かな会議となった.また,3件の招待講演を実施し,活発な議論が行われた.さらに,併設イベントとして匿名化技術を競うコンテストiPWS Cupを開催し,日本を含む4ヶ国から計10チームが参加し,国際交流や技術力の向上につながった. -
マルチメディア,分散,協調とモバイル(DICOMO2024)シンポジウム:
10研究会と1研究グループが集い幅広い分野をカバーしたシンポジウムとして,2024年6月26日~28日に花巻温泉で開催した.
CSECからは7つのセッションに分けて発表が行われた(うち1つはSPT研究会との合同セッション).
また,CSECの発表から,2件の優秀論文賞が授与された. -
論文誌「サプライチェーンを安全にするサイバーセキュリティ技術」
サプライチェーンを安全にするサイバーセキュリティ技術をテーマとした特集号を企画した.
28件の投稿から19件(英語論文は11件)の論文を採録し,2024年9月に発行した.
2025年9月発行の予定で次の特集号「AI社会を安全にするコンピュータセキュリティ技術」を企画し,編集作業を進めている.
3.総括
定例研究会の発表件数は昨年度よりも増え,特に2024年7月開催の合同研究会(CSECは第106回)では発表件数が大きく増加した(67→89件).現地開催が通常になったことが大きいと考えられる.加えて,108回から学生向けにCSEC優秀学生研究賞の表彰を実施し、若手会員の活性化を行うこととした.
また,2024年10月に開催された国内シンポジウムCSS2024は,昨年度と比べ参加者数,発表件数ともに増加し.1000名を超える規模となった.
来年度も定例研究会,国内シンポジウム,国際会議の参加者数・発表件数の増加を含む,本研究会の活動をさらに活性化させるための施策を継続していく.また,本研究会の活動に留まらず,我が国のコンピュータセキュリティ分野全体の発展への貢献に努めていく.
◆高度交通システムとスマートコミュニティ(ITS)研究会
[主査:石原 進,幹事:佐藤健哉,白石 陽,鈴木理基,湯 素華,寺岡秀敏,吉廣卓哉]
1.定例の研究会活動報告
定例研究会:
- 第97回:2024年5月15日(木)~17日(金)/沖縄県青年会館
MBL研究会主幹.DPS,MBL研究会と合同,信学会SeMI研究会との連催.全53件(ITSは15件)の研究発表.口頭発表者の希望者による合同ポスターセッションを実施. - 第98回:2024年9月14日(土)/日本大学駿河台キャンパス(ハイブリッド)
信学会ITS研究会(連催),電気学会ITS研究会(共催・主幹)と連携開催.招待講演1件と全12件(IPSJは6件)の研究発表を実施. - 第99回:2024年11月5日(水)~7日(金)/和歌山市 新和歌ロッジ・和歌山県民文化会館
ITS主幹でMBLと共催.両研究会合わせて9件の一般研究発表と11件のWork-in-Progress(WiP)発表を実施.WiPは合宿形式で実施. - 第100回:2025年3月11日(火)〜12日(水)/同志社大今出川校地
単独開催.1日目に当研究会の研究発表会100回記念のパネルディスカッションを実施.歴代の主査が登壇,ITS関連研究の動向と将来像を議論.2日目の一般セッションでは全18件の研究発表.
毎年,定例研究会から優秀な論文や発表を選定している.2024年(第96~99回研究会)を通じて,研究会優秀論文6件,研究会優秀発表6件,研究会奨励発表5件,研究会WiP奨励発表3件を選定した.発表内容は自動車および自動車交通に加え,人,自転車,ロボット,鉄道,航空機,UAVへ広く移動体を対象としたテーマへと拡大している.また経路問題に量子計算を適用する研究が増加している.
2.シンポジウム・国際会議等の報告
- ITS研究フォーラム2025:2025年3月11日(火)/同志社大今出川校地(ハイブリッド)
ITS Japan,MBL,DPS,CN研究会協賛.「実用間近,自動運転テクノロジの今」をテーマに5件の招待講演,研究会表彰式を実施.54名が参加. - マルチメディア,分散,協調とモバイルシンポジウム(DICOMO 2024)シンポジウム:2024年6月26日(水)~6月28日(金)/花巻温泉 ホテル千秋閣
DPS,CN,MBL,CSEC,ITS,UBI,IOT,SPT,CDS,DCC合同シンポジウム.「デジタルが繋ぎ,デジタルが拓く,新たな世界」を統一テーマに,特別招待講演1件,招待講演8件,一般講演223件,デモ16件の研究発表を8パラレルセッションで実施.当研究会関連では,20件の一般講演,大野和則教授(東北大)による招待講演「実世界で活躍するタフなロボット×AIの研究:自動運転や災害対応ロボットから使役犬の能力の拡張」. - 論文誌特集号「多様なリアリティを繋ぎ・創るモバイルコンピューティングと高度交通システム」(2025年6月号掲載予定)
MBL研究会と共同で毎年論文誌特集号を企画.ゲストエディタに吉村健氏(NTTドコモ)を迎えた.15件の投稿に対し,9件を採録(採録率60%)ミクロ・マクロな観点での都市分析技術,乗用車や小型ロボットのための移動通信技術,バーチャル・リアリティと物理空間の相互作用に資するユーザインタフェースなど当初の狙いにそった論文を採択した上で,トラストや量子計算など本特集号のテーマと相補的なトピックも採択することができた.奥村貴史教授(北見工大)に感染制圧に向けた計測技術に関する技術論文を招待論文として寄稿いただいた.
3.総括
4回の定例研究発表会,シンポジウム,研究フォーラム,論文誌特集号を通して,高度交通システムとスマートコミュニティに関わる研究者の交流と意見交換の場を提供することができた.今年度は航空関連の発表が加わるなど本研究会が対象とする領域は益々広くなった.また,量子計算を使った研究は複数の研究機関を巻き込んで増加している.より多様な研究者との交流の場を形成し,本分野の研究の活性化に貢献していきたい.◆ユビキタスコンピューティングシステム(UBI)研究会
[主査:前川卓也,幹事:新井イスマイル,磯山直也,大越 匡,岩井将行,大西鮎美,中村優吾]
1.定例の研究会活動報告
第82-85回の研究発表会を開催した.
- 第82回研究発表会 2024年5月9日(木)~5月11日(土),屋久島環境文化村センター
※発表:19件 - 第83回研究発表会 2024年9月26日(木)~9月27日(金),愛媛大学城北キャンパス
※共催:高齢社会デザイン(ASD)研究会
※共催:コンシューマ・デバイス&システム(CDS)研究会
※共催:モバイルコンピューティングとパーベイシブシステム(MBL)研究会
※発表:53件(共催分を含む) - 第84回研究発表会 2024年11月18日(月)~11月19日(火),淡路夢舞台国際会議場
※共催:ヒューマンコンピュータインタラクション(HCI)研究会
※2024年度UBI研究会国際発表奨励賞(前期)の受賞式を実施
※発表:33件(共催分を含む) - 第85回研究発表会 2025年2月27日(木)~2月28日(金),大阪大学中之島センター 10F 佐治敬三メモリアルホール
※共催:モバイルコンピューティングと新社会システム(MBL)研究会
※連催:電子情報通信学会 センサネットワークとモバイルインテリジェンス (SeMI) 研究会
※発表:31件(共催分を含む)
2.シンポジウム・国際会議等の報告
- マルチメディア,分散,協調とモバイル(DICOMO2024)シンポジウム
2024年6月26日(水)~6月28日(金) 開催場所:花巻温泉
※共催:一般社団法人情報処理学会 マルチメディア通信と分散処理(DPS)研究会,コラボレーションとネットワークサービス研究会(CN)研究会,モバイルコンピューティングと新社会システム(MBL)研究会,コンピュータセキュリティ(CSEC)研究会,高度交通システムとスマートコミュニティ(ITS)研究会,インターネットと運用技術(IOT)研究会,セキュリティ心理学とトラスト(SPT)研究会,コンシューマ・デバイス&システム(CDS)研究会,デジタルコンテンツクリエーション(DCC)研究会 - インタラクション2025
2025年3月2日(日)~3月4日(火),学術総合センター内一橋記念講堂
※共催:ヒューマンコンピュータインタラクション(HCI)研究会,コラボレーションとネットワークサービス研究会 (CN),エンタテインメントコンピューティング(EC)研究会,デジタルコンテンツクリエーション(DCC)研究会 - Japan UBI Symposium 2025
設立20年を越えたことを記念してシンポジウムを開催.歴代主査がユビキタスコンピューティング研究の過去,現在,将来像を語るとともに、42件の最新の研究成果がポスター発表された.
3.総括
2024年度も4回の定例研究発表会を開催し,他分野や産業界との連携および,研究会内での学術的連携に力を入れた.前者としては,他研究会や他学会との研究会共同開催を通じて,本研究会関係者に対して多様な機会を創出できた.
研究会としても,分野を盛り上げるために,研究発表会での発表から,6件の優秀論文賞と,7件の学生奨励賞,1件の企業発表賞,8件のUBIヤングリサーチャー賞を選出した.また,国際発表奨励賞についても引き続き,学生に対してユビキタスコンピューティングシステム関連著名国際会議への参加をサポートし,有力国際会議における本研究コミュニティのプレゼンス向上につながった.さらに,UBI研究会の発足から約20年を記念してJAPAN UBIシンポジウム2025を開催した.歴代の主査らの講演や最新研究成果の発表の場を設け,会員らの懇親や連携の促進を図った.
4.その他
本研究領域における国際的なプレゼンスをさらに高めるために,学生や若手研究者の活躍に寄与する施策を推進する.特に,若手研究者による招待講演,引き続き実施する各賞の授与はこれにあたる.また,若手研究者による著名国際会議採録を支援するような講座の開催を行う.
産業界との接合を強力化するために,民間企業を研究会に引き込む施策を実施する.具体的には研究会に協賛制度を構築し,より多くの若手研究者を支援する仕組みやより良いジェンダーバランスに寄与しうる仕組み等を検討し,企業と大学の情報交換を緊密にする.
これまで10回以上にわたって継続している論文誌特集号は引き続き実施し,本分野の研究成果蓄積を狙っていきつつ,そうした成果が著名国際会議での発表につながるような施策を検討していく.
◆インターネットと運用技術(IOT)研究会
[主査:北口善明,幹事:大森幹之,小川康一,柏崎礼生,坂下 秀,櫻田武嗣,中村 豊,中山貴夫,藤原一毅,三島和宏]
1.定例の研究会活動報告
以下に示すように第65~68回の研究発表会を開催した.
- 第65回 2024年 5月30日 (木) ~ 31日 (金)
場所:とりぎん文化会館 (鳥取市) + オンライン
発表件数:一般10件 (全体: 一般26件, 招待講演2件)
※コンピュータセキュリティ (CSEC) 研究会と共催
※電子情報通信学会情報通信マネジメント (ICM) 研究会と連催 - 第66回 2024年 7月19日 (金)
場所:J:COM ホルトホール大分 (大分市) + オンライン
発表件数:一般6件, 招待講演1件 - 第67回 2024年 9月 19日 (火) ~ 20日 (水)
場所:大阪教育大学 天王寺キャンパス みらい教育共創館 (大阪市) + オンライン
発表件数:一般10件 (全体: 一般13件)
※システムソフトウェアとオペレーティング・システム (OS) 研究会と共催
※国立大学法人情報系センター協議会 (NIPC) 学術情報処理研究集会と連続開催 - 第68回 2025年 3月 3日 (月) ~ 5日 (水)
場所:アマホームPLAZA (奄美市) + オンライン
発表件数:一般32件 (全体: 一般69件)
※電子情報通信学会インターネットアーキテクチャ (IA) および技術と社会・倫理 (SITE) 研究会と連催
いずれの研究会においても,情報教育関連,インターネット運用技術,分散システム運用技術,ネットワーク構築,セキュリティ,性能評価,研究データ管理など,幅広いテーマで議論が行われた.研究会は現地開催が主ではあるが,昨年度に引き続きオンライン対応を併用した開催形態を維持した.
2.シンポジウム・国際会議等の報告
- 第17回インターネットと運用技術シンポジウム (IOTS2024)
本シンポジウムは,「AIによる人間中心のネットワーク構築を求めて」というテーマのもと,2024年12月 5日 (木) ~ 6日 (金) に東北大学 医学部 艮陵会館にて開催された (後援:東北大学大学院情報科学研究科,電子情報通信学会インターネットアーキテクチャ (IA) 研究会,ACM SIGUCSS Tokyo Chapter).今回のシンポジウムは,昨年に引き続き現地開催で,情報交換会も開催した.また,口頭発表のみオンラインでも配信するハイブリッド開催とた.
今回のシンポジウムは,論文発表9件,ポスター発表17件 (口頭・ポスターともに査読あり)で構成し,特別セッションとして,東京農工大学の山井 成良氏の司会による安東孝二先生の足跡を振り返りるセッションを企画した.この特別セッションでは、パネリストにユニアデックス株式会社の高橋 優亮氏,CO-CONV株式会社の丸山 伸氏,広島大学の西村 浩二氏の三名を迎え,残された我々が目指す運用管理について考える意見交換が多くの参加者間で行われた.
シンポジウム併設企画として企業展示を実施し,24社の企業様からのご出展をいただいた.プログラムにおいては両日ともに企業展示セッションコアタイムを設け,十分に企業展示ブースを見ていただけるようにした.また,シンポジウムでお馴染みの企業協賛の冠賞には,今年もアラクサラネットワークス株式会社に協賛いただき,現地での企業展示は盛況となった.
論文発表9件のうち,学生発表は4件であり,また,17件 (うち学生発表11件) のポスター発表となり,多くの学生にも参加いただいた.シンポジウム参加者は,現地179名 (一般参加者90名,出展企業参加者89名),オンライン9名となり,発表者と現地参加者を中心に密な議論が展開され,有意義な意見交換がなされたシンポジウムとなった. - 第14回災害コミュニケーションシンポジウム (DCS2023)
本シンポジウムは,2024年12月26日 (木) にオンライン + サテライト会場 京都大学防災研究所 (宇治市) として,セキュリティ心理学とトラスト (SPT) 研究会および情報システムと社会環境 (IS) 研究会との共同主催 (協賛:コラボレーションとネットワークサービス研究会 (CN) 研究会,共催:京都大学防災研究所) で,災害時の情報共有や課題などについて情報交換を行った.講演は,併設しているISCRAM勉強会やIFIPWG5.15およびITDRR2024の報告と,基調講演が4件であった.また,「阪神淡路大震災から30年:令和6年能登半島地震における災害対応」をテーマとしたパネルディスカッションを実施し,基調講演者とともに支援の課題点などに関して議論が行われた. - マルチメディア,分散,協調とモバイルシンポジウム (DICOMO2024)
本シンポジウムは,2024年 6月26日 (水) ~ 28日 (金) に花巻温泉 ホテル千秋閣 (花巻市) にて本研究会を含む10研究会の共催により開催された.本研究会に関連したテーマで4つのセッション (一般13件,招待講演1件) が開催された.招待講演として,中村 隆喜氏 (東北大学) に「データ駆動型社会を支える高信頼データ基盤を目指して」と題して講演をいただいた. - The 12th IEEE International Workshop on Architecture, Design, Deployment and Management of Networks & Applications (ADMNET2024)
本ワークショップはIEEE Computer Societyが主催し本会が後援する国際会議COMPSAC2024の開催日程 (2024年 7月 2日 (月) ~ 4日 (水)) に大阪市にて開催され,5件の採択論文が発表された. - 論文誌「気づきのあるネットワーク運用技術」特集
本特集号では前年末のインターネットと運用技術シンポジウム (IOTS2023) との連携を図っている.IOTS2023の「気づきのあるネットワーク運用技術を目指して」というテーマを受けて,論文誌として「気づきのあるネットワーク運用技術」という特集名を設定した.本特集号には7編の投稿があり,最終的に4編の論文を採録した (採択率57.1%).今年度も論文募集に先立って論文執筆アドバイスの取り組みを実施し,2編の論文に対してアドバイスを実施し,そのうちの1本が採録へとつながってたが,前年の取り組みと比較してアドバイス制度利用の件数自体も少なくなっていることから,十分な効果が得られたとはいい難い.なお,過去数年間でIOT研究会による特集号への投稿数は減少傾向にあるが,10件前後を集めることができており,IOT研究会による特集号は一定の評価を得ていると考えるが,投稿数の増加と採択率向上に関して検討する必要がある. - 論文誌トランザクション デジタルプラクティス「気づきのあるネットワーク運用技術」特集
論文誌特集号と同じテーマによる論文誌トランザクションにおける特集号を企画した.本特集号には10編の投稿があり,4編が条件付き採録に至っている (昨年度の特集号は6編の投稿に対して4編を採録).ただ,2021年度からの取り組みとして実施している”シンポジウムから特集号論文誌および特集トランザクション論文誌”という一連の流れを形成しているが,シンポジウムにて発表された論文を発展させた投稿が1編と少ない結果であり,投稿数向上に向けた取り組みを検討しつつ継続的に特集号企画を実施する予定としている.
3.総括
IOT研究会では,従来から計算機・ネットワーク運用技術に関する優れた研究を高く評価し,それらを論文化したり国際的に発表したりすることを推奨している.計算機やネットワーク運用上のベストプラクティスに関する研究発表に対する藤村記念ベストプラクティス賞 (2015年度創設) を今年度も授賞し,論文誌トランザクション ディジタルプラクティスへ推薦論文として投稿を促している.またIOT研究会元主査や幹事,運営委員が中心となって2014年度に設立したACM SIGUCCS東京支部も本研究会と連携して活動しており,このような研究活動をますます促進している.
今年度は,現地開催を主軸に,オンライン参加も可能とするハイブリッド開催による研究会開催を継続した.特に,発表者には原則現地発表として研究発表ごの意見交換を十分に実施できる方針としている.次年度以降も,現地参加を原則としたハイブリッド開催を堅持し,多くの参加者が集える研究会環境を提供できるように努めていく予定である.◆セキュリティ心理学とトラスト(SPT)研究会
[主査:島岡政基,幹事:金森祥子,畑島 隆,山本 匠,葛野弘樹]
1.定例の研究会活動報告
2024年度は,第55回~第58回の研究発表会を開催ならびに企画した.
- 第55回 2024 (令和6) 年05月10日 (金) オンライン
- 第56回 2024 (令和6) 年07月22日 (月)~07月23日 (火) 札幌コンベンションセンター(札幌市)
- 第57回 2024 (令和6) 年12月3日 (火)~12月4日 (水) 福井県繊協ビル(福井市)
- 第58回 2025 (令和7) 年03月6日 (木)~03月7日 (金) 沖縄県立美術館・博物館(那覇市)
2.シンポジウム・国際会議等の報告
2024年度は,次のシンポジウム,論文誌ジャーナル特集号,勉強会等を実施した.
- マルチメディア,分散,協調とモバイル (DICOMO2024) シンポジウム (共催)
2024 (令和5) 年06月26日 (水) ~06月28日 (金) 花巻温泉(花巻市) - コンピュータセキュリティシンポジウム(CSS)2024(共催)/ユーザブルセキュリティワークショップ(UWS)2024
2024 (令和6) 年10月22日 (火) ~10月25日 (金) 神戸国際会議場(神戸市)+オンライン - 第14回災害コミュニケーションシンポジウム
2024 (令和6) 年12月26日 (水) オンライン+京都大学防災研究所(宇治市) - 論文誌「社会的・倫理的なオンライン活動を支援するセキュリティとトラスト」特集
2024年12月発行 - ユーザブルセキュリティ・プライバシ(USP)論文読破会8
2024 (令和6)年11月13日 (水) NICTイノベーションセンター(東京都中央区)+オンライン
3.総括
従前に続き,セキュリティ分野を軸としつつヒューマンファクタやネットワーク・コミュニケーションなど,人間と情報システムの接点におけるセキュリティやトラストに関する幅広い知見共有・連携促進の場となることを志向して研究会活動に務めてきた.
今年度は必要に応じてハイブリッド開催としつつも,基本的に対面開催として実施した.これと関連の有無は確認できていないものの,総じて投稿件数増の傾向が顕著となり,結果的に研究会活動の更なる活性化と充実ができたと実感している.
4.その他
2025年度は,より一層に心理学・社会学も含めた幅広い分野間の知見共有・連携促進の場となることを志向していきたいと考えている.会員及び関係者の方々にはそのような場として本研究会を最大限活用いただきたく,またそのためにも是非積極的な論文投稿と参加をお願いしたい.
[主査:峰野博史,幹事:梶 克彦,神山 剛,神崎映光,齊藤義仰,鈴木秀和,中井一文,廣井 慧,森本尚之]
1.定例の研究会活動報告
第40-42回の研究発表会を開催した.
- 第40回研究発表会 2024年5月30日(木)~31日(金),京都大学宇治キャンパス,発表16件(特別講演1件)
- 第41回研究発表会 2024年9月26日(月)〜27日(火),愛媛大学,発表44件(デモ・ポスターセッション 5件)
※共催:MBL,UBI,ASD研究会
優秀発表賞,学生奨励賞,CDS活動貢献賞の表彰式を実施 - 第42回研究発表会 2025年1月23日(月)~24日(火),アマホームPLAZA(奄美市市民交流センター),発表61件
※共催:CN,DCC研究会
本年度は,前年度よりもさらに新型コロナウイルス感染症の影響が落ち着いてきたため,参加者の対面交流の促進を目的として,コロナ以前の形態である現地開催の研究発表会を3回開催することができた.いずれの研究発表会においても,企業,大学からコンシューマ・デバイスとシステムに関する幅広い分野の発表と活発な議論が行われ盛況であった.
2.シンポジウム・国際会議等の報告
- マルチメディア,分散,協調とモバイル(DICOMO2024)シンポジウム,2024年6月26日(水)~6月28日(金),花巻温泉(※共催:DPS,CN,MBL,CSEC,ITS,UBI,IOT,SPT,CDS,DCC各研究会)
- IEEE COMPSAC 2024: CDS 2024 (The 12th IEEE International COMPSAC Workshop on Consumer Devices and Systems held in conjunction with COMPSAC2024)2024年7月2-4日,Osaka, Japan
- 情報処理学会論文誌:コンシューマ・デバイス&システムの発行状況
計12編(Vol.14, No.2: 5編, No.3: 5編, Vol.15, No.1: 2編)
3.総括
2024年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響がさらに落ち着きつつあり,オンライン型から現地開催型での研究発表会の開催に変わり,コロナ禍以前の状況を思い出しながら進め,例年どおり3回の研究発表会を実施できた.全3回の研究発表会では,様々な企業からの発表および参加があり,実際に運用が開始されたコンシューマシステム,実践的なコンシューマデバイスやサービスに関する発表に対し活発な議論が行われた.なお,2023年度まで開催していた学生スマートフォンアプリコンテストは,近年のAIの進化によりスマートフォンアプリの開発が以前ほど困難なものではなくなったこと等から,当該コンテストに代わる新たな試みとして,9月の第41回研究発表会にてデモ・ポスターセッションを開催した.2024年度において,情報処理学会論文誌 コンシューマ・デバイス&システム(CDSトランザクション)は,12編の論文を採択し掲載済みである.2025年度は,引き続き対面実施を主体としつつ柔軟な対応で研究会の管理・運営を行う.
4.その他
2024年度は,引き続き従来の取り組みをさらに活性化させるとともに,コンシューマ向け技術や研究開発成果の応用的な発表をさらに受け入れ,学会活動を通じて学生と企業をつなぐ架け橋としての役割を担うような新たな取り組みにもチャレンジしたい.また,産学交流,技術者の相互情報交換の場の提供に加えて,研究発表会を通した地域活性化,さらなる学会会員数,研究会登録会員数,社会人・学生会員数,ジュニア会員数の増加につながるようなイベントを検討し,本研究会の更なる活性化を目指す.
◆デジタルコンテンツクリエーション(DCC)研究会
[主査:小川剛史,幹事:鈴木 浩,山崎賢人,義久智樹,渡辺大地]
1.定例の研究会活動報告
第37〜39回の研究発表会を開催した.
- 第37回研究発表会
2024年5月29日(水)
愛知工業大学本山キャンパス
発表件数:11件(DCC優秀賞2件)
- 第38回研究発表会(CGVI,CVIM共催,PRMU連催)
2024年11月29日(金),30日(土)
福井工業大学福井キャンパス
発表件数:40件(DCC 5件)(DCC優秀賞1件),招待講演2件
- 第39回研究発表会(CN,CDS共催)
2025年1月23日(木),24日(金)
アマホームPLAZA(奄美市市民交流センター)
発表件数:65件(DCC 13件)(DCC優秀賞2件,DCON推薦論文1件)
2.シンポジウム・国際会議等の報告
下記のシンポジウムおよび発表会を開催した.
- マルチメディア,分散,協調とモバイル(DICOMO2024)シンポジウム
2024年6月26日(水)~6月28日(金)
岩手県花巻温泉
※主催
マルチメディア通信と分散処理(DPS)研究会
コラボレーションとネットワークサービス(CN)研究会
モバイルコンピューティングと新社会システム(MBL)研究会
コンピュータセキュリティ(CSEC)研究会
高度交通システムとスマートコミュニティ(ITS)研究会
ユビキタスコンピューティングシステム(UBI)研究会
インターネットと運用技術(IOT)研究会
セキュリティ心理学とトラスト(SPT)研究会
コンシューマ・デバイス&システム(CDS)研究会
デジタルコンテンツクリエーション(DCC)研究会
IoT行動変容学(BTI)研究グループ - DICOMO2024併設デジタルコンテンツ制作発表会参加者募集
2024年6月26日(水)
岩手県花巻温泉
発表件数:4件(優秀賞1件) - インタラクション2025
2025年3月2日(日)〜3月4日(火)
学術総合センター内 一橋記念講堂
※主催
ヒューマンコンピュータインタラクション(HCI)研究会
コラボレーションとネットワークサービス(CN)研究会
ユビキタスコンピューティングシステム(UBI)研究会
エンタテインメントコンピューティング(EC)研究会
デジタルコンテンツクリエーション(DCC)研究会
- 情報処理学会論文誌:デジタルコンテンツ(DCON)の発行
23号 (Vol.12, No.2, Aug. 2024)採録:2件
24号 (Vol.13, No.1, Feb. 2025)採録:2件
3.総括
研究発表会については,6月に単独開催,11月にCGVI,CVIMとの共同開催,1月にCN,CDSとの共同開催で実施した.2023年度より,現地開催を中心に研究会運営を進めており,2024年度もその流れを引き継ぎすべて対面であった.本研究会では,通常の「研究発表」に加え,実際の制作物を持ち込み発表する「制作発表」の形式を取り入れている.今年度開催された全3回の研究発表会では,参加者がコンテンツに直接触れながら活発な議論を交わす様子が見受けられ,実体験の重要性が改めて明らかになった.2025年度においても,対面での開催を中心とした運営を予定している.また,DCC優秀賞を5件の発表が受賞した.今後も優れた研究発表に対してDCC優秀賞を授与し,本研究分野の活性化に努める方針である.
◆高齢社会デザイン(ASD)研究会
[主査:石川翔吾,幹事:松浦 博,青野修一,井上創造,清田陽司]
1.定例の研究会活動報告
2.シンポジウム・国際会議等の報告
3.総括
メディア知能情報領域
◆自然言語処理(NL)研究会
[主査:須藤克仁,幹事:井之上直也,齊藤いつみ,佐藤敏紀,萩行正嗣,藤田篤,吉永直樹]
1.定例の研究会活動報告
第260-263回の研究発表会を会場現地での発表を中心とするハイブリッド形式で開催した.
大規模言語モデルのトレンドが顕著となり,構築・解釈性・評価・応用など様々な研究発表が行われた.自然言語処理応用も広がりを見せており,医療や法律などの専門領域やマルチモーダル処理を指向した手法やリソース構築の試みが多く見られる.一方で自然言語処理・計算言語学の基礎的な研究発表も多く見られ,研究会としては分野の広がりと深みの両面で分野の発展を感じさせるものとなった.
- 第260回(2024年6月,北陸先端科学技術大学院大学 金沢駅前オフィス)
*【招待講演】言語進化の構成論:人間の言語に特有の性質はいかに生じるか:橋本 敬(北陸先端科学技術大学院大学) - 第261回(2024年9月,梅田スカイビル スカイルーム2)
*【招待講演】基盤モデル時代に言語で音声を処理したい:高道 慎之介(慶應義塾大学/東京大学) - 第262回(2024年12月,名古屋大学 オークマホール)SLP共催,SP・NLC連催
*【招待講演】日本における大規模言語モデルの研究開発動向:小田 悠介(国立情報学研究所) - 第263回(2025年3月,長崎原爆資料館ホール)NLC連催
*【招待講演】人工知能の歴史と哲学,デジタルゲーム:三宅陽一郎(スクウェア・エニックス)
2.シンポジウム・国際会議等の報告
なし
3.総括
学生を中心に若手研究者の発表が多く,定期的に開催される研究発表の場として活用していただけるようになった実感がある.学生主著発表の優秀研究賞受賞も半数以上を占め,若手奨励賞も含めて学生・若手の優れた研究発表が多く行われていることは喜ばしい.また分野横断的な研究発表も増えつつあり,招待講演も含めて充実したプログラム編成に繋がった.
4.その他
研究発表会の年間発表件数は2022年度以降増加を続けている.シングルトラックで発表や質疑の時間が十分にとれるという研究会のスタイルを活かして研究の議論を深める場として積極的にご活用いただけるようにしたい.発表件数の増加により運営委員による賞選考の負荷が徐々に大きくなってきているため,運営委員数の増員を進めている.今後も分野のさらなる活性化と研究会登録会員数の下げ止まり・反転増加に向け,大会などと比べて運営に小回りが利く研究会の利点をさらに活かせるようにしたい.研究発表会のハイブリッド開催についてはリモート発表・聴講に一定の需要があることから現状の方式を継続したい一方で持続可能性の懸念もあるため,運営負荷軽減策を講じたい.
◆知能システム(ICS)研究会
[主査:福田直樹,幹事:松崎和賢,松野省吾,菊地真人]
1.定例の研究会活動報告
- 第215回研究発表会では,電子情報通信学会,日本ソフトウェア科学会,人工知能学会,IEEE Computer Society Tokyo/Japan Joint Chapterとの連携によりSMASH24 Summer Symposiumとして2024年9月13日に福井市地域交流プラザで開催した.プライバシー面で有利な連合学習における属性欠損への対応の検討などの基礎的技術の検討から,人流解析・避難誘導への技術応用,教育分野への技術応用など多様なアプリケーションに対する知能システム的アプローチについて,シンポジウム全体で23件の発表と活発な議論が行われた.
- 第216回研究発表会は,電子情報通信学会,日本ソフトウェア科学会,人工知能学会,IEEE Computer Society Tokyo/Japan Joint Chapterとの連携によりSMASH25 Winter Symposiumとして2025年2月18日に名古屋工業大学で開催した.モンテカルロ木探索やマルチエージェント強化学習のメッセージ交換方式の検討などの基盤技術的検討から,環境騒音データに対するアプローチ,マルチエージェントパトロールや,AIエージェントによる合意形成支援論支援など多様なアプリケーションに対する知能システム的アプローチについて,シンポジウム全体で32件の発表と活発な議論が行われた.
- 第217回研究会は,人工知能学会,情報処理学会,電子情報通信学会,社会情報学会,日本ソフトウェア科学会の各研究会との共催で「社会システムと情報技術研究ウィーク in 那須 2025(WSSIT2025)」として2025年2月27日から3月1日までの期間でホテルラフォーレ那須の現地およびオンラインでのハイブリッド開催をした.大規模言語モデルによるストーリー生成や漫画キャラクター生成支援分野への応用をはじめ,ハルシネーションを抑える手法の検討やRobocupRescureに関する実装場の課題解決をはかる研究など,人間生活や社会システムと情報技術に関連する基礎的研究から応用研究に関する分野横断的な発表があり,イベント全体で計35件の発表があった.
2.シンポジウム・国際会議等の報告
2024年度は実施なし
3.総括
物価上昇による開催費用の高騰など課題のある難しい状況下でも,例年とおおむね同様の規模の活動を継続しながら,知能システムを核としてそれに関わる広い研究分野の研究者らとの連携や交流・議論の場を作ることができたと考えている.◆コンピュータビジョンとイメージメディア(CVIM)研究会
[主査:田中正行,幹事:田中賢一郎,高橋康輔,波部 斉,峰松 翼,浦西友樹,柴田剛志,槇原 靖,山下隆義]
1.定例の研究会活動報告
第238~241回の通常の研究発表会を下記のように開催した.各研究発表会では,テーマを設定し,テーマに沿った特別講演の企画や一般発表の募集を行った.
- 2024年5月:卒論, D論, キャリアプラン(PRMU連催)
- 2024年11月:生成・創造のためのCV/CG/DCC/PR技術(CGVI,DCC共催,PRMU連催)
- 2025年1月:医用・健康のためのCV/PR/XR技術 (PRMU,MVE連催,SIG-MR合同開催)
- 2025年3月:基盤モデルとその応用(PRM,IBISML連催)
2023年度より,内容の充実や参加者数の増加を図るため,すべての研究会を電子情報通信学会PRMU研究会との連催としている.
各研究発表会では,研究者の注目を集めているテーマを毎回一つ取りあげ,チュートリアル講演を実施している.今年度のテーマは以下の通りである.チュートリアル講演のスライドは研究会Webページで広く公開し,チュートリアル講演の動画を CVIM 研究会登録者限定で公開している.
- 2024年5月:一人称視点映像解析の基礎と応用
- 2024年11月:実世界、3D、ロボティクスと言語理解 ~ 画像と言語の理解を超えて ~
- 2025年1月:3D Gaussian Splattingによる高効率な新規視点合成技術とその応用
- 2025年3月:画像認識における基盤モデル
2.シンポジウム・国際会議等の報告
第27回画像の認識・理解シンポジウム(MIRU2024)を,8月6-9日の4日間,熊本城ホールとオンラインのハイブリッドで開催した.
電子情報通信学会PRMU研究会との共催であり,約1400人の参加者があった.
FIT2024(9月4-6日)においては,イベント企画として「生成AI」を企画した.この企画はPRMU研究会との共同企画であり,本テーマに基づく3件の招待講演を企画した.さらに,トップカンファレンスセッションの推薦リストを作成した.
3.総 括
卒論・D論セッション,ポスターセッション・奨励賞,チュートリアルなど,研究者育成の活動を重視してきた.コンピュータビジョン分野のトップカンファレンスに採択される日本人若手研究者の数は増加傾向にあり,本研究会の現在までの取り組みもその一因となっていると考えられる.
◆グラフィクスとCAD(CG)研究会
[主査:森島繁生,幹事:櫻井快勢,久保尋之,佐藤周平,石川知一,小山裕己]
1.定例の研究会活動報告
第194-197回の研究発表会を以下の要領で開催した.
- 第194回研究発表会
2024年6月29日(土)
会場:東洋大学
テーマ:CG教育および一般
発表件数:7件,招待講演1件 - 第195回研究発表会
2024年9月8日(日)
会場:東洋大学
テーマ:CG/CV分野の技術研究からのビジネスアイデア創出や産学連携の活性化
発表件数:6件,特別セッション1件 - 第196回研究発表会(CVIM/DCC/PRMU共催)
2024年11月29日(金),30日(土)
会場:福井工業大学 福井キャンパス
テーマ:生成・創造のためのCV/CG/PR/DCC技術
発表件数:43件(CG研究会6件) - 第197回研究発表会
2025年3月5日(水),6日(木)
会場:株式会社エクサウィザーズ セミナールーム
テーマ:光学が切り開くCG/CVの産学連携及びCG技術一般
発表件数:12件,招待講演2件
2.シンポジウム・国際会議等の報告
- Visual Computing 2024 シンポジウム
2024年9月10日(火)〜12日(木)
会場:東洋大学赤羽台キャンパス 情報連携学部 INIAD HUB-1
主催:情報処理学会 CG研究会,画像電子学会 Visual Computing研究会,
映像情報メディア学会 映像表現&コンピュータグラフィックス研究会
共催:東洋大学情報連携学部
特別後援:CG-ARTS (公益財団法人画像情報教育振興協会)
3.総括
基礎研究から応用研究,産業応用も含めた幅広い研究発表があった.拡散モデル,Gaussian Splatting,LLMなどの新しいトピックの扱いもあるものの,依然として伝統的なトピックの研究発表・受賞も多かった.
4.その他
- 研究会の会費を下げるための施策を検討中
- アジアのCG研究者との連携を検討中
- 参加者増加を狙って、シンポジウムとの連携を模索中
◆コンピュータと教育(CE)研究会
[主査:長瀧寛之,幹事:赤澤紀子,長 慎也,中園長新,林 浩一,本多佑希]
1.定例の研究会活動報告
第175回~179回の研究発表会を,順に埼玉工業大学,尾道市立大学,福井県国際交流会館,東京女子体育大学,大阪工業大学で.いずれも現地・オンライン参加が可能なハイフレックス形式で開催した.発表総数は79件(うち第177回の23件は,電子情報通信学会 SITE研究会との連催)で,安定した研究発表活動が行われている.
2014年度から設けている学生セッションの発表件数は,2024年度は合計28件となり,学生の研究会参加を促す効果につながっている.また今後の研究の発展を期待し,学生セッションの発表者の中から8件の学生奨励賞を選出した.論文作成のアドバイスを行う研究論文セッションには3件の発表があった.このような模擬査読は情報処理学会論文誌「教育とコンピュータ」と連携して論文投稿の活性化につながっている.いずれの試みも研究発表会の活性化につながっており,今後も継続していきたい.
2.シンポジウム・国際会議等の報告
2024年8月10日~12日に「情報教育シンポジウム SSS2024」をライトキューブ宇都宮(栃木県)で開催した.本シンポジウムでは,情報教育,教育の情報化に関わる幅広い分野の教育者や研究者の参加を募り,初回のSSS99以来熱気のこもった研究発表会となっており,今回は口頭発表26件,デモ・ポスター発表31件の全57件の発表が行われた.また優秀な論文3件についてTCEへの推薦を行った.
また招待講演として,杜甫々氏をお招きして『「とほほのWWW入門」の28年を振り返って』と題した講演をいただき,また吉田 塁氏をお招きして『生成AIがもたらす教育の未来について』をテーマに講演いただいた.
3.総括
当研究会は,情報の本質を理解し,教育の実践をしっかりと視野に捉えながら情報教育の可能性を探ることにより,情報教育に関連する学界と教育界へ寄与することを目的としている.近年では,2022年度から高校で情報I・IIの開始,2024年度入試より大学入試共通テストへの情報科目の導入という大きな動きがあり,小中学校におけるプログラミング教育やGIGAスクール構想を受けたコンピュータ活用学習が本格化する中,情報教育に関する研究成果を積極的に活用,発信していくべき状況となっている.また,学生セッションの定着により,若い世代の研究者が発表しやすい環境が整備でき,新しい技術の利用など柔軟で幅広い視野の研究発表が増えてきており,今後一層,研究会活動の充実が期待される.
一方で,研究会発表論文の質の向上を目指し創刊した論文誌トランザクション「教育とコンピュータ」は,現在安定した掲載数を維持しているが,今後も研究論文セッションやシンポジウムからの論文推薦などを通して,論文数が増加することを期待している.以上のように研究発表会,論文誌の双方を通じて,質的・量的に充実した研究会活動を社会へアピールしていきたいと考えている.
◆人文科学とコンピュータ(CH)研究会
[主査:橋本雄太,幹事:耒代誠仁,吉賀夏子,鈴木親彦,小川 潤]
1.定例の研究会活動報告
- 第135回 2024年5月18日(土)@京都大学人文科学研究所(共催 京都大学人文科学研究所附属人文情報学創新センター)発表14件
例年通り,企画セッションとして学生セッション(ポスター発表)を設け, 9件の発表があった.運営委員の選考により2件の奨励賞を授与した. - 第136回 2024年7月26日(土)@国際日本文化研究センター(国際日本文化研究センター・高麗大学校人文社会デジタル融合人材養成事業団・人間文化研究機構DH推進室) 発表6件
同日開催の「日韓の若手・次世代デジタル・ヒューマニティーズ(DH)研究発表会」「第2回 DH若手の会」との共催イベントとして開催した. - 第137回 2025年2月8日(土) @オンライン 発表11件
年1回のオンライン開催での研究会.
2.シンポジウム・国際会議等の報告
- 第26回人文科学とコンピュータシンポジウム(じんもんこん2024)
日程:2024年12月7日(土)-8日(日)
場所:東北大学 川内キャンパス
主催:情報処理学会 人文科学とコンピュータ研究会
実行委員長:加藤諭(東北大学)
プログラム委員長:堤智昭(筑波大学)【委員長】
「MLAをつなぐデジタルアーカイブ」というテーマに対して,140名の参加者が集まり,合計49件の研究発表(口頭発表20件,ポスター発表29件)が行われた.また,7日には企画セッションとして「Toward a Construction of an International Network of Tripitaka Study via Digital Humanities」が開催された.
シンポジウム内での発表の中から優秀論文賞2件,ベストポスター賞2件,学生奨励賞4件を選考し表彰した.
3.総括
日本国内のデジタル人文学研究の活発化を受けて,さまざまなイベントや団体との共催で研究会を開催することが多くなった(CH135, 136).
シンポジウム「じんもんこん2024」では5年ぶりの対面開催を実施した.コロナ禍の間に相当程度のノウハウが失われてしまったが,現地実行委員の献身的協力もあり大過なくシンポジウムを終えることができた.
4.その他
じんもんこんシンポジウムの収支が20万円以上の赤字となってしまったことは,大きな反省点である.経費節減に努めるとともに,スポンサー募集や外部資金の導入などを積極的に進めたい.
今後とも人文情報学/デジタル人文学の研究を支えるバックボーンとして,当研究会にどのようなことが可能か,検討と実践を継続していきたい.
◆音楽情報科学(MUS)研究会
[主査:森勢将雅,幹事:松原正樹,酒向慎司,中村友彦,植村あい子,大石康智,平田圭二]
1.定例の研究会活動報告
2024年度は,第140~142回研究発表会の研究会を開催した.第140回研究会については,2.で述べる.
- 第141回研究会「夏のシンポジウム2024」(2024/8/26~27)では,音声・音響処理,音楽分析, 音楽と国際動向,作曲支援システムに関する一般発表が15件と,国際会議既発表・デモ・萌芽・議論セッションで26件の発表があった.また,リアルタイム信号処理,音楽創造に関する2件の招待公演を実施し,大変好評であった.また,参加者向けに外部サービスに委託し託児所を設置した.
- 第142回研究会(2025/3/6~8)では,九州大学芸術工学部音文化講座による協賛を受け,感情・認知,ピアノ,ベース・ドラム・リズム,音楽情報処理,歌声,合奏・演奏に関連した一般発表40件に加え,萌芽・デモ・議論セッションで26件の発表があり,国際会議報告も実施した.また,音場再生に関する招待公演や施設見学ツアーを実施し,こちらも大変好評であった.
2.シンポジウム・国際会議等の報告
第140回研究会「音学シンポジウム2024」(2024/6/14~15)では,音に関係するあらゆる研究分野が対象とされており,今年で12回目の開催となった.本シンポジウムでは,MUSとSLPとの共催,かつ電子情報通信学会 音声研究会との連催,電子情報通信学会・日本音響学会 応用(電気)音響研究会,日本音響学会 聴覚研究会, 音声研究会との協賛となり,全研究会の委員が協力して企画を進めた.話者認識,聴覚心理,音楽認知,難聴と音楽,音声翻訳,音源分離に関する6件の招待講演に加えて,73件の一般ポスター発表があった.参加者は312名を超え,活発な議論が行われて非常に盛況であった.
3.総括
2024年度は,3回の開催全てが対面で行われた.国際会議既発表セッションと萌芽・デモ・議論セッションを引き続き実施することで,多様な発表がなされて好評であった.また, 141,142回研究会は聴講参加を無償化し,各研究会で特別企画を実施した.参加者は無料参加枠を含めるとどちらも120名を超えており,大変盛況であった.
4.その他
昨年に引き続き各例会で懇親会を実施し,70~80名以上が参加する盛況な会となった.参加者間の交流を深めるための取り組みについて,今後も継続的に検討する.
◆音声言語情報処理(SLP)研究会
[主査:篠﨑隆宏,幹事:安藤厚志,大町 基,齋藤佑樹,橋本 佳]
1.定例の研究会活動報告
第152-155回の研究発表会を開催した.
- 第152回(6月 日本大学+オンライン):SIG-MUSと信学会SPとともに,音学シンポジウム2024を共催・連催した.ポスターセッションに加えて,6件の招待講演を実施した.SLPからは東京都立大学の塩田さやか先生と日本電信電話株式会社の俵直弘様に話者認識に関する招待講演を,奈良女子大学の須藤克仁先生に自動同時音声翻訳に関する招待講演をお願いした.
- 第153回(10月 オンライン):信学会SP研究会との連催で,招待講演,パネルディスカッション,SLPスポンサーセッションにより構成される研究会を開催した.
- 第154回(12月 名古屋大学+オンライン):NL研究会と共催研究会とし,信学会SP研究会とNLC研究会の共催研究会との連催で音声言語シンポジウムと自然言語処理シンポジウムを合同開催した.一般講演に加えて招待講演および特別招待講演を実施した.また,国際会議報告としてINTERSPEECHおよびACLの研究紹介セッションを開催した.
- 第155回(3月 沖縄県青年会館+オンライン):信学会EA,SIP,SP研,およびAPSIPA JCとの連催でSPEASIPワークショップを開催した.一般講演に加えて3件の招待講演および1件の特別招待講演を実施した.
2.シンポジウム・国際会議等の報告
2024年度は実施なし.
3.総括
研究会を取り巻く環境の変化に対応し,前年度より年回開催数を1回減らし,年4回開催の体制へと移行した.各回は,開催内容や開催方法を工夫し,それぞれに特色のある企画となった.これにより,数多くの参加者の方々から高い評価を頂いた.年間を通じた研究会活動を通しては,現地開催による密なコミュニケーションの促進効果と,オンライン開催による広範な情報共有の効果を実感することができた.
4.その他
SLP研究会は,これまで電子情報通信学会のSP研究会と実体を統合した形で運営してきたが,次年度からは日本音響学会のSP研究会とも統合する.これにより,従来は密接に関連しながらも別個に存在していた音声分野に関する三つの主要な研究会が一本化され,統一的な枠組みのもとで運営する体制が整った.今回の統合に伴い,音響学会SPが独自に主催する研究会は廃止となり,今後は従来のSP/SLP研究会に統合された形での開催となる.これまでも音響学会の春秋の研究発表会ではSPおよびSLPが音響学会と連携して企画・運営を行ってきた実績があるほか,音響学会SPと信学会SPも2020年以前には継続的に共催を行っていたことから,一定の基盤が築かれている体制となっている.しかし,各学会の規則や慣行には違いがあるため,今後も円滑な運営を目指して調整を継続していく予定である.
◆電子化知的財産・社会基盤(EIP)研究会
[主査:小向太郎,幹事:板倉陽一郎,金子啓子,鈴木 悠,橋本誠志,吉見憲二]
1.定例の研究会活動報告
第104-107回の研究発表会を開催した.EIPは,知的財産,個人情報・プライバシー,情報社会の進展による法的問題や社会的問題一般を研究領域とする,文理融合の研究会である.各回の研究会では、こうした社会的課題の解決に資するテーマについて,招待講演,研究成果報告等が行われ,活発かつ有意義な議論が行われた.
特に,法制度と技術の境界領域に関する研究や,情報セキュリティのマネジメントに関する研究,個人情報保護に関する最新の制度動向,制度や社会的課題に関する新たな分析手法の探求などに関して,複数の成果が報告されている.各回の実施概要は以下の通りである.
- 第104回(6/5-6/6):電子情報通信学会「技術社会・倫理研究会(SITE)」との連催研究会.立教大学池袋キャンパス(オンサイト開催のみ).SITE特別企画「現代におけるコンテンツモデレーションの諸相と法:『表現の不自由展』からソーシャルネットワーキングサービスまで(座長: 森下壮一郎氏)、招待講演「データを巡る国家規制と国際経済法の動態(立教大学:東條吉純氏)」などを実施.個別報告15件(うちEIP12件).
- 第105回(9/19-9/20):マルチメディア通信と分散処理研究会(DPS)」との合同研究会.みやづ歴史の館2F文化ホール(オンラインとのハイブリッド開催).個別報告23件(内EIP18件).
-
第106回(12/3-12/4):コンピュータセキュリティ研究会(CSEC)」「セキュリティ心理学とトラスト研究会(SPT)との合同研究会.福井県繊協ビル (オンサイト開催のみ).EIP特別セッション「安田浩先生追悼セッション」を実施.個別報告35件(内EIP13件).
-
第107回(2/13-2/14):EIP単独開催.同志社大学新町キャンパス(オンサイト開催のみ).招待講演「協調型自動運転に向けた情報通信プラットフォームの構築(同志社大学・佐藤健哉氏)」を実施.個別報告31件.
2.シンポジウム・国際会議等の報告
2024年度は実施なし.
3.総括
EIPの主要なテーマである情報処理と社会課題に対しては,他の分野の研究者からも関心が高まっており,レベルの高い報告が増加している.また,学生による報告も増加しておいる.なお,FIT2024で「情報法のこれから」,情報処理学会全国大会で「サイバー事件回顧録」を,それぞれテーマとするEIPの企画セッションを実施した.他の研究会との連催・共催も,互いの研究のスコープを広げレベルを向上させる効果をあげている.今後は,EIPにおける研究成果をさらに社会に発信していくことで,一層のプレゼンスの向上と研究会の安定運営を図って行きたい.
4.その他
2024年度もオンサイト開催を原則として実施しており(一部オンラインを併用),研究者同士の懇親やフランクな意見交換の場としても好評を得ている.
◆ゲーム情報学(GI)研究会
[主査:橋本 剛,幹事:松崎公紀,竹内聖悟,西野順二,佐藤直之]
1.定例の研究会活動報告
これまで研究会は年2回実施していたが,参加者の増加を受け,初めて年3回実施をした.第52回研究会は2024年6月14日(土),15日(日)に島根県松江市の松江オープンソースラボでオンラインとのハイブリッドで行われた.強化学習などゲームAIに関する研究や,組合せゲーム理論に関する研究など計10件の発表が行われた.昨年に引き続き,1日目の最後にボードゲームなどで参加者同士の親睦を深める時間を設け好評を博した.
第53回研究会は2024年9月6日(金)に初のFITとの併催で広島工業大学にて実施した.将棋,囲碁,麻雀やポーカー,カードゲーム,ローグライクゲームに関する研究など,9件の発表が行われた.
2025年3月4日(火),5日(水)には,電気通信大学でGame AI Tournament 2025が開催され,多くの参加者を集めた.続けて第54回研究会は2025年3月6日(木),7日(金)の2日間,東京大学本郷キャンパスでオンラインとのハイブリッドで行われた.発表は12件で,組合せゲーム理論が4件,ゲームソルバーに関する研究が4件,ゲームと人間プレイヤに関する研究が3件,人間らしいAIに関する研究が2件と,多様な目的のさまざまな研究が見られた.
2.シンポジウム・国際会議等の報告
今回で第29回目の開催となるゲームプログラミングワークショップ(GPW)は,2024年11月15日(金)- 11月17日(日)に箱根セミナーハウスで実施された.
16件の口頭発表,12件のポスター発表があり73名の参加者(うち現地55名,オンライン18名)による活発な質疑・議論が行われた.多種のゲーム・パズルに関する様々な観点からの研究発表があり,これらの最新の研究についての熱心な討論や情報交換が行われたいへん有意義であった.なお,今回もチャットツールSlackも併用して発表者と聴講者の情報交換を促進する仕組みを提供した.
今回は1件の招待講演を実施した. (株)サイバーエージェントの伊原滉也氏に「デジタルカードゲームにおけるバランス調整支援システムの実現」という題で,著名なゲームにデッキのバランス調整などさまざまな面で強化学習を応用している話をしていただいた.実践的な内容で,最新の人気ゲーム開発がよく分かるとても興味深い内容で参加者の好評を博した.
また,恒例のナイトイベントでは囲碁AIの大会などが実施され,大いに盛り上がった.
このように一般発表,ポスター発表,招待講演,関連イベントと大変活発なワークショップとなり,この分野の研究のさらなる発展につながる実りのある場となった.来年度も引き続きこのワークショップを実施する予定である.
3.総括
近年の発表者増加を受けて初めてFIT併催研究会を実施し年3回の研究会を開催したが,本研究会は発足後26年が経過し,この分野の発表の機会を与えるものとして十分に定着してきたと言える.発表の内容を見ると,従来のパズルや将棋,囲碁などの伝統的なゲームに加え,ガイスターやなど不完全情報ゲーム,ビデオゲームや戦略シミュレーションなど新たな分野の研究が今年も増加した,強化学習に関する手法の研究が今年も多かったが,他分野同様にLLM関係の発表が増加傾向にある.オンラインと現地でのハイブリッドでの開催も順調に行えたので,今後もハイブリッドでの開催を検討している.4.その他
来年度もFITとの共催研究会を実施し,年3回の研究会,及び,GPWの開催を行う予定である.
◆エンタテインメントコンピューティング(EC)研究会
[主査:松下光範,幹事:小泉直也,橋田光代,松浦昭洋,橋本 直]
1.定例の研究会活動報告
第72-75回の研究発表会を開催した.
- 第72回 2024年6月6日(木) - 7日(金) 東京大学山上会館(東京都文京区)
情報処理学会ヒューマンコンピュータインタラクション研究会(HCI)と合同,日本バーチャルリアリティ学会,ヒューマンインタフェース学会デバイスメディア指向ユーザインタフェース専門研究委員会(SIG-DeMO),映像情報メディア学会 ヒューマンインフォメーション研究会(HI)と共催,電子情報通信学会メディアエクスペリエンス・バーチャル環境基礎研究会(MVE)と連催で,人工現実感,エンタテインメント,メディアエクスペリエンスおよび一般をテーマにオンラインでの研究会を開催した.全体で36件の発表があった. - 第73回 2024年9月1日(日) 北海道情報大学札幌サテライトオフィス(北海道札幌市)
研究と分野の方向を考えるメタ研究会として開催した.今回はライトニングトーク形式で,14人の委員が話題提供者となり,自らの研究を通じてエンタテインメントコンピューティング研究の視座を語るとともに,本研究分野の多様性や通底する本質的な学問的な問いについての相互議論を行い,「心を動かす情報学」としての本研究分野の研究のあり方や将来像を探った. - 第74回 2024年 11月16日(土) サンポートホール高松 (香川県高松市)
5件の一般発表と3件の萌芽発表が行われた.2023年度までは秋期の研究会は日本バーチャルリアリティ学会複合現実感研究会(SIG-MR)・第82回サイバースペースと仮想都市研究会(SIG-CS)との共催で行っていたが,2024年度はエンタテインメントコンピューティングシンポジウム2024を9月初頭に北海道で開催したため,共催で行う場合,場所・発表日が非常に近くなる(9/26-27, 北海道)ことを鑑み単独開催とした. - 第75回 2025年 3月17日(月) -19日(水) 2025年京都大学 百周年時計台記念館 (京都府京都市)
24件の一般発表と18件の萌芽発表,15件のデモ発表(6件の一般・萌芽発表のデモ分を含む)が行われた.また,3月17日には招待講演として, 白水 菜々重氏(株式会社JR西日本イノベーションズ)による「心を動かすメディアとしての鉄道」の講演を実施した.
2.シンポジウム・国際会議等の報告
主催シンポジウム1件,および共催シンポジウム1件を開催した.
- エンタテインメントコンピューティング2024(主催)
2024年9月2日(月)-9月4日(水)に,北海道江別市の北海道情報大学にて,「試されるEC」をテーマに北海道情報大学の湯村翼先生を実行委員長として開催され,208名の参加者があった.基調講演として,(1) SIAF LAB. による「「雪の都市と自然のR&D」,(2) 加藤創氏による「地図,デザイン,可視化 −情報をわかりやすく伝えるために−」の2つの講演を実施した.また,初日の昼休みには,パネル討論形式での産学連携ランチョンミーティングが開催された.特選セッション6件,一般口頭発表59件,デモ・ポスター発表96件(口頭発表と重複あり)で、投稿論文数は111件となった.昨年より26件増え,近年では2015年に次ぐ投稿数であった.また,エンタテイメントコンピューティングシンポジウム2024で導入したPC委員による投票制度と連携しその投票理由や推薦理由を言語化・講評してもらう仕組みである「Re:commend-demo 」を昨年に引き続き本年も実施した.当初は現地開催のみの予定であったが,会期中に台風が上陸する可能性があり,直前に急遽ハイブリッド開催とした.実際には台風は逸れて,ほとんどの参加者が現地にて参加した。参加者は208名となり,通常の研究会と比較してシンポジウム開催の意義は大きいと言える. - インタラクション2025(共催)
2025年3月2日(日)~ 3月4日(火)に,学術総合センター一橋記念講堂にてヒューマンコンピュータインタラクション研究会(HCI),グループウェアとネットワークサービス研究会(GN),ユビキタスコンピューティングシステム研究会(UBI),デジタルコンテンツクリエーション研究会(DCC)との共催で開催した.登壇発表25件,インタラクティブ発表270件(口頭発表デモの7件を含む)がなされた.参加申込数は831名であった.
3.総括
研究会の年間発表件数は,第74回研究会を単独開催としたため微減となったものの,研究会単体での投稿数で考えると昨年度より増加となっていることから,研究コミュニティの活動は安定して行えていると考える.特に第75回研究会では,招待講演の実施や昨年に引き続きデモ発表セッションを実施したこともあり,昨年同期の研究会よりも投稿数・参加者数が増加し盛会となった.昨年度のECシンポジウム2023で行ったRe:commend Demo やエンタテインメント企業との交流会をECシンポジウム2024でも実施し,当研究分野の特色ある取り組みとして根付かせることができたと考えている.研究会の継続した発展に繋げていくため,今後もECシンポジウムの取り組み強化や通常研究会でのデモ発表の定着などを検討していく.
4.その他
国内のエンタテインメントコンピューティングコミュニティの活性化については,研究会への投稿数や情報処理学会誌EC特集号の投稿数から,一定の効果が確認できる状況となった.2025年度は,国際会議IFIP-ICEC2025の開催を通じて,海外への情報発信・成果蓄積に向けた活性化策を推進していく.
◆バイオ情報学(BIO)研究会
[主査:佐藤健吾,幹事:倉田博之,加藤有己,大林 武]
1.定例の研究会活動報告
第78-81回,合計4回のBIO研究発表会を開催した.
- 第78回は,2024年6月20~22日沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス・セミナー室において開催した.数理モデル化と問題解決(MPS)研究会と共催し,電子情報通信学会ニューロコンピューティング(NC)研究会および情報論的学習理論と機械学習(IBISML)研究会と連催した.総発表件数59件(うちBIOより14件)であった.2023年度にくらべて,総発表件数は10件減少し,BIO発表件数は6件減少した.
- 第79回は,9月6日広島工業大学五日市キャンパスにおいて,ハイブリッド型で開催した.第23回情報科学技術フォーラム(FIT2024)の併催研究会として開催した.発表件数9件であった.
- 第80回は,計測自動制御学会「ライフエンジニアリング部門統合情報生物工学部会」の協賛を得て,11月29日早稲田大学西早稲田キャンパスにおいて開催した.発表件数16件であった.
- 第81回は,2025年3月6~7日に,北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科講義棟において開催した.分子ロボット倫理研究会(3月7日),オープンバイオ研究会(3月8日)との連続開催という形で連携した.発表件数17件であった.
各回の研究発表会で優秀な研究発表をした発表者に贈呈するSIGBIO優秀プレゼンテーション賞を,第78回3名,第79回1名,第80回2名,第81回3名に授与した.SIGBIO学生奨励賞は第81回に発表した学生1名に授与した.
2.シンポジウム・国際会議等の報告
2024年度の主催行事はなかった.「バイオインフォマティクス技術者認定試験」を協賛した.
3.総括
昨年度と同様に,関連研究会や学会との共催や併催を積極的に進めて,合計56件のBIOの発表があった.2020年度発表件数27件,2021年度41件,2022年度44件,2023年度44件,2024年度65件と較べると,発表件数はコロナ禍の影響から完全に脱し,横ばい傾向にある.
4.その他
2025年度は年3回の研究発表会を計画している.「第82回バイオ情報学(SIGBIO)研究会」は,2025年6月21日~6月23日,「第153回数理モデル化と問題解決(MPS)研究会」と合同研究会とし,電子情報通信学会ニューロコンピューティング(NC)研究会,情報論的学習理論と機械学習(IBISML)研究会と連催する.琉球大学において開催の予定である.「第83回バイオ情報学(SIGBIO)研究会」は,10月23日に中央大学後楽園キャンパスにて開催予定である.
◆教育学習支援情報システム(CLE)研究会
[主査:島田敬士,幹事:新村正明,宮崎 誠,毛利考佑,畠山 久]
1.定例の研究会活動報告
2024年度は,第43回~第45回の研究発表会を開催した.
- 第43回は2024年6月15日に近畿大学において,電子情報通信学会教育工学研究会(ET研究会)と合同で開催した.テーマ「身体知・スキル教育および一般」に関連する13件の発表があった.
- 第44回は2024年11月15日~16日に広島大学において開催した.テーマ「生成AIと学習・教育支援および一般」に関連する9件の発表および2件の招待講演があった.また,研究会企画セッションとしてCLE分野における研究の活性化をテーマにディスカッションを行った.
- 第45回は2025年3月20日~21日に群馬大学において,エビデンス駆動型教育研究協議会(EDE)と合同で開催した.テーマ「データに基づく学習活動のモデリングおよび一般」に関連し,24件の発表および1件の招待講演があった.また,エビデンス駆動型教育研究協議会と共催している教育データ分析コンテストの結果発表・表彰も行った.
2.シンポジウム・国際会議等の報告
2024年度は実施なし.
3.総括
本研究会では,教育学習活動を支援する情報システムに関する研究開発及び実践に関する発表が19年間に渡り行われてきた(平成17年度から始まった研究グループ時代を含む).その間,教育現場を支える各種のシステムが登場し,とりわけ学習支援システム(LMS, Learning Management System)やコース管理システム(CMS, Course Management System),ポートフォリオシステムがその中心となり,本研究会でも多数の発表が行われてきた.一方で,教育,学習に関する学生情報システム(SIS, Student Information System)とのデータ連携や,教育・学習活動のプロセスのデータが日々蓄積されるスタディログに関する研究も近年活性化している.ラーニングアナリティクスは,学習のログに加えて,成績・アンケートなどの教育機関が保有する様々なデータを統合・利活用して,教育・学習活動の改善に資する情報を教育現場にフィードバックする目的を主なものとして,本研究会でも主要テーマとなりつつある.当研究会では,今後もシステムの実装,安定運用,教育データの利活用,教育・学習活動の改善のためのフィードバックなど幅広いテーマを時代の変遷に合わせて取り上げるとともに,研究と実践が密接に連携した議論・交流の場を提供できるよう取り組みを進めていきたい.
4.その他
今後も引き続きCLE研究分野の研究を推進する.特に,オンライン授業をはじめとした教育学習を支える環境や情報システム,対面授業とのブレンド,ハイブリッド/ハイフレックス授業を実践するための技術開発は,実践的な取り組みを通してノウハウや知見が蓄積されるものであるため,データ分析や効果検証,その結果のフィードバック等の研究にも引き続き研究会として取り組んでいく予定である.また,コロナ禍が契機となり,ICTを活用した新しい教育の実施や学習活動の支援,システムに蓄積されるデータを活用したデータ駆動型教育など,様々な研究や教育現場での実践的取り組みがなされているため,ニューノーマルな時代における教育・学習の在り方やそれを支える基盤システムならびに支援システムについて幅広く議論を進めていきたい.さらに,生成AIの教育利用や教育学習支援システムとの共存など,時代の潮流も注視しながら研究会のテーマ設定や関連する企画,イベントの立案などを進めたい.あわせて,研究分野の活性化のため,関連する研究会・学会と様々な形での連携を進めたい.
◆アクセシビリティ(AAC)研究会
[主査:杉原太郎,幹事:西﨑実穂,湯野悠希,西田昌史,平賀瑠美,三枝 亮]
1.定例の研究会活動報告
第25-27回の研究発表会を開催した.
2024年度は前年度から引き続き,情報保障のあり方をハイブリッド形式で検討することを念頭に置いた形式での開催となった.参加形態がフレキシブルになったこともあり,研究内容にも変化が見られた.これまで同様に聴覚障害者支援と高齢者支援の研究発表が大半を締めたが,発達障害などの調査発表も増えるなど着実に認知度が高まってきた.
Zoomを用いた情報保障のあり方も暫定解のようなものは見つかりつつあり,第26回ではAAC研究会としては初めて関東圏から出て,浜松にて開催できた.
表1 参加人数
| 研究会 | 全参加者 | 視覚障害者(発表者) | 聴覚障害者(発表者) |
| 025 | 会場25名 Zoom47名 発表13件 |
1名(1日目) 1名(2日目) 発表0件 |
2名(1日目) 2名(2日目) 発表1件 |
| 026 | 会場37名 Zoom13名 発表12件 |
0名(1日目) 0名(2日目) 発表0件 |
4名(1日目) 5名(2日目) 発表1件 |
| 027 | 会場28名 Zoom226名 発表9件 |
1名(1日目) 0名(2日目) 発表0件 |
13名(1日目) 9名(2日目) 発表6件 |
2.シンポジウム・国際会議等の報告
2024年度は実施なし.
3.総括
1でも述べた通り,ハイブリッド方式の開催方法を堅持できるように工夫した点,ならびにハイブリッドの特長を活かして地方開催を実施できた点がAAC研究会としてのチャレンジであった.現地とオンラインの両方の環境に十分な情報保障をお届けするために,これまで以上に工夫と労力を要することになった.現地に来られない方を呼び込みつつ,対面でのコミュニケーションによる議論の活発化を図ったためであり,それらの点は機能した.ただし,情報保障では担当者の負担が大きくなってしまった点は,前年度から引き続いての反省事項であった.
4.その他
今年度から引き続き,ハイブリッド方式での開催にチャレンジすることになる.ただし,AAC研究会は小所帯の運営体制であるため,毎回負担の大きなハイブリッド開催はできない.オンライン方式のみ,対面方式のみとの組み合わせを検討しつつ,担当者にとって妥当な負担感に収まるよう研究会を運営していく.
AAC研究会がこうした挑戦を続けられるのは,情報処理学会本体からのご支援があってこそである.主査として研究会を代表し,改めてここに謝意を表す.
http://ipsj-aac.org
◆スポーツ情報学(SI)研究会
[主査:松原 仁,幹事:北原 格,木村聡貴,相原伸平]
1.定例の研究会活動報告
第1-2回の研究発表会を開催した.
- 第1回研究会 2024年6月21日(金) 国立スポーツ科学研究センター 発表 50件(基調講演,特別講演,パネル討論,ポスター発表を含む)
現地参加者 約100名 オンライン参加者約100名 - 第2回研究会 2024年11月1日(金),2日(土) 北見工業大学
映像情報メディア学会と共催
発表23件(招待講演,パネル討論,一般発表を含む)
現地参加者 約50名 オンライン参加者 約50名
2.シンポジウム・国際会議等の報告
第1回の研究会は設立記念シンポジウムを兼ねて実施した.研究会を設立した趣旨を説明し,スポーツ情報学の分野で中心的な研究を行なっている研究者に講演をお願いし,多くの研究者にポスター発表をしてもらった.スポーツ情報学はこれまでもっぱら情報処理学会とは異なるところで研究を含めた活動がなされてきたので,本研究会が立ち上がったことを多くの関係者に知ってもらうことができたのはよかったと思われる.
3.総括
発表件数が多いことからも本研究会を設立した意義は大きいと思われる.引き続きた学会などとの協力を含めて活動を広げていきたい.
4.その他
スポーツ情報学に関わっている人の多く(というかほとんど)が情報処理学会と縁がなく会員ではない.研究会に対する関心は非常に高いものの,研究会会員になってくれずに非会員として参加する人が多いのが問題である.研究会会員になるためには情報処理学会の会員になる必要があるが,学会員になるメリットを感じてもらえていないものと思う(すでに他の学会に入っていてこれ以上学会を増やせないということであろう).全国大会でもスポーツ情報学に関する発表は多く分野としては広がっているのは明らかなので,地道に少しずつ学会および研究会の宣伝に努めていきたい.
◇ネットワーク生態学(NE)研究グループ
[主査:鳥海不二夫,幹事:田中 敦,山野泰子,中条雅貴,今井哲郎,守田 智,藤木結香,伏見卓恭,伊東 啓]
1.定例の研究会活動報告
第20回の研究発表会
日時:2025年3月7日~8日
場所:金沢勤労者プラザ
46名の参加者があった.
3件の招待講演,1件の国際会議活動報告,1件の記念講演,20件のポスター発表が行われた.
2.総括
定例のシンポジウムを行い,昨年以上の多くの参加者が現地に集まり活発な議論が行われた.また,東京大学と共催でネットワーク科学勉強会をオフライン・オンライン同時開催にて定期的に開催した(2024年度は7回開催).毎回オフラインでは5名程度,オンラインでは20名程度が参加しており,ネットワーク科学研究に一定の寄与が出来ていると考える.
3.その他
- 2025年度は2026年3月に東北大にてシンポジウムを行う予定である.
- ネットワーク科学勉強会は引き続き継続して共催する.
◇会員の力を社会につなげる(SSR)研究グループ
[主査:筧 捷彦,幹事:寺田真敏,中山泰一]
1.定例の研究会活動報告
会合名:第13回 情報科教員を目指す学生さんに向けてのガイダンス会 2024
日時:2024(令和6)年09月29日(日)
場所:オンライン
https://sites.google.com/isl.im.dendai.ac.jp/ssr/20240929
2.シンポジウム・国際会議等の報告
2024年度には特に開催しなかった.3.総括
情報科教員を目指す学生さんに向けてのガイダンス会は,高校の先生と大学の先生のコミュニティを活用して,複数大学間にまたがって,情報科の先生になりたい学生さんを応援しようという思いを形にしたものである.2024年度はハイブリッド(聴講者はオンライン,講師は東京電機大学 千住キャンパスで,一部オンラインで参加)で開催した.学生37名,高校教員19名,大学教員7名,その他7名の構成で69名の参加があった.ハイブリッド開催でオンラインでの参加を可能としたことで,大分舞鶴高等学校,神奈川大学,関西学院大学,千歳科学技術大学,長野大学,奈良教育大学など関東地区以外からも参加があり,学生37名,高校教員19名,大学教員7名,その他7名の構成で69名の参加となった.
研究グループの活動も10年目となり,主催イベントは定着化したことから,新たな取り組みへの着手や関東以外の地域とのコミュニケーションなどの協働の場の整備を,オンライン会合を併用していくことで普及発展に努めていく.引き続き,関係者の方々には積極的な参加をお願いしたい.今後も,様々な声を拾い上げながら,課題をひとつずつ解決していくことで,「教育に携わる諸部門とのさまざまな形での協働の推進に努めます」を実践していく.
◇情報処理に関する法的問題(LIP)研究グループ
[主査:高岡詠子,幹事:市毛由美子,中山泰一,登 大遊]
1.定例の研究会活動報告
2015年9月に立ち上げた「情報処理に関する新たなルール作り」に関する研究グループは,設立当初から新たなソフトウェア契約のモデル案を提案しようという方向で勉強会を続けてきた.アジャイル開発を採用する企業・団体が急増しているが,外注を行う・受ける際に契約をどのように締結するのかが悩みの一つとなっており,2024年度も引き続きアジャイル開発を行う際の契約の問題点について深掘りを行った.まず,アジャイル開発のユーザ・ベンダに対して,アジャイル開発における契約種別の選択,モデル契約の利用状況,契約締結上の課題などについてアンケートを行い,プレセミナーを行った.
第87回全国大会において,「行政におけるアジャイル推進の障害と突破口についてのトークセッション」では,政府・自治体職員向けに、行政DX推進などの課題解決に役立つフレームワークの実践ガイドやワークシート,実践事例,スキルマップなどのコンテンツを含む「公的機関向け課題解決ツールボックス」の紹介が行われた.また,「弁護士から見たアジャイルについてトークセッション」において,上記のアンケートの結果を報告するとともに,最近増えてきたアジャイル開発に関する裁判例について紹介を行った.
- 第1回(通算第58回) 2024年6月11日(火) 18:30~19:30 Zoom
- 第2回(通算第59回) 2025年3月11日(火) 18:00~19:30 Zoom
2.シンポジウム・国際会議等の報告
- アジャイル開発契約に関するオンラインセミナーを開催:アジャイル開発〜契約における課題の解決〜弁護士によるフリートークあり
2024年9月27日(金) 17-18時 - 情報処理学会第87回全国大会にてイベントセッションを行った
第87回全国大会イベント
2025年3月14日(金) 12:40-15:10
場所:第3イベント会場(ハイブリッド)
タイトル:アジャイル開発契約の課題
3.総括
アンケートやセミナー,トークセッションを通して,アジャイル開発に取り組みたいが,個別の条件に合わせて契約モデルをどのように変更すれば良いのかという指針のようなものが必要なことがわかってきた.2025年度は,アジャイル開発の裁判例を一つ一つ深く研究し,提案している契約モデルの活用を,周知啓発していく事を目指し活動する.