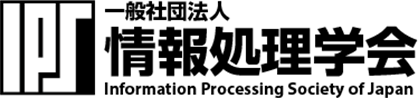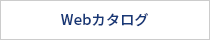2025年度受賞者
2025年度コンピュータサイエンス領域功績賞受賞者
コンピュータサイエンス(CS)領域功績賞は,本領域の研究会分野において,優秀な研究・技術開発,人材育成,および研究会・研究会運営に貢献したなど,顕著な功績のあったものに贈呈されます.本賞の選考は,CS領域功績賞表彰規程およびCS領域功績賞受賞者選定手続に基づき,本領域委員会が選定委員会となって行います.本年度は10研究会の主査から推薦された下記10件の功績に対し,本領域委員会(2025年10月3日)で慎重な審議を行い決定しました.各研究発表会およびシンポジウムの席上で表彰状,盾が授与されます.
| 角谷 和俊 君 (データベースとデータサイエンス研究会) |
| [推薦理由] 本会正会員角谷和俊氏は,データベース技術を基礎としたマルチメディア・システムおよびSNS分析分野における我が国の代表的な研究者の1人であり,地理情報データ,放送型データ分析,Web情報検索の研究で多大の業績を上げ,VLDB,DEXA,ACM GIS等のトップレベルの国際会議において発表すると同時に,DEWSおよびDEIMベストプレゼンテーション賞等を受賞している.さらに,これらの研究成果に関連して,50件を超える国内外の特許出願を行っており,学術的貢献に加えて技術的・社会的インパクトも極めて大きい.これに加え,情報検索・情報推薦に関する書籍として,コンピュータとWebサイエンスシリーズにおける「Webで知る -Web情報検索入門」(サイエンス社(2020/4/22))や,情報推薦や検索インタフェースの「情報推薦入門」(共立出版(2012/6/22)),「情報検索のためのユーザインタフェース」(共立出版(2011/4/9))の翻訳書で監訳を担当するなど,データベースとデータサイエンスの普及,教育にも貢献されている. また,IEEE BigComp, DASFAA, W2GIS等の主要な国際会議の各種委員長や運営委員を務めると共に,現在の「データベースとデータサイエンス研究会」の前身であるデータベースシステム研究会主査,本学会理事(調査研究担当),情報処理学会論文誌:データベース(TOD)共同編集委員長等を歴任するなど,本学会の活性化に大きく貢献している.特に,2008年にデータベースシステム研究会主査として,データベース・データ工学・情報検索に関連する学会・研究会のシンポジウム,フォーラム,研究会を対象とし,産学官連携を図る3イベント群への再編・統合へ先導するなど,我が国のデータベースコミュニティの興隆に極めて顕著な貢献がある. このように,角谷和俊氏は,我が国のデータベースコミュニティの発展に極めて顕著な貢献をされており,CS 領域功績賞に相応しい人物として強く推薦する. |
| [ 戻る ] |
| 鵜林 尚靖 君 (ソフトウェア工学研究会) |
| [推薦理由] 鵜林先生は、ソフトウェア工学において、特に人工知能やプログラミング言語理論、形式手法・形式検証といった幅広い分野を巧みに融合し、学術・産業・教育の各領域でめざましい成果を挙げてこられました。2024年より早稲田大学理工学術院 国際理工学センター教授(任期付)として着任される以前は、九州大学大学院システム情報科学研究院教授として長年活躍されており、同大学の名誉教授の称号も得ていらっしゃいます。Scopusデータによると2025年時点で論文数148本、引用数2,095件、h-index 19という国際的にも高い評価を得ており、トップカンファレンスへの論文採択や産学連携プロジェクトへの積極的な参画を通じて、国内だけでなく世界のソフトウェア工学分野を大きく牽引してこられました。 また、情報処理学会フェローとして学会活動にも多大な貢献を続け、ソフトウェア工学の研究会や国際会議の運営に携わりながら、若手研究者や学生の育成に力を注いでいます。教育面では「レクチャーソフトウェア工学」を単著で上梓し、最先端の理論から現場での実践までを分かりやすく解説しており、多くの技術者や研究者がその知見を活用しています。さらに、AI技術のソフトウェア開発への応用(SE for AI)およびソフトウェア工学へのAI応用(AI for SE)を推進し、不確かな環境下でも高品質なシステムを構築・維持するための手法を研究することで、社会実装の面でも大きな指針を示してこられました。 こうした研究活動においては、国内外の学会やシンポジウムで多くの賞を受賞し、産業界との共同研究でも問題解決型のアプローチを実践してきたことが高く評価されています。実際に「ソフトウェアリポジトリマイニング」や「自動バグ修正」など革新的な手法を提案・検証することで、プログラミングやシステム開発の生産性と信頼性を著しく向上させる成果を挙げています。その功績は、九州大学や早稲田大学のみならず、幅広い産業分野にインパクトを与えるものであり、今後ますますの発展が期待されています。 以上のように、学術界と産業界の橋渡し役として多方面で活躍し、先進的な研究成果と教育・人材育成に尽力されている鵜林先生は、本賞にふさわしい優れた研究者であると確信し、ここに強く推薦いたします。 |
| [ 戻る ] |
| 谷本 輝夫 君 (システム・アーキテクチャ研究会) |
| [推薦理由] 谷本輝夫氏は,我が国のコンピュータ・アーキテクチャ分野に対して,研究活動と学会運営の両面において,大きく貢献を続けている人物である.特に量子コンピュータをはじめとする,新規デバイスのコンピュータシステムへの導入に関して優れた成果をあげている.学会運営の面でも,2020~2023年度にシステム・アーキテクチャ研究会の幹事,また2019年度ならびに2024年度から現在まで同運営委員を務めており,当研究会運営に大いに貢献している.量子ソフトウェアや高性能計算などのコミュニティでも存在感を発揮しており,境界領域における交流の活発化に対する貢献も非常に大きい.さらに,本分野の学生を対象に若手教員を中心とした講習会を企画するなど,分野の活性化にも意欲的に取り組んでいる.以上のとおり,同氏によるシステム・アーキテクチャ研究会ならびにコンピュータ・アーキテクチャ分野に対する貢献は極めて大きいことから,CS領域功績賞の受賞候補者にふさわしいと判断しここに推薦する. |
| [ 戻る ] |
| 河野 健二 君 (システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会) |
| [推薦理由] 本会正会員河野健二氏(フェロー)は、長年に渡りシステムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会の運営に大きく貢献してきた。2002年度から2006年度まで同研究会の幹事を務め、2011年度から2014年度まで主査を務めた。国際会議 APSys の実行委員長、その運営委員、USENIX Annual Technical Conference (ATC) のプログラム委員など国際的なコミュニテイに対する貢献も顕著である。同氏のシステムソフトウェア分野における研究成果は国内外で高く評価されており、国内随一の研究業績を有している。当該分野で国際的な評価の高いUSENIX等のトップコンファレンスにおいて継続的に論文発表を行なっている。特に仮想化に関する一連の研究業績は高く評価されており、その成果の一部は Linux/KVM にも取り込まれるなど学術的な成果にとどまらないものとなっている。これらの研究成果に対して,本会山下記念研究賞、論文賞 4回、日本ソフトウェア科学会基礎研究賞、ソフトウェア論文賞、IBM Faculty Award など多くの受賞がある。 また、学生の指導を通じて当該分野における多くの優秀な人材を輩出しており、これまでに 17 名の博士(工学)の取得者を指導してきた。同氏の薫陶を受けた多くの学生が、本会山下記念研究賞、コンピュータサイエンス領域賞、システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会優秀学生発表賞を受賞している。さらに、JST/CRESTの領域アドバイザを務めるなど、当該分野全体の底上げにも尽力されている。 このように、同氏によるシステムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会ならびにコンピューティングシステム分野における貢献は極めて顕著であり、CS領域功績賞受賞者としてふさわしいと考えここに推薦する。 |
| [ 戻る ] |
| 五十嵐 友則 君 (システムとLSIの設計技術研究会) |
| [推薦理由] 五十嵐氏は、SLDM研究会の運営委員会幹事として、2023年度から2024年度の2年間にわたり活動され、合計6回の運営委員会を主催し、研究会の円滑な運営に大きく貢献されました。 また、2021年度から2022年度にかけては、SLDM研究会が主催するフラッグシップイベントである「DAシンポジウム」において実行委員幹事を務められました。特に2022年度の開催では、コロナ禍によるオンライン開催が続いた後、3年ぶりの現地開催となる中、感染症対策として初のオンライン併催を試みるという困難な状況に直面しました。そのような中、五十嵐氏は、過去の現地開催経験者の知見を集約し、事前の配信システム構築を含む綿密な準備を主導することで、シンポジウムの成功に大きく寄与されました。 このように、五十嵐氏は研究会の運営やイベントの企画・実行において多方面にわたり貢献されており、SLDM研究会として、CS領域功績賞の候補者として強く推薦いたします。 |
| [ 戻る ] |
| 竹房 あつ子 君 (ハイパフォーマンスコンピューティング研究会) |
| [推薦理由] 竹房あつ子君は,並列分散処理およびその基盤ソフトウェアに関する優れた研究開発を行ってきた.その成果は,SCやHPDC等のトップカンファレンスで評価されている.また,計算機やネットワークなどの多種資源管理システムやIoTミドルウェア等の開発も行っており,国内外の学術コミュニティに貢献してきた.また,総合研究大学院大学,お茶の水女子大学の学生の研究指導を行っており,CS領域における人材育成への貢献も大きい. 以上の研究・開発業績だけではなく,情報処理学会ハイパフォーマンスコンピューティング研究会幹事・運営委員,HPC Asia 2022 Finance Chair、SCA/HPCAsia2026 Finance Co-chair,xSIG 2023PC委員長をはじめ情報処理学会主催・共催を含む多数の国際会議の委員を歴任し,CS領域の発展に顕著な貢献を行ってきた.これらの多年にわたる竹房君のCS領域への貢献を評価し,同君をCS領域功績賞に推薦する. |
| [ 戻る ] |
| 八杉 昌宏 君 (プログラミング研究会) |
| [推薦理由] 八杉昌宏氏は,1998~2019年度にかけて,プログラミング研究会の運営委員・幹事・主査,および論文誌「プログラミング」の編集委員・編集長を歴任されました.20年以上にわたり継続的に委員を務められた方は他になく,研究会および論文誌の運営への多大なるご尽力はだれもが認めるところです.また,論文誌の査読にも長年継続的にご協力いただいており,論文誌の質の維持・向上へのご貢献も顕著です。加えて,PRO分野にとどまらず,他分野とも関連する研究集会・雑誌においても数多くの委員を務められております。たとえば,JSPP'97実行委員会幹事,SACSIS2005プログラム委員長,ACSI2016組織委員長などが挙げられます。 同氏は,委員在任中はもちろん,退任後も引き続き,プログラミング言語およびその処理系に関する研究会発表を数多く行っておられます。共著も含めて年間平均約2件のご発表をほぼ30年継続されており,累積発表回数は歴代最多となっております。もちろん,内容の質も高く,2009年度には主著として執筆された論文が論文賞を受賞されております。 同氏は研究会へ出席率の高さでもよく知られております.しかも,出席された研究会においては,理論・実装を問わず,ほとんどあらゆる発表に対して鋭い質問をなさっていらっしゃいます.プログラミング研究会は,20分という比較的長い質疑応答時間を設けており,議論を通して研究を発展させてゆくことを重視しております.氏の姿勢はまさにこの思想を体現されているものです.この四半世紀にPRO分野で研鑽を積んだ学生・若手研究者はもれなく,氏のご質問によって育てられたと言っても過言ではないでしょう. 以上のように,八杉氏の長年にわたる研究会運営への貢献ならびにプログラミング研究分野における研究,人材育成への貢献は顕著です。よって,同氏をコンピュータサイエンス領域功績賞にふさわしい方として,ここに推薦申し上げます. |
| [ 戻る ] |
| 加藤 直樹 君 (アルゴリズム研究会) |
| [推薦理由] 加藤直樹氏は離散アルゴリズムおよび最適化理論の分野において国際的に卓越した研究業績を挙げており、計算機科学、特にアルゴリズム分野における日本の研究の発展に多大な貢献を果たしてきた。計算幾何学、組合せ最適化、ビッグデータ解析など多様なテーマに取り組み、STOC、FOCS、SOCG、SODAといった理論計算機科学分野トップ会議での論文発表は16件にのぼり、日本のアルゴリズム研究の国際的地位の確立に大きく寄与している。また2010年代には、JST CREST「ビッグデータ時代に向けた革新的アルゴリズム基盤」において研究代表者として多数の理論計算機科学者を組織し、国際的にも先導的な研究成果を生み出したことにより、その活動は高い評価を得ている。このように加藤氏は、学術研究のみならず研究コミュニティ全体の牽引役としても極めて重要な役割を担ってきた。特筆すべき研究成果としては、組合せ剛性理論における25年間未解決であったMolecular Conjectureの解決があり、その成果は分子構造解析など異分野への波及効果も生んでいる。情報処理学会においても加藤氏は精力的に活動しており、1998年および1999年にはアルゴリズム研究会の主査を務め、当該分野の研究推進とコミュニティ形成に尽力した。以上のように、加藤氏は計算機科学分野において、国際的に評価される第一級の研究成果を継続的に生み出すとともに、研究コミュニティの活性化や、他分野にも波及する分野横断的な成果の創出においても顕著な貢献を果たしてきた。これらの功績・貢献はいずれも情報処理学会CS領域功績賞にまさにふさわしいものであり、加藤直樹氏を本賞に強く推薦する。 |
| [ 戻る ] |
| 関嶋 政和 君 (数理モデル化と問題解決研究会) |
| [推薦理由] 関嶋政和氏は、数理モデル化・ライフサイエンスや化学にかかわる情報学の融合領域において卓越した研究実績を挙げるとともに、学会運営・論文誌編集を通じて我が国の計算科学・情報学の発展に長年にわたり多大な貢献をされてきた。 関嶋氏は、情報処理学会「数理モデル化と問題解決(MPS)研究会」において、 - 研究会主査(2019~2022年度) - 研究会幹事(2011~2014年度、2023年度~現在) - 研究会運営委員(2007~2010年度) を歴任し、計14年以上にわたり研究会の企画立案・実施、コミュニティ拡大、若手育成に中心的役割を担った。主査在任中には研究会活動の高度化と分野横断連携の強化を牽引し、研究会の活性化に大きく寄与した。 同研究会と連動して発刊される情報処理学会論文誌「数理モデル化と応用」において、 - 副編集長(2019~2022年度) - 編集委員(2016~2019年度、2024年度~現在) を務め、特集企画や査読体制の整備、掲載論文の質的向上に尽力された。分野横断テーマの可視化と国際的認知向上に資する編集方針を推進し、学術コミュニティの発展に顕著な貢献を行っている。 関嶋氏は、バイオ/ケモインフォマティクス、分子最適化、強化学習を用いた化合物探索、構造に基づく創薬設計などの先端領域で数多くの査読付き論文を発表し、近年も精力的に成果を発信している。SARS-CoV-2の主プロテアーゼ阻害化合物探索、熱帯病(例:シャーガス病)創薬への計算科学的アプローチなど、社会的要請の高い課題に対して実問題解決型の研究を遂行し、国内外から高い評価を獲得している。 多数の学協会委員、学術会議・国際会議のプログラム委員等を歴任し、わが国の関連分野の可視性向上に寄与してきた。経済産業省 令和2年度「情報化促進貢献個人等表彰」経済産業大臣賞をはじめとする受賞歴は、学術のみならず産業応用面での貢献が顕著であることの証左である。 大学・大学院での豊富な担当科目を通じて、数理・情報・生命を横断する教育プログラムを構築・実践し、次世代研究者・技術者の育成に大きく寄与している。研究指導においても、ソフトウェア開発や知財化、共同研究を伴う実践的研究を推進し、社会で活躍する人材を多数輩出している。 以上のように、関嶋政和氏は、研究会運営や論文誌編集など学術基盤の整備・発展に長年尽力されるとともに、学術研究・社会実装・人材育成の各側面で極めて大きな成果を上げている。近年の我が国のコンピュータサイエンス領域、とりわけ数理モデル化とその応用領域の発展に対する功績は誠に顕著であり、 *CS領域功績賞*の受賞候補者としてふさわしい人物である。ここに同氏を強く推薦する。 |
| [ 戻る ] |
| 山下 茂 君 (量子ソフトウェア研究会) |
| [推薦理由] 本会正会員山下茂君(フェロー)は,早くから量子計算分野における量子回路設計自動化に関する研究に従事し,これまでに先駆的な研究業績を数多く残している.例えば、ブール関数を計算する量子回路の設計理論に関して,局所変換ルールによる最適化という新しい研究分野を切り開かれた.この成果は今日でも広く引用され,IBMのQiskitでも応用されるなど国際的に高く評価されている.その先駆的な研究業績に対して,The 2000 IEEE Circuits and Systems Society Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems Best Paper Award,2010年度丸文学術賞,本会2010年度山下記念研究賞,2024年度電子情報通信学会論文賞等を受賞している. また,国際会議AQIS (Asian Quantum Information Science Conference) の運営を長年担い,アジア最大規模の量子情報科学会議へと発展させることに大きく寄与されたほか,国内では本会量子ソフトウェア研究会の主査・幹事および,電子情報通信学会量子情報技術特別研究専門委員会の幹事として,国内外の量子計算の研究コミュニティ形成に尽力されている. このように,山下茂君は,我が国の量子計算の研究コミュニティの発展に極めて顕著な貢献をされており,CS 領域功績賞に相応しい人物として強く推薦する. |
| [ 戻る ] |