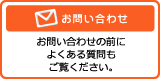- SJ2015ホーム >
- ITフォーラムセッション >
- IPA/SEC 情報処理推進機構(関連団体)
本セミナーは、ITコーディネータ協会(ITCA)に後援をいただいていますので、実践力ポイント獲得の機会となります。当日受付も行っておりますのでITコーディネータの方も奮ってご参加ください。
※ポイント認定につきましては、遅刻・早退を認めておりませんので、あらかじめご了承ください。
● 出席証明書はセミナー受付時にお渡ししますのでお申し出ください。
● セミナー終了後、事務局確認印を押印いたします。
氏名、ITC資格No.をご記入の上、受付にお越しください。(事務局確認印が無い場合、ポイントは無効です)
プログラム[09:30〜12:00]
| [09:30-09:35]オープニング/本セッションの趣旨説明 | |
 |
司会:山下 博之(独立行政法人情報処理推進機構(IPA) 技術本部 ソフトウェア高信頼化センター(SEC) システムグループリーダー) 【略歴】1981年京都大学大学院修士課程(情報工学)修了。同年、日本電信電話公社(現NTT)入社。以後、研究所において、通信制御処理システム、高機能通信プロトコル、分散協調処理、著作権管理、コンテンツ流通等に関する研究開発・標準化活動に従事。2003年10月に(株)NTTデータに転籍。2004年~2008年、JSTに出向。2009年4月に(株)NTTデータアイ入社、同時にIPAに出向。2003年10月~2008年4月、科学技術振興調整費プログラムオフィサー。2010年4月~2014年3月、本学会電子化知的財産・社会基盤研究会主査。情報規格調査会SC6専門委員会委員長。IEEE、情報処理学会、電子情報通信学会各会員。 |
| [09:35-10:10]講演(1):障害事例情報共有の取組みと事例分析により得られた教訓 | |
| 【講演概要】IPA/SECでは、重要インフラ分野を中心に、製品や機器及びITサービスの高信頼化を目指し、システムの障害事例情報の分析や対策手法の整理・体系化を通して得られる「教訓」を業界・分野を超えて幅広く共有し、類似障害の再発防止や影響範囲縮小につなげる仕組みの構築に取り組んでいる。本講演では、その取組みの概要とその中でまとめられた「教訓」の内容について紹介する。 | |
 |
山下 博之(独立行政法人情報処理推進機構(IPA) 技術本部 ソフトウェア高信頼化センター(SEC) システムグループリーダー) |
| [10:10-10:45]講演(2):サイバーセキュリティ情報共有の取組みにおける分析結果 | |
| 【講演概要】IPA/ISECは、重要インフラ関連事業者を中心に、サイバー攻撃に関する情報共有と早期対応の場として、サイバー情報共有イニシアティブ(J-CSIP:Initiative for Cyber Security Information sharing Partnership of Japan)を発足させ、5業界、50の参加組織間で情報共有を行い、高度なサイバー攻撃対策に繋げていく活動を行っている。本講演では、J-CSIPの活動状況と、その中で報告された事例の分析により得られた、国内組織に対する標的型サイバー攻撃の実態を紹介する。 | |
 |
松坂 志(独立行政法人情報処理推進機構(IPA) 技術本部 セキュリティセンター(ISEC) 情報セキュリティ技術ラボラトリー 主幹) |
| [10:50-11:25]講演(3):ソフトウェアサプライチェーンの課題とつながる世界のセーフティ&セキュリティ設計の見える化 | |
| 【講演概要】IPA/SECではソフトウェア開発のサプライチェーンに関わる課題調査を実施。今後、ユーザが自らアプリやサービスを組み合わせて利用する世界が広がり、ソフトウェア品質が異なる製品間の連携動作時に制御可否判断を行う仕組みや、想定されるリスクや不安な組み合わせを利用者に知らせるために警告する仕組みの構築等が必要とされている。これらの仕組み構築の環境整備の一つとして、つながる製品に求められるセーフティ&セキュリティ設計の見える化の取り組みについて解説する。 | |
 |
鈴木 基史(独立行政法人情報処理推進機構(IPA) 技術本部 ソフトウェア高信頼化センター(SEC) ソフトウェアグル—プ 研究員) 【略歴】1984年ローランド(株)入社 世界初フルデジタル ミュージックシンセサイザ D-50デジタルエフェクト部設計、1989年(株)松下電器情報システム名古屋研究所 入社、ATMネットワークを使った疎結合マルチプロセッサシステムのビデオサーバ開発(BS静止画システム)、2006年 松下電器軟件開発(大連)有限公司 出向、2007年 Panasonic R&D Center Vietnam Co.Ltd. 駐在、2013年 IPA/SEC出向 |
| [11:25-12:00]講演(4):イノベーション創出に向けたIT融合人材の育成 | |
| 【講演概要】ITは従来からの効率化の追求に加え、近年では新たな価値を創造するための推進力としての役割を担いつつある。このようななか、ITとビジネスの融合領域で新事業・新サービスを創出する「IT融合人材」の育成が課題となっている。新たな価値創造を通じてイノベーションを創出する人材が担う役割や求められる能力について紹介する。また「IT融合人材」が活躍するためには組織としての取組みが重要になるが、新たな価値創造を促進する組織のあり方とはどのようなものかについて紹介する。 | |
 |
武田 敏幸(独立行政法人情報処理推進機構(IPA) IT人材育成本部HRDイニシアティブセンター) 【略歴】PwCコンサルティング株式会社にて、ERP基幹系システムやその他のITシステム導入においてプロジェクトマネージャーを担当。その後、国内ERPベンダーで人事制度策定及び人材育成を担当。2011年より独立行政法人情報処理推進機構(IPA)HRDイニシアティブセンターでIT人材育成に関する企画業務を担当。IPAおいては2012年に中小企業のサービス型ビジネスへのシフトを促進することを目的とした「サービスインテグレーション型ビジネス」テンプレートの作成事業を担当。2013年から、イノベーションを起こし新たな製品・サービスを創出する「IT融合人材」について育成や組織環境のあり方について検討する「IT融合人材育成連絡会」の事務局を担当。また、「IT融合人材」の育成フレーム整備事業においてイノベーション創出におけるタスク定義やそのタスク実行の際に求められるスキル定義などを行う。 |
All Rights Reserved, Copyright (C) Information Processing Society of Japan