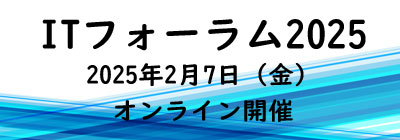サービスサイエンスフォーラム オンライン開催
ITフォーラム2025
─サービスサイエンスフォーラム─
日時:2025年2月7日(金)9:00-12:00
会場:オンライン
サービスサイエンスとイノベーションとビジネスモデルを考える
今回のITフォーラムでは、サービスビジネスを劇的に改善してくれるイノベーションやビジネスモデルについて議論してみたい。これまでの研究でサービスビジネスの収益性を改善するためにイノベーションやビジネスモデルが重要であることを主張してきたが、イノベーションやビジネスモデルを開発する方法は明確になってこなかった。このヒントになる議論を展開してみたい。
-
[9:00-9:05]オープニング
 司会:柴崎 辰彦(国立大学法人 香川大学 客員教授 富士通株式会社)
司会:柴崎 辰彦(国立大学法人 香川大学 客員教授 富士通株式会社)
【略歴】富士通株式会社にてネットワーク、マーケティング、SE、コンサル等、様々な部門での“社線変更”を経験。富士通で初めてのデジタル部門の創設や「FUJIHACK」など様々なプログラムの立ち上げ、サービス開発に取り組む。現在、「EnterpriseZine」にて「富士通 柴崎辰彦の『一番わかりやすいDX講義』」を連載中。CRMビジネスの経験や社会課題をテーマとしたコミュニティサイトの立上げを踏まえ、サービスサイエンスやオープン・サービス・イノベーションを実践 。サービス学会発起人 。日本ナレッシジマネジメント学会、情報処理学会、電子情報通信学会、大学等で講演多数。著書『勝負は、お客様が買う前に決める!』(ダイヤモンド社)。 -
[9:05-9:45]Session1「イノベーションが進まないのは何故か?~EMIC(イノベーションの場の評価モデル)によって分かったこと~」

イノベーションの場の整備はブームと化した感がありますが、目的を達成しているのは20%にも満たないとのショッキングな調査結果もあります。
このような局面を打開するため、FCAL: Future Center Alliance Japanは、2019年に世界に先駆け「イノベーションの場のインパクト」調査をもとにEMIC (Evaluation Model for Innovation Centers)モデルを提案し、ベンチマーク調査を実施してきました。
今回は、一連のリサーチから明らかとなったイノベーションの場が機能不全に陥る要因と、苦衷からの脱却ストーリーを紹介します。中分 毅(FCAJマイスター、多摩大学大学院客員教授)
【略歴】日建設計代表取締役副社長、日建設計総合研究所代表取締役所長
世界のトップ5にランクされる日建設計にて、プロジェクト・マネジメント、工場跡地等の開発、駅まち一体型再開発の海外マーケティング、会社経営に従事し2020年退任。その後、中国華東建築設計研究院総院などを対象にコンサルティング活動中。プロジェクトの成功率を高めるためのプロジェクト・デザインの方法論開発が中心テーマである。その一環としてイノベーションの場の整備が直面している課題の解決にも取り組んでいる。
〈著書〉
「駅まち一体開発~公共交通思考型まちづくりの次なる展開」新建築 2013(編集・分担執筆)
「土地はだれのものか」白楊社 2019(分担執筆)
「駅まち一体開発TOD46 の魅力」新建築 2019 (分担執筆) -
[9:45-10:30]Session2「地方発!修理から始まる伝統産業活性化プロジェクト」

創業明治41年、刃物の製造・修理をしている鍛冶屋で、石川県能登半島の漁業や農業の営みや人々の生活を道具の力で支えてきました。能登は言わずと知れた少子高齢化等に伴う過疎地で、商圏を拡大していかないと商売が成り立たないことから、地元役場から転職した4代目が、2018年にポチスパ(包丁研ぎ宅配サービス)を開始し、2023年にはネットを通じて全国から2万本以上の包丁の修理が舞い込むビジネスモデルに成長した。
しかし、能登半島は2024年1月の震災や9月の豪雨で過疎に更なる拍車が掛かり、能登の産業は壊滅的な状況に追い込まれた。そうした中、このビジネスモデルを改良し、他の産業でも活用できるように新たなプロジェクトを開始し、この震災からの復興を象徴する事業として成長を目指した。リペアから始まる新しい消費の形を目指す、伝統産業活性化プロジェクト。物があふれている時代。愛着のある物を修理して長く大事に使う時代へと移行してきている転換期。課題先進地である地方から、全国、世界へと事業展開を進めたい。干場 健太朗(株式会社ふくべ鍛冶 代表取締役)
【略歴】石川県能登町にある老舗鍛冶店「ふくべ鍛冶」4代目店主。大学卒業後は能登町役場にUターン就職し、中小企業支援などの業務を担当していたが、2015年に母の病死を受け傾いた家業を立て直すべく職人の世界へ。最短でも15年かかるといわれる専門技術の習得に励みつつ、コロナ禍のキャンプ需要にヒットした万能ナイフ「能登マキリ」や、切れなくなった包丁を箱に入れて送ると美しく磨がれて返送される包丁研ぎの宅配サービス「ポチスパ」など、独自のアイデアでヒットを生み事業拡大に成功。鍛冶屋として生き残ることで、漁師や海女が昔から愛用する専門性の高い道具も製造・修理が可能な砦となっている。年始の能登半島地震以降は、火災跡から掘り出された輪島塗職人の道具の優先的な修復活動や、ポチスパの受注管理システムを生かした伝統産業品の修理プラットフォーム「リペアクラウド」の立ち上げなど、さらに多方面で地域支援を行っている。 -
[10:30-11:10]Session3「イノベーションドライバーでビジネスモデルを作る」

日本の多くのサービス業は、顧客満足向上を目指して努力してきた。この結果、インバウンド顧客から日本のサービスは高く評価されている。顧客満足の向上はサービス事業を安定継続するためには必要だが、この努力だけではサービスの収益性は改善できないことが明白になってきている。収益性を高めるためには、サービスの価値を高めることが大切で、このためイノベーションを実現しなければならない。また、妥当なプライシングも必要である。そして、決め手になるのが利益を出せるビジネスモデルの創造である。
私は多くの企業の方々とお付き合いしてきたが、ビジネスモデルを作れる方には出会っていない。日本のGDPの7割がサービス業で残りの大半を占めている製造業もサービスで競争する時代になっている。ところが大学ではビジネスモデルの事例は教えているが、ビジネスモデルの作り方までは教えてくれない。この問題の1つの解決策を示してみたい。諏訪 良武(ワクコンサルティング 常務執行役員)
【略歴】71年オムロン入社。85年通産省のΣプロジェクトに参加。95年情報化推進センター長。97年オムロンフィールドエンジニアリングの常務取締役として保守サービス会社の変革を指揮。06年ワクコンサルティング常務執行役員(現職)、10年多摩大学大学院客員教授。サービスや顧客満足を科学的に分析し、サービス企業の変革を支援するサービスサイエンスを提唱している。著書「顧客はサービスを買っている」ダイヤモンド社、「いちばんシンプルな問題解決の方法」ダイヤモンド社、「サービスサイエンスによる顧客共創型ITビジネス」翔泳社、「サービスの価値を高めて豊かになる」リックテレコム社、「心理ロイヤティマーケティング」翔泳社など。 -
[11:10-11:15]休憩
-
[11:15-12:00]パネルディスカッション
3人の講演についての質問を受け付ける。柴崎さんの司会で議論を展開する。
その後、サービスビジネスを劇的に改善してくれるイノベーションやビジネスモデルについて議論する。これまでの研究でサービスビジネスの収益性を改善するためにイノベーションやビジネスモデルが重要であることを主張してきたが、イノベーションやビジネスモデルを開発する具体的な方法は明確になってこなかった。このヒントになる議論を展開する。
-
 柴崎 辰彦(国立大学法人 香川大学 客員教授 富士通株式会社)
柴崎 辰彦(国立大学法人 香川大学 客員教授 富士通株式会社)
-
 中分 毅(FCAJマイスター、多摩大学大学院客員教授)
中分 毅(FCAJマイスター、多摩大学大学院客員教授)
-
 干場 健太朗(株式会社ふくべ鍛冶 代表取締役)
干場 健太朗(株式会社ふくべ鍛冶 代表取締役)
-
 諏訪 良武(ワクコンサルティング 常務執行役員)
諏訪 良武(ワクコンサルティング 常務執行役員)
-
 渡部 弘毅(ISラボ 代表)
渡部 弘毅(ISラボ 代表)
【略歴】日本ユニシス(現 BIPROGY)、日本IBM、日本テレネットを経て、2012年にISラボ設立し、心理ロイヤルティマネジメントのコンサルティング活動中。お客様の心理ロイヤルティアセスメントに関する独自の方法論を提唱。ファンづくりの科学的かつ実践的なコンサルティング手法が注目されている。業界団体や学術団体での研究活動、啓蒙活動にも積極的に取り組んでいる。
〈著書〉
「顧客ロイヤルティ丸わかり読本」(2023/11 リックテレコム)
「お客様の心をつかむ 心理ロイヤルティマーケティング」(2019/12 翔泳社)
「営業変革 しくみみを変えるとこんなに売れる」(2005/1 メディアセレクト)
-
 佐藤 秀樹(日本電気株式会社 ビジネスアプリケーションサービス統括部)
佐藤 秀樹(日本電気株式会社 ビジネスアプリケーションサービス統括部)
【略歴】2007年日本電気株式会社入社。IT戦略およびデジタル化支援のITサービス事業を多数経験、企画・提案・設計・実推進・管理・改善など全領域を牽引。近年はリテール業向け設備LCM領域のDX新事業企画に従事、コンサルティング・データサイエンス・エンジニアリングの3領域横断サービスを推進。サービスサイエンスフォーラム共創プロセスモデル分科会リーダー。サービス学会SIG実学としてのサービス科学・知識科学研究会メンバー。書籍「Business Innovation with New ICT in the Asia-Pacific: Case Studies」(Springer)執筆メンバー。
-
 倉増 京平 (一般社団法人インディペンデント・プロデューサーズ・ギルド 代表理事)
倉増 京平 (一般社団法人インディペンデント・プロデューサーズ・ギルド 代表理事)
【略歴】1979年大阪府生まれ。高校卒業後、進学を口実に上京するも受験失敗。新聞配達員、ホテルマン、英会話教材セールス、駅でのお弁当販売員、人材派遣の営業、ITベンチャー営業など様々な職を転々とし紆余曲折の末2002年 電通グループ企業(現社名 電通デジタル)に入社、ようやく定職に就く。2009年心臓病を患い人生の転機を迎える。その後、様々な社会情勢の変化の中で「会社の仕事だけしてる場合ではないな」と複業活動を始める。2023年、Independent Producer(自律した職業人)の養成・連帯・分配を目的とした、一般社団法人インディペンデント・プロデューサーズ・ギルドを設立。挑戦者を応援するのが人生ミッション。
-