人とロボットが共存し協調して働く社会のプラクティス
参加者:小野田弘士(早稲田大学),増田景一(京セラコミュニケーションシステム(株)),深田雅之((株)ゼンリン),後藤 悠((株)日建設計)
司会:江谷典子(全日本空輸(株))
インタビューイ:久保 仁(川崎重工業(株))
インタビューア:江谷典子(全日本空輸(株))





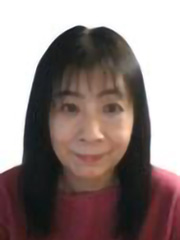
座談会 超スマート社会のサービス実現に向けたロボットの情報技術の課題
座談会の趣旨
江谷:本日司会を務めさせていただく江谷です.人とロボットが共存し協調して働く社会のプラクティスでは,社会実装における課題を解決する上で情報処理技術に関する期待はあるのですが,その必要性が十分に認知されていない状況です.実証実験にかかわれてこられた皆様には「超スマート社会のサービス実現に向けたロボットの情報技術」の課題をお話いただき,共有し,課題解決に向けた議論を行いたいと思います.
参加者の自己紹介と取り組み紹介
江谷:本日お集まりになった皆様の自己紹介と取り組み紹介をお願いします.
小野田:早稲田大学の小野田でございます.小型モビリティ・配送ロボットの開発や地域等におけるモビリティ関連プロジェクトのマネジメント等を実施しています.現在は,南栗橋駅前街区でのまちづくりと一体となったプロジェクトでの経験を中心に議論に参加させていただきます.
江谷:現在取り組んでおられるプロジェクトについてご紹介ください.
小野田:「BRIDGE LIFE Platform構想」は,埼玉県久喜市の南栗橋駅前街区で進められているいわゆるグリーンフィールド型のまちづくりと次世代モビリティの導入検討を一体的に進めているプロジェクトです.マイクロコミュニティ内での自動配送や非接触型ごみ収集等の複数の用途で活用可能なマルチベネフィット型モビリティの開発とPoCおよびまちづくりのインフラ整備を一体となって進めるアプローチを特徴としています.
増田:京セラコミュニケーションシステムの増田です.私どもでは車道を走行する無人の自動配送ロボットに取り組んでいます.物流における人手不足や過重労働に対する取り組みであるとともに,ロボットが巡回することで人だけではなくサービスも移動するような,未来のまちづくりを目指しています.
深田:ゼンリンの深田です.AI・ロボティクス・位置情報ビッグデータを活用した先進まちづくりの支援が専門です.現在,秩父市をフィールドとしたドローン物流やAIデマンド交通,遠隔医療等の社会実装に取り組んでおります.
後藤:日建設計の後藤です.日建設計は1900年に創業した都市計画や建築設計に携わる会社で,都市・建築やその周辺領域を通して社会課題を解決することに取り組んでいます.スマートプラスラボでは,ビル管理のスマート化,設計プロセスの効率化などに取り組んでいます.
江谷:都市計画や建築設計のお立場からのスマート化への取り組みは,情報処理技術者としてはぜひお聞きしたいことです.
後藤:弊社では清掃・警備・館内配送などビル管理・運営業務における人手不足の解消として,Smart Operation Buildingという構想を2020年に発表しました.建築設計上の工夫とIoTの活用により人手不足の解消に貢献しようという思想ですが,その中の重要な要素の1つがロボットでした.
江谷:建物とロボットというのはいろいろと課題がありそうですね.室内というのは,自律移動ロボットの身動きができないデッドロックとなる場所があるので通行禁止にしたり,光によるセンサ類の誤認識があるのでバイザーを取り付けたりして,ロボットが確実に動作するように場所を整えることも必要でしたから.
後藤:重要なのはロボットを普及するためには建物も変わらなければいけないという視点.今でいうところのロボットフレンドリービルの実現を目指して,課題抽出,安全対策の実証から開始しました.その後,経産省のロボットフレンドリー環境構築事業やロボットフレンドリー施設推進機構☆2にも参加しています.
サービスロボットの課題
江谷:みなさん,大変な取り組みに携わっておられますね.自動配送ロボットやドローンを使った新しいサービスの実証実験やビルなど屋内環境をロボットフレンドリーに構築する実証実験にかかわらないと分からない課題,特に情報技術の課題は分からないですね.
では,皆さんが発見された課題や問題点をお話しください.
小野田:モビリティ・ロボット等のハードウェアだけでなく,通信インフラや既存インフラ(道路等)との一体的な取り組みが社会実装のためには必要です.
たとえば,再開発等では,モビリティ・ロボットの専用レーンや移動しやすい道路整備を配慮するだけでも実装しやすくなります.さらに,街区内にセンサ等を設置し,モビリティ・ロボットと通信する仕組みも有効と考えます.
江谷:増田様の取り組みは,無人の自動配送ロボット(図1)という観点から,小野田先生が指摘される視点が共有できるのではないでしょうか.

増田:課題は,コストバランスと早期の社会実装だと思います.
無人のロボット専用に通信や道路インフラを整備していては,社会全体のコストは高くなり普及が遅れます.一方で,既存の通信や道路インフラは,無人のロボットが走行することを考慮していない.既存の利用者からの反発を招き,社会受容的にも技術的にも高い困難を生じてしまいます.
既存インフラを活用して,利用者の理解も得ながら,早期の社会実装を図るために,バランスの取れたインフラ整備と社会全体の取り組みが必要です.
江谷:無人の自動配送ロボットによるサービスの課題はありますか.
増田:サービス空間の運用について課題はあります.たとえば,移動する商店ともいうべきサービスカーをスマートフォンで呼び出し,お昼のご飯を買う,という道路上の商行為は道路交通法では認められていません.今は許可を取って私有地に退避して移動販売を行ったりしていますが,場所を限定してしまうと,移動することのメリットが出せず,ロボットは自動販売機と同じような提供価値になってしまいます.
江谷:空間を動くことができるサービスロボットの価値を社会的に認めていただくことが必要ですね.
増田:大丸有の実証実験のように道路をサービス空間とすることができれば,街の賑わいにもつながるため,こうした賑わい空間が全国の住宅街に広がると,ロボットが活動しやすいと考えています.
江谷:ドローンによるサービスの課題はありますか.
深田:中山間地域特有のロボット(ドローン)導入に向けた課題について説明いたします.国の規制緩和は進んでおり,2023年12月には一定の要件を満たせば,道路横断の際に監視者や立て看板の設置が不要となり,現地運用のコスト低減が期待されます.一方で,ドローンは現在位置やバッテリー残量等の把握には通信が必要ですが,中山間地では通信環境の不感地域が多く,飛行できない場所が多数存在します.また,配送用の機体は,数㎏の荷物を10㎞程度飛行可能なスペックであり,最大積載量350㎏の軽貨物車両と比較してもコスト効率が上がりません.収益性も課題になっています.
江谷:屋外のインフラについて課題が多くあるようですが,建物という屋内ではいかがでしょうか.
後藤:前に発言したとおり,これまでの建物はロボットを想定した設計は行われていませんでした.
江谷:そのこと自体が課題であり問題であるわけですね.建築設計のお立場からはどのようにお考えでしょうか.
後藤:ロボットを普及するには建物のロボットフレンドリー化が必要ですが,対策には費用がかかるところです.新築なのか既存の建物なのか,オフィスビルや集合住宅などの建物用途,導入されるエレベータなどの設備によっても,対策も予算も異なる.それぞれに対して,優先順位をつけたロボットフレンドリー化の整理が必要だと考えています.
課題に対する提言
江谷:情報技術と社会基盤整備の問題を多くご指摘いただきました.今後,どのように対応すれば良いかについてご意見を伺えますか.
後藤:現在,ロボットフレンドリー施設推進機構(RFA)では,建物内の各空間がどの程度ロボットフレンドリーな環境になっているかを評価するロボフレレベル☆3という指標を作成しており,弊社もそこに参画しています.
江谷:ロボフレレベルとはどのような指標でしょうか.
後藤:施設管理分野における評価指標です.床の段差や扉幅,使われている素材の反射や光沢,日射の有無などが評価項目として挙げられており,基準値をもとにA〜Cの3段階で評価を行います.
まずは,どの空間のどの要素がロボットフレンドリー化を進める上でのハードルになっているかを明確にすることができる指標だと考えています.
江谷:建築設計が対応できる課題を抽出できるわけですね.
後藤:課題が明確になれば,弊社のような設計事務所にご相談いただければ,その建物に応じた対策のご提案ができますし,対策の例示などもしていきたいと思います.
今後の期待
江谷:いろいろなプロジェクトが行われて,実証実験による課題を提示してきているようです.今後,さらに実証実験を続けて,社会実装を成功させるために期待されていることがあればお話しください.
小野田:各プロジェクトの知見・経験を共有し,それを効率的に水平展開する取り組みが必要であり,期待しているところです.たとえば,地図情報や学習データ等を共有化できるプラットフォーム構築の必要性を強く感じています.
江谷:後藤様が取り組んでおられる施設管理分野の評価指標ロボフレレベルから水平展開する動きが見えてきたというところですね.
都市計画や建築設計のお立場から期待されていることは何かありますか.
後藤:弊社はまず建物内のロボットフレンドリー化から取り組んでいますが,今後は建物の中も外も,できれば共通化されたプラットフォームもしくはスマートシティOS☆4などの上位システムと連携して街全体がロボットにも当然人にもやさしい環境になっていくことを期待しますし,実現していきたいと思います.
江谷:小野田先生のご指摘が,サービスロボットを導入するための評価指標だけではなく,都市OSにまで取り込まれると実証実験は取り組みやすくなり,社会実装の成功事例が増えていきそうです.
本日は,どうもありがとうございました.
インタビュー ロボットフレンドリーな環境構築から見えたサービスロボットの課題と可能性
江谷:58号特集の企画構想中に,「そろそろ始まるか」という感覚で,「Future Lab Haneda」の資料☆5を拝見いたしました.サービスロボットの研究開発と現場(レストラン)が一体化した環境でロボットフレンドリーな環境を実現するという実証実験には非常に興味を持ちました.産業用ロボットとは異なり,空間には人間も存在する.人間も開発者だけではなく,レストランで食事をされるお客様もいらっしゃるという非常にシビアな環境であると思います.
社会実装の取り組みは,人間社会と新しい技術との接点で,Society 5.0が提唱する人間を中心にした社会に上手く新しい技術を導入することが求められています.技術面だけではなく,人間社会面にも多くの課題がありそうです.
今回,川崎重工業様の「Future Lab Haneda」でロボットフレンドリーな環境構築から見えたサービスロボットの課題と可能性についてお話をいただきます,久保様,自己紹介をお願いいたします.
久保:川崎重工業の久保と申します.よろしくお願いします.
川崎重工業に入社した当初からロボット部門に所属し,10年以上,産業用ロボットの本体ソフトウェアの開発に従事しておりました.主に,自動車メーカ向けの機能開発を担当していたことから,4年ほど米国に赴任した経験もあります.米国では自動車関連顧客を中心に,現地エンジニアのサポートや技術教育に従事する傍ら,北米における新規市場開拓にもかかわっていました.ロボット分野でも台頭し始めてきたスタートアップとの協業を模索しており,ロボットの活用の場の拡大を考える上で,良い経験になりました.
2021年8月に川崎重工業に帰任し,まだ,ロボットの導入が進んでいないサービス業界などの分野向けの自律移動型ロボットの試作機の開発に従事し,現在に至ります. 学生時代の研究テーマに「ロボットの歩行」を選んでいたこともあり,まわりまわってここに来たかという因果のようなものを感じながら,業務にあたっています.
江谷:素敵なお仕事に従事されてきて,今,どのような取り組みをなさっているのですか.
久保:会社の背景を説明し,現在の担当について説明いたします.
川崎重工業のロボット事業は,1968年 米国ユニメーション社と技術提携し,日本初のロボットメーカとして事業を開始.現存する世界最古のロボットメーカです.
産業用ロボットメーカとして歩みを進めてきたが,50周年を機に,産業界のみならず,さまざまな業界の課題をロボティクスの力で解決する総合ロボットメーカへ転身を目指し,近年は産業用ロボット・医療ロボットに加え,広く社会に役立つソーシャルロボット☆6の開発にも注力しています(図2).世間的にサービスロボットと言われている分野とも言えますが,その中でも,社会貢献するロボットを,弊社では,「ソーシャルロボット」と呼んでいます.私の部門では,アーム付き自律移動型ロボット「Nyokkey」(図3)や2脚のヒューマノイド「Kaleido」「Friends」の開発を担当しています.


江谷:双腕のある「Nyokkey」はFuture Lab Hanedaでウェイタとして働いているロボットですね.
久保:はい.現在,自律移動型ロボットが市場に出始めていますが,その多くは,簡単な運搬やコミュニケーションの用途にとどまっています.その一因として,多くの自律移動ロボットが腕を持たないことにあると考えています.
人が使うように設計されている空間で,人と同じように行動でき,人に代わってさまざまなタスクをこなせるように,「Nyokkey」には,2本の腕を持たせています.実際にビジネスベースとして成り立たせるため,社内外のPoCや展示会などを通じて,その有用性の確認や課題の抽出を行っているところです.
今回,招待論文で取り上げているのは,Nyokkeyの社会実装を目指した,羽田イノベーションシティ(HICity)内のKawasakiのラボ「Future Lab HANEDA」(FLH)での取り組みについてです.
江谷:ロボットの働く環境はどのように捉えておられますか.
久保:はい.自律移動型ロボットは,さまざまなセンサを用いて,周りの状況を把握して動作しますが,人を中心として設計された空間は,必ずしもロボットにとってフレンドリーではありません.
FLHでは,什器(椅子・机)のデザインを工夫したり,マーカを付けたりしています.また,通信の脈動/遅延,遮蔽物の問題などもあり,通信の環境を整えるのも重要と考えています.
これらの点は自律移動型ロボットに携わる人の共通認識であり,たとえば,ロボットフレンドリー施設推進機構(RFA)では,あらゆるタイプの施設においてロボットの導入を実現するため,ロボットフレンドリーな環境の構築を支援する活動を行っています.
江谷:ロボットフレンドリーな環境ではサービスロボットの運用について,どのようにお考えですか.
久保:産業用ロボットを運用する上で,セーフティーを考慮して,すでに多くの規格やルールが存在しています.
サービスロボットに関しても,利用者や周りにいる人の安全を考え,同様に規格やルールが必要になってくるであろうと思います.しかし,人とのかかわり方は,産業用ロボットとサービスロボットで同じように考えられるところと,異なるところが存在すると考えています.
江谷:すでに,サービスロボットの国際安全規格ISO 13482☆8が日本主導で2014年に策定され,規格の普及が進んできていますが,ロボット本体が機械として安全であっても,運用方法を誤れば危険な状況が起こる可能性はあります.運用方法について,産業用ロボットとは異なる規格やルールが必要ですよね.
久保:日本ロボット工業会(JARA)では,サービスロボットの国際標準化に向けてISO化への活動をしており,その中で,サービスロボットの運用によるリスク管理手法を一般化し国際標準化することで広く知見を共有しグローバルなサービスロボット市場の拡大に繋がると考えられたISO 31101☆9の発行が間近です.
しかしながらISO 31101ではすべてのアプリケーションサービスを包含することを狙った要求事項を設定したため抽象度の高い内容を多く含んでいるため実際のサービスにおける実施事項はアプリケーションサービスプロバイダ次第であり,規格適合に向けたハードルは高いです.
江谷:センサで得られる個人情報の扱いなどセキュリティはいかがでしょうか.
久保:業界やアプリケーションを絞り込んで,具体的実施事項を抽出しガイドラインとしてまとめることで,サービスプロバイダが運用・安全上行うべき具体的事項を提供し,ロボットサービス実施の敷居を下げる必要があります.
江谷:セキュリティの課題へのアドバイスをありがとうございます.最後に,サービスロボットへの今後の期待をお話しください.
久保:ロボット自体の高性能化です.たとえば,「ロボットが人の情報を取る」「ロボットが人を理解する」です.精神的面では心理的な情報,身体的面ではヒトの動き(位置情報),指の動き,物理的接触の情報をあつかえることです.
江谷:人の状態を扱うことで,サービスロボットの働く場所が広がりそうです.
技術は日々進歩しますが,その技術を受け入れる人間社会における規格やルールなどガイドラインや評価指標の準備を進めなくてはなりません.サービスロボットが人間社会を助けてくれて,安全安心な生活が送れる未来を願います.
脚注
- ☆1 Society 5.0資料-内閣府.
https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/society5_0.pdf - ☆2 ロボットフレンドリー施設推進機構(RFA).
https://robot-friendly.org/ - ☆3 ロボフレレベル─経済産業省,ロボットフレンドリーな社会の実現に向けて~ロボット導入環境のイノベーション~,2022年.
https://www.nedo.go.jp/content/100953531.pdf - ☆4 スマートシティOS─スマートシティにおける都市OS.内閣府,スマートシティリファレンスアーキテクチャ ホワイトペーパー(日本語版),2023年.
https://sbircao02-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kagisoukatsu1_sbircao02_onmicrosoft_com/EWetOIFrC0FMo1SQ-WXc_pgBkiqf0-bdM8785FsOmh75PA?e=JnPnFl - ☆5 https://kawasakirobotics.com/jp-sp/future-lab-haneda/
- ☆6 グループビジョン2030・進捗報告会,2023年.
https://www.khi.co.jp/ir/library/other_presen_210601.html
https://www.khi.co.jp/ir/pdf/etc_231212-1j.pdf - ☆7 FORRO(フォーロ).
https://www.khi.co.jp/groupvision2030/deliveryrobots.html - ☆8 ISO 13482 2014年2月1日に発行されたサービスロボットや生活支援ロボットの安全規格である.
- ☆9 ISO 31101, Robotics —Services provided by service robots —Safety management systems requirements(サービスロボットによって提供されるサービス─安全管理システム要件)
会員登録・お問い合わせはこちら
会員種別ごとに入会方法やサービスが異なりますので、該当する会員項目を参照してください。