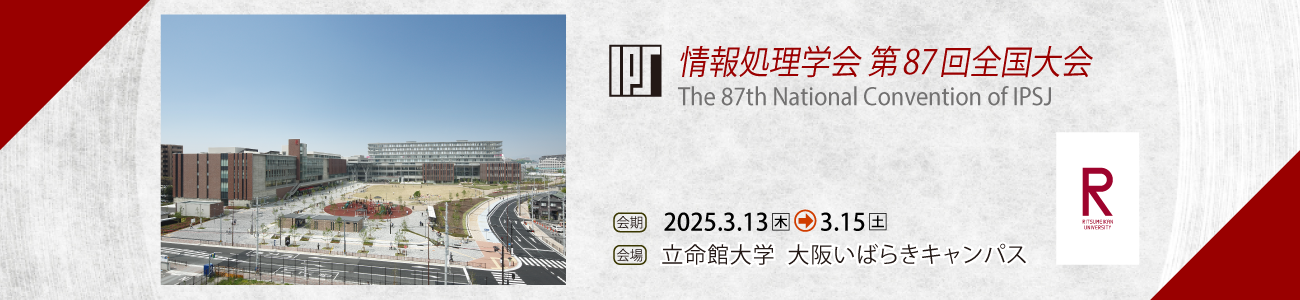
【セッション概要】78回大会より毎年開催している一年間のサイバー事件を振り返る企画。2024年は、元旦から能登半島地震が発生し、情報技術の利点・欠点共に改めて再認識することになった。情報法制面では、プロバイダ責任制限法がついに情報プラットフォーム対処法に更新され、EUではAI法が成立している。また経済安全保障関係では日本版のセキュリティ・クリアランス制度である重要経済安保情報保護法も成立した。一方で能動的サイバー防御の為の法整備は延期されている。技術的な話題としても、AIに関する新しい技術やサービスが次々に登場し、ノーベル物理学賞、化学賞までもがAIに関係するものであった。このようにデジタル情報・知的財産・社会基盤の法制度と情報技術の関係は、ますます重要な論点になっている。本パネル討論では、こうした法と技術の関係を扱うEIP研究会のメンバーによって、情報社会の健全な発展について意見を述べ合うものである。

【討論概要】・ネットワーク上の誹謗中傷問題やプラットフォーマー,媒介者の責任問題
・LLMを始めとするAIの影響
・EUのAI法,データ法を始めとする諸外国の情報関連法の最新動向と国内対応
・個人情報保護法制を始めとする国内の情報関連法の最新動向
・SNS等が政局に与える影響
・能動的サイバー防御や経済安全保障
・サイバー攻撃や情報セキュリティの課題
・DXやICTに関するガバナンス
・自動運転を始めとするICTと市民生活
・その他,情報処理学会に関連する分野の様々な事件や裁判例など
【略歴】新潟大学大学院法学研究科修了.修士(法学).専門は情報法で,サイバー犯罪,デジタル知的財産,情報セキュリティ制度,デジタル・フォレンジックなど,先端技術と法律の関係を中心に研究している.共著に「ITセキュリティカフェ--見習いコンサルの事件簿」(丸善),「実践的eディスカバリー米国民事訴訟に備える」(NTT出版),「基礎から学ぶデジタル・フォレンジック」(日科技連),「~法律構成の違いがわかる!~依頼者の属性別 弁護士が知りたいキャッシュレス決済のしくみ」(第一法規)など.本会「電子化知的財産と社会基盤研究会(EIP)」前幹事.
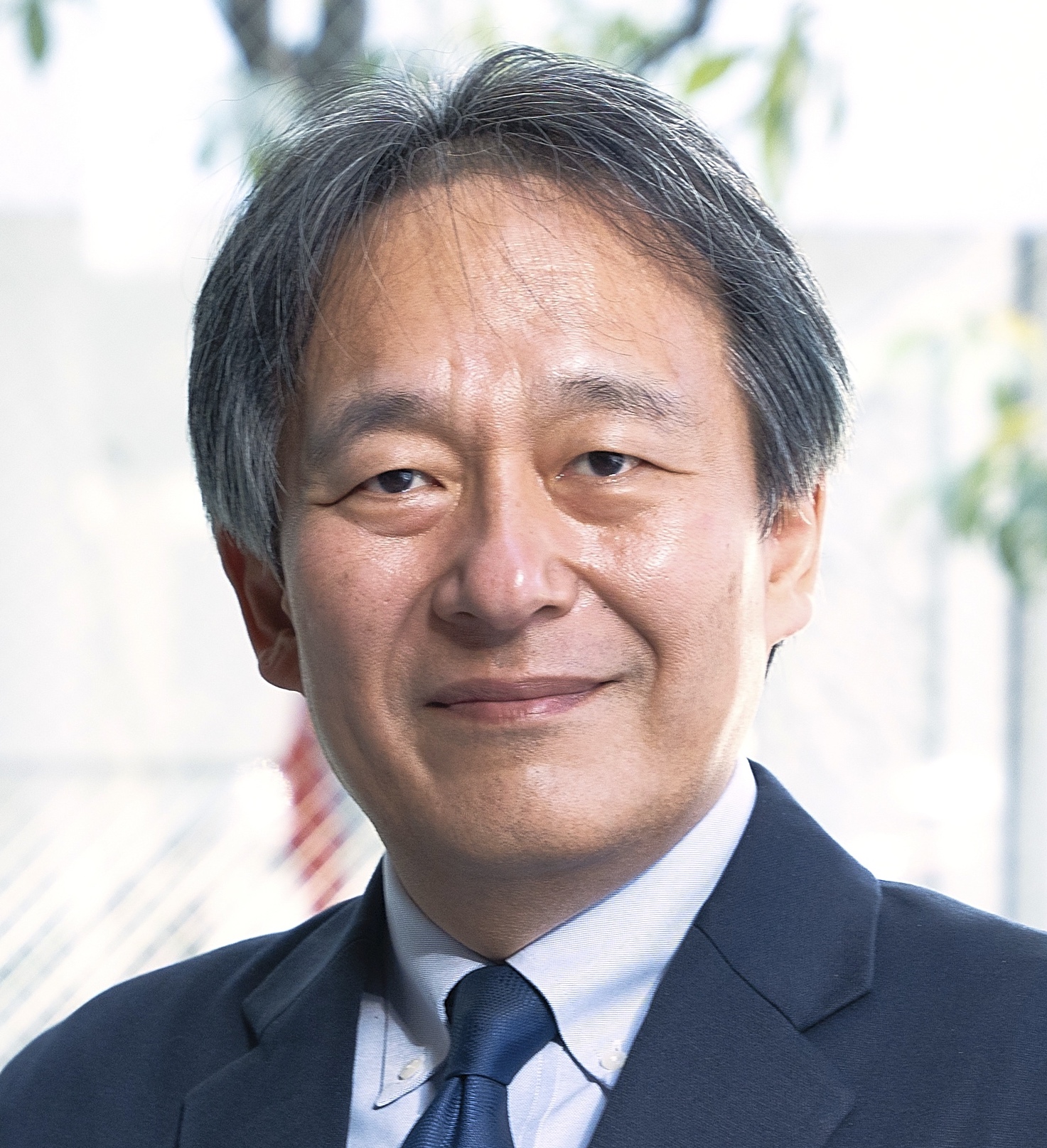
【略歴】情報通信総合研究所取締役法制度研究部長、早稲田大学客員准教授、日本大学教授等を経て、2020年より中央大学教授。1990年代初めから、情報化の進展によってもたらされる法制度上の問題をテーマとして幅広く研究を行う。主な著書として『情報法入門(第7版)デジタル・ネットワークの法律』(NTT出版、2025年)、『クラウドシステム移行・導入』(共著、オーム社、2022年)、『概説GDPR-世界を揺るがす個人情報保護制度』(共著、NTT出版、2019年)など。情報処理学会電子化知的財産権・社会基盤(EIP)研究会主査。

【略歴】2002年慶應義塾大学総合政策学部卒,2004年京都大学大学院情報学研究科社会情報学専攻修士課程修了,2007年慶應義塾大学法務研究科(法科大学院)修了.2008年弁護士(ひかり総合法律事務所).2016年4月よりパートナー弁護士.2010年4月より2012年12月まで消費者庁に出向(消費者制度課個人情報保護推進室(現・個人情報保護委員会事務局)政策企画専門官).2017年4月より理化学研究所革新知能統合研究センター社会における人工知能研究グループ客員主管研究員,2018年5月より国立情報学研究所客員教授.2020年5月より大阪大学社会技術共創研究センター招へい教授.当会EIP研究会幹事,法とコンピュータ学会理事等。
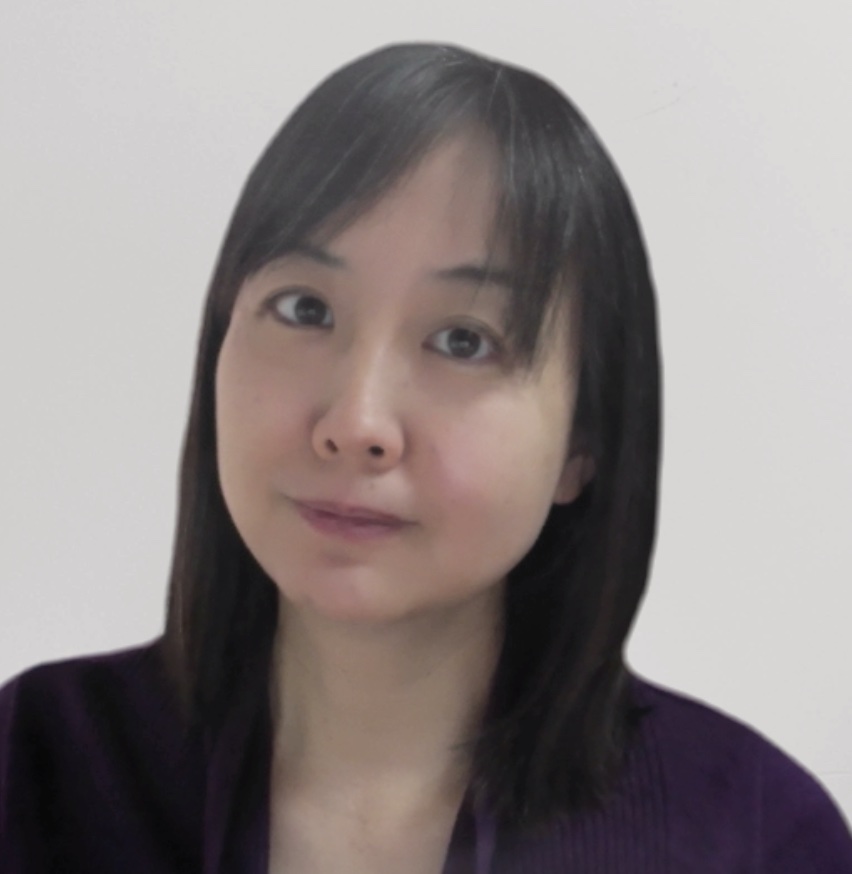
【略歴】1998年慶應義塾大学総合政策学部卒,2000年慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修士課程修了,2007年同大学同研究科にて博士(政策・メディア)取得.中央大学ビジネススクール助教,慶應義塾大学特任講師,米国ケネソー州立大学Visiting Assistant Professor等を経て現職.死後のデータやAIによる再生といった新たな技術と人・社会に関わる問題に関心を持つ. EIP研究会運営委員.情報社会学会理事.

【略歴】株式会社KDDI総合研究所において、情報法制(プライバシー・個人情報等)を中心とした法制度や技術の調査・研究・コンサル業務に従事。また、大学の非常勤講師として、情報法、知的財産法、情報セキュリティに関する講義を担当している。総合研究大学院大学複合科学研究科情報学専攻単位取得満期退学、修士(情報学)、理化学研究所革新知能統合研究センター客員研究員、神奈川大学非常勤講師、慶應義塾大学SFC研究所上席所員、一般社団法人次世代基盤政策研究所・理事・事務局長。