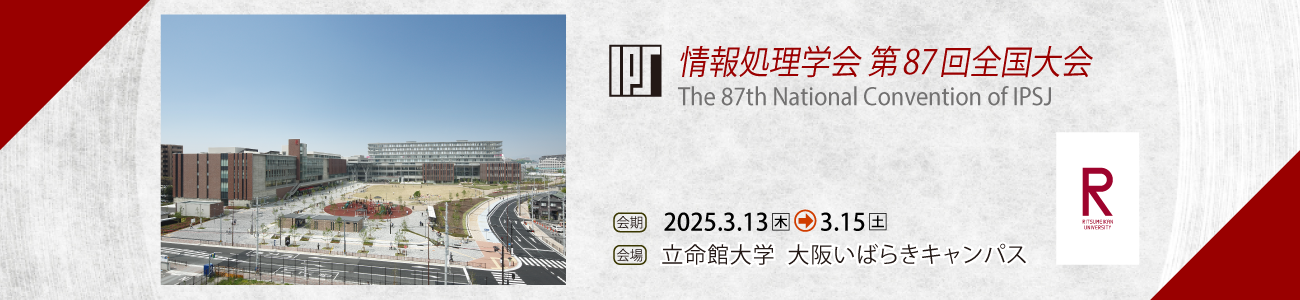
【セッション概要】新課程で「情報Ⅰ」を学んだ高校生が初めて臨んだ2025年度入学者選抜。大学入学共通テストに高校教科「情報」が導入され、また、大学によっては一般選抜の個別入試で「情報」を出題した。新課程「情報入試」元年を終えたこの時期に、出題された入試問題を振り返り、それを大学・高校・社会に伝えるとともに、今後の情報教育について議論する.

【略歴】日本大学文理学部 教授.(一社)情報オリンピック日本委員会 専務理事.計算論的位相幾何学・複雑ネットワーク解析などの研究,および,情報科学の普及活動に従事.IPSJ MOOC(https://sites.google.com/a.ipsj.or.jp/mooc/)「コンピュータとプログラミング」の制作に携わる.

【略歴】1988年 京大工学部情報工学科卒,1990同大学院 修士,1995同博士(社会人)了.博士(工学).1990~2004年 NTT研究所に勤務.2004年 北大情報科学研究科 助教授,2010年 同教授.2018年 京大情報学研究科 教授(現職).2009~2015年 JST ERATO湊離散構造処理系プロジェクト 研究総括.2012年 日本科学未来館「フカシギの数え方」展示監修.2020年より科研・学変(A)「アルゴリズム基盤」領域代表.2018~2019年および2021年より情報処理学会理事.2023年より「情報科学の達人」プログラム運営委員.情報処理学会フェロー,電子情報通信学会,IEEE 各シニア会員,人工知能学会,日本計算機統計学会 各会員.

【講演概要】高等学校情報科の発展と共通テストへの情報科の導入に伴い、これまでにない人数の高校生が毎年、プログラミングをはじめとするコンピュータサイエンスの内容を学びつつある。このことは、我が国の社会を大きく変える可能性をもたらしている。その一方で、これまで専門高校、高専、専門学校、大学で学んでいく中で学習者が身につけて来たコンピュータサイエンスの常識や素養に触れないままコンピュータやプログラミングに接する人たちが急増することで、さまざまな問題を引き起こす可能性があり、それを回避するための活動が今後求められて行くと思われる。
【略歴】1984年 東京工業大学理工学研究科情報科学専攻 単位取得退学。理学博士(東京工業大学)。東京工業大学助手、筑波大学講師、助教授、教授、電気通信大学教授を経て、現在電気通信大学特命教授、筑波大学名誉教授。本会 初等中等教育委員会、情報処理教育委員会、情報入試委員会、情報科教員・研修委員会 委員。日本学術会議 情報学委員会 情報学教育分科会 連携会員。プログラミング言語、ユーザインターフェース、情報教育に関心を持つ。
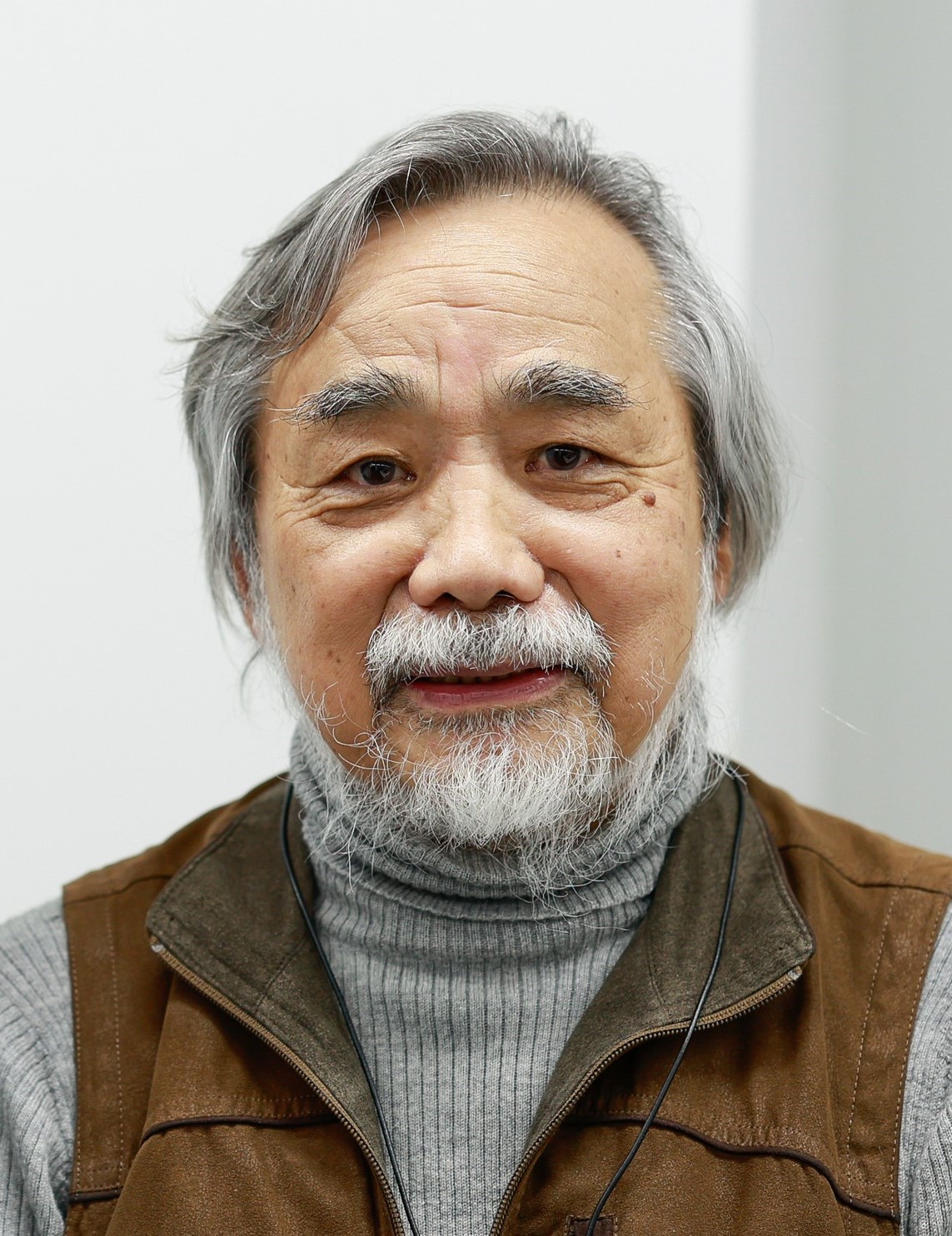
【講演概要】竹内が大学入試センターの「情報関係基礎」の作題に関わったのはもう25年近く前である.試験科目として見るととても厄介な性質を持つ「情報」を試験としてどう成立させるかについて大いに苦労した記憶が甦る.その苦労は20年ほど前に新設され,いろいろな迂余曲折を経て今日に至る教科としての「情報」のあり方でもずっと繰り返されていたように思う.講演では「情報関係基礎」の作題を担当していた当時の苦労と,新しく始まった共通テストの必修科目「情報I」の模擬試験を実際に作成してみて感じたデジャブなどを織り混ぜて,大学入試における「情報」について話題を提供したい.それを通じて,「情報」を学問の端くれとして世の中に認知させたいという願望を述べる.
【略歴】1971年東京大学数学専攻修士. 同年, NTT研究所.以来, 主に基礎研究部門において, 記号処理システムなどを研究・開発. 1997年電気通信大学情報工学科教授,2005年東京大学情報理工学系研究科教授,2011年早稲田大学基幹理工学研究科教授を歴任.現在,IPA未踏事業統括プロジェクトマネージャ,一般社団法人未踏代表理事など.東京大学名誉教授.博士(工学).
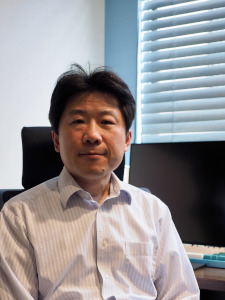
【講演概要】電気通信大学では,2025年度入試から始まる大学入学共通テストの出題教科「情報」の実施に合わせて,個別試験においても「情報」を導入する.具体的には,一般選抜前期日程において,これまで必須であった個別試験科目「数学」「英語」「物理』「化学」に「情報」を新たに加えた上で,「物理」「化学」「情報」については,これら3科目から2科目を選択する科目選択制に変更する.本講演では,その最初の個別試験「情報」の実施概要について紹介する.
【略歴】1996年豊橋技術科学大学大学院工学研究科博士課程修了.博士(工学).同年京都大学大学院工学研究科情報工学専攻助手.2003年豊橋技術科学大学情報工学系講師.2007年1月電気通信大学大学院情報システム学研究科助教授を経て2016年より現職.プログラミング言語と言語処理系の研究に従事.本会情報入試委員会委員.本会シニア会員.

【講演概要】京都産業大学の前期一般入試において情報理工学部・理学部を対象に「情報プラス」型入試が実施された。情報プラス方式は対象学部が求める受験者の情報分野の資質・能力を適切に評価できるよう設けられた受験方式である。しかし科目「情報」による入試は始まったばかりであり、受験者が自己の能力評価が相対的にどの程度になるか予測しづらい問題がある。それをリスクとして「情報」科目による受験を忌避することなく、情報に自信のある受験者が安心して実力を発揮できるよう情報プラス方式では科目選択と評価方式を工夫している。それらの効果を含めて実施した結果をまとめ、報告する。
【略歴】1988年京都産業大学理学部計算機科学科卒業,京都産業大学計算機センター,1995〜2002年神戸大学経済経営研究所講師などを経て,現在京都産業大学情報理工学部准教授.SDN,分散処理とその応用に興味をもつ.情報処理学会,ACM会員.

【講演概要】大学入学共通テストに高校教科「情報」が導入され、その最初の試験が実施された。多くの受験者を対象とした共通テストでどのように「情報」が出題がされたかを振り返る。合わせて、人文社会系学部・学科の個別入試「情報」の出題例として、日本大学文理学部の出題を振り返る。
【略歴】日本大学文理学部 教授.(一社)情報オリンピック日本委員会 専務理事.計算論的位相幾何学・複雑ネットワーク解析などの研究,および,情報科学の普及活動に従事.IPSJ MOOC(https://sites.google.com/a.ipsj.or.jp/mooc/)「コンピュータとプログラミング」の制作に携わる.

【討論概要】新課程で「情報Ⅰ」を学んだ高校生が初めて臨んだ2025年度入学者選抜が実施された。大学入学共通テストに高校教科「情報」が導入され、また、大学によっては一般選抜の個別入試で「情報」を出題した。新課程「情報入試」元年を終えたこの時期に、出題された入試問題を振り返り、今後の情報教育について討論する。
【略歴】日本大学文理学部 教授.(一社)情報オリンピック日本委員会 専務理事.計算論的位相幾何学・複雑ネットワーク解析などの研究,および,情報科学の普及活動に従事.IPSJ MOOC(https://sites.google.com/a.ipsj.or.jp/mooc/)「コンピュータとプログラミング」の制作に携わる.

【略歴】駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部准教授.博士(工学).2016年から現職.情報処理学会音楽情報科学研究会運営委員.

【略歴】1990年京都大学工学部卒業.1997年京都大学博士(工学).1995年奈良先端科学技術大学院大学助手,その後,京都大学助手,助教授を経て,現在,南山大学教授.本会では,アクレディテーション委員会ソフトウェアエンジニアリング分科会(1999年~2004年),情報教育委員会ソフトウェアエンジニアリング教育委員会(2007年~2012年)で幹事をつとめるなど,情報教育カリキュラムの策定等に関与してきた.

【略歴】1996年4月から2004年3月まで横浜中学校・高等学校勤務。この間に情報科免許取得。
2004年4月より現職。情報科教諭として学科主任、分掌としてメディア教育部部長や生活指導部の生徒会顧問を務める。
現在京都府私立中学高等学校情報科研究会副委員長を務める。

【略歴】雲雀丘学園中学校・高等学校,情報科・数学科・探究科教諭.兵庫県立大学情報科学研究科博士後期課程在学中.高等学校におけるデータサイエンス教育・統計教育・AI教育のカリキュラム開発,人工知能,オントロジー工学の研究に従事.JDSSP高等学校データサイエンス教育研究会主査.【人工知能学会・日本統計学会公認】全国中高生AI・DS探究コンペティションを開催し,高校生や高等学校教員へのAI・DS教育の普及に努める.第17回日本統計学会統計教育賞,2023年度人工知能学会研究会優秀賞を受賞.

【講演概要】立命館大学では高校情報科をとり入れた入試企画として、特別入試における情報Iのオンライン教材の履修を出願要件にしたAO入試方式「UNITE Program方式」や、 一般入試における大学入学共通テスト/情報の成績を活用する入試方式をこれまで順次導入してきた。 これらに加え、26年度入試より新たに情報の独自出題による試験を採用した一般入試の導入を予定している。これらの入試企画の展開について紹介する。
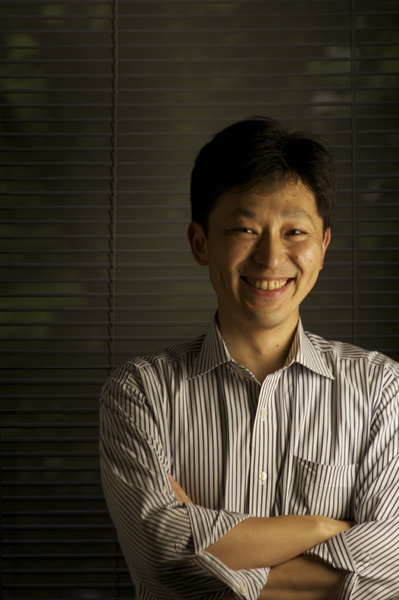
【略歴】慶應義塾大学環境情報学部教授。博士(政策・メディア)。1995年3月電気通信大学大学院電気通信学研究科情報工学専攻博士前期課程修了。1997年4月慶應義塾大学政策・メディア研究科後期博士課程入学、2000年3月単位取得退学。2003年3月、慶應義塾大学より博士(政策・メディア)の学位を授与。1995年4月以降は、慶應義塾大学において研究員、助手、特任教員などを経、2022年より現職。専門はインターネット、コンピュータサイエンス、高度道路交通システム(ITS)、地理位置情報(GIS)など。