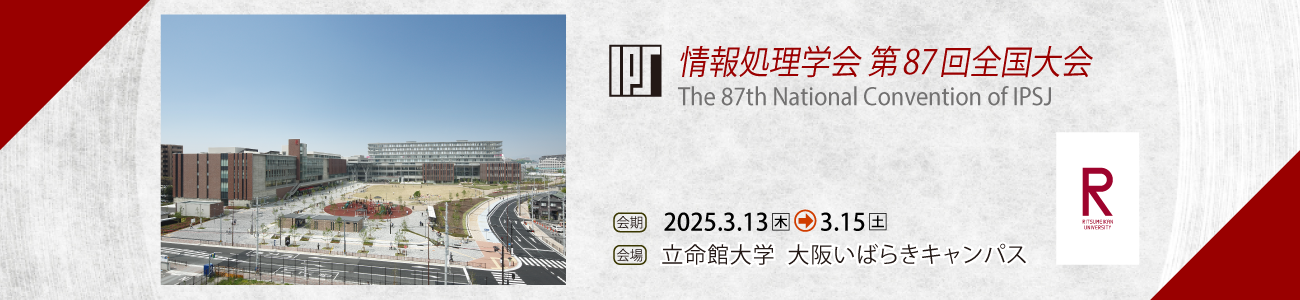
【セッション概要】2023年から始まった生成AIの急速な普及と高度化は、教育にも大きな影響を与えている。文部科学省は大学には対応指針の作成を求め、また、初等中等教育機関にはガイドラインの初版を提供した。一般情報教育の現場においても、授業手法の検討、教材の作成、課題・問題の作成に活用できるだけでなく、学生の演習での使用、提出物作成における利用など、避けられない課題が発生している。科研費研究「一般情報教育のデジタル・トランスフォーメーション」での調査結果でも、一般情報教育におけるAIの利用について期待の声が寄せられている。本企画では、まず、生成AIや業務DXについて基調講演を行う。その後、大学初年次教育における生成AIについて、特にプログラミング、データサイエンス、情報倫理、メディアリテラシー、情報デザインなどの教育の観点からパネル討論、および、参加者との質疑応答を行い、議論を深める。

【略歴】東京女子大卒業後、 女性SE第一期生として富士通入社, ASCIIでビジネスパソコンスクール開校、OAインストラクタを経て、ライティング業として独立。1995年から大学の非常勤講師を始め、2007年から現職。学部の情報教育、および一般情報教育のマネジメントを行う。一般情報教育委員会副委員長、教育担当理事、会誌・出版担当理事を務め、現在会誌副編集長。J17では文部科学省の委託による全大学を対象とした情報教育の実態調査を担当。

【略歴】1991年早稲田大学理工学部数学科卒業。2014年筑波大学博士(システムズ・マネジメント)。1993年早稲田大学情報科学研究教育センター助手。その後、神戸大学、東京農工大学を経て、現在、放送大学教授。本会広報広聴戦略委員会、一般情報教育委員会、教科書委員会、会誌編集委員会NWG、初等中等教育委員会、情報入試委員会の各委員等。2020年6月から2022年5月まで本会理事(新世代)。

【講演概要】企業では、どのようなAI活用が行われ、さらに、今後広がっていくのかについて、事例紹介と課題の考察を行う。本講演を通して、本イベント後半のパネルディスカッションでの「企業におけるAI活用・DXと大学での一般情報教育との接続」のために、企業側の立場から話題提供をする。
【略歴】お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科修了。博士(理学)。NTTドコモ、NICTにて対話AIの研究開発に従事。2020年10月より、AIプランナーとしてヤフー(株)(現 LINEヤフー(株))に勤務。AIの設計・導入に携わる。人工知能に関する講演や記事執筆、監修等も多数行う。著書・監修書に「いちばんやさしいAI〈人工知能〉超入門」(マイナビ出版)、「超実践!AI人材になる本 プログラミング知識ゼロでもOK」(Gakken)がある。

【略歴】1991年早稲田大学理工学部数学科卒業。2014年筑波大学博士(システムズ・マネジメント)。1993年早稲田大学情報科学研究教育センター助手。その後、神戸大学、東京農工大学を経て、現在、放送大学教授。本会広報広聴戦略委員会、一般情報教育委員会、教科書委員会、会誌編集委員会NWG、初等中等教育委員会、情報入試委員会の各委員等。2020年6月から2022年5月まで本会理事(新世代)。

【略歴】1986年秋田大学鉱山学部電子工学科卒業、1988年同大学大学院修士課程修了、2008年東北学院大学大学院博士課程修了。博士(学術)。1988年秋田県立西目高等学校電子機械科教諭を経て、1991年静岡県立大学経営情報学部助手.現在、同大学同学部教授、同大学ICTイノベーション研究センター長.情報教育、遠隔講義システム等の研究に従事。情報処理学会一般情報教育委員会委員。

【略歴】1993年上智大学大学院理工学研究科博士前期課程修了。1993年株式会社三菱総合研究所研究員(情報政策、メディアデザイン)。2001年広島大学助手、助教授を経て、2013年より現職。広島大学では全学のメディアリテラシー教育、社会情報、博物館情報、メディア論の専門教育を担当。情報処理学会では、一般情報処理教育研究委員会、高等学校情報科教員研修委員会委員。

【略歴】2000年慶応義塾大学政策・メディア研究科修士課程修了。2008年青山学院大学附置情報科学研究センター助手、その後、2014年島根大学教育・学生支援機構教学企画IR室助手、2016年帝京大学高等教育開発センター助教・講師を経て、2021年から現職。高崎商科大学では、データリテラシー教育やIRを担当。本会一般情報教育委員会、情報システム教育委員会の各委員。

【略歴】お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科修了。博士(理学)。NTTドコモ、NICTにて対話AIの研究開発に従事。2020年10月より、AIプランナーとしてヤフー(株)(現 LINEヤフー(株))に勤務。AIの設計・導入に携わる。人工知能に関する講演や記事執筆、監修等も多数行う。著書・監修書に「いちばんやさしいAI〈人工知能〉超入門」(マイナビ出版)、「超実践!AI人材になる本 プログラミング知識ゼロでもOK」(Gakken)がある。