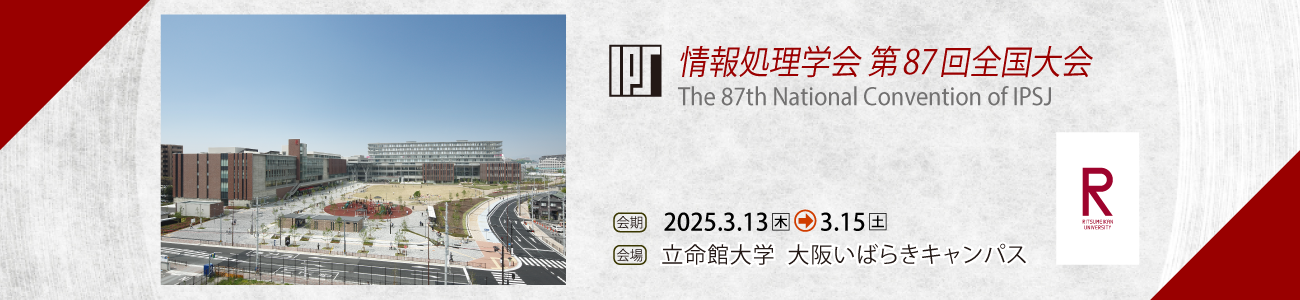
【セッション概要】情報分野に興味を持つ生徒・学生を継続的に育成することは現代社会において重要な課題となっている。従来は大学や企業がその役割を担っていたが、現在は小学校から高等学校までの初等中等教育においてもプログラミングやデータサイエンスを含む情報教育が積極的に展開されている。また、2025年から大学入学共通テストで「情報」が出題される。このような環境の中、情報の基礎教育を行う教員に対して発表の機会を提供することで、本会員との交流を深めることができ、中学生や高校生に本会ジュニア会員として入会を促すことにもつなげることができる。そのため、特に初等中等教育機関の教員に特化した研究発表セッションを設けるものである。

【略歴】技術士(総合技術監理・情報工学). 情報処理学会シニア会員,情報処理学会初等中等教育委員会副委員長.情報オリンピック日本委員会理事. 日本IBM大和研究所,三重県立高校,千里金蘭大学,大阪電気通信大学,神戸市立高校を経て,工学院大学附属中学校・高等学校校長兼工学院大学教育開発センター特任教授. 情報処理学会山下記念研究賞(2015),情報処理学会学会活動貢献賞(2016),科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞(2017),情報処理学会大会優秀賞(2018),視聴覚教育・情報教育功労者文部科学大臣表彰(2024)

【略歴】技術士(総合技術監理・情報工学). 情報処理学会シニア会員,情報処理学会初等中等教育委員会副委員長.情報オリンピック日本委員会理事. 日本IBM大和研究所,三重県立高校,千里金蘭大学,大阪電気通信大学,神戸市立高校を経て,工学院大学附属中学校・高等学校校長兼工学院大学教育開発センター特任教授. 情報処理学会山下記念研究賞(2015),情報処理学会学会活動貢献賞(2016),科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞(2017),情報処理学会大会優秀賞(2018),視聴覚教育・情報教育功労者文部科学大臣表彰(2024)

【講演概要】本校は、2021年にJAET(日本教育工学協会)による学校情報化先進校に選定される。校内研究テーマを「情報活用能力の育成」に設定し、各教科に応じたICTの効果的な活用法を研究している。具体的には、校内における情報活用能力チェックシートを用いた児童のアセスメントにより、学年の実態に応じた実践を重ね、年間を通じてR-PDCAサイクルを回して改善に努めている。本講演では、これまでの実践から得られた成果と課題について報告する。
【略歴】大阪市立今里小学校教頭。大阪市学校教育ICT推進リーダー、大阪市教育委員会の現場教育ICT活用検討会委員および教育ICTビジョン策定ワーキンググループ作業部会委員として活動。また、Microsoft Innovative Educator ExpertやNHK GIGAスクール研修ファシリテーターとしても活躍するなど、最新のICT教育に関する知見を地域や全国に広めている。その他、ICT夢コンテスト「地方再生・創生賞」(2024)やNHK for Schoolレポートアワード「大賞」(2021・2023)といった受賞歴を有しており、教育ICT分野での取り組みが高く評価されている。

【講演概要】オンラインミーテングやチャット会議が日常化し、生成AIの活用が急速に進むといった社会現象の中、「Society5.0で活躍する力を身につけるにはどうしたらいいのか」という「問い」に向けての学びが重要になってくる今日、より一層、言語を含む文化の多様性、『障がい』を含む『もちあじ』の多様性など、様々な個性を持つ人たちで組むワークチームでの協働する力が必要となってくる。Teamsをコミュニケーションプラットフォームとして活用しながら21世紀型の学習デザイン(21CLD)のルーブリックに従って学習デザインを行った取り組みについて紹介するとともに、研究の中で見えてきた『生成AIやICT活用のメリットとデメリット」についての見解と、マジョリティが強くなりがちな情報化社会において、人権教育を推進してきた立場から見た『いかにして豊かな人権感覚を育みながらSociety5.0を生き抜く力を身につけていくか』についての考えなどについて報告し、豊かな人間性と多様な情報の活用、生成AIの活用を共存させていくかについてみなさんと共に考えてみたい。
【略歴】1996年大阪教育大学小学校教員養成課程数学専攻卒業後、1996年4月より大阪市教員として勤務。外国人教育を軸に人権教育の研究を推進しながら、ICT教育についても研究を進めてきた。新型コロナウイルス感染症の流行の真っただ中の2020年より大阪市立北鶴橋小学校校長として赴任、学校全体でTeamsを教育Platformとしたグランドデザインのもと、21CLDルーブリックに従った授業デザインに取り組み「Society5.0を生き抜く子どもの育成」を推進している。北鶴橋小学校は2021年-23年にMicrosoftによりShowcase Schoolに認定され、2022年には時事通信社教育奨励賞特別賞を受賞するなど様々な取り組みについて積極的に実践を行っている。

【講演概要】神戸市にGIGA端末が配備されて4年目を迎えた。学校全体でGIGA端末を積極的に活用していくため、講演者はこの4年間、GIGA担当として様々な取り組みに従事してきた。令和4・5の2年間は「学習の基盤となる資質・能力としての情報活用能力の育成」をテーマに、神戸市の研究指定校として取り組んできた。本講演では、この取り組みを遂行するにあたっての、教員研修や授業実践の実際、そして取り組みを行ってきた中での教師の意識変容等について、事例を踏まえて述べる。
【略歴】2018年神戸市立中学校の理科教諭として採用。
勤務校にてGIGAスクール担当として従事。

【講演概要】市内のすべての小中学校および特別支援学校の児童生徒にタブレット端末が配布されてから4年が経ち、効果的に活用できるようデジタルドリルや常設の電子黒板も整備された。タブレット端末は教科書やノートとともに机の上に置かれ、特別なものではなく日常的に活用されている。導入当初はまず慣れることから始まり、現在では学びを深めるフェーズに入っている。全国学力学習状況調査の結果を見ると、本市は全国や県と比較しても活用が進んでいることが分かりる。本講演では、日々の活用、研修、支援体制について紹介する。また、2025年度に開催される技術家庭科の近畿大会で本市が情報の授業を担当する予定であり、本市の技術科における取り組みについても紹介する。
【略歴】1991年に明石市立中学校の英語科教諭として採用。2001年には兵庫県立教育研修所にてIT教育推進研修員として1年間勤務。その後、明石市立中学校でICT教育を推進し、2018年よりあかし教育研修センターで指導主事として勤務。当初2年間は研修担当を務め、2020年より情報教育担当となり、プログラミングを含む情報教育、GIGAスクール端末、校務支援システム等の導入に力を注ぐ。2024年より明石市立中学校の校長として勤務。

【講演概要】共通テストにおける「情報Ⅰ」の必須化、GIGAスクール構想、コロナ禍におけるICTを使った学習支援など、昨今、情報について学び教養を高めることは、生徒や教員だけでなく、様々な世代や立場のひとにとって重要な意味を持つようになりました。私は、ここ数年で勤務校以外にも、地元三重県の小学校や中学校に研修や講演などをさせていただく機会があり、小学校・中学校の児童生徒・教員の声に触れることがありました。内容は、ChatGPTなどの生成AIを利用する際のコツや、ハルシネーションに関連するものでしたが、それらの経験から現場の抱える戸惑いや課題などが見えてきたと感じています。今回は、現任校での「プログラミング教育」「デジタルシチズンシップ教育」などに関連する普通科高校における情報Ⅰの授業実践例を中心に、様々な現場の声を紹介させていただきます。
【略歴】2002年中京大学情報科学部認知科学科卒業。2003年より主に普通科高校にて情報科の指導を行ってきた。これまでに大阪府など他府県での採用経験があるが、現在は三重県立神戸高校に在籍している。探究ICT部の部長を務め、校内のICT活用のサポートをしつつ、県内の小中学校にて研修や講演会を行っている。2020年より三重県情報教育研究会副会長を務める。

【講演概要】情報Ⅰ「データの活用」の分野において、どのようなアプローチでどのレベルまで踏み込むのかは現場の生徒の習熟度により多岐に渡る。大学にてMDASH(数理・データサイエンス・AI 教育プログラム認定制度)[リテラシーレベル]に準拠した講義を担当することができたことにより、情報Ⅰとの接続を意識することができた。情報ⅠとMDASHとの高大連携を意識した授業デザインについて述べる。
【略歴】大阪の樟蔭中学校・高等学校で数学科の教員として15年勤務し、その後、情報科に転科して現在に至ります。学内では中高のICT関連の主幹教諭、授業全般の指導教諭という立場で幅広い教科の先生方に授業に関わっています。学内ではSTEAM Lab.に常駐し、デジタルものづくりを推進しています。また、情報処理学会の学会誌「情報処理」の2023年度の表紙デザインを担当しました。

【講演概要】小学校や高等学校との教育内容の接続を考慮すると、中学校での学びにおいては、体系的なアプローチや縦の連携について、より一層意識する必要がある。本取り組みでは、中学1年生を対象に、プログラミングの基本概念や情報デザインを学習できる統合型アプリケーション「Pictogramming」の派生アプリ「Pictoch」を用いて授業を実践した。ブロック型のビジュアルプログラミングや、幾何学的な要素を含んだ描画課題などを設定することで、小学校や高等学校との連携を意識し、対象生徒の教育効果を高めることを目指した。本取り組みの内容とその効果について詳細に述べる。
【略歴】情報科教諭 修士(学術).2021年より東大寺学園中学校・高等学校に勤務.
日本産業技術教育学会 実践事例書籍編集委員会,技術科教員指導力認定試験委員会 委員
日本情報科教育学会 情報科教育連携委員会 委員
日本知財学会 知財教育分科会 副代表
日本産業技術教育学会 学会賞(2022・2023年度)
日本教育情報化振興会 ICT夢コンテスト優良賞(2022・2023年度)

【講演概要】中等教育、特に高等学校における情報教育について、現状と課題を、実践事例を交えながら紹介し、今後の展望を提案します。
【略歴】情報学修士(関西大学)、大阪私学教育情報化研究会会長
高等学校情報科教員として勤務。2006年JICAのシニアボランティアでドミニカ共和国(ネットワーク構築)。帰国後再び高校で教員として大阪府、京都府、兵庫県、奈良県で勤務。
IT-Literacy 3DCG編(2004,日本文教出版)、専門教科「情報メディア」(2014,実教出版)共著。日本情報科教育学会第11回全国大会優秀実践賞(2019)。2023年より現職。

【略歴】国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官。文部科学省初等中等教育局における共通教科情報科及び専門教科情報科の教科調査官を併任。2003年3月東京理科大学大学院修士課程経営工学専攻修了後,埼玉県私立高等学校,東京都立高等学校で情報科を,千代田区立中等教育学校で情報科及び技術・家庭科(技術分野)を担当し,東京都学校経営支援センター学校経営支援主事,東京都立中学校副校長を経て現職。