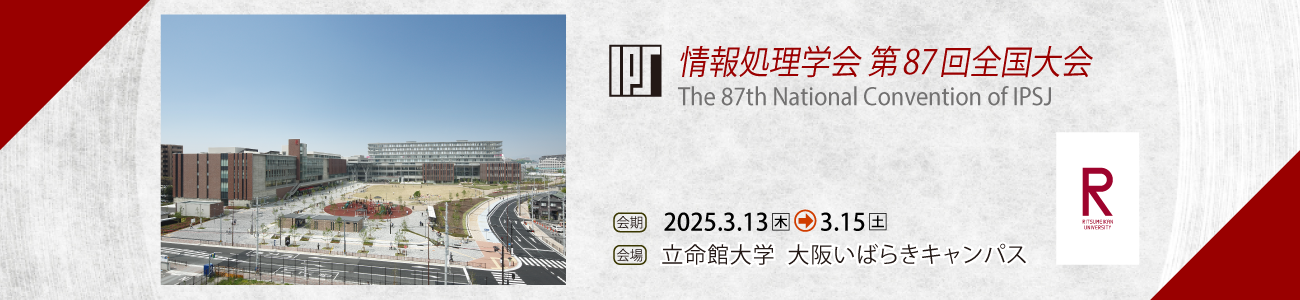
【セッション概要】JSTにおいて新規ファンディングプログラム「情報通信科学・イノベーション基盤創出(CRONOS)」を2024年度に開始しました。革新的な情報通信技術の創出と構想力を有した研究人材育成を通して、我が国の情報通信技術の強化を目指しています。情報通信科学の常識を変えるビジョンを有すると共に社会問題への大きなインパクトをもたらす挑戦的な目標(グランドチャレンジ)を設定し、その貢献に向け、基礎研究と応用研究の垣根を越える運用スキームにより、社会変革につながる基礎研究とその成果の概念実証(POC:Proof of Concept)等を促進します。 本企画セッションでは、プログラムのうち主として情報処理分野の領域全体のマネジメントを担当する川原POの基調講演に加えて、初年度採択課題の研究開発担当者を交えたパネルディスカッションを行います。
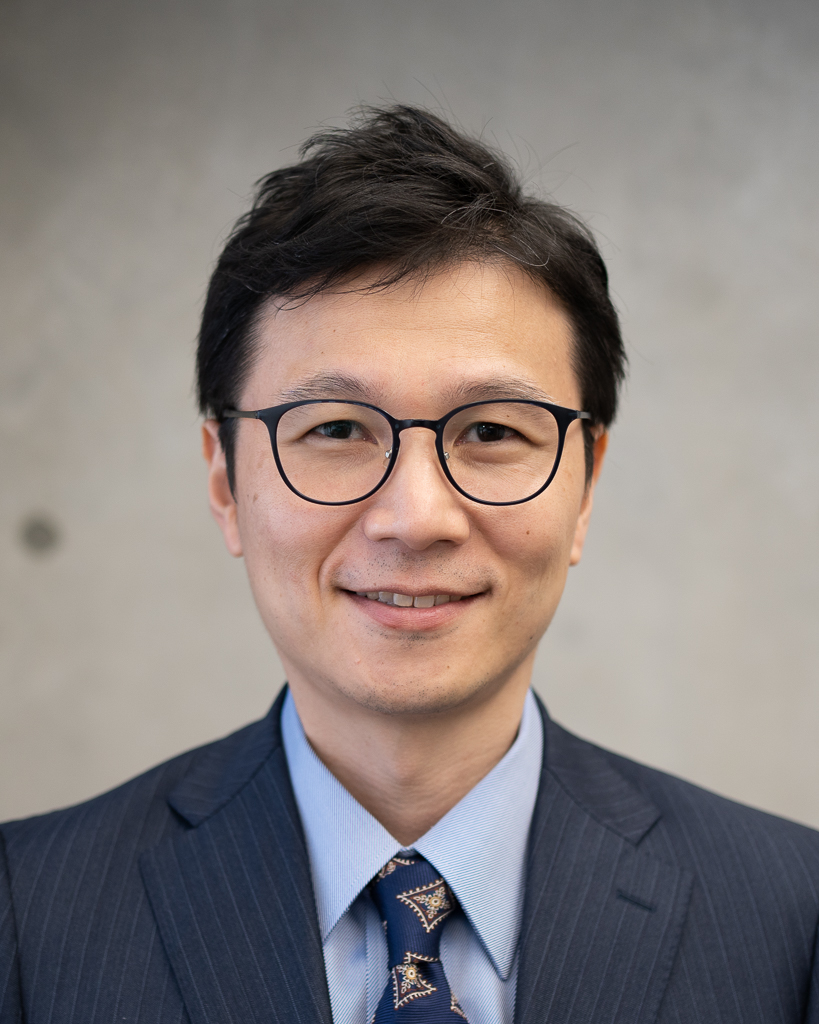
【略歴】東京大学工学系研究科教授。2000年東京大学工学部電子情報工学科卒業、2005年に同大学院博士課程修了、博士(情報理工学)。東京大学で助教、准教授を歴任し、2019年より現職。専門はIoT、デジタルファブリケーション、AI応用。2018年情報処理学会新世代担当理事。2019年学術振興会賞受賞、2024年文部科学大臣表彰。2023年より内閣府AI戦略会議構成員、2024年よりJST CRONOSプログラムオフィサー。
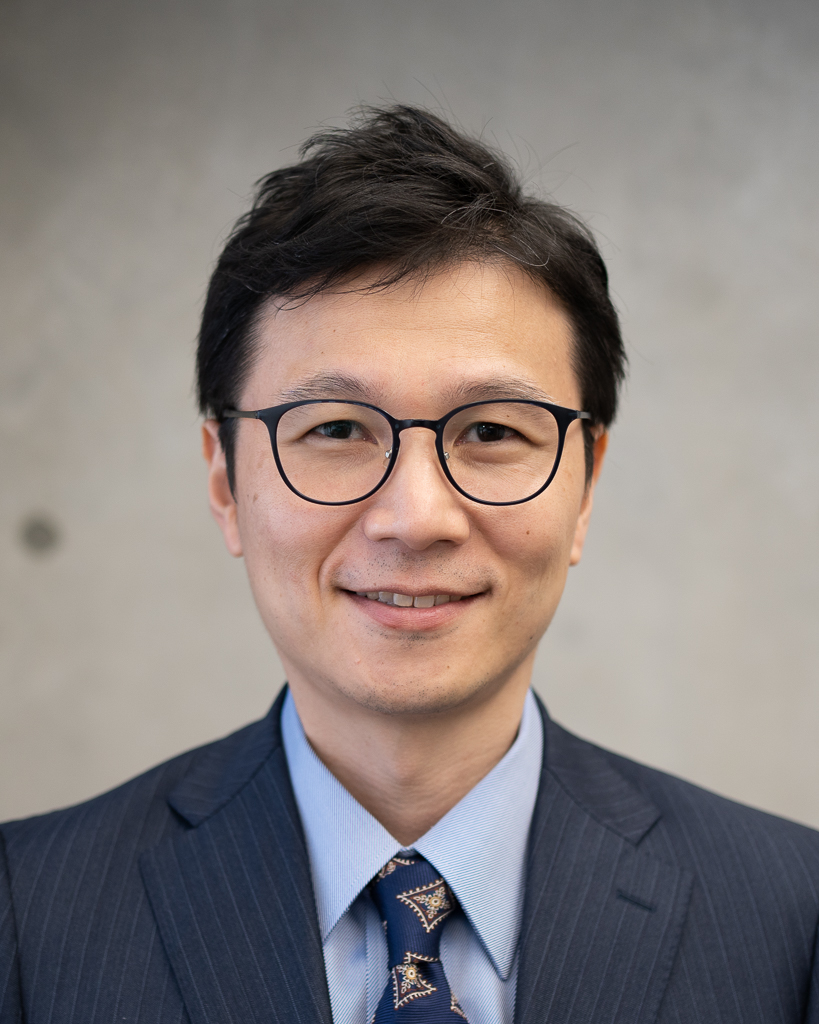
【講演概要】本講演では、JST「情報通信科学・イノベーション基盤創出(CRONOS)」プログラムの概要と目指す未来像を説明します。本プログラムは、グランドチャレンジとしての課題設定を通じて、学術コミュニティに広く影響を与える技術基盤の創出を目的としています。最先端研究と社会実装の架け橋を築き、日本が国際競争力のある研究開発の発信地となることを目指します。これまで検討されたグランドチャレンジを振り返るとともに、ワークショップを通じて設定されたいくつかのグランドチャレンジについても共有いたします。
【略歴】東京大学工学系研究科教授。2000年東京大学工学部電子情報工学科卒業、2005年に同大学院博士課程修了、博士(情報理工学)。東京大学で助教、准教授を歴任し、2019年より現職。専門はIoT、デジタルファブリケーション、AI応用。2018年情報処理学会新世代担当理事。2019年学術振興会賞受賞、2024年文部科学大臣表彰。2023年より内閣府AI戦略会議構成員、2024年よりJST CRONOSプログラムオフィサー。
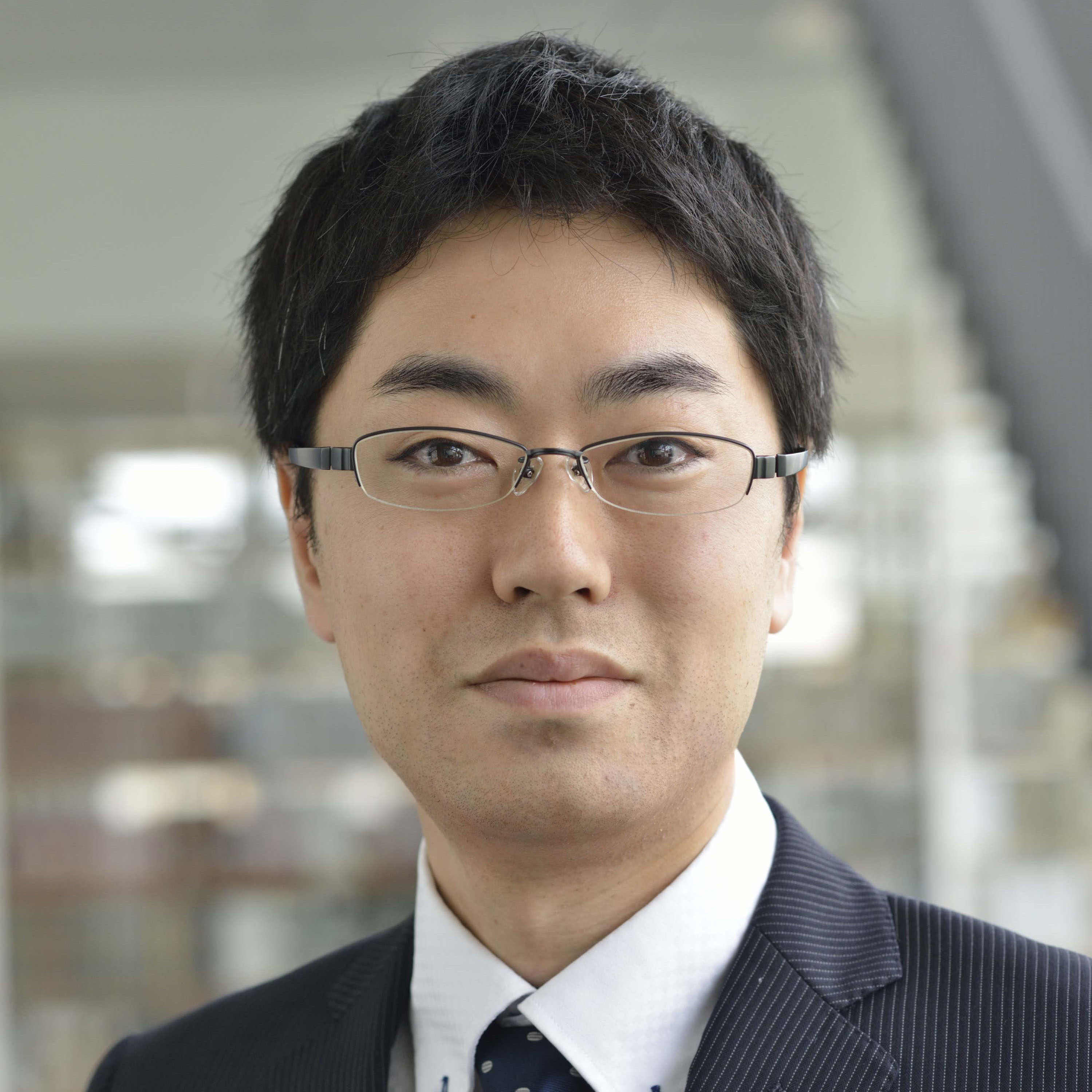
【講演概要】更なる周波数利用効率の向上に向け、サブテラヘルツ・テラヘルツ帯の周波数領域を活用する無線通信技術が必要不可欠である. 次世代・次々世代の6G/7G通信規格を見据え,「テラヘルツギャップ」と呼ばれる周波数領域を開拓するため,「無線・光融合技術の確立による超高効率・広帯域無線通信システム」を集積回路, 光回路, そして光デバイスの専門家による分野横断によって創出する. 光を通過させるだけで推論する超省エネルギー光ニューラルネットワークモデルを開発し, 光アナログドメインでサブテラヘルツ波を復号処理する全く新しい無線受信機アーキテクチャを提案する.
【略歴】2002年東京大学工学部卒業. 2007年同大大学院工学系研究科電子工学専攻博士課程修了. 2007年-2009年ザインエレクトロニクス株式会社にて高速通信インターフェース向け回路設計に従事. 2009年より東京大学大規模集積システム設計教育研究センター助教. 現職は東京大学大学院工学系研究科附属システムデザイン研究センター准教授. 2013年-2015年カリフォルニア大学ロサンゼルス校客員研究員. アナログ集積回路設計技術に関する研究に従事.

【講演概要】半導体集積回路製造プロセスの微細化に伴って、性能向上が可能なIoTの開発について紹介します。
7nm FinFETプロセス等の先端プロセスを活かした0.3mm角以下のサイズの微細IoTの開発、
ならびにその応用開拓について現在の取り組みを講演します。
アンテナサイズの小さい無線送信器は通信距離が短いため、
デバイスサイズと通信距離の間にトレードオフがありましたが、
微細CMOSの特性を活かすことで小型化と長距離通信化の両立を目指します。
0.3mm角以下のサイズを活かした応用として、バイオ・医療応用に向けた
センサシステムを提案し、付加価値の高い応用開拓を目指します。
【略歴】2006年慶應義塾大学理工学部卒業.2008年同大学院修士課程修了.同年日本学術振興会特別研究員.同年グローバルCOEプログラムRA.2010年同大学院博士課程修了.同年群馬大学大学院工学研究科助教.2012年名古屋大学大学院工学研究科講師.2015年JST さきがけ研究者(兼任).2018年名古屋大学大学院工学研究科准教授.2020年JST さきがけ研究者(兼任).2022年京都大学大学院情報学研究科教授. 2024年JST CRONOS研究代表者. 文部科学大臣表彰 若手科学者賞、末松安晴賞、IEEE BioCAS 2016 Best Paper Award, IEEE BioCAS 2018 Best DEMO Award 受賞

【講演概要】材料・デバイス・システム協調研究で、超脳(脳を超える)ニューロモルフィックシステムとして、メモリスキャパシタ・スパイキング計算原理によるトランスフォーマを研究する。Society 5.0で懸念のビッグデータ解析・大量データ通信に要する莫大な電力消費を1/100へ削減することを目的とする。日本の優れた材料・製造技術を武器とし、集積化・システム・アプリケーションの不利な状況を払拭し、エレクトロニクス業界の最後の大逆転につながることを夢見る。
【略歴】1991年 京都大学大学院 工学研究科 修士課程 物理工学専攻 修了
2001年 博士(工学)(東京農工大学)(電子工学) 取得
2018年 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 博士後期課程 修了
2018年 博士(理学)(奈良先端科学技術大学院大学)(情報科学) 取得

【講演概要】本プロジェクトは、未来の交通システムにおける人間と移動体AIの円滑なコミュニケーション基盤を構築することを目指します。従来のITS通信標準に依存せず、ベンダー間のメッセージを相互運用し、人間と移動体AIの双方向インタラクションを実現します。基盤モデルを用いて多様なデバイスとの通信を実証し、成果をオープンソースで公開し、コミュニティを先導する画期的な成果と、未来の交通システムにおける安全性と効率性の向上を目指します。
【略歴】現在は、東京大学 大学院 情報理工学系研究科の准教授。2021年より、名古屋大学特任准教授も兼任。2005年慶應義塾大学環境情報学部卒業。2007年慶應義塾大学政策・メディア研究科修士取得。2007年よりフランス・パリ国立高等鉱業学校 (Mines ParisTech) ロボット工学センター博士課程在籍および、フランス国立情報学自動制御研究所 (Inria)にて研究員として勤務。2011年博士号取得。2014年よりSoftware Defined Media(SDM)コンソーシアム・チェア。 2014から2022年までWIDEプロジェクトのボードメンバー。自動運転のネットワーク通信、インターネット映像音声に取り組む。
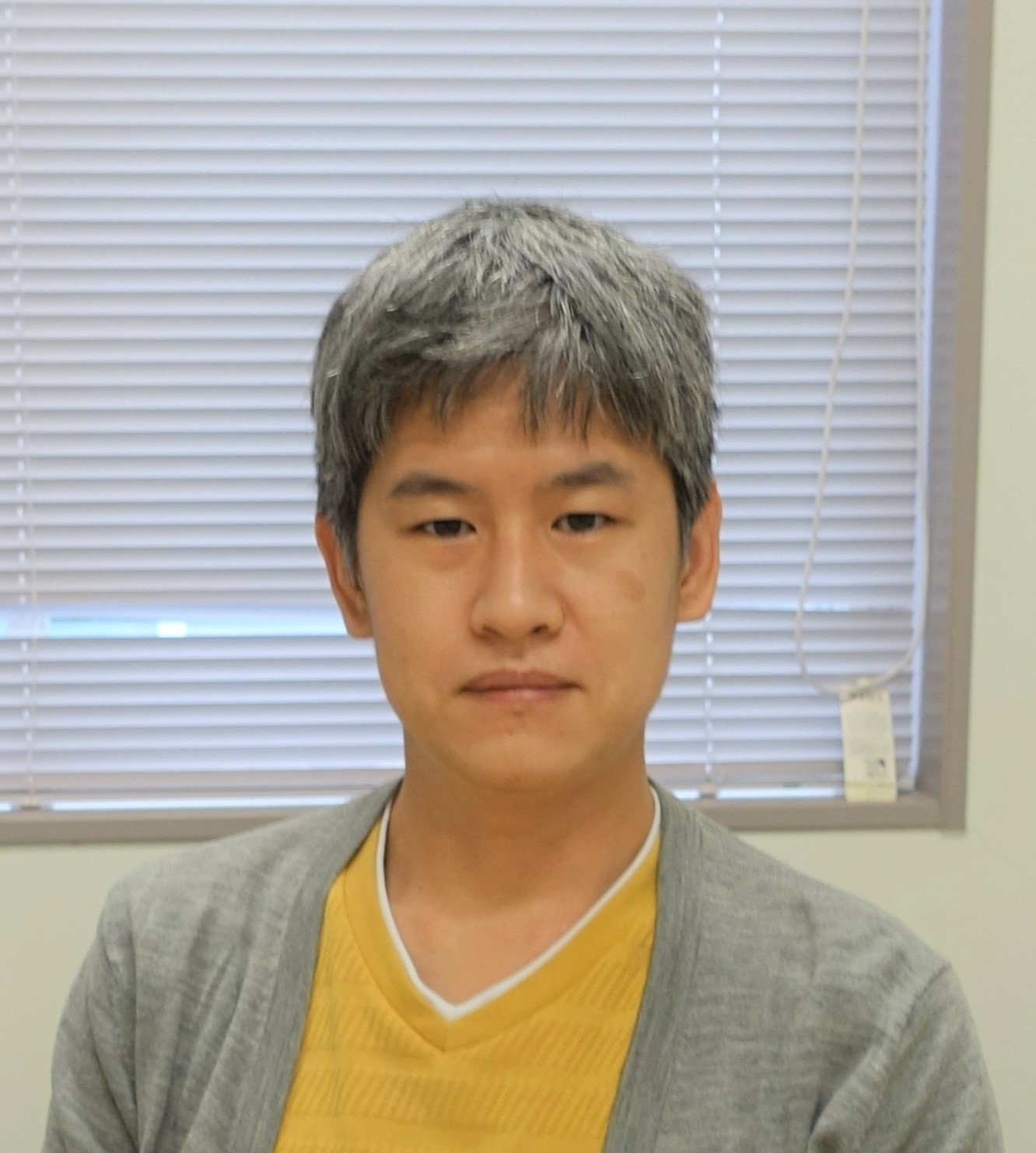
【講演概要】サイバー空間を形成する多様な系・サービスは本質的に自律分散的であり,その安全かつ公正な制御は重要な技術的要請である.このような現状に対して,本研究は「公正な割り当てと合意の自律分散的制御」を目的としたアルゴリズム研究に取り組む.オープンな自律分散系ではユーザは利己的かつ匿名的であり,また任意のタイミングでの参加離脱や嗜好の変化といった多種複雑なダイナミズムを内包するため,「誰かを信頼する/何らかの原理原則を信頼する」という行為が本質的に困難である.本研究は,分散計算理論、計算論的経済学、情報セキュリティの3分野からなる融合的な研究チームを組織し、自律分散性に由来する多種複雑な性質や制約に対処可能な割り当て・合意技法の創出を目指す.
【略歴】大阪大学大学院情報科学研究科コンピュータサイエンス専攻准教授.2006年3月大阪大学大学院情報科学研究科博士後期課程修了(情報科学).2006年10月~2009年3月名古屋工業大学助教,2009年4月~2020年9月准教授,2020年10月より現職.専門は理論計算機科学,特に分散システムのためのアルゴリズム理論.

【講演概要】本研究では、グランドチャレンジへの挑戦として、人間・動物・AIが三位一体となり成長できるこれまでにないコミュニケーションサービスを通じて、動物の行動、心理、生理を理解し、適切に介入する”Human and Animal in the Loop (HAITL)“インタラクション基盤の創生を目指す。
【略歴】1997年東京工業大学工学部電気・電子工学科卒業.2002年同大学博士後期課程修了,博士(工学).同年、理化学研究所脳科学総合研究センター研究員.2004年より東京農工大学,現在同大学教授.
その間,2011年ハワイ大学マノア校客員研究員.2022年より同大学動物共生情報学拠点代表.
2022年株式会社Sigronを共同で設立,取締役CTOとして産学連携に取り組む.
【討論概要】パネルディスカッションでは、2024年度採択者の課題紹介を踏まえて以下のような観点から議論を行います。(1)「新しい領域におけるコミュニティ作り」協働的な取り組みがもたらす可能性や価値創出の仕組みとは。(2)「国内外において考慮すべき注目動向」技術や社会環境の変化が今後の発展にどのような影響を及ぼすか。(3) 「従来の枠を超えた挑戦的な視点」既存の領域分けや発想にとらわれない革新的なアプローチまた、異なる領域やコミュニティ間の連携をどのように促進し、未来への新たな展望を切り開くか。
パネリストや聴講者との議論を通して創造的な発想と戦略を見出すことを目指します。
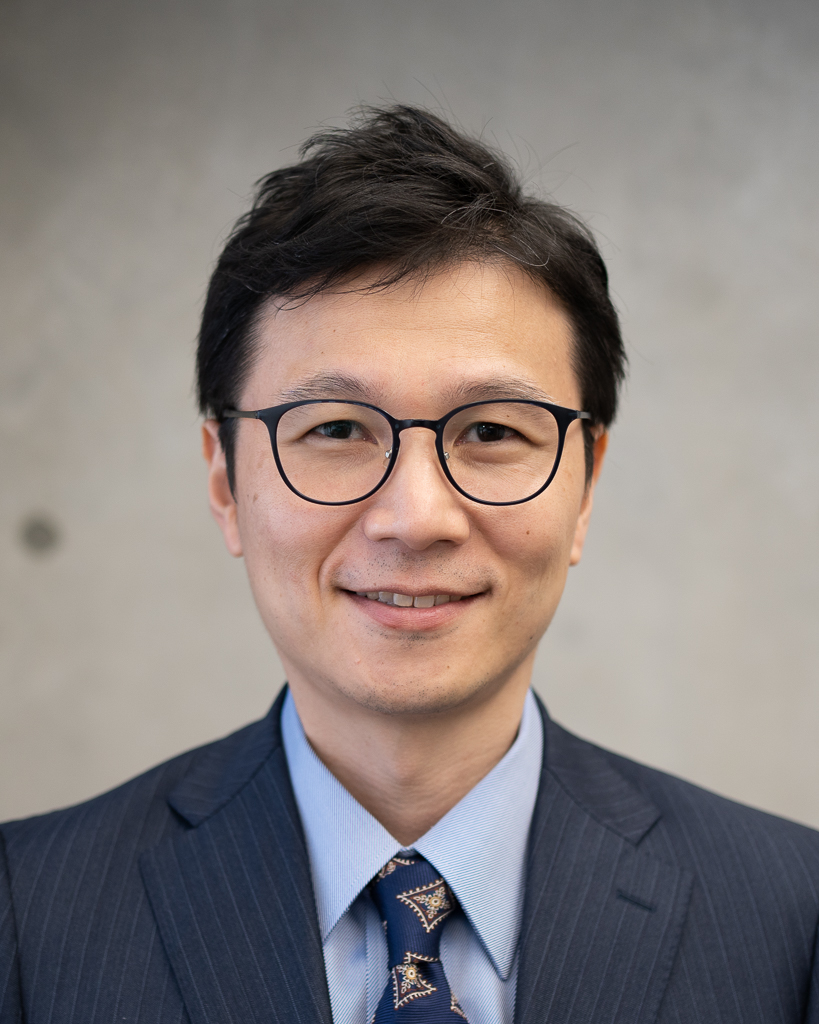
【略歴】東京大学工学系研究科教授。2000年東京大学工学部電子情報工学科卒業、2005年に同大学院博士課程修了、博士(情報理工学)。東京大学で助教、准教授を歴任し、2019年より現職。専門はIoT、デジタルファブリケーション、AI応用。2018年情報処理学会新世代担当理事。2019年学術振興会賞受賞、2024年文部科学大臣表彰。2023年より内閣府AI戦略会議構成員、2024年よりJST CRONOSプログラムオフィサー。

【略歴】1986年3月慶應義塾大学工学部電気工学専攻博士課程修了。工学博士。1985年慶應義塾大学理工学部助手。1989年同専任講師。同年Stanford大学Computer System Lab.Visiting Assistant Professor。1994年慶應義塾大学理工学部助教授、2001年同教授。1993年研究賞、1994年ベストオーサ賞、1996年および2008年論文賞、1997年坂井記念特別賞などを情報通信学会より受賞。2024年4月より慶應義塾大学名誉教授、東大大学院工学研究科附属システムデザイン研究センター上席研究員です。

【略歴】大阪大学情報科学研究科のビッグデータ工学研究室を率い、グラフマイニングやAI駆動のデータベースクエリ最適化を研究しています。NTTで20年以上勤務し、拡張可能型主記憶データベース(LiteObject),XMLストリーム処理エンジン(XMLToolkit),グラフ分析ツール(Grapon)などを研究開発。日本データベース学会理事(2024~),情報処理学会の理事(2019-2021年)を務め、多くの国際会議で委員や共同委員長として活動。幅広い学術貢献を通じて、データベース技術の発展に寄与しています。
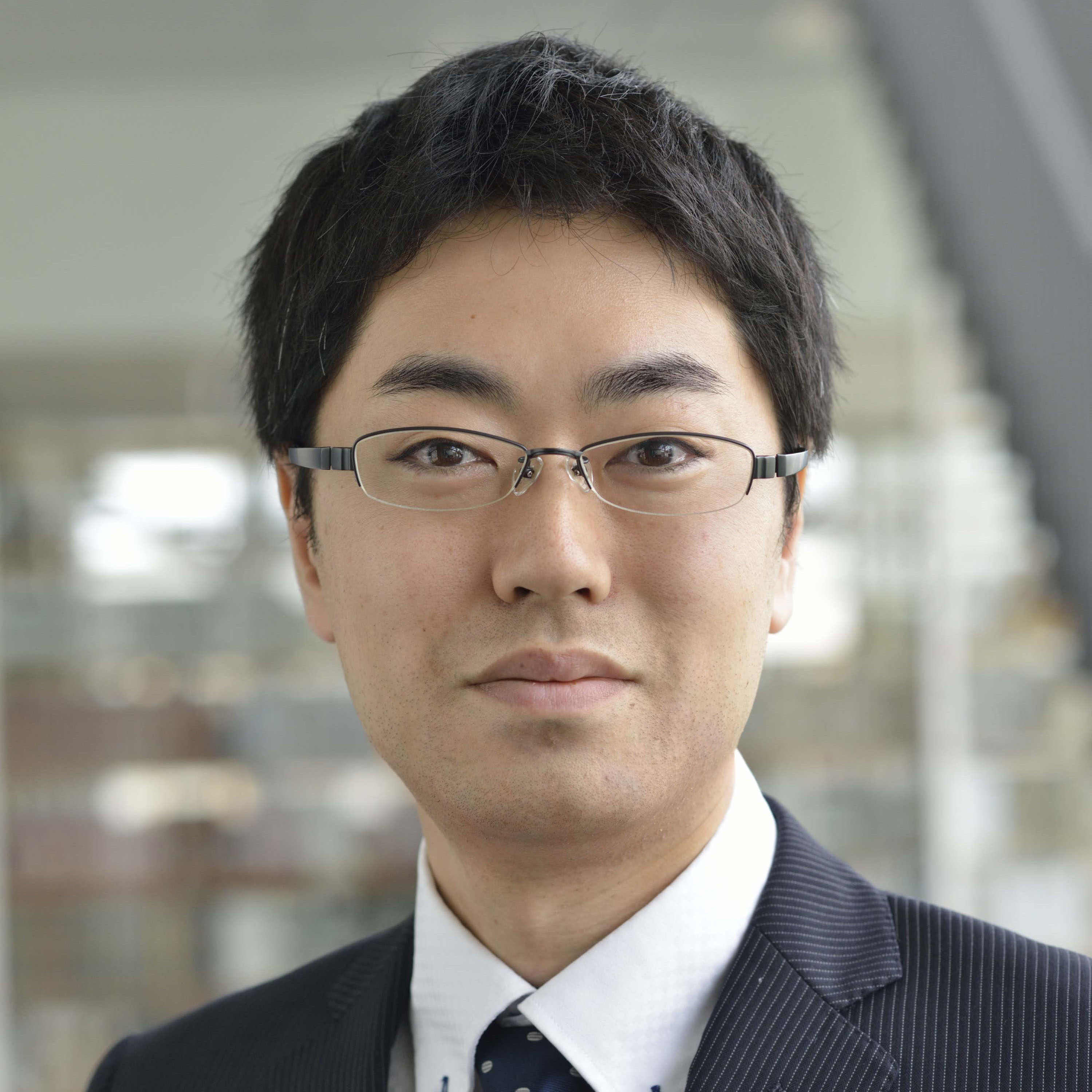
【略歴】2002年東京大学工学部卒業. 2007年同大大学院工学系研究科電子工学専攻博士課程修了. 2007年-2009年ザインエレクトロニクス株式会社にて高速通信インターフェース向け回路設計に従事. 2009年より東京大学大規模集積システム設計教育研究センター助教. 現職は東京大学大学院工学系研究科附属システムデザイン研究センター准教授. 2013年-2015年カリフォルニア大学ロサンゼルス校客員研究員. アナログ集積回路設計技術に関する研究に従事.

【略歴】2006年慶應義塾大学理工学部卒業.2008年同大学院修士課程修了.同年日本学術振興会特別研究員.同年グローバルCOEプログラムRA.2010年同大学院博士課程修了.同年群馬大学大学院工学研究科助教.2012年名古屋大学大学院工学研究科講師.2015年JST さきがけ研究者(兼任).2018年名古屋大学大学院工学研究科准教授.2020年JST さきがけ研究者(兼任).2022年京都大学大学院情報学研究科教授. 2024年JST CRONOS研究代表者. 文部科学大臣表彰 若手科学者賞、末松安晴賞、IEEE BioCAS 2016 Best Paper Award, IEEE BioCAS 2018 Best DEMO Award 受賞

【略歴】1991年 京都大学大学院 工学研究科 修士課程 物理工学専攻 修了
2001年 博士(工学)(東京農工大学)(電子工学) 取得
2018年 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 博士後期課程 修了
2018年 博士(理学)(奈良先端科学技術大学院大学)(情報科学) 取得

【略歴】現在は、東京大学 大学院 情報理工学系研究科の准教授。2021年より、名古屋大学特任准教授も兼任。2005年慶應義塾大学環境情報学部卒業。2007年慶應義塾大学政策・メディア研究科修士取得。2007年よりフランス・パリ国立高等鉱業学校 (Mines ParisTech) ロボット工学センター博士課程在籍および、フランス国立情報学自動制御研究所 (Inria)にて研究員として勤務。2011年博士号取得。2014年よりSoftware Defined Media(SDM)コンソーシアム・チェア。 2014から2022年までWIDEプロジェクトのボードメンバー。自動運転のネットワーク通信、インターネット映像音声に取り組む。
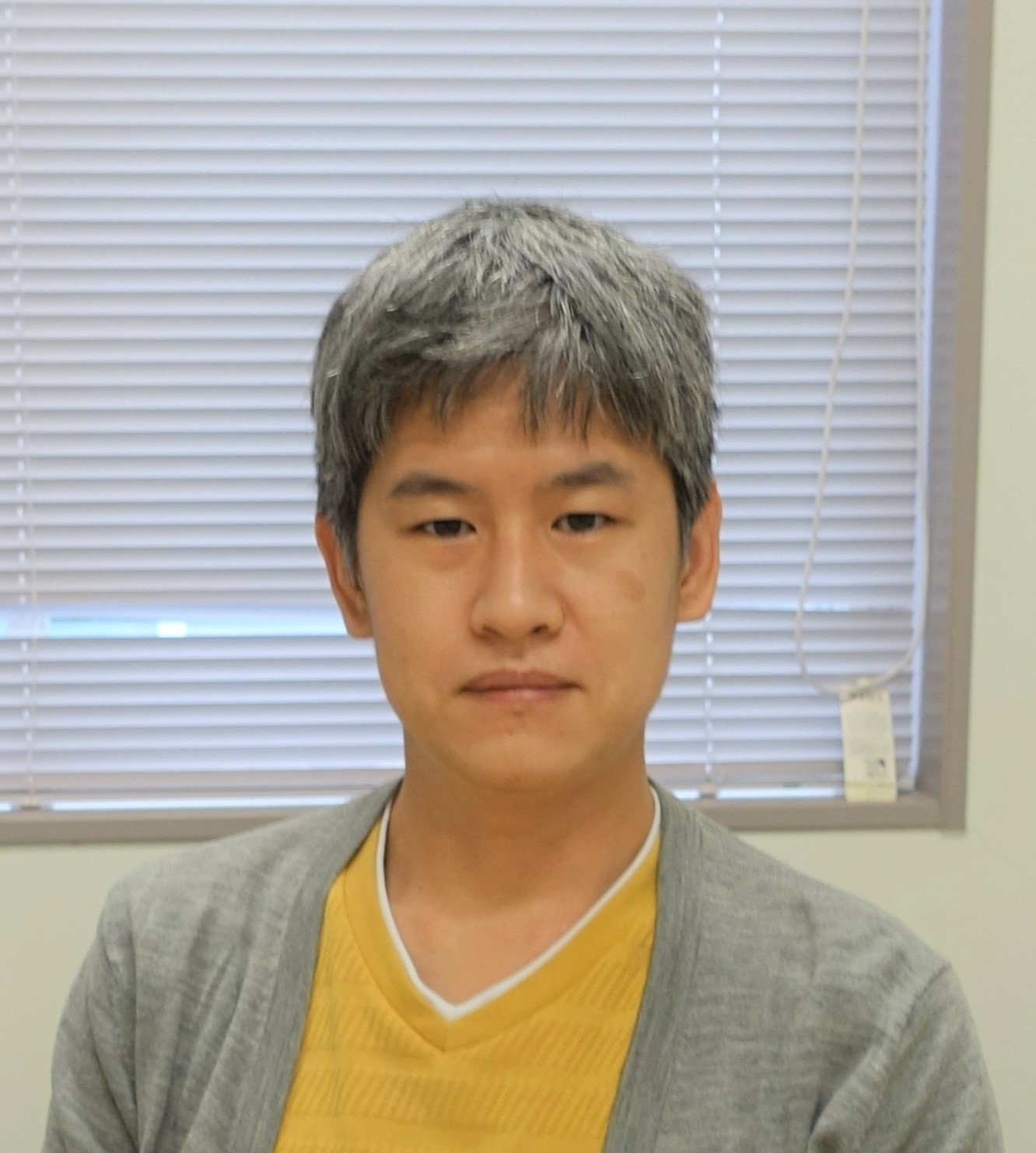
【略歴】大阪大学大学院情報科学研究科コンピュータサイエンス専攻准教授.2006年3月大阪大学大学院情報科学研究科博士後期課程修了(情報科学).2006年10月~2009年3月名古屋工業大学助教,2009年4月~2020年9月准教授,2020年10月より現職.専門は理論計算機科学,特に分散システムのためのアルゴリズム理論.

【略歴】1997年東京工業大学工学部電気・電子工学科卒業.2002年同大学博士後期課程修了,博士(工学).同年、理化学研究所脳科学総合研究センター研究員.2004年より東京農工大学,現在同大学教授.
その間,2011年ハワイ大学マノア校客員研究員.2022年より同大学動物共生情報学拠点代表.
2022年株式会社Sigronを共同で設立,取締役CTOとして産学連携に取り組む.
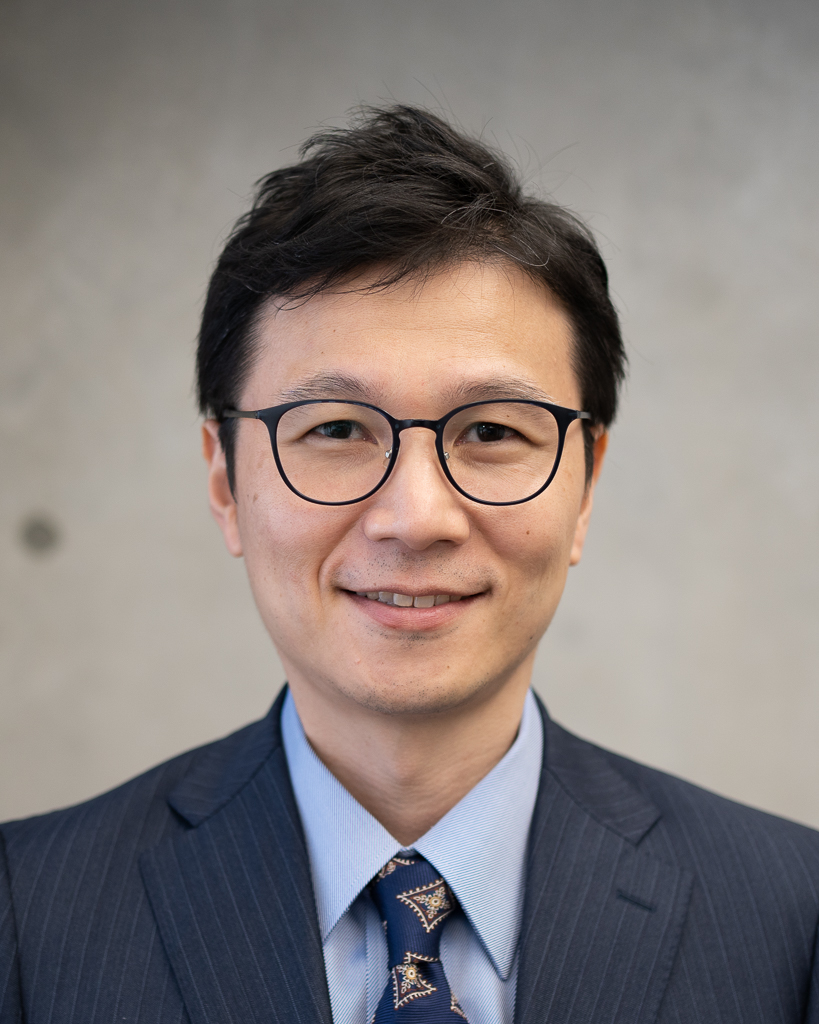
【略歴】東京大学工学系研究科教授。2000年東京大学工学部電子情報工学科卒業、2005年に同大学院博士課程修了、博士(情報理工学)。東京大学で助教、准教授を歴任し、2019年より現職。専門はIoT、デジタルファブリケーション、AI応用。2018年情報処理学会新世代担当理事。2019年学術振興会賞受賞、2024年文部科学大臣表彰。2023年より内閣府AI戦略会議構成員、2024年よりJST CRONOSプログラムオフィサー。