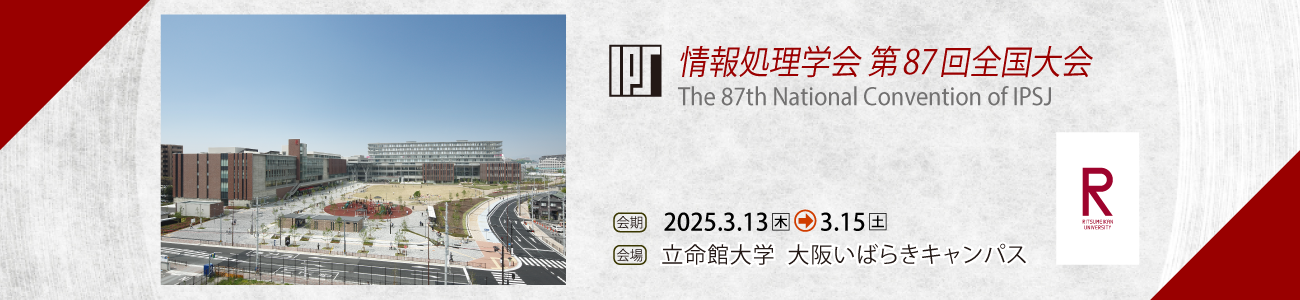
【セッション概要】機械学習、生成AIの急速な発展に伴ないクラウドや端末上のみならず、実世界でのAI技術活用が浸透し始めている。今世紀初頭からネットワークやセンサーなどIT機器が遍在化するUbiquitous Computingの時代を経て、いまはまさに知能自体が遍在化する、万有知能化(Ubiquitous Intelligence)の世紀に突入しつつある。本特別講演ではAIの浸透する実世界を「モビリティ」、「都市空間」「宇宙」の3つの分野について、それぞれの第一人者に登壇いただき、それぞれでの知能化の現状と今後について解説する。3つの各分野からの2名ずつの講師による対談形式で構成し、最後に全員参加してのパネルディスカッションを実施する。

【略歴】1962年、愛知県生れ。東京大学工学部計数工学科を卒業後、東京大学大学院理学系研究科情報科学専攻を修了。1992年より有限会社アクセス(当時)研究開発室、1993年より慶應義塾大学環境情報学部および政策・メディア研究科に勤務。2003年より立命館大学理工学部に赴任。2005年より同大学情報理工学部教授(現職)。2000—2004年JSTさきがけ研究21「協調と制御」領域研究者、2007-2008年Google Inc. Visiting Scientistを併任。博士(政策・メディア)。
【講演概要】自動運転、MaaS、スマートモビリティと「移動」の高度な知能化が急速に進んでいる。加藤氏は「自動運転の民主化」を謳い、自動運転スタートアップのティアフォーを起業し、オープンソースソフトウェアのAutowareを世界中に普及している。 金出氏は1995年No Hands Across America自動運転デモを達成し、関連のコンピュータビジョン・ロボティックス技術を数々研究開発してきた。ここではモビリティに発してそれにとらわれず現在の知能化の流れを概観し今後のあるべき姿について講演する。

【略歴】株式会社ティアフォー 創業者 代表取締役社長CEO。一般社団法人The Autoware Foundation代表理事。東京大学情報理工学系研究科 特任准教授。
1982年神奈川県生まれ。 2008年慶應義塾大学理工学研究科開放環境科学専攻博士後期課程修了。博士(工学)。2009年から2012年まで米国カーネギーメロン大学などで博士研究員、2012年から2016年まで名古屋大学情報科学研究科准教授。2016年より東京大学情報理工学系研究科准教授(現在は特任准教授)。その間、2015年に株式会社ティアフォーを創業、2018年に一般社団法人The Autoware Foundationを設立。専門はオペレーティングシステム、組込みリアルタイムシステム、並列分散システム。文部科学大臣表彰科学技術賞などを受賞。

【略歴】カーネギーメロン大学 創始者記念全学教授。
1973 年京都大学工学博士、京都大学工学部助手・助教授、1980 年米国カーネギーメロン大学に移る。ロボット研究所所長など歴任。コンピュータビジョンと知能ロボット研究者。世界初のコンピュータによる人の顔画像認識や顔の検出技術、1995年アメリカ東部から西海岸まで98%を コンピュータビジョンによる 自動運転で走破 、動画像処理に広く用いられる Lucas-Kanade 法、 第35回スーパーボウルでの360度視野映像「アイビジョン」に代表される多数カメラ画像技術など、今日日常的に使われる多くの技術で知られる。 京都賞、フランクリン財団メダル・バウアー賞、IEEE創始者記念メダル、米国AI学会アレン・ニューウェル賞、BBVA財団知識のフロンティア賞など。文化功労者、 日本学士院会員。
【講演概要】デジタルツイン及び高次の情報空間の社会実装が進み、実空間との高次かつ高解像度の接続の必要性が顕在化している。豊田氏にはエージェントと環境の関係性及びシームレス化を実現するコモングラウンドおよびNHA(Non-Human Agent)概念を、三宅氏にはゲーム開発でのご経験からメタバースとスマートシティをつなぐ空間知能(スペーシャルAI)に関する技術開発の現状を講演する。

【略歴】安藤忠雄建築研究所、SHoP Architectsを経て、建築デザイン事務所 NOIZ 、スマートシティのコンサルティング gluonを設立。大阪・関西国際博覧会 誘致会場計画アドバイザー、建築情報学会副会長、コモングラウンド・リビングラボ、Metaverse Japan設立理事。2021年より東京大学生産技術研究所特任教授。

【略歴】京都大学で数学を専攻、大阪大学(物理学修士)、東京大学工学系研究科博士課程を経て、博士(工学、東京大学)。2004年よりデジタルゲームにおける人工知能の開発・研究に従事。情報処理学会ゲーム情報学研究会運営委員、人工知能学会理事・学会誌編集委員長、日本デジタルゲーム学会理事、国際ゲーム開発者協会日本ゲームAI専門部会(チェア)。2020年度人工知能学会論文賞、2023年度日本デジタルゲーム学会学会賞を受賞。著書に「人工知能のうしろから世界をのぞいてみる」「人工知能のための哲学塾」「ゲームAI技術入門」「戦略ゲームAI 解体新書」など多数、共著に「ゲーム情報学概論」など多数。
【講演概要】JAXA岡田理事は今後の日本の基幹ロケットとなるH3ロケットのPMとし て、徹底したユーザ視点で「柔軟性」、「高信頼性」、「低価格」を目指し、 2023年3月に試験機1号機の打上げに臨んだが、第2段エンジンが着火せず失敗 に終わった。一方で稲川氏は民間の宇宙スタートアップであるインターステラ テクノロジズ株式会社で代表取締役CEOとしてロケット開発に携わり、やはり 数々の困難を経験してきた。本講演では、JAXAおよび民間スタートアップの目 指す世界とその開発の過程、および、どのように失敗を克服できたかをマネジ メントの視点から、そして今後のエンジニアリングへの知能化に限らず新技術 発展への期待について講演する。

【略歴】1989年 JAXAの前身である宇宙開発事業団に入社
入社以来、種子島宇宙センター、筑波宇宙センターなどで液体ロケットおよびロケットエンジンの開発に従事
2015年 H3プロジェクトチームプロジェクトマネージャ
2024年 理事 宇宙輸送技術部門長(現職)

【略歴】東京工業大学大学院機械物理工学専攻修士号修了後、2013年にインターステラテクノロジズに入社、2014年から代表取締役に就任。技術者出身の経営者としてチームを主導し、2019年に観測ロケットMOMOで日本初となる民間単独開発のロケットの宇宙到達を達成。現在は小型人工衛星打上げロケットZEROと人工衛星Our Starsを通じて、国内初のロケット×人工衛星の垂直統合ビジネス実現を目指している。2020年「宇宙開発利用大賞」内閣府特命担当大臣(宇宙政策)賞、2023年「ものづくり日本大賞」経済産業大臣賞を受賞。