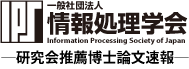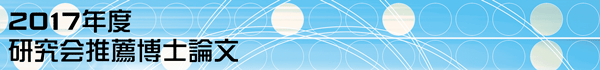| 野口 康人 聖徳大学 短期大学部 総合文化学科 准教授 |
[背景]非同期環境における共食のニーズの高まり
[問題]非同期共食コミュニケーションの実現
[貢献]食事進捗同調システムの実現と効果の検証
[問題]非同期共食コミュニケーションの実現
[貢献]食事進捗同調システムの実現と効果の検証
ここ数十年の間に,ビデオを介したコミュニケーションはオフィスだけでなく家庭においても広く普及してきている.そうした中,離れている人と共に食事をしたいというニーズが高まってきている.一般に普及しているSkypeやFaceTimeのようなビデオチャットツールを用いれば,人々はお互いに簡単につながることができる.常時接続した状態であれば,離れた場所にいる家族や友人たちと一緒にいるような感覚が得られるし,共に食事を行うこともできる.しかしながら,時差があるような地域間であったり,生活リズムが異なったりする場合,このようなツールは有効ではない.時間的制約を受けず,非同期にコミュニケーションを行いたい場合は,ビデオメッセージの方が有用である.
このような時間的・距離的制約を解決するため,KIZUNAと呼ばれる非同期型共食手法が提案されている.この手法では,あらかじめ撮影されたビデオメッセージを用い,それを利用者が視聴しながら食事を行うことで疑似的に非同期型共食環境を設定している.対面の共食コミュニケーションでは,相手の摂食行動から影響を受けて,意識せずとも自らの摂食速度を調整することが知られているが,非同期共食環境では,食事相手がビデオ映像であるため食事スピードが変化することがなく,「一緒に食事をしている」感覚が十分に得られないことが予想される.そこでこの手法では,ビデオ視聴者の食事進捗に合わせて動的にビデオの再生速度を調整することで,ビデオ内人物の食事進捗を同調させる.
本研究では2つの取り組みにより非同期共食コミュニケーションの実現に寄与した.ひとつめの取り組みとして,非同期疑似共食環境を構築し,食事進捗を同調させることがそこで行われるコミュニケーション行動にどのような影響を及ぼすかについて実験的に検討した.この結果食事進捗同調は,発話頻度の増加傾向やビデオ内人物の発話に対して応答が素早くなるなど,ビデオ視聴者のコミュニケーションへの積極的な参加を促すことが明らかとなった.このことは,非同期共食コミュニケーションの特性の理解の一助となる.続くもうひとつの取り組みとして,これまでに実現されていなかった,食事進捗同調を自動的に行う非同期共食コミュニケーション支援システムを構築した.システム利用時の様子を図に示す.このシステムは,実験者が手動で食事進捗の同調を図る場合と遜色のない定性的評価が得られ,時間的解像度のより高い制御を実現可能とする.非同期環境における共食コミュニケーションの実現方法について具体的に検討し,その有効性を実証したことは,今後非同期共食コミュニケーション支援システムを設計する際や非同期共食コミュニケーション支援を行う上での参考となる.本研究を通し,現在はまだ日常的に行われていない非同期共食コミュニケーション実現に向けて一定の貢献ができた.
このような時間的・距離的制約を解決するため,KIZUNAと呼ばれる非同期型共食手法が提案されている.この手法では,あらかじめ撮影されたビデオメッセージを用い,それを利用者が視聴しながら食事を行うことで疑似的に非同期型共食環境を設定している.対面の共食コミュニケーションでは,相手の摂食行動から影響を受けて,意識せずとも自らの摂食速度を調整することが知られているが,非同期共食環境では,食事相手がビデオ映像であるため食事スピードが変化することがなく,「一緒に食事をしている」感覚が十分に得られないことが予想される.そこでこの手法では,ビデオ視聴者の食事進捗に合わせて動的にビデオの再生速度を調整することで,ビデオ内人物の食事進捗を同調させる.
本研究では2つの取り組みにより非同期共食コミュニケーションの実現に寄与した.ひとつめの取り組みとして,非同期疑似共食環境を構築し,食事進捗を同調させることがそこで行われるコミュニケーション行動にどのような影響を及ぼすかについて実験的に検討した.この結果食事進捗同調は,発話頻度の増加傾向やビデオ内人物の発話に対して応答が素早くなるなど,ビデオ視聴者のコミュニケーションへの積極的な参加を促すことが明らかとなった.このことは,非同期共食コミュニケーションの特性の理解の一助となる.続くもうひとつの取り組みとして,これまでに実現されていなかった,食事進捗同調を自動的に行う非同期共食コミュニケーション支援システムを構築した.システム利用時の様子を図に示す.このシステムは,実験者が手動で食事進捗の同調を図る場合と遜色のない定性的評価が得られ,時間的解像度のより高い制御を実現可能とする.非同期環境における共食コミュニケーションの実現方法について具体的に検討し,その有効性を実証したことは,今後非同期共食コミュニケーション支援システムを設計する際や非同期共食コミュニケーション支援を行う上での参考となる.本研究を通し,現在はまだ日常的に行われていない非同期共食コミュニケーション実現に向けて一定の貢献ができた.

(2018年4月30日受付)