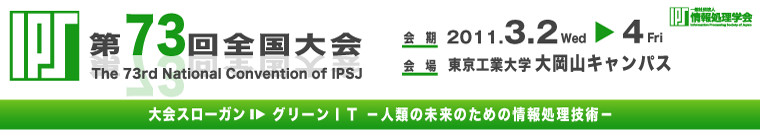
スマートシティ実現のためのIT技術開発と省エネビルの現状
日時:3月4日(金)9:30-12:00
会場:第2イベント会場 (西5号館講義棟 2F W521)
【セッション概要】IT技術などを駆使しエネルギー効率を高め、省資源化を徹底した環境配慮型の街づくりが進んでいる。都市環境においては、オフィスビルなどが費やすエネルギー消費は膨大であり、効率的なビルエネルギー管理が望まれている。特に、中小規模のビルを総合的に管理し、管理コストを低減するための試みがされている。本セッションでは、スマートシティの実現において、現在進む省エネビルの実現に向けた技術課題、標準化について講演を行う。
| 司会:瀬戸 洋一 (産業技術大学院大学 産業技術研究科 教授) | |
 |
【略歴】1979年慶應義塾大学大学院修了、同年(株)日立製作所入社、システム開発研究所にて、リモートセンシング、医療情報システム、情報セキュリティの研究開発に従事。セキュリティ研究センター副センター長、セキュリティビジネスセンターセンター長、主管研究員を歴任後、2006年公立大学法人首都大学東京産業技術大学院大学教授に就任。プライバシーリスクマネジメント、データ保護の教育研究に従事。最近スマートシティのセキュリティに興味を持つ。工学博士(慶大)、技術士(情報処理)。 |
| 9:30-10:30 講演-1 スマートシティの一翼を担うZEBの実現 | |
| 高見 牧人 (経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー対策課 課長) | |
| 【講演概要】2010年6月に閣議決定されたエネルギー基本計画において、2030年までに新築ビルの平均でZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)を達成する目標が掲げられた。ZEBの達成のためには、省エネ建築や自然エネルギー利用、照明・空調など多様な新技術の組み合わせと、運用段階における各技術の統合制御が必要である。一方で、統合制御を可能にするためには、各種設備・機器のインターフェースやデータ仕様の標準化も重要である。経済産業省では、ビル管理システムのベンダーやビルオーナー、IT関連企業などが参画する「省エネビル推進標準化コンソーシアム」を設け、中小ビルの省エネ推進に向けた各種設備・機器のインターフェースやデータ仕様の標準化について検討してきた。ZEBを巡る最近の政策動向及び「省エネビル推進標準化コンソーシアム」について説明をする。 |
|
 |
【略歴】1988年京都大学大学院卒、同年通商産業省に入省。以後、リサイクル推進課、化学物質管理課、大臣官房政策審議室、経済協力課、秘書課、資源エネルギー庁省エネ新エネ部国際室等の業務を経て新エネルギー産業技術総合開発機構(NEDO)ワシントン事務所長を経て2010 年7月より資源エネルー庁省エネ新エネ部省エネ課長。 |
| 10:30-11:00 講演-2 省エネビル推進標準化プロジェクトについて(省エネビル推進標準化コンソーシアム) | |
| 藤原 孝行 (財団法人東京都環境整備公社 東京都環境科学研究所 調査研究科 主任研究員) | |
| 【講演概要】わが国の最終エネルギー消費の推移の内、業務部門については、1990年比で4割程度増加した後、高止まりしており、中でも業務セクターの約1/3を占める中小のビルや公共施設は省エネ対策の更なる強化が求められている。中小ビルにおける従来のビルエネルギー管理システムにおいては、異なるメーカー間では接続インターフェースやデータ仕様に互換性が乏しいとともに、通信プロトコルが非公開であり相互接続が困難である。このため、機器選択や最適なシステム構築に自由度が乏しく、コスト低減・技術競争が生じにくい等の問題が存在している。これらのインターフェースや通信データ仕様が標準化されることにより、異なるベンダーの製品でも相互接続が可能となり、機器のモジュール化と価格競争によるシステム構築時のコスト低下、ベンダーに依存しない最適なシステム構築、ネットワーク経由での省エネサービスのアウトソース等の新ビジネス参入が期待される。 |
|
 |
【略歴】1966年東京都庁入庁。都庁では、建築設備の設計工事監督など営繕系の仕事に従事。主な経歴は新宿東京都庁舎の設計工事を6年間、東京都市博覧会の計画を5年間担当など。2008年都庁定年退職後、(財)東京都環境整備公社 東京都環境科学研究所に入所し現在に至る。研究所では、建築物の省エネ対策手法の研究、設備制御システムのオープン化研究、都市づくりにおけるCO2削減技術のポテンシャルの調査研究などを担当。 |
| 11:00-11:30 講演-3 企業の目指すスマートシティ | |
| 岩野 和生 (日本アイ・ビー・エム株式会社 未来価値創造事業 執行役員) | |
| 【講演概要】現在、人口の都市集中化や低炭素化を背景にして都市をスマート化するプロジェクトが起こっている。IBMはエネルギー、水、交通などの分野でこれまでのハードウェア中心の社会インフラをイノベートするスマータープラネットを提唱している。近年爆発的に普及したセンサーや機能化デバイスを通信で相互接続し集まる大量のデータを統合し解析してフィードバックすることにより、地球上のさまざまな無駄を減らし人々の行動に影響をあたえることが可能になってきている。特に顕著な進化としては、精緻なモデルの上に大量に集まる需要側のデータを短時間に解析、シミュレーション、予測できることで供給側は設備投資やオペレーションを最適化できる情報技術の登場である。 |
|
 |
【略歴】1975年 東京大学理学部数学科卒業後、日本アイ・ビ-・エム(株)入社。1987年米国Princeton大学Computer Science学科よりPh. D 取得。1995年から2000年まで東京基礎研究所 所長、その後、米国ワトソン研究所を経て、2002年より先進事業 (Emerging Business)、2004年より大和ソフトウエア開発研究所 所長を担当し、2009年より現職。東京工業大学、筑波大学客員教授。情報処理学会フェロー、日本学術会議連携会員。IEEE, ACM, SIAM会員。専門分野: グラフアルゴリズム、組み合わせ最適化、オートノミックコンピューティング、クラウドコンピューティング。 |
| 11:30-12:00 講演-4 スマート&スムース:社会インフラの高度化を実現する情報制御融合技術 | |
| 前田 章 (株式会社日立製作所 情報制御システム社 CTO) | |
| 【講演概要】21世紀の都市においては、地球温暖化、資源問題、都市の少子高齢化などの課題を解決し、サステイナブルな社会、企業、生活を実現することが求められる。そのためにはITを活用し、都市全体をシステムとして高度にマネジメントすることが必要であり、ここではそれを「スマートシティ」と呼ぶ。従来、電力・交通・水といった社会インフラは、個別に制御技術によって高い信頼性を実現してきたが、スマートシティではこれらを連携させた全体最適化が必要となる。そのためには物理的に広域に分散している社会インフラシステムを高信頼かつリアルタイムに制御する技術と、豊富な計算リソースを活用した大規模データ処理技術・シミュレーション技術等の情報システム技術をいかに融合させるかが重要である。この分野における日立の技術開発コンセプトと、具体事例における取り組み状況を紹介する。 |
|
 |
【略歴】1981年、㈱日立製作所入社、システム開発研究所・中央研究所・情報制御システム社にて、画像処理や高度情報処理に関する研究開発、技術マネジメントに従事。情報処理学会、電気学会、IEEE等の会員、工学博士。 |